2021年8月17日
思い出すままに――森桂さんの「つれづれ抄」②
二つの選集

外国から帰って何回か引っ越しを重ねた。そのたびに物を整理したが、今でも手許に置いている選集がある。谷崎潤一郎と井上靖の文豪作品だ。どちらも昭和二十年も半ばの出版で、父は敗戦直後の新聞社で社会部長の職にあった。すべてがまっさらな社会。どんなことでも書ける。GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の厳しい検閲が待っていたものの、輝かしい未来を予言する社会面づくりに全力を費やした。GHQで働くタイプライター嬢、上野の地下道で生活する少年たちなどを描いた連載「東京24時間」は、読みごたえがある。
そこに昭和二十三年、思わぬ異動の話が持ち上がる。出版局長への転出である。生涯一記者を志していたので、この職には熱い意義を感じていた。部内にも残留を求める同輩が少なくなかったという。だが父は、あえて出版の道を選んだ。大学でロシア語を専攻し、ゴーリキーやトルストイなどの文学に親しみ、一時は小説家を志望したほどだから、思うところがあったのだろう。
世の中は出版ブームにわいていた。だが紙がない。その点、新聞社は製紙会社とは縁が深い。GHQとの交渉次第で紙は、そんなに苦労しなくても手に入る。出版局にも日の目が来る時だと考えた。
最初に思いついたのは谷崎さんへ新作を依頼することだった。谷崎さんとは京都支局時代からの知己であった。「少将滋幹(しげもと)の母」を書いてくれることとなった。これは王朝物の時代小説。戦後の谷崎文学の傑作の一つで、多くの作家や文芸評論家から賞讃された作品ある。作者自身の幼い頃の母の記と、永遠の女性像を二重写しにしている作品でもある。
新聞連載が終わり、豪華本の型見本が出来上がった。装丁は安田靫彦(ゆきひこ)。当時としては珍しいカラー印刷だ。
それを熱海の谷崎さんに届ける日、僕は父から「今日は偉い先生にお目にかかるのだから、大人しくしているんだよ」と諭された。会社から車が迎えに来た。連合軍から払い下げられた米国製のシボレーである。右側の助手席にはおかもちに入った新鮮な魚が飛び跳ねている。食通の谷崎さんに食べて頂こうと父が築地の河岸から取り寄せたものだ。
伊豆山の谷崎邸に着いた。谷崎さんはにこにこと僕らを迎えてくださった。谷崎さんは「今どき上出来ですね」とご満悦だったいう。だが小学生の僕には、二人の会話はさっぱり分からない。十分もしないうちに、僕は運転手さんの元へ戻り父の戻るのを待った。父から言われた「お暇をする時は、お座布団を裏返して」という言いつけを守って…。父はその日の日記に
「大作家に会ったことを、どれだけ覚えてくれるだろうか」と記している。
父の命日の一月十一日は、毎年かつての同僚が夭折した父をしのんで酒を酌み交わした。その宴は三十三回忌にまで及んだ。いま、その寄せ書き帖が残っている。「森は生きている」といった揮毫のなかに「井上靖」と名前だけが、遠慮がちに記されているのが目につく。
戦争が激しくなり情報源が東京に集中したこともあって、腕利き記者が東京に集められた。井上さんは大阪本社へ入社、学芸部に配属された。日中戦争のため召集を受け出征するが、翌年には病気のため除隊され、学芸部へ復帰する。玉音放送の時も東京社会部にいた。
そして社会面を埋める原稿を書く。
頭を挙げ得るものは一人もいない。
正午の時報がある。ついで君が代の曲が奏でられる。敵弾に破られまさに沈み行こうとする艦の上で聞く君が代にも等しい。
その曲が終わる。そして「朕深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み……」拡声器から流れる玉音である。畏れおおい。無念だ。誰もの目からは降り落ちる涙、そしてやがてそこからもここからも聞こえてくる嗚咽。それがだんだんと繁く大きくなって来る。地でまろどんで慟哭したいところを一心に我慢しているのである。そして御一言も聞き漏らすまいと皆が努力している。玉音にも御うるみが拝されるではないか。ああ何たる畏れおおいことか。御放送は終わった。
それから五年。井上さんは「闘牛」で芥川賞を受賞した。土佐(高知県)を舞台にした、闘牛の興行師と地元新聞記者の物語である。正賞はスイス製の懐中時計、副賞は五十万円だった。大学の初任給が四千二百円、ラーメンが一杯二十円の時代である。いまのように高い賞金や豪華な賞品がつく賞などなく、芥川賞は地位と名誉を象徴する存在だった。だから周囲の妬みや羨望は、考えられないほど強かった。
井上さんも、その淵に立たされた。悩んだ末、井上さんは父に相談する。父は「次の作品ができるまで社に留まるように」と、出版局付きという席を特別に設けて、井上さんを守った。井上さんは下山事件を題材にした「黯(くろ)い潮」で、毎日の記者たちを描いているが、あくまでもノンフィクションの世界でのことだ。芥川賞を受賞したころの気持ちが残っていないのは残念だ。
以下は、父森正蔵が出版交渉に谷崎邸を初めて訪れた時の日記である
昭和二十五年八月二十日(日曜日) 雨 ― 熱海へ、雪後庵訪問 ―
家を出る時には降っていなかったが途中で雨となった。東京駅の東口に自動車を降りてみると、出札口の前は一ぱいの人だかり。とても順番を待っていては切符を買うことが出来ないので、一番先頭にいる学生に頼んで、熱海までの一等の切符を一枚買って貰って、ようやく発車の間に合う。私の乗る九時五十五分発の電車はすでに大変な混雑である。こうなれば二等も三等もあったものでなく、その混雑は新橋、品川あたりからいよいよひどくなったが、藤沢を過ぎると、また幾分かやわらいだ。十二時過ぎじゃんじゃん雨の降る熱海駅に着く。そこで谷崎潤一郎氏の秘書の小滝に会う。同じ電車に乗っていたのである。
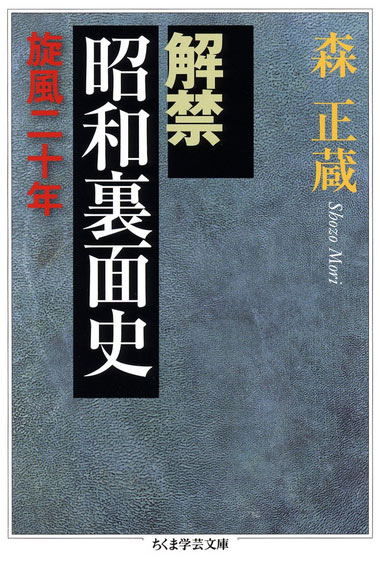
駅前で自動車を雇う。これがまた大変である。後で谷崎氏とも話したことだが、これは観光地熱海の大きな欠点である。自動車は次ら次へと来るのだが、各旅館の客引き男に横取りされて、それぞれの旅館に泊まる客がそれに乗って先に行ってしまう。旅館につながりのないわれわれのような旅行者は待てど暮らせど、自分の乗れる自動車を掴まえることは出来ないのである。それでも半時間も待ってやっと一台を手にした。つまり旅館行きの客が一通りさばかれた後である。
谷崎氏の新居雪後庵は仲田と言うところにある。誰かの別荘を買ったもので、「細雪」の出来た後の住居であるというのが、雪後庵の名の来るところだという。きわめて狭い玄関、靴を脱ぐと、そこに小さな卓と小倚子三、四が置いてある。同じく狭いまく雑巾がかけられて、艶の出た廊下を通って突当りを右に折れると六畳の日本間になる。そこへ通された。客間であろう。左手の上席に私が座り、谷水、小滝がこれに続く。部屋にはマホガニーの木目の美しいピアノが置いてあった。天井の低い数寄屋造りの一室である。中央にかなり大きな木の卓、水色の麻の座布団。庭も狭い。そして余り手の入った跡もない百合の花がしぼんで、降る雨に打たれていた。
隣が茶の間らしく、昼食の後でもあろうか、食器を取り片づける音が聞こえていたが、やがてその部室のあたりから主人が現れた。薄い麻の関西ではジンベという丈の短い着物を着ている。挨拶が終わるなり「少将滋幹の母」の話に移った。小滝が今日も装幀本を五冊提げて来た。谷崎氏は非常な喜びかたで、この本の出来栄えを誉めた。戦前にもこれくらいの本は出たことがなかったと言っている。慾を言えば本文の印刷がもう少しうまく行ったら ― と思うと言った。そして函にもう少しゆとりがあった方がよかったとも言った。京都でこの本の見本刷一冊が届いた時に舟橋聖一が来ていたが、大そう驚いていた。舟橋と一緒に来ていた舟橋の娘が「お父さんの本は何だってくだらぬ装幀ものばかりなんでしょう」と言ったのに対して舟橋は、何の言葉もよう出さなかったそうである。「少将滋幹の母」は今度「東おどり」で上演されることになっていて、その脚色を舟橋が引き受けている。今晩はそれについての打合せのため舟橋に招かれているのだ ― と言っていた。それから話はいろいろのことに及ぶ。
主人はもう一度支那に行きたいそうである。殊に北京で暫らく暮らしてみたいという。谷崎氏の作品を英訳したエリセーエフというアメリカにいる日本語学者のことにも及んだので、それは今東京のフランス大使館にいるエリセーエフの一族であろうということも話題となり、私がエリセーエフはモスクワの現在の第一ゴストロノム(註:百貨店)の前身エリセーエフ食糧品店の主人の一族であることを話すと、谷崎氏もそのことを知っていた。
雪後庵では今、書斎の新築が進んでいる。ものを書くのに、家人との連絡を絶つが望ましいというところから、今建ちかかっている書斎は、他の部屋から直接行き来できないようになっている。一度庭下駄を履いて庭に降り、雨の降る日は傘をさして、そこへ行かねばならぬのである。
話題はなおいくつもあった。尽きるところのない話である。主人は非常に満悦らしく実によく語り、私たちが帰るというのに、まだ帰らしたくないような様子に見えたが、二時間近くも喋ったので、自動車を呼んでもらって辞去することにした。夫人は何度も客間に出て来て茶菓を自ら接待してくれた。きれいな若い夫人だった。
(つづく)
※森桂さんの父、正蔵さんは明治33年7月滋賀県生まれ。大正13年大阪毎日新聞入社。ハルビン支局長、モスクワ特派員、大阪本社ロシア課長、東京本社論説委員を経て、昭和20年社会部長、編集局次長,出版局長、同26年取締役。同28年1月病没 著書『旋風二十年―解禁昭和裏面史』は昭和20年12月に発行され、満州事変など戦争中に国民に知らされていなかった事実を明らかにし、ベストセラーになった。写真は2009年に「ちくま学芸文庫」として復刻されたもの。