2021年8月20日
思い出すままにーー森桂さんの「つれづれ抄」③

コバちゃん
何でも占領軍の払い下げの時代だった。社の車はアメ車だったし、パンツなど下着までもが当てがわれた。そんな時「三きたな」と呼ばれた三人の記者がいた。「きたな」とは汚いを指す。その一人が古波藏(こはぐら)保好さんだ。
紙のパンツを避け、自前のパンツをはいていたのだが、周囲が不潔な生活をしている男と勝手に思い込み、不本意なあだ名がついてしまったらしい。
名前で想像がつく通り、琉球国朝廷の末裔だ。誇りをもっていたから、昨日の敵に従いたくなかったのだろう。沖縄日報の記者から当時の大阪毎日新聞に入り、東京本社の社会部記者を経て論説委員を勤めた。福湯豊さんらと並んで名文家で知られた。敗戦の一年後には、密航船で沖縄にわたり、悲劇の島をルポしている。
古波藏さんの身のこなしは格別だった。七二年には第一回のベストドレッサー賞(学術・文化部門)を受賞したほどである。パートナーはファッションデザイナーの鯨岡阿美子さんだから、男のおしゃれは身について当然だ。
亡くなる一年ほど前、六本木に近いお宅を訪れた。「起きてみると、すぐ横で阿美子が息絶えているのにはびっくりした。僕も去年、吐血して死にかけたけれど、阿美子が守ってくれたんだと思うよ」と語っていた。
一度だけ夜更けの六本木の通りを、最愛のパートナーと手を組んで散歩する古波藏さんの姿が忘れられない。
僕がデスクをしていた「毎日中学生新聞」に連載のお願いをした、原稿が手許にあったので紹介する。
大男の強盗しきり
「――日何時ごろ、ナニ町何番地某方に大男の強盗が押し入って「云々」という記事がよく新聞の社会面に出た」。
廃墟となった街は、日が暮れると暗ヤミとなり、何が出るかわからないという気味悪さである。あちこちにションボリと街灯がついていたと覚えているが、照らす範囲はきわめて狭かった。暗くなりだすころから、人々は家路を急ぎ、あとはどこもかもシーンとなる。
廃墟のヤミで、おそれを知らないのは、強盗くらいだったのではなかろうか。特に大男の強盗にとっては、コワイものなしだったはずだ。
外地からやっと引揚げて、毎日新聞社の社会部記者に復帰したばかりのわたしは、「大男の強盗」という意味するものがわからず、「この二、三日しきりの大男強盗の記事が出ているが、同じヤツが荒らしているのかね」と同僚にきいたら、相手はニヤニヤと、「アタマをはたらかせろ。数知れぬ大男が今の東京にはきているんだ」と答えたのである。
やっと察しがついて、「だとしたら、どうしてハッキリと占領軍のGIらしいと書かないんだ」といえば、「引揚げてきたばかりのお前には、まだ被占領国の弱さがわかっていないんだ」ということだった。
民家に押し入った強盗が占領軍のGIだと明らかになっているのに、つねづね公正な報道をうたいあげている新聞が、奥歯に物の挟まったような表現をしたというのは、被占領国新聞の悲劇――ではなくて、むしろ喜劇だったとみていいだろう。
GIとハッキリと書かないで、GIと感じさせるにはどんな言葉を使えばいいか、といろいろアタマをひねったあげくの「大男」なることばをヒネリだすまでの苦心が察しられて、なんとなくおかしくなってしまうのである。
日本人にも大男はいるのに、こっちの迷惑は同胞のよしみで――ということだ。
ある教師のお弁当
ある日、わたしは、取材のためだったと思う、神田の小学校へいった。職員室に通されて、椅子を与えられたのだが、ちょうど昼休みで、先生たちが弁当を食べはじめている。
わたしの目近でも、先生のひとりがアルミニューム製の、やや大きめの弁当箱をひらいて食べはじめた。なんとなくわたしの視線がその弁当箱に向く。
この弁当箱の中に詰められていたものを、わたしはいまもアリアリと覚えている。
ふたを抑えつけるようにして、ギッシリと詰められているのは、青々とした菜っ葉だった。
ご飯は、と見れば、箱の隅に、つまりはこの中を六つに仕切るとしたら、その一つに相当する量が白く輝いているに過ぎないのである。
かつて弁当箱のフタをとれば、白いご飯が多くの面積を占め、オカズは小箱の中に――というのがふつうだった。その先生が持参している食事はアベコベだったわけだ。
あまりにも青々としている菜っ葉は、当時軒先きに少しの土でもあれば、食べられる野菜をつくるということが習いとなっていたので、先生の弁当箱に満ちているのも、小さな菜園からの取り立てだったのであろう。
新鮮には違いなかったが、あぶらで炒めたのではなく、サッツと茹でただけのようだということは、色の鮮やかさで感じられたのである。
先生は青い菜っ葉をよく噛んでた。よく噛まないと、繊維だらけの菜っ葉はなかなかノドへ通るものではない。いつ食べ終わるかと気になるくらいシッカリと噛んでいる。そして白いご飯にはなかなか箸をつけなかった。
あのころ白いご飯のことを銀メシ、あるいは銀シャリといって尊重していたのだが、弁当箱の片隅で光る白いご飯は、最後の楽しみにトッテオキということらしかったのである。
ラク町ファッション
有楽町はラクチョウ、銀座はザギン、上野はノガミと言われるようになって、東京の由緒ある町が格落ちした。いわゆる「パンパン」やヤクザのアンちゃんたちが使う隠語を、堅気の衆までおもしろがって口にするようになったのである。食べるものをちゃんと腹に入れて、フテくさったあげくの元気いっぱいに見えるのは、彼女たちと彼らだった。
「パンパン」とはオカネとひきかえに、からだをまかせる女性のことだったが、はじめて現れたこの言葉は、どこからきたのだろう。
戦争の末期、台湾の海軍基地に報道班員として滞在していたころ、水兵たちの会話に「パンパン屋」という言葉が出るのを聞いた覚えがある。もちろん男たちの欲望を次々に処理する女性のいる家のことだった。しかし水兵たちがどこでこの言葉を覚えたかということになると、もうわからないのである。
いずれにしても、「ラク町」にたむろする彼女たちは、はじめ惨めな姿だった。着古したモンペ、父親のお古とおぼしきズボン、布地の織目がゆるんだスカート、ロクに食べていない顔の色が哀れで、不敵な面構えならまだしも、つつましくマジメに戦時中を暮らしてきたのではないかと思われる若い女性もいた。
化粧といえば、やっと手に入れたルージュを使っていると感じられるだけだったのが、みるみる真新しい花柄のワンピースを着て、カチーフで顔を包むなど、姿がキレイになり、悪びれなくなったのである。
風呂敷くらいの大きさがあるカチーフは、花をプリントしてあったり、これを三角に折って、折り目を額の上に当て、下にさがる両端をアゴの下で結ぶというシャレッ気は、米軍基地で暮らすGIの女房たちからの見よう見まねだったのであろう。顔がカチーフで囲まれると不思議に美人らしくなるため、堅気の娘たちまでがマネをして、ファッションの第一号となった。
(つづく)
2021年8月18日
吉田ハムさんがガリ版を切った同人誌「五番線」創刊号
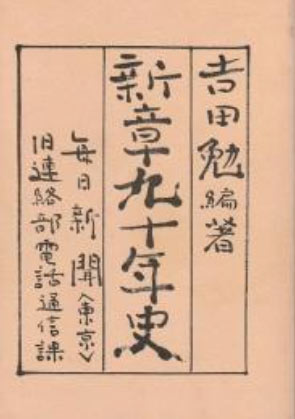
経済評論家・鈴田敦之さんが連絡部時代の先輩・吉田公一さん(2021年7月12日逝去98歳)を偲んだ追悼録。同人誌「五番線」の詳細が吉田勉編著『新章九十年史』(自費出版1989年刊)にあった。
昭和26年6月9日―電話通信課同人誌『五番線』創刊号発刊。
「どうやら誕生のうぶ声を挙げ得たということを皆様と共に喜びたいと思います」(吉田公一)——昭和31年12月発行の第8号まで続き、社内の注目を集めた。
創刊号はガリ版刷り。吉田ハムさん(社会部では吉田姓が他にもいたので、ハムさんと呼んでいた)がガリ版を切った、とある。
9月18日に第2号。「よし、3号も、という気になります」とあとがきにハムさんが書いているが、12月に発行した第3号の編集責任者は坂本充郎(のち政治部、地方自治専門)鈴田敦之、青木茂の3人にバトンタッチしている。出しゃばらないハムさんらしい。
『新章九十年史』には「五番線」全号の目次と、主だった原稿が採録されている。残念ながらハムさんの文章は載っていない。
その代わり89年4月3日勉さんに届いた手紙が採録されている。
ハムさんは1947(昭和22)年12月入社。61(昭和36)年4月内信部。71(昭和46)年2月社会部。77(昭和52)年新社発足に伴い退社。
《29年11ヶ月の在社を、前中後期と分けると、前期の連絡は約13年いた。当たり前のことだが、青春時代であり、仕事も遊びも思い切ってやれた》
《社会部時代で楽しかったのは、浅草の東支局の5年間だった。染太郎のおばちゃん、神谷バーの渋谷支配人など、下町の心のふれあいがうれしかった。あの昭和50年前後、東支局から出稿した街ダネには「また〇〇が消えていく」という歴史・人情ものが多かった》
いつもニコニコ、温顔で怒った顔を見たことがなかった。
◇
『新章九十年史』を制作・発行した吉田勉さん(2003年没70歳)。1988(昭和63)年2月1日に毎日新聞社が速記を廃止した年に定年退職した速記者で、東京本社連絡部にあった昭和6年から42年までの3冊の部内連絡帳を、習い始めのワープロで打ち込み、それ以前の電話電信、速記史をまとめた。B5判、本文745ページの大部なものだ。
速記の廃止に伴い《さよなら「電話速記」》を「記者の目」に書いた。
速記が新聞に導入されたのは、1899(明治32)年2月1日で、その生みの親は、当時の大阪毎日新聞社長の原敬(のち首相)だった。
速記者の特ダネとして、1950(昭和25)年3月1日、当時の池田勇人蔵相(のち首相)が国会で「中小企業の5人や10人自殺してもやむを得ない」と発言した。それを速記録から起こして紙面に掲載、特ダネとなった。速記録が動かぬ証拠となったというのだ。もっとも池田蔵相の放言としては、その年12月の「貧乏人は麦を食え」の方が有名だが。
(堤 哲)
2021年8月17日
思い出すままに――森桂さんの「つれづれ抄」②
二つの選集。

外国から帰って何回か引っ越しを重ねた。そのたびに物を整理したが、今でも手許に置いている選集がある。谷崎潤一郎と井上靖の文豪作品だ。どちらも昭和二十年も半ばの出版で、父は敗戦直後の新聞社で社会部長の職にあった。すべてがまっさらな社会。どんなことでも書ける。GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の厳しい検閲が待っていたものの、輝かしい未来を予言する社会面づくりに全力を費やした。GHQで働くタイプライター嬢、上野の地下道で生活する少年たちなどを描いた連載「東京24時間」は、読みごたえがある。
そこに昭和二十三年、思わぬ異動の話が持ち上がる。出版局長への転出である。生涯一記者を志していたので、この職には熱い意義を感じていた。部内にも残留を求める同輩が少なくなかったという。だが父は、あえて出版の道を選んだ。大学でロシア語を専攻し、ゴーリキーやトルストイなどの文学に親しみ、一時は小説家を志望したほどだから、思うところがあったのだろう。
世の中は出版ブームにわいていた。だが紙がない。その点、新聞社は製紙会社とは縁が深い。GHQとの交渉次第で紙は、そんなに苦労しなくても手に入る。出版局にも日の目が来る時だと考えた。
最初に思いついたのは谷崎さんへ新作を依頼することだった。谷崎さんとは京都支局時代からの知己であった。「少将滋幹(しげもと)の母」を書いてくれることとなった。これは王朝物の時代小説。戦後の谷崎文学の傑作の一つで、多くの作家や文芸評論家から賞讃された作品ある。作者自身の幼い頃の母の記と、永遠の女性像を二重写しにしている作品でもある。
新聞連載が終わり、豪華本の型見本が出来上がった。装丁は安田靫彦(ゆきひこ)。当時としては珍しいカラー印刷だ。
それを熱海の谷崎さんに届ける日、僕は父から「今日は偉い先生にお目にかかるのだから、大人しくしているんだよ」と諭された。会社から車が迎えに来た。連合軍から払い下げられた米国製のシボレーである。右側の助手席にはおかもちに入った新鮮な魚が飛び跳ねている。食通の谷崎さんに食べて頂こうと父が築地の河岸から取り寄せたものだ。
伊豆山の谷崎邸に着いた。谷崎さんはにこにこと僕らを迎えてくださった。谷崎さんは「今どき上出来ですね」とご満悦だったいう。だが小学生の僕には、二人の会話はさっぱり分からない。十分もしないうちに、僕は運転手さんの元へ戻り父の戻るのを待った。父から言われた「お暇をする時は、お座布団を裏返して」という言いつけを守って…。父はその日の日記に
「大作家に会ったことを、どれだけ覚えてくれるだろうか」と記している。
父の命日の一月十一日は、毎年かつての同僚が夭折した父をしのんで酒を酌み交わした。その宴は三十三回忌にまで及んだ。いま、その寄せ書き帖が残っている。「森は生きている」といった揮毫のなかに「井上靖」と名前だけが、遠慮がちに記されているのが目につく。
戦争が激しくなり情報源が東京に集中したこともあって、腕利き記者が東京に集められた。井上さんは大阪本社へ入社、学芸部に配属された。日中戦争のため召集を受け出征するが、翌年には病気のため除隊され、学芸部へ復帰する。玉音放送の時も東京社会部にいた。
そして社会面を埋める原稿を書く。
頭を挙げ得るものは一人もいない。
正午の時報がある。ついで君が代の曲が奏でられる。敵弾に破られまさに沈み行こうとする艦の上で聞く君が代にも等しい。
その曲が終わる。そして「朕深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み……」拡声器から流れる玉音である。畏れおおい。無念だ。誰もの目からは降り落ちる涙、そしてやがてそこからもここからも聞こえてくる嗚咽。それがだんだんと繁く大きくなって来る。地でまろどんで慟哭したいところを一心に我慢しているのである。そして御一言も聞き漏らすまいと皆が努力している。玉音にも御うるみが拝されるではないか。ああ何たる畏れおおいことか。御放送は終わった。
それから五年。井上さんは「闘牛」で芥川賞を受賞した。土佐(高知県)を舞台にした、闘牛の興行師と地元新聞記者の物語である。正賞はスイス製の懐中時計、副賞は五十万円だった。大学の初任給が四千二百円、ラーメンが一杯二十円の時代である。いまのように高い賞金や豪華な賞品がつく賞などなく、芥川賞は地位と名誉を象徴する存在だった。だから周囲の妬みや羨望は、考えられないほど強かった。
井上さんも、その淵に立たされた。悩んだ末、井上さんは父に相談する。父は「次の作品ができるまで社に留まるように」と、出版局付きという席を特別に設けて、井上さんを守った。井上さんは下山事件を題材にした「黯(くろ)い潮」で、毎日の記者たちを描いているが、あくまでもノンフィクションの世界でのことだ。芥川賞を受賞したころの気持ちが残っていないのは残念だ。
以下は、父森正蔵が出版交渉に谷崎邸を初めて訪れた時の日記である
昭和二十五年八月二十日(日曜日) 雨 ― 熱海へ、雪後庵訪問 ―
家を出る時には降っていなかったが途中で雨となった。東京駅の東口に自動車を降りてみると、出札口の前は一ぱいの人だかり。とても順番を待っていては切符を買うことが出来ないので、一番先頭にいる学生に頼んで、熱海までの一等の切符を一枚買って貰って、ようやく発車の間に合う。私の乗る九時五十五分発の電車はすでに大変な混雑である。こうなれば二等も三等もあったものでなく、その混雑は新橋、品川あたりからいよいよひどくなったが、藤沢を過ぎると、また幾分かやわらいだ。十二時過ぎじゃんじゃん雨の降る熱海駅に着く。そこで谷崎潤一郎氏の秘書の小滝に会う。同じ電車に乗っていたのである。
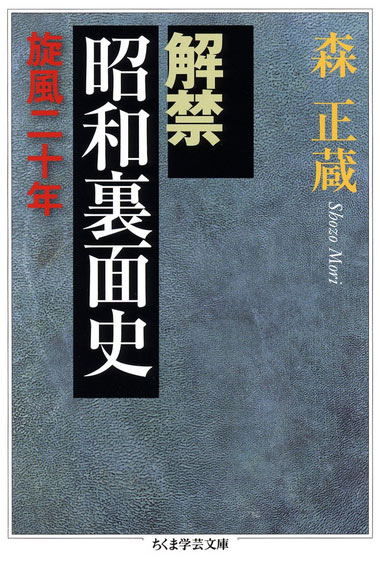
駅前で自動車を雇う。これがまた大変である。後で谷崎氏とも話したことだが、これは観光地熱海の大きな欠点である。自動車は次ら次へと来るのだが、各旅館の客引き男に横取りされて、それぞれの旅館に泊まる客がそれに乗って先に行ってしまう。旅館につながりのないわれわれのような旅行者は待てど暮らせど、自分の乗れる自動車を掴まえることは出来ないのである。それでも半時間も待ってやっと一台を手にした。つまり旅館行きの客が一通りさばかれた後である。
谷崎氏の新居雪後庵は仲田と言うところにある。誰かの別荘を買ったもので、「細雪」の出来た後の住居であるというのが、雪後庵の名の来るところだという。きわめて狭い玄関、靴を脱ぐと、そこに小さな卓と小倚子三、四が置いてある。同じく狭いまく雑巾がかけられて、艶の出た廊下を通って突当りを右に折れると六畳の日本間になる。そこへ通された。客間であろう。左手の上席に私が座り、谷水、小滝がこれに続く。部屋にはマホガニーの木目の美しいピアノが置いてあった。天井の低い数寄屋造りの一室である。中央にかなり大きな木の卓、水色の麻の座布団。庭も狭い。そして余り手の入った跡もない百合の花がしぼんで、降る雨に打たれていた。
隣が茶の間らしく、昼食の後でもあろうか、食器を取り片づける音が聞こえていたが、やがてその部室のあたりから主人が現れた。薄い麻の関西ではジンベという丈の短い着物を着ている。挨拶が終わるなり「少将滋幹の母」の話に移った。小滝が今日も装幀本を五冊提げて来た。谷崎氏は非常な喜びかたで、この本の出来栄えを誉めた。戦前にもこれくらいの本は出たことがなかったと言っている。慾を言えば本文の印刷がもう少しうまく行ったら ― と思うと言った。そして函にもう少しゆとりがあった方がよかったとも言った。京都でこの本の見本刷一冊が届いた時に舟橋聖一が来ていたが、大そう驚いていた。舟橋と一緒に来ていた舟橋の娘が「お父さんの本は何だってくだらぬ装幀ものばかりなんでしょう」と言ったのに対して舟橋は、何の言葉もよう出さなかったそうである。「少将滋幹の母」は今度「東おどり」で上演されることになっていて、その脚色を舟橋が引き受けている。今晩はそれについての打合せのため舟橋に招かれているのだ ― と言っていた。それから話はいろいろのことに及ぶ。
主人はもう一度支那に行きたいそうである。殊に北京で暫らく暮らしてみたいという。谷崎氏の作品を英訳したエリセーエフというアメリカにいる日本語学者のことにも及んだので、それは今東京のフランス大使館にいるエリセーエフの一族であろうということも話題となり、私がエリセーエフはモスクワの現在の第一ゴストロノム(註:百貨店)の前身エリセーエフ食糧品店の主人の一族であることを話すと、谷崎氏もそのことを知っていた。
雪後庵では今、書斎の新築が進んでいる。ものを書くのに、家人との連絡を絶つが望ましいというところから、今建ちかかっている書斎は、他の部屋から直接行き来できないようになっている。一度庭下駄を履いて庭に降り、雨の降る日は傘をさして、そこへ行かねばならぬのである。
話題はなおいくつもあった。尽きるところのない話である。主人は非常に満悦らしく実によく語り、私たちが帰るというのに、まだ帰らしたくないような様子に見えたが、二時間近くも喋ったので、自動車を呼んでもらって辞去することにした。夫人は何度も客間に出て来て茶菓を自ら接待してくれた。きれいな若い夫人だった。
(つづく)
※森桂さんの父、正蔵さんは明治33年7月滋賀県生まれ。大正13年大阪毎日新聞入社。ハルビン支局長、モスクワ特派員、大阪本社ロシア課長、東京本社論説委員を経て、昭和20年社会部長、編集局次長,出版局長、同26年取締役。同28年1月病没 著書『旋風二十年―解禁昭和裏面史』は昭和20年12月に発行され、満州事変など戦争中に国民に知らされていなかった事実を明らかにし、ベストセラーになった。写真は2009年に「ちくま学芸文庫」として復刻されたもの。
2021年8月16日
58年前、有楽町時代の社会部出番表があった‼
社会部旧友・倉嶋康さん(88歳)はFacebookで、記者生活の自伝を連載している。そこに社会部の黒板の写真が載っていた。
58年前の1963(昭和38)年5月23日(木)と24日(金)の内勤出番表である。むろん有楽町駅前に毎日新聞東京本社があった時代である。
倉嶋さんは宿直勤務になっている。2方面(大崎警察署)のサツ回りだった。懐かしい名前ばかりなので、フルネームで再現してみる。

まず黒板の左側から。
1963(昭和38)年5月23日(木)
デスク:夕刊=末安輝雄、朝刊=柳本見一
夜勤:藤原康彦、大澤栄作、植竹英樹
宿直:倉嶋康、大桶浩、太田稀喜
遊軍:浅野弘次、吉野正弘、吉沢敏夫、田中浩、中野謙二、丹羽郁夫、岩崎繁夫、小峰澄夫、吉岡忠雄
宿明:木下剛、中村均、近藤健
公休:浦野勝三、石谷竜生、浜田禎三
次に右側。
5月24日(金)
デスク:夕刊=村山武次、朝刊=末安輝雄
夜勤:坂野将受、田中浩、山本祐司
宿直:吉沢敏夫、前田行男、堀井淳夫
遊軍:吉野正弘、浦野勝三、田中久生、小峰澄夫、吉岡忠雄、石谷竜生、浜田禎三、丹羽郁夫、飯泉栄次郎
宿明:倉嶋康、大桶浩、太田稀喜
公休:浅野弘次、中野謙二
備考:塚田暢利、原田三朗、堀込藤一=組合出張20~24日
1日経つと、今度は左側に25日(土)の出番表が書き込まれる。
私(堤)はこの年の秋に入社試験を受け、翌64年4月に入社した。初任地は長野支局だった。黒板にあるデスクの末安輝雄さん(49年入社。山内大介、渡辺襄の元社長2人、安倍晋太郎と同期)は、翌65年2月の異動で長野支局長としてやってきた。末安さんが横浜支局長になって、後任の長野支局長が村山武次さん(48年入社)、さらに一代置いて坂野将受さん(53年入社)、その後倉嶋さんも務めた。倉嶋さんは98長野冬季五輪を控え、スポニチの初代長野支局長に転進した。父親は長野市長2期、革新市長だった。
社会部長はパリ特派員だった角田明さん。筆頭デスク立川熊之助さん。デスクは非番の佐々木武惟さんと出番表にある3人を含め計5人。
警視庁キャップは藤野好太朗さん。実家の浅草寺仲見世・煎餅かわち屋は今も営業している。前任警視庁キャップの牧内節男さん(8月31日に96歳の誕生日を迎える。多分社会部旧友会最長老)は遊軍長だった。「大阪社会部から東西交流で来ていた立川筆頭デスクは、この年の8月に大阪本社社会部長になった。その時、白木東洋(55年入社)と2人が大阪に連れて行かれた。私は大阪社会部のデスクとなった」といっていた。
最若手は、61年入社の山本祐司さん。当時の社会部の名簿の右隣に60年入社松尾康二さん(84歳)。エビセンと呼ばれていたが、後にカルビー会長を務めた。
62年入社の瀬下恵介さんが八王子支局、冨田淳一郎さん(82歳)が武蔵野支局に名前がある。
ちなみに編集局長斎藤栄一、編集局次長滝本久雄、田中菊次郎、政治部長小林幸三郎、経済部長福井信吉、学芸部長村松喬、科学部長福湯豊、運動部長仁藤正俊、地方部長若月五郎、地方取材部長土師二三生、外信部長大森実、写真部長日沢四郎、論説委員長橘善守、副委員長藤田信勝、林三郎、山本正雄の各氏だった。
(堤 哲)
2021年8月16日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その15 子安観音の石像と女人講(抜粋)
文・写真 平嶋彰彦 毎月14日更新。
わが家のおばあさんネコの掛かりつけの病院が、船橋大神宮(意富比神社)の近くにある。名前はサリー。もうすぐ16歳になる。「猫年齢早見表」によると、人間の年齢なら80歳に相当する。ひと月ほど前のことになるが、そのおばあさんネコが食事をとらなくなり、しきりになにか吐いている。ふだんよくみる毛玉ともちがう。妻も私も心配でたまらない。居ても立ってもいられなくなり、動物病院で診てもらうことにした。

昨年来のコロナ渦のあおりで、動物病院の館内に入れる付き添いは1人に制限されていたので、私は外で待っていた。隣は瓦葺き木造平屋建ての風薬師堂に祀られた子安観音の石像。船橋市宮本6-26情のある建物がしばらく前まで残っていた。米屋だったということだが、いまは有料駐車場になっている。その角を曲がったつきあたりに瓦葺き平屋の建物があり、切妻の壁に薬師堂と書いているのが見えた。薬師如来といえば、治病や延命の仏様である。さらに乳薬師とか夜泣き薬師などと称される変種もあって、安産や子育ての仏様として庶民信仰の篤い対象になってきた。
行ってみると、お堂は鍵が掛かり、本尊も厨子の扉が閉じられていた。お賽銭をあげて、病院に戻ろうとして、お堂の手前に幼児に乳を飲ませる不思議な石仏像が祀られているのに気づいた。地蔵菩薩が幼児を抱いた石像は、いまでもあちこちで見られるが、その意匠とも明らかに違ったものである。
近づいてよく見ると、仏は胸をはだけて乳房を露わにし、右手で幼児を抱き、乳を飲ませている。それにたいして、幼児の方は両足をふんばって胸元にしがみつき、乳房にむしゃぶりついている。仏が左手に持つのは、とうぜん、蓮の花だろう。なんという仏か分からないが、どこにもいるありふれた俗人女性の姿に化身して現われ、献身的に安産と育児を守護してくれているのであろう。
仏が腰をおろす台座には「女人講中」とあるが、願主の個人名はない。そのほかに刻まれた銘は「天保十二丑(1841)年三月吉日」とあるのみである。改めて仏の顔に眼をやると、人前で平気で乳房を露わにする大らかさと裏腹に、うつむきかげんに目を伏せた表情は、どことなく憂いをおびて気高く感じられる。
石仏像はこのほかに2基ある。隣の1基は銘もなにもないが、よくある弘法大師像である。もう1基は「上丁子共(上町の子ども)」とあることから、地蔵菩薩ではないかと思われる。そのさらに1つ隣に、これは仏像ではないが、丸みを帯びた平たい自然石が置かれている。確証はないが、ひょっとすると、女性の性器に見立てた道祖神ではないかと思われる。3基の石仏像との間に境界を設けているが、明治時代初期の神仏分離までは、3基の石仏と一緒に崇められていたかもしれない。
薬師堂から動物病院に戻るとまもなく、妻がサリーを連れて病院から出てきた。診察の結果をきくと、血液検査のデータは正常だし、いまは吐き出すべき異物も体内には見あたらないといわれたという。そこで妻が2、3日前の出来事を思い出し、トリの手羽元を盗み食いして、骨まで食べていたと話すと、トリの骨は危険だから、食べさせてはいけない、はっきりと断定はできないが、その骨が腸のどこかに突き刺さり、それを無理に吐き出そうとして内壁を傷つけた可能性がある、というのである。サリーの体調不良は原因がはっきりしないが、とりあえず治療の必要はなく、体力増強の点滴をしてもらっただけで、その日のうちにすっかり元気になった。
薬師堂をお参りしたのは、ぐうぜんの出来心でしかないし、その場しのぎの神頼みで賽銭をあげたにすぎない。しかし、胸をはだけて幼児に乳を与える仏の姿は、私に衝撃的な印象をあたえた。わが家のおばあさんネコの一大事から1週間後、今度はカメラと三脚をもって、改めて薬師堂を訪れることにした。
その途中、船橋大神宮のすぐそばにある東光寺に立ち寄ってみた。この寺院は『江戸名所図会』でも取りあげられていて、明治の神仏分離までは船橋大神宮と同じ境内にあり、天道念仏を執り行っていたことで知られる。天道念仏の面影を伝えるものは見当たらなかったが、代わりに思ってもいなかったものを見つけた。なんというべきか、これから行こうとする薬師堂の石仏像と同じ形式のものが、寺の一画に祀られていたのである。
お寺に尋ねてみると、子安観音と呼ばれていて、幼くして亡くなった子どもを供養するため、若い世代の女性たちが建てたものだという。東光寺の石仏像は「天保十亥年」とあるから、薬師堂のものより2年前の建立になる。台座は二重になっていて、それぞれ「女人講中」、「深川講中」と刻んでいる。「深川」は江戸の深川かと思われる。こちらの台座は石仏像と材質が違っている。あるいは建立当初はなかったのかもしれない。
帰りがけに船橋中央図書館で、子安観音の信仰について調べてみた。というのも、薬師堂の周りで地元の人から話を聞くつもりでいたのだが、これがとんでもない見込み違いだった。周りに住んでいる人や通りすがりの誰に尋ねても、一致して知らないという答えしか返ってこなかったのである。
子安観音信仰の中心的な役割を担ったのは、『船橋市史』によれば、女たちだけで構成され女人講で、その前身は十九夜講とも女人念仏とも呼ばれたという。
子安講の前身は十九夜講で毎月十九日の夜集まり念仏などを唱えており女人念仏ともいわれた。十九夜の主尊である如意輪観音を信仰していたが、近世末期に十九夜講は安産子育てを祈念する子安講に移行して、本来儀軌にない子安観音を主尊とすることが多くなり、明治から近年にかけて子供を抱いた子安観音が盛んに造立されるようになった。
また別のところでは、こうも書かれている。
しかし江戸時代中期の安永年間(1772-80)ころから子安信仰がひろまってきた。二世安楽を願う女人信仰から現世利益へとむかったといわれる。その結果、如意輪観音に幼児を抱かせた「子安観音」の像が創案され、十九夜講と子安講と年齢による区分を行って並立する地域も出てきた。
同じ『船橋市史』からの引用だが、前者と後者では記述内容に矛盾がある。また事実関係の誤りもある。しかし、そうしたことを考慮に入れても、この2つの記述から子安信仰の歴史や子安観音の由緒を大雑把にうかがえるように思われる。
江戸時代の中期か末期に、それまでの十九夜講は子安講に変容していった。それにともない、主尊として祀られてきた如意輪観音も、それまでの半跏思惟像から転じて、子どもを抱く子安像が案出された。墓地や道端で多く目にする如意輪観音像は、両足を組んで腰をおろし、右ひじをひざにつき、右手を頬にふれて思索する姿である。この如意輪観音像に、右手で子供を抱かせ、左手に蓮の花を持たせたのが子安観音像というわけである。(中略)
私は子どもを亡くした体験がある。生まれたばかりで、まだ出生届もすませていなかった。北九州市にある毎日新聞西部本社に赴任中のことである。このとき、産院と市役所で、水子として取り扱うかどうかを問われた。生まれたばかりといっても、ごみくずといっしょくたにするわけにはいかない。無性に腹が立ち、情なかった。火葬場で骨にしてもらったあと、父親に連絡をとり、先祖代々の墓に納めるつもりだといって承知してもらった。
五来重の『石の宗教』に「石像如意輪観音と女人講」という短い論考がある。五来重は宗教民俗学者で、専門的に取りくんだ研究対象は庶民信仰だった。1909(明治四十二)年、茨城県日立市生まれだが、この論考によれば、少年時代に如意輪観音の石仏を見る機会が多かった。しかし、その印象はまことに暗かった。というのも、この石仏は間引きされた子どもの供養のために建てられたという風評があったからだ、というのである。
如意輪観音石像には、多く女人講中が建てた銘がある。貧困女性たちはその悩みを女性だけの女人講で語り、心の痛みをこの石仏に託したのであろうとおもう。その講世話人は宗門改めなどする菩提寺の住職ではなくて、放浪してきて村の観音堂や地蔵堂に住みこんだ道心者か六十六部であったろう。
文中にある貧困女性たちの「その悩み」とは、いうまでもなく間引のことである。間引は貧困の女性たちのギリギリの罪業であり、一種の自己防衛であったし、間引かなければならない胎児も多数生まれた、とも五来重は述べている。
「七歳までは神のうち」という諺がある。昔は死産が少なくなかった。医学も医療制度も未発達だったから、無事に生まれても、天然痘その他の流行病に感染すると、命を落とす危険性も高かった。もう1つは、口減らしのための間引きの問題があった。同書によれば、間引きは現在とちがって、江戸時代には刑法上の罪を問われることはなかった、ということである。どういうことかといえば、人間の誕生と育児は人知のおよばない神仏の支配する領域の出来事に見立てられていたのである。
柳田國男の「故郷七十年」に間引絵馬のことが出てくる。13歳というから明治20(1887)年ごろ、茨城県利根町布川に住んだことがあった。この町へ移ってきて驚いたのは、どこの家でも一軒に男子と女子の2人しか子どもがいないことだった。柳田が私は兄弟が8人だと話すと、そんなにたくさんの子どもを作って、「どうするつもりだ」と町の人たちは目を丸くした、というのである。
約二年間を過ごした利根川べりの生活を想起する時、私の印象に最も強く残っているのは、あの河畔に地蔵堂があり、誰が奉納したものか堂の正面に一枚の彩色された絵馬が掛けてあったことである。
その図柄が、産褥の女が鉢巻を締めて生まれたばかりの嬰児を抑えつけているという悲惨なものであった。障子にその女の影絵が映り、それには角が生えている。その傍に地蔵様が立って泣いているというその意味を、私は子供心に理解し、寒いような心になったことを今も覚えている。
それより7年前、柳田は6歳のときに、兵庫県加西市北条町で飢饉を体験している。長じて国家官僚として農政にたずさわる一方、民俗学の研究に生涯をささげたわけだが、そのきっかけは、少年時代に貧困のもたらす悲惨な情況を目の当たりにしたことにある、と同じ「故郷七十年」で回想している。
十九夜講や子安講にまつわる『船橋市史』の記述には、間引の言葉はまったく出てこない。そうだからといって、この地域の女性たちの文化遺産ともいうべき石造子安観音像が、間引という禍々しい歴史的体験と無縁であったとは考えにくいのである。
2021年8月13日
思い出すままにーー森 桂さんの「つれづれ抄」①

僕はいま病院にいる。狭心症の発作を起こし手術をしたが、その際に細菌が体中を巡り、四十度近い高熱に見舞われて長期の療養を強いられているのだ。いい機会だ、頭がしっかりしているうちに、めぐりあった人たちの思い出をしたためてみよう。しばらくご辛抱を――
麻子
いまでは懐かしくなったドーナツ盤が、勇ましい軍歌を奏でていた。昭和五十年だったと思う。銀座七丁目のバー「麻」。戦後の爪痕が残ってはいないが、そんな雰囲気が漂う。小部屋のような空間には、客が訪れることは少ない。エレベーターのない寒々とした四階まで登って来る呑兵衛はめっきり少なくなっていたからだ。

「異国の丘」「軍艦行進曲」「ラバウル小唄」……ドーナツ盤から勇ましい軍歌が流れる。すぐそばでママの麻子はへぼ将棋をしているのだ。お相手は作家の安岡章太郎さん。軍歌が途切れる。「ほら森、次の曲、次の曲」。聞いていないと思ったら、ちゃんと聞いている。将棋を打つ乾いた音が続く。すると今度は「先生に氷を入れて、薄く注ぎ足して」。商売も忘れていない。
麻子は気仙沼育ち。半農半漁の家で細々と暮らしをたてていた。東京に憧れ中学を卒業してから上京。銀座の高級クラブのホステスにたどり着く。その間にどんな苦労があったか、彼女は多くを語らなかった。こちらも、何か聞いてはならない気がして聞かなかった。
好景気に沸いていたころのクラブは、金持ちの社交場だった。客を相手にするホステスはほとんどが大金持ちになった。そこに大作家が加わった。編集者との打ち合わせはクラブが舞台となっていたから。作家もクラブで働く彼女たちの生きざまを描く。川口松太郎の小説「夜の蝶」はその代表だろうか。
麻子は文学少女だった。読書量の多さが会話の中でうかがわれた。「麻」は、客が歳を取り、四階まで登って来られなくなったので、二十数年の歴史に幕を閉じた、その後、以前いたクラブの名をとって駒込に小さな店を開いた。何度か顔を出したが、往年の面影はなく客層も変わって、足は遠のいてしまった。
十数年たって、三笠会館で開かれた「久保田万太郎さんをしのぶ会」の集まりで、安岡さんにお目にかかった時、「麻子」の話が出た。安岡さんは、つい昨日のように「懐かしいな」と目を細めておられた。しゃがれ声だった麻子。どこで余生を送っているだろうか。
「アンダンテ」
新宿ゴールデン街のはずれにあった。馬蹄型のテーブルに、七、八人も座れば満席となる。秩父の山奥から取り寄せたという、透き通った氷がカウンター越しにみなぎっている。いつも満員で二、三十分も立ち飲みしなければ座れないことも。

店の名は「アンダンテ」。ママは、なっちゃん。女子大を卒業したばかりの姿で客をあしらう。アンダンテで頭に浮かぶのはモーツアルトの、「フルートのためのアンダンテ」。なっちゃんにそのことを聞くと「私も好きよ」と認め、大いに盛り上がった。
常連客は多彩だ。当時は挿絵画家で知られ、後に小説や随筆をも書くようになった司修さん。大柄の体を持て余すように、にこにこと話に耳を傾けている。ヴァイオリニストの佐藤陽子さんも名器を持って、ちょくちょく訪れた。その日も佐藤さんに「ベートーベンのヴァイオリン・ソナタのうちで何が一番好きですか」と伺うと、「七番」と即座に答え、ケースから楽器を取り出して弾こうとするので、聞きたかったけれどもご遠慮していただいた。

冨士眞奈美さんもその一人。彼女が入って来ると、その場が華やぐ。世間話に興がのったころ、なっちゃんが「冨士さん、お嬢ちゃんから電話」と伝える。冨士さんは「じゃすぐに帰るからね」と言って電話を切り、「宿題が判らないから教えて、と言っているので家に戻るけど、その話、続けておいてね」と言って姿を消した。彼女はもう夜が白みかけたころに話に加わったが、さっきの話はとっくに終わって次に移っていた。
「アンダンテ」には、家族のような空気が流れて、時間に追われる仕事に携わっている身にとっては、ほっとする瞬間があった。いまでも、その光景を思い浮かべるのである。
冨士さんの秀作。
海底のやうに昏れゆき梅雨の月
まず足の指より洗ふ長き夜
もう、お仕舞にしようかと話し合っている時、ふらりと男性が現れた。どこかで見た人だ。「あら先生、お久しぶり」。なっちゃんが手を止めて、客を招き入れる。すぐに、その人は作家の野間宏さんだと分かった。野間さんの名は知っているけれど、代表作の一つ「真空地帯」しか読んでいない。それもかなり苦労して。人間を非人間的な兵士に変えてゆく、旧軍隊と戦争の本質を問う作品ぐらいしか知識はない。
客は僕のほかは、一組のカップルしかいない。なっちゃんと手伝いの妹さんは明日の準備と跡かたづけで手いっぱいだ。僕は父が新聞記者だったこと、大本営は戦争犯罪を隠し通し、国民を欺いた実相を暴いた「旋風二十年」という単行本が、戦後初のベストセラーになったことなどを懸命で話した。野間さんは父の名前をご存じで、じっと前を見つめながら聞いてくださっていた。
話が途切れた時、野間さんは「もう一軒行きましょうか」とおっしゃる。夜更けである。空いている店はあるのだろうか、心配になったが、その店は馴染みらしく照明を点けてわれわれを招じてくれた。小一時間経ってお勘定となった。野間さんはゆっくりと内ポケットに手を入れ財布を探している。そのとたん、背後で「財布を忘れた」という静かな声がした。僕はその日はちょうど給料日で、決して安くはないお勘定を支払った。
数週間たって「アンダンテ」に立ち寄ったら、野間さんの姿があった。連日のように僕を待っておられたそうだ。(つづく)
(森 桂)
※森 桂さんは昭和16年10月東京生まれ、41年4月、東京本社入社。横浜支局、宇都宮支局、外信部、社会部、学生新聞編集部、事業部を歴任。平成7年9月 東京本社文化報道センタ―編集委員で退職。
2021年8月10日
漫画家、サトウサンペイさんを発掘した「夕刊新大阪」小谷正一さん
——作家や画家などの若い頃の作品を「若書き」といい、勢いを感じさせるものが多い。サトウサンペイさんの場合、入社試験の履歴書を漫画で描いたというから、相当な大胆さである▼産声をあげた頃、そして戦中戦後の自分を絵にして、短い文も添えた。面白い奴(やつ)だという重役もいて、百貨店に採用され宣伝部で働き始めた。さらにはその話を聞きつけた夕刊紙の幹部から、うちで描かないかと誘われた▼そうやって漫画家サトウサンペイが生まれた…
8月7日付朝日新聞朝刊1面「天声人語」である。
サトウサンペイさん(7月31日逝去、91歳)が漫画家となるきっかけを作った「夕刊紙の幹部」とは、元毎日新聞の記者・小谷正一さん(1992年没、80歳)である。
小谷さんのことは、この毎友会HP追悼録(2021年7月15日)で天才ヴァイオリニスト・辻久子さん(ことし7月13日没、95歳)を売り出した伝説のイベントプロデューサーとして取り上げた。
小谷さんが亡くなって1年後に開かれた偲ぶ会には、辻久子さんも、サトウサンペイさんも参加している。
夕刊紙とは、1946(昭和21)年2月4日に創刊した「夕刊新大阪」である。GHQ(連合国軍総司令部)が新聞用紙の割り当てを管理、毎日新聞、朝日新聞は朝刊2ページしか発行できなかった。一方で新たに創刊する新聞には用紙を割り当てたことから、各社とも系列の夕刊紙を発行した。「夕刊新大阪」は、毎日新聞大阪本社内に編集局を置き、印刷も毎日本社で行った、と『毎日新聞百年史』にある。
創刊当時のスタッフは、編集局長・黒崎貞治郎、編集総務兼報道部長・後藤基治、整理兼企画部長・小谷正一ら。毎日新聞から出向した。
朝日新聞は「大阪日日新聞」、産経新聞は「大阪新聞」を系列紙とした。
「夕刊新大阪」創刊からのことを書いたノンフィクション、足立巻一著『夕刊流星号』(新潮社1981年刊)を紹介した記事を見つけた。

1981年11月20日付毎日新聞夕刊で、筆者は、当時編集委員の四方洋さん(2016年没、80歳)である。
記事の中に、サトウサンペイさんの漫画を連載する経緯もある。
《小谷さんのところへ大丸(百貨店)の宣伝部員が遊びに来た。「おもろい人間おらんのかい」「リレキ書をマンガで書いた新入社員がおります」「それ、つれてきてくれ」。男がやってきた。「連載やらんか」。シリごみするのを描かせた。第一回は「飛行機から宣伝ビラをまいたら、海の中へ落ちる。デパートで大売り出しの日、やってきたのはサカナばっかりだった。小谷さんは四コママンガを見て腹をかかえて笑った》
井上靖は小説『闘牛』で芥川賞を受賞したが、そのモデルは「夕刊新大阪」の小谷正一さんである。
この闘牛大会は小谷さんが企画した。毎日新聞入社同期の井上靖は、このイベントに興味を持って、小谷さんから取材をした。
毎日新聞1950年2月2日朝刊に井上靖が「『闘牛』について」を寄稿している。

《廿二年一月新大阪新聞社主催で闘牛大会が西宮球場で開かれた。…一日私も闘牛見物に会場に出掛けた。みぞれの降る寒い日だった。天候に祟られてその日の入場者は極めて少なかった。リングの中央で、角を突き合せたなりで微動だにせぬ二頭の牛。それを取巻くまばらな観客。垂れ下がっているのぼり。スタンドの所々から人々は外とうのえりを立てて、声もなくリングを見降ろしている。その会場に立ちこめている異様な空気が私の心に冷たく突き上げて来た》
《この闘牛大会は新聞社の事業としては宣伝効果からしても大きな成功をおさめ新大阪はために盛名を天下にとどろかした》
「夕刊新大阪」は、復刻版が不二出版から刊行されている。足立巻一さんが提供して兵庫県立図書館が所蔵しているものだ。
(堤 哲)
2021年7月26日
元エコノミスト編集長、高谷尚志さんが、舟木一夫さんの「高校三年生」の想い出を――フェイスブック「もういくつ寝ると<ユルリとね>」第559話転載
赤い夕陽が校舎を…。高校三年生・舟木一夫
モデルの学校は私が育った地区の女子高校だった
丘灯至夫作詞、遠藤実作曲。「高校三年生」

数々の名曲を作詞した丘灯至夫氏、いくつかの仕事へて毎日新聞の記者。
作詞家となった後も毎日新聞社には籍を置き続けており1972年に毎日新聞社を定年退職している。その際、毎日新聞社会長より終身名誉職員の名を与えられ出版局特別嘱託となる。 主に「毎日グラフ」の記者。 ということなので私より5歳ぐらい上の方は、「毎日グラフ」で丘灯至夫氏と一緒に仕事をしておりその思い出を、毎日新聞 OB の交流サイトに掲載しておりました。大島幸夫さん。
丘灯至夫というペンネームは、新聞記者は「押しと顔」(オシトカオ)である。
また毎日グラフ編集部とアサヒグラフ編集部の対抗野球大会があった時には、丘灯至夫さんの配慮で日活ロマンポルノ田中真理さんが応援に駆けつけてくれたなんていうのも紹介しておりました。なんとも羨ましい。
「高校三年生」には実は思い出がありまして、車を運転していてカーラジオをかけておりましたが多分、丘灯至夫さんだと思うんです。作曲の遠藤実さんではないとは思うんですが、まあ丘灯至夫さんということにしましょう。
高校3年生の思い出をラジオで語っているんですね。それが強烈な記憶になっておりましたので、この際、高校三年生、丘灯至夫のネット検索をしてみました。
そうしますと、赤い夕陽が校舎を…のモデルになったのは「松陰学園」。思わず ワナワナと震えがきました。 ここは女子高校なんです。私の家がご近所なもので、よく知っています。丘灯至夫さんが毎日グラフの仕事で「松陰学園」を取材にあがったときの印象を歌詞にまとめたとのことです。ここは世田谷区渋谷区目黒区の三つの区が接しているところ、「松陰学園」は目黒区です。
♪ぼくらフォークダンスの手をとれば、甘く匂うよ、黒髪が~♪
普通、男女がフォークダンスをするというと、男女共学をイメージしますよね。しかし女子高には男子はいないことになっている???
<第560話>女子高校に男子学生がいた秘密
松陰学園は男女共学の幼稚園を併設してました。私の同学年ぐらいの男の子も松陰幼稚園に通っているのがいました.
目黒区世田谷区渋谷区の接点の目黒区側に位置しているわけですので、三つの区から男の子女の子が通っていました。ですのでここには男子学生というか、男の子の幼児がいたことは間違いありません。
渋谷区側の飲食店2代目男の子、松陰幼稚園に通っていて、高校卒業後は店の後を継ぐべく修行にはげみ、松陰学園にもしばしば出前を持って行ったという体験があります。廊下で小走りの女子高校生3、4人とすれ違うと、スカートの裾から女の匂いがこぼれてくる。女子高校生の集団の中に出前を持ってったこともあって、視線がこちらにじっとそそがれると恥ずかしかったな。二代目は中高一貫の男子校に進学したもんで、女子の集団には極めてナイーブな反応を示します。
松陰学園の中には「高校3年生」の記念石碑があるのですが、二代目はそんなのがあるの?気がつかなかったなー。校門を入ると、何本か木が植わっていたけど、あれニレって言うの? 道路拡張に伴い二代目は店を閉めて、いまは全く別なところに居住しています。松陰学園を探訪された方がネットに載せておりますので、引用させていただきますと説明板には以下のように記されていました。
作詞家丘灯至氏は昭和37年、新聞記者として高校の文化祭の取材にあたっていた。取材先として訪れた松陰学園では、当時、定時制高校があり、文化祭のリハーサルで男女の生徒が手をつなぎ、フォークダンスを踊っていた。
そこで最初に浮かんだのが「フォークダンスの手を取れば甘くにおうよ黒髪が……」というフレーズであり、詩が作られ、遠藤実とのコンビでこの歌が生まれるに至った。
社会に飛び立とうとする10代後半の若い人たちが夢や心を大事に、抒情性を豊かに育んでほしいという願いが、舟木一夫氏に歌われ、瞬く間に、多くの人々の心を捉え、現在も皆が声を合わせて歌える国民的な歌となっている。
つまり定時制高校があって、そこは男女共学。つまり幼稚園と定時制には男の子がいた。松陰学園では数少ない貴重な男の子を丘灯至夫さんは目撃したことになるんですね。
二代目は松陰学園に定時制があった?知らなかったなー。出前があっても昼か夕方で、夜は行かない、男子学生の姿は見たことがなかったなあ。
仕事をしながら勉学をしたいという男子学生に門戸を開いた松陰学園の経営者も立派ですが、それに応じた男子学生たちもたたえるべきでしょう。おかげで後世に残る「高校3年生」神話が学園のものになったのですから。みんなこの男子学生たちのおかげです。定時制も女子ばかりだったらあの名曲は生まれなかった?!
今は松陰学園は男女共学、定時制は今はないようです。
高谷さんのフェイスブック。
2021年7月19日
一日駅長で展望車に乗ってしまった百閒センセイ
酒井順子著『鉄道無常 内田百閒と宮脇俊三を読む』(角川書店)に、百閒センセイ(当時63歳)が東京駅の一日駅長を務めたときのことが書かれている。
制服・制帽で東京駅へ現れ、一日名誉駅長の辞令を受けた。駅構内を視察したあと、12時30分発の第3特別急行列車「はと」が発車する際、「出発進行」の合図を出すハズだった。
ところが百閒センセイ、発車間際に最後部展望車の展望デッキに乗ってしまったのだ。
列車は、そのまま発車、百閒センセイは熱海まで乗車したという。
「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」
というセンセイだけのことはある。
同行したヒマラヤ山系こと平山三郎さん(国鉄職員)には事前にこの計画を話していたようだ。
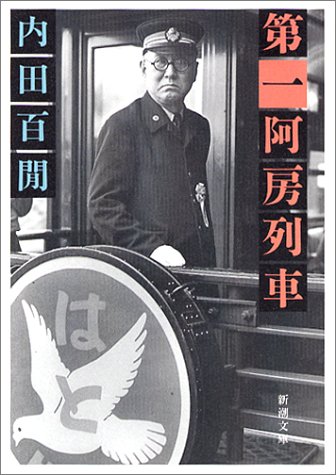
ネットで検索すると、新潮文庫の表紙に、そのときの写真が載っている。
1952(昭和27)年10月15日。一日駅長は、国鉄の80周年記念イベントだった。
東京駅は百閒センセイ、新宿駅は毎日新聞OBで当時政治評論家・阿部真之助(元大阪毎日社会部長、東京日日政治部長、学芸部長を歴任。その後NHK会長)、上野駅は元日経新聞の経済評論家・小汀利得、渋谷駅は歌手の藤山一郎、有楽町駅も歌手の越路吹雪…。
多彩である。国鉄が黒字経営の時代だった。
図書館で毎日新聞の紙面を検索すると、その日15日の夕刊社会面に「有名人が一日駅長」という見出しで載っていた。四ツ谷駅では荒木町花街のキレイどころ7人が改札に並び、「(切符に)ハサミを入れるかたわら、乗降客に香水をシュッシュッとふりかけるというサービスぶり」。写真付きだ。
写真はもう1枚。有楽町駅の越路吹雪で、見出しは「訓示早々コンパクト」。コーちゃんは、遅刻したらしく、訓示の後、「早速コンパクトを取り出し、女駅長のみだしなみとばかり、軽くお化粧をして構内視察を行った」。
今から69年前である。鉄道開通は、1872(明治5)年。毎日新聞は同じ年の2月21日創刊だから、鉄道とともに、来年150年周年を迎える。

さて、酒井さんの著書にあるもうひとりの鉄道作家・宮脇俊三さんも、取手駅で一日駅長をしている。1985(昭和60)年、58歳の時だった。
楽しみにしていたのは「酔いつぶれた客を揺り起こしたい」。
「取手です。終点ですよ」。降りていく客を眺め、達成感を覚えた宮脇は「胸を張って駅長室へ引き揚げた」のだった、と酒井さんは書いている。
「鉄道の『時刻表』にも、愛読者がいる」
鉄道全線完乗車・宮脇俊三さんの名言である。
(堤 哲)
2021年7月19日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その14 ワクチン接種の一日(抜粋)
文・写真 平嶋彰彦 毎月14日更新。
全文は http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53443545.html
先月の22日、新型コロナウィルスの第1回目のワクチン接種を受けた。
場所は自衛隊の大規模接種センターになっている大手町合同庁舎。12時の予約だったが、40分前に会場についた。早すぎたかなと思ったが、待たされることもなく、てきぱきと案内してくれ、あれよあれよという間に接種を終えただけでなく、その場で第2回目の予約もすますことができた。接種のあと、15分ほど経過をみていたが、どうやらワクチンの副反応はなさそうだった。
私の住んでいるのは習志野市で、ワクチン接種の予約受付は5月17日からだったが、こちらの不慣れや不手際もあり、うまくとることができなかった。予約は妻がスマートフォンを使ってとろうとしたのだが、繋がったときには、いつも予約はいっぱいになっている。一昔か二昔前に、ブルース・スプリングスティーンやローリングストーンズといったミュージシャンの公演チケットを電話予約して愕然としたことがある。発売日当日、受付開始と同時に予約を入れるのだが、よさそうな席はたいてい売り切れてしまっているのである。ワクチン接種は音楽コンサートとは違う。いい席も悪い席もない。希望する人には漏れなく接種するのが建前である。不慣れや不手際は行政の側でも同じかもしれない。そのうちになんとかなるだろうと、のんびりかまえていた。
ところが、街歩きの仲間たちから、ワクチン接種の予約がとれたとかとれないとか、メールで報告や問合せが入ってくるようになった。街歩きの仲間は9人いて、1人を除けば、すべて60歳代後半から70歳代の高齢者である。しかも半数はガンなどの基礎疾患を持っているから、ワクチン接種は切実な関心事なのである。私の場合は高血圧と糖尿病で、一昨年の暮れには肺炎に掛かっている。感染すると重症化し、命を落とす可能性が高い。
それに加えて、従来のものより感染力の強いアルファ型とかデルタ型とか称される変異ウィルスが発見されているのが気になった。それがいつの間にか国内に持ち込まれ、急速に感染が拡大しているということである。3密を避けるとか、マスクをする、うがいをする、手を洗うといっても、どこまですれば安全で安心なのかとなると、確かな指標と根拠が示されているわけではない。
デルタ型の変異ウィルスについては、感染力が2倍近いといわれている。通勤電車やスーパーマーケットはうーんと思うほど混雑していても、アルコールを提供する飲食店と違って、厳しい営業規制を受けていない。ウィルスの方は日進月歩で進化し攻撃力を強めているのに、人間の方はこれまでのような感染対策で大丈夫なのだろうか、私のような医学的素人には判断がつかない。分からないから自ずと不安にもなる。自分が感染するのも嫌だが、人に感染させるのはもっと嫌である。そんなことから、ワクチン接種は早めに受ける努力をした方がいいと思うようになった。
それから20日ほどして、習志野市のホームページを開くと高齢者のワクチン接種方法を抜本的に変更し、6月7日までに予約をすませていない人には、市役所が接種日時・場所を指定し、6月中旬から年齢別に順次、郵便で通知することになった、というのである。私と妻の場合は7月7日に発送される予定になっていて、高齢者の接種は、9月中旬までにすべて完了させる計画だというのである。
6月14日、同居している息子が勤め先の会社から妻にメールを入れてきた。たまたま新型コロナについて調べていたら、大型接種会場の大手町合同庁舎は予約が空いている。ここは習志野からの交通の便がいいし、実施しているのは自衛隊だから仕事はきちんとしている。習志野市からの通知を待つことはやめて、こちらに予約を入れた方がいいと思う。ついでに、二人でご飯を食べてくるというのもいいかもしれない、というのである。
ふだん息子は用事があってこちらから連絡しても返事もよこさない。滅多にないことだから、なにか思うところがあったにちがいない。考えてみれば尤も至極で、いわれる通りに予約することにしたのだが、私と妻の都合が折りあわず、接種日は一緒にならなかった。

そんな次第で、大手町合同庁舎でワクチン接種をすることになった。その帰りがけのことである。会場の出入口で何人もの人たちがスマートフォンのカメラで写真を撮っていた。私も彼ら彼女たちに倣って、バックから一眼レフのカメラを取りだした。そういえば、会場内のあちこちで撮影と録音を禁止する立札を見かけた。
私は前歴が報道カメラマンだったせいで、駄目だといわれると、隠れて撮ろうとする悪癖がいまでも抜けきらない。立札はもちろん報道メディアに向けたものではない。接種に訪れた人たちにワクチン接種の妨げになる行為は遠慮して欲しいということだろう。見方を変えれば、いまや誰もが何かあれば写真やビデオに記録する時代になったのである。
こうした現象はスマートフォンの普及が大きく影響している。かつてのように専門的な撮影技術は重要視されなくなった。写真は目の前の事物や出来事を正確に写しとると同時に、自分がその時その場にいた、という事実の証明にもなりうる。日記をつけるのと同じように、誰もが写真を撮るようになったといってもいい。連載その12でも言及したが、ドナルド・キーンは『百代の過客 日記にみる日本人』のなかで「日記をつけるのは、歴史家にとってなんの重要性もない日々を、忘却の淵から救い上げることである」と述べている。
私が2009年まで勤めていた毎日新聞社は合同庁舎から目と鼻の先にある。知り合いの後輩もいるから、立ち寄ってみるつもりでいたが、時計を見るとまだ12時をまわったばかりである。夕刊の校了までは1時間以上もある。それまでどこかで時間つぶしをすればいいのだが、それもなんとなくうっとうしいので、街歩きをして帰ることにした。

合同庁舎があるのは日本橋川に架かる神田橋の皇居側である。連載エッセイその11で八百屋お七に言及しているが、事件当時に火付加役だった中山勘解由の邸宅は神田橋のすぐ外側にあった。また神田橋の近く(神田錦町2丁目)には、お七の事件から5年後になるが、それまで湯島にあった護持院(知足院)が移転してきた。多くの寺院が江戸市中の内から外へと移転させられたのと逆方向になる。護持院は将軍綱吉とその生母桂昌院が数十度も参詣し、その庇護のもとで隆盛を極めたとされる。連載その11を書いた後になってから知ったのだが、桂昌院の出自は京都堀川通西藪屋町の八百屋仁右衛門の次女ということである。それが事実だとすれば、将軍綱吉の生母はお七と同じ町人身分で、実家の生業も同じ八百屋稼業だったことになる。
神田橋から雉子橋までの日本橋川沿いの一帯は、『江戸切絵図』をみると、火除地になっていて、護持院原と呼ばれた。護持院原の地名由来になった護持院は1717(享保2)年に焼失するが、幕府は再建を許さず、音羽の護国寺に合併された、ということである(註5)。
神田警察通りに出て、西側を眺めると、千代田通りとの交差点の先、護持院原のすぐ北側とみられる箇所に、戦前の築造と思われる古めかしいビルが見えた。近づいてみると取り壊されると聞いていた博報堂ビルに紛れもないのだが、どこかようすがおかしい。よくみると西側の3分の1がなくなっている。建築デザイン的に特徴のある東側の塔屋と円柱の並ぶ正面中央を残すというよりも、おそらく復元する形で、テラススクエアと呼ばれる高層の複合ビルに再開発したものとみられる。
東側は広場に整備されていて、ビルの下では若いサラリーマンの男女が1列に腰かけて、昼食の弁当を食べていた。対面の食事に比べて新型コロナの感染リスクも少ないし、目の前は木立の林になっているから、雨さえ降らなければ爽快な気分になれる。私の会社勤めをしていたころにはあまり見かけなかった風景である。コロナ渦の新しい世代が見つけた新しい生活スタイルなのかもしれない。
テラススクエア西端を右折すると神田神保町の書店街に通じる裏通りがある。書店街は竹橋の毎日新聞社から歩いて10分もかからない距離である。仕事が忙しくないときは、職場の同僚たちとこのあたりまで出かけて、昼食をとった。そのあと、本屋めぐりをするか、喫茶店でお茶を飲むとかするのである。
神保町は昨年の3月20日に訪れることがあった。街歩きの仲間の1人鈴木淑子さんが西村陽一郎の教えている美学校の写真工房(神田神保町2丁目)に通っていて、共同作品展の案内をもらったのである。
この日は3連休の初日にあたっていた。都営新宿線の岩本町で下車し、写真を撮りながら神保町の美学校まで歩いたのだが、意外なことに、休日は閑散としているはずの書店街がたくさんの人で混み合っていた。靖国通りとすずらん通りの間にひっそりした路地があるのだが、そこにはミロンガ・ラドリオ・さぼうるなど知る人ぞ知るという風情の喫茶店が点在する。神保町界隈で一番なつかしいのは、この路地の佇まいである。覗いてみると、どこの喫茶店も外で空席を待つ人がならんでいた。路地裏のうらぶれたような喫茶店が、いつの間にか脇役から主役に抜擢され、観光名所として脚光を浴びているのである。
それより1週間後の3月27日、仲間たちと大森の街歩きをする予定だった。月に1度の恒例行事で、これが100回目だった。ところが3月24日になって、東京都の新型コロナウィルスの感染者数が急増して40人に達したというニュースが流れた。その日の夜、幹事の福田和久君から連絡があり、感染が鎮静化するまで、街歩きは延期しようということになった。東京都の小池百合子知事から、新型コロナの感染拡大を防ぐため、週末の外出を自粛する要請が出されたのはその翌日である(以下略)。
2021年7月19日
三原浩良さんに原稿を真っ赤にされたノンフィクション作家

西部本社で報道部長をつとめ、退職後、葦書房社長、弦書房代表として良書を出版し続けた三原浩良さん(61年入社、2017年没79歳)の名前を18日付け読売新聞の読書欄で見つけた。
ノンフィクション作家澤宮優さんが『巨人軍最強の捕手』(2003年晶文社刊、現在は『戦火に散った巨人軍最強の捕手』河出文庫)を出版するときのことだ。
巨人軍最強の捕手とは、ビルマで戦死した吉原正喜捕手である。熊本工業では川上哲治(巨人軍監督)とバッテリーを組み、甲子園で準優勝した。のちに打撃の神様と呼ばれる川上は、吉原捕手を獲得するために、ついでに入団契約になったといわれる。
澤宮さんは、川上さんからも取材をして、半年かけて原稿を書き上げたが、原稿を送った20社から出版を断られた。知人の紹介で葦書房にたどり着く。
《葦書房の三原浩良社長は、すぐに原稿を読んでくださり、出版を決めてくださった。ただし何度も推敲をさせられ、目が回るほど赤字が入った。だが、そのお蔭で作品は、柔らかく練れた内容に変わった》
《その年の秋のある日、突然段ボール箱が葦書房から送られてきた。そこには私の原稿があった。手紙には「ある事情で出版ができなくなった」という報告が書かれてあった。後日新聞記事で知ったのは、ある一件で社長、社員が退職せざるをえなくなったトラブルがあったことだった》
◇
「葦書房 オーナーが社長解任 全従業員も退社の異常事態」と読売新聞は報じた。
三原さんは、1994(平成6)年に葦書房の社長になった。前社長の死去に伴うもので、8年間、黒字経営したが、2002(平成14)年にオーナーに解任される。
「株(出資金)の買い取り価格や、私の後継社長をめぐってどうしても折りあうことができず、ついに私の解任となったのである」と三原さん。
社員も8人全員が退社し、2002年暮れ、弦書房が船出した。
三原さんは、こう書き残している。
《翌年5月から新生弦書房のあたらしい本が次々に書店に並んだ。高木尚雄『地底の声』、島尾ミホ・石牟礼道子対談集『ヤポネシアの海辺から』、菊畑茂久馬『絵かきが語る近代美術』、渡辺京二対談集『近代をどう超えるか』、中山喜一朗『仙厓の○△□』、多田茂治『夢野久作読本』『玉葱の画家』などなど、いずれも旧知の著者たちの力作ぞろいである。数えてみるとこの年は5月からの半年の間に7点も刊行している。
その後も2004年10点、2005年9点、2006年17点、2007年16点、2008年11点と新刊を送りだしてきた。
なかでも野見山暁治『パリ・キュリイ病院』、佐木隆三『改訂新版 復讐するは我にあり』はいずれも大手出版社が重版をしぶって絶版になっていた本の復刊で、小出版社ならではの仕事として印象に残っている。
前者は最初に講談社、のちに筑摩書房が刊行した野見山さんの最初の著書で、野見山ファンからの復刊の要望が強いことを知り、25年ぶりに復刊した。今年になって重版したと聞いてうれしかった。既刊書が売れなくなっている出版不況のなかで、息ながく売っていくことは至難のことと言ってよい。
後者は佐木さんの直木賞受賞作だが、これも絶版になって久しく、著者の希望であらたに手を入れて「改訂新版」として刊行、版を重ねたあといまでは講談社文庫にもはいっている。
渡辺京二『江戸という幻景』は、葦書房時代に刊行した不朽の名著『逝きし世の面影』(いまは平凡社ライブラリー)の姉妹編とも言える著作で、向こうが来日外国人の目を通して描かれた江戸・明治の姿だとすれば、こちらは日本人の目がとらえた江戸の人々の生きいきとした諸相を活写した書きおろしで、刊行当初から増刷をつづけている。
こうして歩みだした弦書房は創業10年を過ぎ、著者や関係者の協力をえて順調な歩みをつづけているが、2008年、後事を小野君に託して弦書房を去ることにした。
当初から「70歳引退」と心づもりだったが、予定を一年過ぎていた。「葦書房の灯を消すな」という声に応えることができたのであろうか》
そして2008年郷里の松江に戻った。
出版不況といわれた時のアンケートに「私が葦書房を引き受けた時考えたことは、絶対に大きくしないということだった。どうしても必要とする人に向けて、少々高くても我慢して買ってやろうと言われるような内容を備えた本を作るしかない、と思っている」と答えている。
良書がすべて、なのである。
葦書房時代、石牟礼道子編著『天の病む 実録水俣病闘争』(1974年1月刊)を出版した。執筆者に、石牟礼道子・渡辺京二・江郷下一美、三原浩良、日高六郎・杉本栄子・浜本二徳・川本輝夫・田上義春・松浦豊敏・本田啓吉、富樫貞夫、宮沢信雄ほかとある。
元ソウル支局長・論説委員の下川正晴さんは、この毎友会HP(2020年7月7日)で自著『占領と引揚げの肖像BEPPU』を紹介しているが、『忘却の引揚史―泉靖一と二日市保養所』(2017年刊)、『日本統治下の朝鮮シネマ群像~戦争と近代の同時代史』(2019年刊)といずれも「弦書房」からである。
三原さん自身の著作は『熊本の教育』『地方記者』『噴火と闘った島原鉄道』『古志原から松江へ』。編著に『古志原郷土史談』『当世食物考』などがある。
私は一緒に仕事をしたことはなかったが、同期入社の片山健一(故人)の前の西部本社報道部長だった。
(堤 哲)
2021年7月9日
報道レースは本社が「金」―68メキシコ五輪の社報

この写真は、64年東京五輪の閉会式。浴衣の日本人女性の手にキスをするソンブレロを被ったメキシコ男性。68メキシコ五輪への引継ぎのつもりか。
日本外国特派員協会(千代田区 丸の内 3-2-3「丸の内二重橋ビル」5階)で8月6日まで開かれている1964東京五輪の写真展にあった。
断捨離中に何故か、昭和43(1968)年11月1日付社報が出てきた。
見出しに
メキシコ五輪、報道レースは本社が「金」
特派員←→各本社が一体化
みごとカラー印刷
原稿の流れもスムースに
特派員団は、8人。キャップは、社会部デスク牧内節男(当時43歳)。メキシコ臨時支局の支局長である。
社会部・大桶浩(当時37歳、1994年没63歳)
運動部・岡野栄太郎(当時38歳、2020年没90歳)▽浮田裕之(当時39歳)▽奈良井輝(大阪、当時38歳、2010年没80歳)
写真部・阿部三郎(当時42歳、2013年没87歳)▽松野尾章(当時35歳、2008年没76歳)
連絡部・大川延司(当時36歳、2011年没79歳)
元気なのは、ことし96歳を迎える牧内さんと、浮田さん92歳だけか。
牧内支局長の現地報告が載っている。
《社員のみなさん「ポエナスタルデス」(こんにちは)——私たちの朝のあいさつは「ポエノスデイアス、コモエスタウステ(おはよう、ごきげんいかがですか)「ムイビエン・ウステ」(大変よい、あなたは?)「ムイビエン」と始まる。時差(15時間)の関係から毎晩寝るのが午前2時すぎだから「コモエスタウステ」という言葉にも実感がこもる。
大阪外語スペイン語科を出た奈良井特派員は別として、他は日本を出るまでスペイン語は少しも知らなかったが、阿部特派員などは写真部との電話応答の中で無意識のうちに「シー・セニョール」(はい、わかりました)という言葉が飛び出るから大したものだ》
「こんにちは」は、ブエナスタルデスと旅行書にはあるが、現地の発音は「ポエナス」なのであろう。
「競技が終えて、余ったドルを全員に分けて、好きなところを旅行して帰国するよう、言ったんだ。名支局長だろう」と何かの折に聞いたことがある。
◇
毎日新聞のHPには、《第19回メキシコ大会は、112カ国と地域から約5500人の選手が参加し、1968(昭和43)年10月12日から27日まで開かれた。日本からは183人の選手が参加し、金11、銀7、銅7、計25個のメダルを獲得した。日本では大会期間中に川端康成さんのノーベル文学賞受賞が発表され、12月には東京都府中市で「3億円事件」が発生した》とあり、その脇に釜本邦茂がサッカー3位決定戦でゴールを決める写真。阿部三郎撮影とある。
(堤 哲)
2021年7月2日
レイルウェイ・ライター、種村直樹君を偲ぶーー牧内節男さんの「銀座一丁目新聞」から
柳 路夫。



それは種村直樹君に呼び止められた感じであった。行きつけの古本屋の前を通ったら種村直樹著『時刻表の旅』(中公新書・定価380円)が眼にとまった。どれも100円の値段のついた新書版の本を並べている場所である。早速買った。種村君とは昭和38年8月、毎日新聞大阪社会部で知り合った。彼は府警察本部の記者クラブにいた。入社4年目の事件記者であった。
東京社会部で筆頭デスクをしていた立川熊之助さんが大阪の社会部長になるというので私を大阪のデスクとして連れっていった。大阪にいたのは1年半であったが、実りの多い記者生活であった。大阪社会部の多くの人材を知った。後で大いに役立った。一緒にデスクになった檜垣常治君とは後にほぼ同時に役員となり、助けたり助けられたりであった。政治部にきた岩見隆夫君、サンデー毎日にきた徳岡孝夫君、八木亜夫君、武田忠治君らに知的刺激を受けた。
種村君はもともと学生時代から汽車旅が好きで、それが鉄道記者生活を通じて助長され、「レイルウェイ・ライター」にまでになってしまった。昭和48年、毎日新聞をやめるのは当然の帰結であった。この本にも昭和48年4月武蔵野線府中本町―新松戸間開業の日以来、フリーのレイルウェイ・ライターとして、趣味と仕事の境界が判然としない日々を過ごすことになると書いている。当時私は論説委員であった。種村君が毎日新聞を去ったのを後で聞いた。
この本は昭和54年8月25日の初版である(私の手元にある古本は昭和55年11月20日6版)。既に著書は『周遊券の旅』(ブルー・ガイドブックス)7冊も出版している。『時刻表』1本で生きた男といってよい。「数字と駅名が無数に並ぶページを捲ると、各地を走る列車の姿が目に浮かび、大きな駅のコンコースの雑踏、ひなびたローカル線を行く車両のきしみも伝わってくる」と表現する種村君である。まさに時刻表にとりつかれた男である。平成26年11月26日なくなった。享年78歳であった。
子供の頃よく歌った歌『汽車』(作・不詳、曲。大和田愛羅)を口ずさんで彼を偲びたい。
「今は山中 今は浜
今は鉄橋渡るぞと
思うまもなくトンネルの
闇を通って広野原」
※種村直樹さんは1936年、大津市生まれ。京都大学法学部卒。毎日新聞記者を経て1973年からフリー。レイルウェイ・ライターとして鉄道と記者旅をテーマに著作を続けた。2014年、転移性肺がんにより死去、78歳。
(プロフィール写真、名刺は種村さんの公式ホームページから)
※「銀座一丁目新聞」のURLはhttp://ginnews.whoselab.com/
2021年7月2日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その10(終わり)
追悼集「岸井寿郎」には「正力松太郎氏との秘話」など5編の遺稿が掲載されています。激動の昭和時代に直面した出来事とさまざまな方々のお名前が出てきます。
「日記より」⑤昭和36年7月1日
午後、成格(当時高校2年)が友人の吉田昌光と同道で帰ってきた。只ならぬ気配に、大きな荷物をかかえて応接に入って来た。昨夜は10時すぎにやっとスピーチコンテストの原稿が出来上った状態では、励ましのため「一位間違いない」といったものの、とうてい入賞するとは思わなかったので、何事かと瞳をこらすと、いきなり「どうです」という。「入賞か?」「しかも優勝です」「ヘエー、それは大出来だ」と答えて、じっと顔をみる。「ここ1カ月めっきりやせたと思われる顔に精悍の気をたぎらせて「まだ夢のようです」と優勝当時の状況を説明する。番外から始まった入賞発表が2位まできた時はガックリして、外に出て風にでもあたりたいと思ったトタン名前を呼ばれ、一瞬何のことかわからなかったとのこと。
昭和36年7月2日
成格、巍次を連れて日本橋の「橋本」へうなぎを食いに行く。成格は昨日の興奮が残っているようだ。それに疲れがアリアリと顔にみられる。うなぎでも食わせて回復させるほかない。それにつけても「お祝いにビールを飲ませてほしい」というのでやむなく承知した。良くないことだが折角の勝利の日だ仕方がない。しかし、咳がひどいようだ。若い者は健康の持ち方を知らないから、コンテストに夢中になって身体中がコッたのだろう。アンマが一番良いんだが、だるくてやってやる気がしない。
昭和36年7月29日
午後4時すぎても32度。何という暑さか。印度人が40―50度の中で暮らすというのがどうにも考えられない。人間という奴はどんな所でも食さえあれば住むものらしい。しかも人類史上、最も早く開けたのは暑い印度や、中近東にアフリカだった。やはり身に一糸もまとわない生活でなければ成立しなかった原始時代を想像すれば酷暑地帯が最初というのもうなずける。ダーウィンが人類の発生をアフリカと言い、“ミッシングリンク”を予言した事はさすがに大思想家、大研究家として観測に誤りなかったことに頭が下がる。今後、人類の古い歴史が開かれてくれば数々の面白い事実が発見せられ、また想像せられるであろう。自分存命中にはこのような興味ある書物が出るとは考えられぬが、今後の人は楽しみだ
昭和36年8月7日
連日の降雨ですごしやすくなった。午後1時27度。今年は大変な豊作であろう。6年続きの豊作で天下は泰平。金さえあれば何でも手に入る時代が来た。世の人は血まなこになって金を追い右往左往するだろう。それも困る。成格が何か教育問題で悩んでいるようだが、近いうちに言いきかせなくてはならない。中、高校時代、誤まらずに進ませるには、親がつききりでみてやらねばならぬ。早くそういう時期が過ぎてもらいたいものだ。
昭和36年8月8日
立秋、自唱して嬉しい。今年の暑さにはほとほと参った。これからは一日一日と涼しく美事な果実が得られる。立秋には文人の遺文が多いが、一種の喜びの中に寂しさがつきまとうのはどういうわけか。読書のシーズンであり、馬肥ゆる季節で、人もまた肥える嬉しい時期でありながら、これを賛美する喜びの文章は少なく淋しさがいつもつきまとう。草木の何となく衰えるサマが人生の終盤を想起せしめるためだろう。人間はいつまでも生きたいのが本心であってみればやむをえない。しかし、名文の書き手が若い人であったうえとは違った遺文が多くなったかもしれぬ。しみじみとする文章は若い者には書けない。(つづく)
昭和39年5月28日
古稀の祝のことを想い出す。あれからもう2年になる。今日また73歳の誕生日のため大井クラブで例の近親の連中を集めて一席をすごすことにする。あいさつをする。
僕の誕生祝を諸君とともにするのはこれで3回目である。あの時と今日とで満2年になるが、どんなに変化したであろうか。イヤ余り変っていない。一面から言えばみんなに大きな変動がなかった証拠である。昔は正月が全国民の誕生祝であって僕の郷里では誕生祝は生まれた翌年のその日にやるだけでやらなかった。だからバースデーというのは、どうもピンとこない。白人社会はとくにこの日を重んずるらしいので例の日本人の物真似で近頃大変盛んである。悪いことではない。祝いたく祝えるものは祝うが良い。一休禅師だと思うが、「門松や冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし」と詠んでいる
正月が全国民のバースデーに相当(年がわりする)する慣習の中で住んだものの本当の心境であろう。若き者は喜びにあふれ、老いたるものは一里塚のいよいよ終末に近づけると思って各々異った心境で新年を迎えるであろう。小生も一里塚が73を数える。
昨日、ネール・インド首相が突如他界した。マスコミは一斉に大騒ぎの報道である。74歳だそうだ。僕の来年だ。何ものも逃がれることのできない瞬間がきたのだ。僕にもいつそれがくるかもしれないと思うと、しみじみと「めでたくもあり、めでたくもなし」である。
ただ今日、最も近しいみんなが、一堂に会して会食し近況を語り合うことは、誕生日であろうとなかろうと良いことに違いないとの意味で、今席の集りも意義がある。みわたす限り、みんな丈夫で結構。生活も一日一日進歩安定していく様子で結構である。
昔、僕が新聞社にいたころ、時のトップクラスの財界人で藤原銀次郎と製紙界に覇を争うていた大川平三郎という人があって、藤原氏のむこうを張って富士製紙を持っていた。それが古稀の祝いか、還暦の祝いであったか、帝国ホテルの大部分を借り切って大盤振る舞いの大宴を催した。当時は小生も思想的にも生活的にも余リピンとこないで「バカバカしい催しだ、実業家というものは妙なところに喜びを持つものだ」と冷笑をもって列席したことがある。今から30年以上も前のことである。
それから間もなく王子に合併せられ、製紙の天下は藤原のものとなった。爾来、製紙界といわず財界においても藤原の声望はますます上ったが、藤原氏はいつかな王子を去ろうとはしない。社内は人事の行詰りで窒息しそうな空気であった。いたずらっ子の小生が、太平洋石油株式会社を創立して藤原氏をかつぎ上げて藤原氏を王子から去らしめたものだ。当時の500円の会社で、今の金で20か30億円の会社である。僕にも創立者として中心の一人としてやってもらいたいという話であったが、関係者の大部分を役員に入れてもらうことを条件にして私は役員にはならなかった。
話をすれば大変長くなるので略すが、それから幾変遷、王子製紙は財閥解体、独禁法のため沢山の製紙会社にわかれてしまった。とにかく変化の激しい時代に生きてきた小生のごときは語れば尽きるところのないほどの激動と興亡の試練を経てきた。その結果は碌として73歳の誕生を迎えることになった。
先日、交詢社で久し振りに岸田幸雄氏(元兵庫県知事)に会った。色々懐旧の話の末に岸田曰く「君は我々同窓中では、最も活動的な男であったが、結局これというものを握らなかったネ」といった。これは少々小生を椰楡したものであったろう。「つかむというのは何だネ? 俺は天下をつかもうとしたができなかっただけだ。君は何かつかんだかネ」彼黙す。「参議院でもつかんだつもりか。イヤ、君は金を、それも僕がいえば小金をつかんだのだろうが、金は金でいつまでいっても金だ。大小はあってもネ。それも社会を左右するほどのものならともかく、ただ生活が派手にやれるほどのものじゃないか。五十歩百歩だよ。マァーお互いにゴールに近寄っただけのことだ」。(「日記より」おわり)
「追悼集」には、告別式の写真をはじめ、三豊中、三高時代から成格さんのお宮参り、軽井沢時代、そして最後に一家の写真が掲載されています。その一部を紹介します。
・成格さんお宮参りの日。昭和19(1944)年の衆議院議員時代(玉川用賀自宅)
・軽井沢の鬼押し出しにて
・成格さん英語スピーチ優勝を記念して(昭和36年7月)
・大井の自宅にて




【岸井成格さんの父・寿郎さん=番外】
長い紹介になりました。読み直しながらフェイスブックに連載して、何とも言えない爽やかな気持ちに浸っています。それはこの追悼集をいただいた30年ほど前にくらべて、世の中が殺伐としているからだと思います。とりわけ、安倍・菅二代政権の下で続く政治の現状の下で。そして人間どう生きるべきか、政治・事業はいかにあるべきか等々について、改めて目を開かせられた思いです。
この端正な追悼集には、序文もあとがきも奥付もありません。編集・発行された方のお名前もありません。「岸井寿郎さんと家族について、最低限伝えておきたいことを記しておく。読むも自由、読まぬも自由だ」と考えたのでしょうか。
岸井寿郎さん 1891年5月28日生、1970年10月1日没。79歳。岸井成格さん 1944年9月22日生、2018年5月15日没。73歳。

2015年に頂いた年賀状が最後でした。2017年暮れには、弟・巍次さん(71歳)、甥・大太郎さん(62歳)永眠の喪中はがきが届きました。
岸井成格さんは、父・寿郎さんの精神を受けついで生き抜いたのだと思います。それだけに、73歳という若さで亡くなられたことは残念でなりません。
岸井さんを知る毎日新聞のみなさんが中心になって、岸井さん父子の生きざまを世の中に知らせる本を出版してほしいと思います。
2018年6月3日付サンデー毎日に掲載された倉重篤郎さんと佐高信さんの岸井成格さんへの追悼文を紹介しておわります。
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは2021年6月28日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その9
追悼集「岸井寿郎」には「正力松太郎氏との秘話」など5編の遺稿が掲載されています。激動の昭和時代に直面した出来事とさまざまな方々のお名前が出てきます。昭和史の一断面として貴重だと思います。
「正力松太郎氏との秘話」⑤
僕が東日をやめてからは、日本倶楽部に顔を出すことが多くなった。正力氏は常連で、ほとんど倶楽部を自分の別事務所のように使っていた。岩田宙造、有馬忠三郎、原邦造等も碁の好敵手で、正力氏は顔をみると何をおいても「おい、岸井君一番」と、一番どころでない数番、互いに毒舌を楽しみながら闘う仲であった。そんな中で、陸軍の横暴は次第にこうじ、僕はかつがれて東条内閣の選挙に立候補して衆議院に出た。
それからの時代は今度は日本そのものをひっくりかえして終戦を迎えた。追放の二重パソチをうけて働らくにも働けない。これから社会をどうリードしようもない。既に50の坂を越して今さら何をかいわんや。静かに余生を送ろう。それが当時の心境だった。日本倶楽部で碁仲間と談じている時、永野護君が「一寸」といって別室に連れていった。
「岸井君、実は正力君が戦犯容疑で入獄している。同君の仕事および留守家族の一切のことは僕が託されている。君は報知新聞の再興をやりかけたぐらいだ。読売新聞を引受けてくれないか。丁度、今読売は共産主義者に占領されている。君ならやれる。家族も困っている。百万円あれば良い」という。「正力氏は出獄したら社に復帰したいだろう。その点はどうなる」「イヤ、それはそんなことはない。一切自分に一任されているのだから絶対に心配はない」「よし考えてみよう」といって別れた。
僕は前述のように自分の活動は一切やめる決心をしていたが、友人の楢橋渡君は、今は時めいているが、当時彼はまだ自分の足場を持たない。自分はやる気はないが彼は何とか将来の足場を保持することが必要だと思ったので彼に話した。彼も即座に承知して、百万円つくるというのでこの旨、永野君に伝えた。永野君も喜んで、「いつでもきれいに引渡す」との約束もできた。しかし、楢橋君はなかなか金ができたといってこない。
丁度弁護士会長の選挙があって立候補していた。遂に会長は不成功に終った。彼日く「読売の方は、弁護士会長選で金を使ってしまったからダメだ」。僕は非常に困った。永野君は正力氏の家族に伝えてあるだろう。困ったけれどそのままにしておくことはできない。その旨永野氏に話して断った。
永野氏は「残念だな。家族の人々にもいいようがない」といって真に困惑の様子であった。その後、永野氏が、一、二度こぼしたことがあったのをみるとよほど困ったことだろう。かくて読売は引渡しの相手も現われず、正力氏が出獄するまで共産主義者の溜場のような有様で過ぎた。それは結局正力氏の再起の足場となった。社内のシコリをほぐすのに数年かかったが、例のエネルギッシュな活動で再び読売を自分の手に戻した。正力氏出獄後も、僕は永野君から身売りの話があったことは、どんなことになるかもしれないので、絶対正力氏にも他人にも一切話さずにしまった。(「正力松太郎氏との秘話」おわり)(つづく)
「知友の死に思う」①
近頃は思いがけない時に思いがけない旧友知人の訃(ふ)を知らされる。生前関係の親疎によって受ける感じは様々だが、如何にも己が老齢を自覚させられるので心境は複雑である。
「何れは自分もまた後程」といったような生半かな割り切り方で、さも故人に日頃無沙汰のお詑びでもなし得たかの様な心境で、自分自身を誤魔化して過ごすことの多い近頃である。
「正力松太郎氏が熱海の病院で亡くなった」との訃が伝えられたのは去る10月10日のことであった。同君の入院療養中であることは前から知っていたし、また今度はどうも病気が重い様だとは関係筋では噂(うわさ)されていたことであったが、現実に「死んだ」と聞かされてはショックを受けた。が、所が熱海であり、その後の様子はわからず、後報を待った。「遺骸は逗子の自宅に引き取られたが、家族関係や事業関係が複雑で、門外の一旧友が罷(まか)り出る場ではなかった。私は生前の自分との接触を走馬灯の様に懐想しながら、同君の冥福 (めいふく)を祈ったのであった。
越えて23日、まだ正力氏の墓の土も乾かぬ時、TBSの鹿倉吉次君が突如他界したとのことである。これは全く唐突であった。一カ月程前に故杉山幹君の回想パーティーで 顔を合せた時には健康そのもののような顔付で面白おかしく裏話に談興湧いたばかりである。私は自分の耳を 疑うが如く直に関係筋に問合わせたが、もちろん真実であった。取る物も取り敢えず自宅に駆けつけた時に、僧侶が読経していた。
暫らくして僧侶が別室に退いた時、やっとそのままになっていた病室に入って同君の仏顔に対面した。顔は生前の顔そのままで、少しも苦しんだ跡はなく、今にも物を言い出すかと思われる程であった。聞けば大阪旅行でサンザン、ゴルフをやり、麻雀もやり、元気一杯で帰ったばかりの夜、突如心不全で他界したとのこと。もちろん遺言もなければ病床の言葉らしい言葉一つないのであった。
両君は現代マスコミ界の両雄であった。互に時には辛辣(しんらつ)な批判を交わし合うが、内心では畏敬しあっている好ライバルであった。正力氏は次々と新しい企画を事業上に盛り、善悪はとに角、常に斯界の尖端を突走らなくては気の済まぬ男であった。虎之門事件で官界の足を洗い、新聞界に飛込んだ経歴が示す通りの働き振り。一方、鹿倉君は新聞社時代の長い下積生活を堪え忍び、一度逆境を脱するや着々とその基盤を築き、時到るや民放に転進し、民放界の第一人者として動かざる地位を固めた。
両氏はその人生行路でも面白いコントラストを示していた。正力君亡き後の民放の行方など、機会あれば鹿倉君に聴きたいテーマであったが、その機さえも与えず、ソソクサと彼は正力君の後を追うが如く、この世を去ってしまつた。両氏共に84歳、死因は共に心不全。何という暗合か? マスコミの一角に繰り広げられた両氏の競演も、もう見られなくなったのは淋しい。(つづく)
「知友の死に思う」②
古来、人類は何れの民族も人間の「生と死」という解き難き謎を解かんと苦しみ悩んだ。しかしアラビアンナイトの魔神でも連れて来ないでは、一旦死んだ人間を再び戻し、死の真相を確認することは出来ない。それは科学以前の問題であり、宗教の世界である。聖人といい、誓人といい、あるいは教祖と崇(あが)められる人々が、如何にも解答らしい教理を説いても、結局は本人の信仰如何による外はなかった。だからマホメツトの様に左右の手にコーランと剣を持って民衆を引廻さねばおさまらぬお節介さえ出て来たのが人間の歴史である。
所詮(しょせん)人間自身が解決し得るのではな<大自然の力のまにまに人間は流されて行く。ただ人間には自殺という自由が許されているが、それも煎じつめれば死に方に尽きる。だから多くの人は最後の時を予想して「自分はこうして死にたいという感懐を洩(も)らす人があるが、それもただ希望に過ぎない。身近な所を考えてみても毎日新聞の創始者の一人本山彦一氏は「自分は死ぬまで仕事をしたい。死ぬ時は仕事をしながら死ねぬものか」と洩らしていた。鹿倉君も「死ぬ時は突然コロリと死にたいものだネ」と。正力君は病 院で主治医の注射を受けると手を振って「アアもうこれで良い。これから東京へ帰るんだ」といいつつ息を引き取ったとのこと。
現代の英雄として仰がれる英国のチャーチル氏は晩年、友人や待医から養生法などの説教を聞いていたが遂に「もう生きるのが面倒臭くなった」という言葉を残して他界した。 今私がこんなことを書いている間にも、運命に反抗し自らその生命を断っている人間が何人かいるであろう。自殺は人間の特権であろうか。後期ローマ帝国のハドリアヌス皇帝は衰頽(すいたい)したローマ帝国を再び地中海全域に君臨する大帝国に再建した賢帝として誉高い名君主であったが、晩年病気に悩まされた。帝は病苦に堪えかねて遂に自殺を決意し、側近に仕える奴隷(どれい)に殺してくれと頼んだら、奴隷は逃げて行方をくらました。
今度は侍医に毒薬を飲ませろと迫ったら、侍医自身が自殺してしまった。帝は遂に自ら死ぬ以外に途はないと悟って、やっと短剣を見つけ出し、将(まさ)に自刃(じじん)せんとする時、側近に取押えられて短剣をもぎとられてしまった。帝嘆じて曰(いわ)く『誰でも死刑にすることが出来る自分が、自分自身の生命を断つことが出来ぬとは何事か』と悲しんだ。そして宮中を逃げ出して餓死に等しい生活でやっと自分に終止符を打ったという。自殺さえも出来ない人はハドリアヌス帝だけではあるまい。
今は科学の時代だという。然り。これを肯定するに吝(やぶさか)ではない。しかし人間の『生と死』は科学の力を以ってしても如何ともすることの出来ない永久の謎であり、神秘である。若い時代の友人達と人生間題を口角泡(あわ)を飛ばして論議した時代は、それは一種の思想的遊戯であった様だ。近頃はそれが具体性を持って自分独りで考えるようになったのは、単に脳細胞の狂いだろうか。
ああ、弱き者よ汝の名は人間。
(昭和44年10月26日付。東京ポスト「山の手日記」より転載)(つづく)
「日記より」①昭和36年4月10日
今日は婦人の日だそうだ。女の日ということだろう。男の日、女の日、一体何を意味するのか。近頃しきりに政界でも休日増加を論じている。働く者の心は彼等にはどうもわからないらしい。日本民族の将来のためスバラシイ政策を樹立する人はいないものか。思切って年500億位を投じて海外移民を促進するような政治家がほしい。
昭和36年5月18日
梅雨近くなって毎日どんよりした天気が続くが、今日は珍しく天気が良い。5時10分に起きたら巍次が早起きして雨戸は開け放たれている。庭木を廻ってみるに梅は実がドッサり付いている。梅の下のバラが沢山蕾を持ち、7、8個咲いている。うすい赤色が目覚めるように美しい。一枝を切って鏡の前に投入れる。奇麗だ。昼食後、ベランダにいると慶子がとんできて鉢のザクロを指し、「ご覧なさい。今年は沢山花をつけますよ。小さい花の誉が小さな枝にビッシリです」「エッ?本当か」。よくよく見れば、蕾が一杯だ。僅か内径一尺立方程の鉢の木がそんなに花を咲かせるとは驚いた。今見る限りでも3,40は咲くだろう。4月初め頃から毎朝、ミルクのビン底に残ったのを集めて、薄めて君子蘭とザクロにかけていたためだろう。ミルクが肥料に良いことが証明せられた。これは面白いと思わず叫んだ。花の咲く日を待ちわびる。(つづく)
「日記より」②昭和36年5月28日①
慶子が忙しく数日間「富士屋」へ往復してパーティーの準備を進めていたが、いよいよ当日が来た。何だか自分のことだか他人のことだかわからぬような気持ち。「和服にしますか、洋服ですか」との質問にも確答しなかったが、いよいよでかける時に社交服と決めてでかけた。
会場は3階、全階を提供してくれたので本当の水入らずだ。生花もきれいにできてすがすがしい気持。慶子が開会の辞を述べ、岩田君が祝辞。そして僕が70歳のあいさつ。
人間七十古来稀なり。日本人は明治に入って西欧思想が受け入れられる前は、思想といえば論語であり孟子であった。孔子の説も色々批判すべきであるが、とにかく東洋の大思想家であり、政治学者であり、倫理学者であり大したものだ。今から孔子や孟子の時代を振返って想像してみれば、当時の人が70歳まで生命を保つということがどんなにむずかしいことか。当時から人生50年といわれている。孔子も「我十有五而志学」といってから50にして天命を知ると人生の完成を50で区切っている。すなわち、50まで生きれば天寿を全うしたものであり、なすべきことは50までに仕上げなければならぬと思ったのであろう。人間完成後、なお20年生きのびるのが古稀だ。古来稀なりも無理からぬ。
これに自分が達したことを思うと何とたわいのないことかとしみじみ感じる。ただ平々凡々と仕事をしたようにみえるが、何もしなかったといっても良い。しかし、何をして何になる。何もしなかったからといってどうということもできない。ある者は人生を虚無と断じ、ある者は人生を苦悩の世界と断じ、ある者はドラマと感じ、ある者は笑劇と断じている。しかし何者が普遍的結論を下し得たろうか。結局人生不可解と諦観に逃避するのがオチである。
自分も心づいてから、人生問題をはじめ、各種の思想問題にひき入れられてきたが、結局、何ものにも達せず、現実の環境に迫られて馬車馬のごとく働いてきた。ある時は文学者になろうと考え、ある時は思想家を志し、ある時は政治家たらんとし、ある時は財界にも幾多の変遷をたどっている間に人生完成の50年は全く夢のごとくに過ぎ、さらに古稀を迎えるにいたった。
静かに考えてみると、あまり経済的苦しみもなく、したいことをして晩年を迎えることは全く幸福と感ぜざるを得ない。今自分がすべて快よく感じることは他人を深刻に苦しめることなく過ぎたことである。今日の自分を仇敵視するものはまずない。また大きな財産を持たぬ身としては身辺のものから死後、相続関係から、自分の死を早かれとひそかに思っているものもないはずである。最近独立した岩田君は八面六臀というか、一人十役の活躍で、すでに困難な広告界の中堅にのしあがり活躍している。年わずか35歳である。(つづく)
「日記より」③昭和36年5月28日②
自分は東条時代に逮捕され、株殺されるかもしれなかった身である。敗戦後は追放されたが同僚や友人たちが、追放解除にやっきとなって運動しているのを見て「お気の毒な人たち」としてみていた。時に成格一才、巍次は生まれたばかり、もはや、政界にも志を断ったが、せめて文筆だけは捨てずに、本当の声を世に出してやろうと報知新聞再興を志し、スタートしたが、追放の追いうちでオジャンになった。
爾来、晩年を静かに後輩および子供らのために陰のアドバイザーとして世を送る決心をした。その時の報知再興の志望の時、宅の門を叩いて秘書となったのが岩田君である。丁度16年前、君19歳の時だ。今となってはほとんど自分の分身のごとき交際が続いている。その岩田君が一城の主としてデビューするのをみたい。また、幼いといっても高校だから少年から青年の間に入ろうとする成格、巍次の社会にデビューするのもみたい。
先日、大平官房長官の就任祝賀会があった。それまで一度もこのような選挙区関係の会合には顔を出さなかったが、もはや、選挙区の形勢も定まっている今日、今までの自分の心境の一端を発表するものも無駄であるまいと思って出席した。
その時、宴の始まらぬ前に、世話人から「岸井先生一同を代表して祝辞を述べて下さい」との依頼があったので立った。
「大平君が官房長官に就任したのは郷里の喜びであり誇りである。どうか今後とも研鑽して国家のために働いてもらいたい。本日一同を代表してあいさつするのは、私より他に適当な人が沢山あると思うが。世話人の指名もあるので一言お祝いを申上げるとともに私の心境をチョッと申上げたい。大平君は中学の後輩であり、世間では私が相当手を貸していると思うだろうが、私は追放以来、追放解除のためGHQに運動するのは一切やらなかった。政治には志を捨てて、静かに晩年を送るつもりでいた。選挙ごとに郷里の候補者から、助勢を頼まれた。大平君自身は頼んでこなかったが、関係者からは度々あった。しかし、私は追放をうけた身が未練がましく選挙運動に顔を出すことを嫌い、一切何者にも応援はせず、いずれは誰かが選挙区を掌握するであろう。力がないものが出てもいつかは没落する。形勢は自然に定まる。かえりみないのが人材の胎頭を促す由所と考えたからだ。だから、大平君も決して私と親密な間柄ではない。むしろ非常に疎遠な人である。しかし長いこと苦闘の甲斐あって官房長官という内閣の大番頭になったのだからめでたい。選挙区もどうやら定まったらしい。一面からいえば後輩の待ちわびた形勢である。その意味からも大いにめでたいとお祝いを申上げる。ただ一言、最近の新聞などでみると池田首相の言動に対して、大平君は神経質すぎる。政治家でもトップクラスになると公私を問わずその人の裸の姿がありのまま出てくるものだ。周囲でいくら心配してもその人の持味はまるだしになるものなので、池田首相がそのために失脚することがあっても大平君が、自分の心づくしが足らぬと考えることはない。最善を尽すのは良いが、そのために健康まで害することだろうから、ただ一言、これだけのことをお祝いの辞に添えておく」といった。(つづく)
「日記より」④昭和36年5月28日③
その言葉は大平君のためでもあり、自分の立場を表明するためでもあった。僕が追放された時には自分のあとに推せんするだけの人物がなかった。また推せんして苦労させても受け入れ態勢ができていない人間には仇になる。少なくとも代議士として立つには相当な人間でなければならぬ。力足りぬ人を推せんすることは個人的にも社会的にも罪悪である。 孔子の「小人は養いがたし」は実に味わいのある処世哲学である。人間は良き説を聞かんをするものはまず自らの受け入れ態勢を養わねばならぬ。いかに貴重な言葉といえども受け入れ態勢のできていないものには大きな仇となる。
ようするに善も悪も貧困も、みな自分の修養の一程度によってわかれていく。一にも修養、二にも修養である。今日の会合は自分より、後輩ばかり、しかも親子、孫程度の人ばかり。結局、今言った言葉もとりよう一つで善し悪し、正邪いずれともなるであろう。私は自分の一生をかえりみて前述のように怨恨をかまえたと思われる人もない。財産的に損害をかけたこともない。また貧困にあえいだこともない。失意に没入したこともない。良き一生を送ってきたと思う。しかも現在は最も安定した時である。
この時、古稀を迎えるのは幸福だ。それに少し言いがたいことであるが、妻は非常に料理が上手だ。今、自分は外出して他の料理を食うよりも、自宅の料理の方が上等だ。外に出て食いたいと思うのはうなぎ、ふぐ、スッポンだけだ。この意味でもかような環境であることは晩年の自分は幸福だと感じている。あまりほめていると妻の鼻が高くなりすぎるので、この辺でよすが、ただ気がかりなのは子供がだんだん料理に敏感になることだ。料理に敏感だと、人間は憶病になることがある。またチョッとしたことのために健康を害することがある。同じ一家で暮している子供とはいえ、別料理を食わせるわけにもいかぬ。それで時々問題をおこすことがあるぐらいで、これも幸福すぎる現象である。今後、妻がさらに老人食に上達してくれると、あるいは岩田君のあいさつにあったように、ますます長命するかもしれない。あまりいっているとおのろけになってもいけない。皆さん集まってくれてありがとう。今後おたがいに幸福に暮らそう。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年6月21日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その8
追悼集「岸井寿郎」には「久富氏の死」「正力松太郎氏との秘話」「知友の死に思う」「日記より」の5編の遺稿が掲載されています。この遺稿の中にも身辺のことに加えて、激動の昭和時代に直面した出来事とさまざまな方々のお名前が出てきます。昭和史の一断面として貴重だと思います。
「久富氏の死」①
(前略)僕が初めて久富君に会ったのは昭和6年、僕が政治部長になった時であった。いかにも威風堂々の偉丈夫が政治部にいた。それが久富君であった。仕事をしているとなかなか細かいところに気のつく男であった。それから僕は同君を注意した。満州事変から上海は事変と大変動の時代であった。新聞社、殊に政治部は毎日毎晩、一刻も息を抜くことのできない緊張の時代だった。その上僕は印刷部長兼務という全く新聞社では異例の激務であった。久富君といわず部員全員は必死の健闘を続けていた。
時も時、僕は政治部員時代や印刷部長時代の不摂生のたたりで身体には異変があった。それは消化器の全機能が全く癒病しているというのである。
時の胃腸病の大家、南大曹博士から、『命が惜しければ絶対禁酒と食物の摂生』とを厳命せられていた時であった。1日の睡眠3、4時間、昼食などトーストに番茶だけ。バターもジャムもつけてはいけないというのである。今思い出しても「よく持った」とため息が出る。
やがて政治部の立て直しの時が来た。僕は久富君を副部長に抜てきしてデスクに据えた。先輩、奥村不染氏に「岸井君は乱暴な人事をやるネ」とからかわれたのもその時であった。久富君の入社年限が短かかったためであろう。しかし、その時代はそんなことに構ってはいられない激動期であった。幸にして久富君はよくその職責を全うしたのみならず、僕の病気による欠陥をカバーしてくれた。新聞は常に社会からも畏敬された。一面、社内にも本山老社長の急死から様々な異変が起った。僕は転じて営業局次長となった。その時久富君は僕の後を襲って政治部長になったのである。久富君と僕とは文字通り内外共に激動の時代を密接に協力して過ごした。外からはほとんど二人は一身同体のように見られていたようであった。
爾来、私は吉武鶴次郎老専務の下にまた新しい仕事と取組んだ。が、社内はこの数年間に他の企業体が10年、20年にも相当する変化を経た。僕の健康は既に回復することができなかった。このまま仕事を続ければ生命も保ち難い。一方、新聞事業に対する僕の情熱もさめていた。社内外の情勢も落ち着きをみせている昭和12年、僕は意を決して新聞から身を引く決心をして辞表を出した。その足で久富君を東京会館に呼んだのである。
やってきた同君は何か異様な空気を察知したのかも知れない。「おそくなりました。何のお話でしょう?」と沈痛な面持ちである。僕も暫く押しだまっていたが、おもむろに口を切った。
「実は予め君達に相談するのが道だが、相談すれば僕の意思が曲げられることは必定なので独りで腹を決めてしまったのだ。僕の健康は君も知っている通り自他共に認める難症だ。また、一方、新聞事業に対する昔日の情熱も消えてしまった。今社内も何とか落着いている。この時を逸しては、このままズルズルと心にそぐわぬ仕事に余生を費やしてしまうことになる。長い間親交を続けてきた多数の諸君に対しは自責の念にたえないのだが、この際引退したいのだ。それで今、限に辞表を庶務部長に渡して来て君にここへ来てもらったのだ」と一気に心境を訴えた。(つづく)
「久富氏の死」②
久富君は一瞬蒼白となって首を垂れていたが、
「それは誠に困ります。ただでは済みません。社に対して不平のためではありませんか?」
「誰でも職務についていつもフルに満足している人はあるまい。いや不平などは少しもないと白々しいことを君にいう気はないが、引退の意を決したのは、それだけではない。健康が第一だ。社の仕事に情熱を失ったのが第二だ。そこで僕はみんなに頼むのだ。この機に僕を解放してもらいたい。僕は人生をこれからやり直したいのだ。君の部員は人材揃いだ。万一、このために軽挙する人があってはその人の前途を誤る。僕は今君にいったとおり既に辞表はその部署を通して公式に大阪本社に出している。無理なことは重々承知の上で君の了解を求めるのだ。また、多数友人の説得を頼むために君に来てもらったのだ。今さらどうにも変更はできない」。
久富君は沈痛な面持ちで幾度か翻意を迫ったが、僕の決意の動かし難いことをみて「兎に角、私は4、5人の諸君と相談してまた、夕方ここにきますから岸井さんはここにいていただきたい」といつてトボトボと会館を出た。夕方、5、6人がやってきて色々興奮する場面もあったが、私は只々、諸君の了解を懇請した。
「すでに庶務部を通じて辞表を出したのだから今更、何ともならない。元から印刷局の諸君、営業局の諸君にもそれぞれ了解を得なければならない。諸君の情誼は心から感謝しているが、これから他の方面の後始末をしなければならぬ。許してもらいたい。ここ暫らくは自宅では誰にも会えない。これも了解してもらいたい」といって会館を出た。
今、久富君の計に接して生々しくその日の記憶が蘇えって離れない。僕にとって久富君は実によきパートナーであった。政治部長として良き女房役を得、良き後継者を得た。その後久富君は編集総務となり、戦時中は下村海南情報局総裁の下で次長となり、縦横に活躍したが、国の敗戦は同君を世の中から葬り去った。二重、三重のパージで蟄居の外はなかった。
僕は衆議院議員として、また言論、出版関係出として二重の追放を喰って、同じ配所の月を眺める身となった。爾来、同君は持前の幅広い活動を開始した途端に病魔に襲われたのである。頑健そのものの体躯、それに似合わぬ細心の心遣い、厚い情誼、同君の好きな真に稀にみる持領の材であった。君を追想すれば数限りない。(つづく)
「正力松太郎氏との秘話」①
今流行の言葉でいえば情報産業の雄、正力松太郎氏が84歳を一期として今暁逝去したとNHKがニュースを報じた(注:1969年10月9日)。自分は自室でニュースを聞かなかったが、慶子が直ぐ伝えたので吃驚した。
一昨日、山下芳允君来訪の時、あるいは彼が正力氏の近況を知っているのかと思って聞いてみたが、「最近は大分良くなって、退院して動きまわっているよ」とのことで、自分が理解しているのとは大分違っているので「そうか」といっただけで正力氏についての話はそれだけで終ったのだが、やはり悪かったのだなと思った。
自分と正力氏との関係は一時は非常に親しくもあり、また色々のできこともあったが自分が新聞界の足を洗ってからはだんだん疎遠になっていた。最後に会ったのは41年の秋ごろ、坂本直道君の出版記念祝賀会の時だ。当時、互になつかしい話をしたものであった。その時既に、見たところ足許が一寸頼りなかったことを思い出す。その時同君が娘婿の小林を副社長にしたことを喜び、彼は学生時代、東大きっての秀才であり、官界においても群を抜いて昇進した話をアケスケに喜んで話していたことが印象的であつた。この際、一寸、同君と自分との関係を書きとめておこう。
正力氏は役人上りであった。山本権兵衛内閣で警視庁の刑事部長と雷名を挙げたのは衆知の通りだが、当時の大逆事件で内閣が崩壊した当時、経営不振で歴史ある読売新聞も気息エンエンたる有様であったが、彼氏どんな確信があっか、後藤新平氏に懇請して資金を得、読売新聞を買収して乗込んだ。当時新聞界に二大紙の村山、本山両鬼才が東京にまで進出、東京朝日、東京日々は隆々たる勢で拡大しつつあった。東京には、尚、国民新聞に老いたりといえども徳富蘇峰健在であり、報知新聞には三木善八郎がいた時代である。「役人上り何するものぞ」というのが新聞界の通説であった。
事実、読売は依然として背伸びをしても思うようにならなかった。しかし、正力氏は真険に研究もし苦心もしていた。僕の日日新聞の友人に宮崎光男という男がいた。小がらで可愛いい顔の男であったが、それがどういう筋からか正力氏に引抜かれ、読売に入り編集の一部を担当していた。当時、日日新聞は旭日昇天の勢で四辺を風びする勢であったから、日々の風を読売に植付けるためであったろう。宮崎君が編集でメキメキと地歩を進め、編集の全面をやり繰りするようになっていた。しかし新聞そのものはまだ問題にならなかった。
一日、僕に会って話した時、突如として、「岸井君、うちの正力社長が君に会いたいから橋渡しをしてくれというんだ。君、会ってくれないか」「何の用事だネ」「いやいろいろ新聞のことについて教えてもらいたいというのだ」(つづく)
「正力松太郎氏との秘話」②
当時、自分は印刷部長で盤根錯節の印刷部を2年がかりで再建してホッとしていた時である。しかも当時、各新聞の競争は血みどろの時代に、読売の社長に会い、しかも内々で会うということはどうも後暗いことだし、万一噂になればとんでもないことになりかねないので、自分はことわった。ところが、その後数日してまた、宮崎君が「君迷惑だろうが、僕を助けると思って会ってくれないか。僕は懇々と何度でも頼まれるので困っているんだ」。
色々考えたが日日時代兄弟のようにして過した飲み友達であり、心から親愛していた宮崎のことで、これ以上ことわることができなくなったのみならず、変り種の正力という男に興味もあった。会うだけのことで何も社内の秘密を話すわけではないのだから新聞人が人に会うだけをビクビクする必要はないと思った。
「それでは会う」といったら数日にしてまた宮崎が訪ねてきて「何月何日、山王の○○茶屋に来てくれ。ボクと小野瀬顧間(新聞界の長老)が正力社長と同道する」という。これは少し変だなと思ったがその時間に宮崎につれられて茶屋に行ったら、正力氏と小野瀬の二人がもう待っていた。
簡単にあいさつして酒宴になってみんなが酒面になった時、正力氏は「岸井さんに迷惑なのは重々わかるのですが、一つあなたに印刷のことを教えていただきたいと思いまして」と話は核心に触れてきた。
「良いですよ」
「実は最近の日日新聞の印刷の見事なことは全く天下の見ものですが、一体どうすればあんな立派な印刷ができるのですか」
「ハアーそれは簡単でもあれば、また複雑でもありますネ。一口にどうすれば良いかといわれてもチョッと返答ができかねますが、しかし、やり方をお教えしても宜しい。たとえば写真スクリーンの目を2割こまかく直すとか、良い機械を入れるとか、良いインキを使うとか、良い活字、良いローラー……。しかしそんなことは何でもない。いくらでもいいますが、それで実効を挙げるということとは別ですよ。あなたはそれを実施できると思いますか。実施するのは工場の幹部です。工員です。それを自由に動かし、当方のいう通りやらせることができれば良いんですよ。要するに良い印刷はその人をつかむか否かにあるんです。僕が今、細かいことをあなたに説明してもおそらく皆さんはわかりますまい。あなたはまず印刷の細部を勉強してからでなければならず、腹心の工員をつくらねばならぬ。おわかりですか」(つづく)
「正力松太郎氏との秘話」③
正力氏はしばらく沈痛な面持ちでジーッとしていたが「良いことを聞きました。わかりました。今日はどうぞ一つゆっくり召上って下さい」といって私の顔を見て笑い出しだ。一瞬、緊張した空気はほぐされた。それからは主として私は小野瀬に向って昔からの新聞の歴史などを聞き3、4時間も談笑して別れた。
会見についてはいう者もいないし、また内容が別に社の機密を漏洩したわけでもないので自分は晴れ晴れとした気持で過した。しかし、読売新聞の印刷はなかなか良くならなかった。その後、東日から小泉某など小生の部下を迎え入れた。鋭意改革を企てたようだが、世に認められるような印刷にはならず、したがって会見が問題になることもなかった。
当時「新聞の新聞」という内報があって、僕のところにも、東日の印刷が評判になっているものだから、年中やってきていたが、正力氏との会見後一年以上も経ったある日、突然、「岸井さん、秘中の秘を聞きこんだ。正力さんと色々話していたら“僕は東日の岸井君に新聞の大切なことを教わった”。何を教わったか聞いても答はない。“秘中の秘”だというんです。何ですか」という。「いや雑談だよ。正力君がいうのは何を意味するかしらぬが、俺は新聞に別に秘密なんかありゃしないというようなことを話しただけだ。正力君が何か 役に立つことがあったのかしらんが俺には覚えがないネ。正力さんに聞けよ」といってとりあわなかった。
その後、同君は何年もの間、いわゆる“秘中の秘”をかぎ出そうと僕を誘ったが、とうとうそのままだった。正力氏は人心をつかまずには何もできないということが多少面恥しかったらしい。だから僕もそのことは誰にも洩らさずに今日になった。
同氏の訃に接して今さらながら、当時の光景がマザマザと目に浮かぶ。正力氏とはその後、普通の新聞人同士の交際が続き、日本倶楽部の常連で良く議論を戦わせた。 (毎日新聞百年史=工場編=によると「政治部長から、東大出の岸井部長がきて、工員一人一人と面接、調査を進めたあと社で初の従業員就業規則をつくった。おそらく岸井部長の草案によるもの」と記されている)(つづく)
「正力松太郎氏との秘話」④
販売部の人々があわただしい動きをしている。何事かと思っていると報告が来た(営業局次長当時)。読売の正力社長が暴漢に襲われ肩を切りつけられたという。「ヘエどうしたんだ」「いやそれが本社に出入りする熱田です」「エッどうしたんだ」「わかりません」「金をゆすり損ったのかな」。その日は不思議に思いながらそれ以上はわからなかった。 私の体は、いわゆる城戸事件以来(これはまた別の機会に書きつける)弱っていた。自分の思うような結果にならなかったことが健康を害したのだ。自分はもう日日新聞の復興に熱意を失っていた。吉武氏(鶴次郎専務兼営業局長)は異状に心痛の様子だった。当時の販売部長は丸中一保君(東大出)だった。
同君は仕事に熱心で、日常の仕事には幾分誇張らしいところがあった。ところが、〇中君が突然姿ををくらました。しばらくは極秘が保たれていたが、だんだん新聞界でも事件の片りんが伝わるようになった。同君は正力刺傷事件のチンピラ暴力団に言葉の上で引込まれ、暴力団員は裁判所で「東日の丸中部長と相談しての上でやった」といったらしく、丸中君は数回、裁判所に呼ばれたのであった。これは新聞界としては大問題だ。
東日に対する陰の誹謗は噴々たるものであつた。城戸事件以来、東日は姿勢の建直しに躍起の際、これは被るべからざる大きな傷である。自分も一回検事局に呼ばれた。吉武氏は当の責任者として矢面に立たされた。これは社内の高石、奥村、山田など反対勢力のこの上もない吉武攻撃の口実となり、社の内外は蜂の巣をつついたような混乱に陥った。
丸中君はその責任に耐えかねて失踪したようだ。この失踪でまた、東日の示唆で正力刺傷があったということが事実となってしまい、遂に吉武氏の失脚となり、営業局長には山田潤二がなった。自分も当の責任者として冷飯の座に坐ったままとなった。丸中君はその後どうしても姿をみせず、数年後、伊豆半島の海岸の洞くつの中で自骨となって顕われた。全く気の毒であった。かくて正力氏の刺傷事件は、東日にとって、吉武、岸井退陣など土台をゆさぶる大問題の結果をもたらした。城戸事件、吉武事件、不思議なものである。何か一つの運命が連続して働いていたような感じだ。
時々、鎌倉に出かけた汽車の中で正力氏と一緒になった。この事件については最後の出合いの時、僕から「いや熱田の事件はとんでもない濡衣でした。大変迷惑なことだが、事実、東日は何のかかわりもないことだった」。「イヤーそれは良くわかっている。マァ一つお互いに新聞界のために手を握って行きましょうや」といって両人の間では呵々大笑の話題にすぎなかった。それから後、時々汽車で会ったが熱田事件が話題になることはなかった。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年6月17日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その13 南房総の野菜畑(抜粋)
文・写真 平嶋彰彦。
全文は 全文は http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53443545.html
野菜作りを始めてかれこれ10年になる。房総半島南端の館山市に実家が残っていて、目の前が畑になっている。両親は2人とも亡くなって、だれも住んでいない。私がいま住んでいるのは習志野市で、週末になると妻と2人で実家へむかう。一般道路だと距離にして110キロ余り、片道3時間半かかる。
畑の広さは、登記台帳を見ていないが、目見当では400坪から500坪ぐらいはある。趣味の家庭菜園としては、3分の1もあれば充分である。しかし、畑を遊ばせておくのがもったいなくなり、ついつい畑いっぱいにあれもこれもと植えてしまう。
そうしたくなる理由はほかにもある。実家のあるあたりは、房総半島でもとくに暖かく、霜の降りることは何年かに1度しかない。ナバナ(菜花)は9月に種をまくと、11月半ばにはつぼみをつける。サニーレタスは1月でも2月でも、種を蒔けば芽が出る。春夏秋冬を問わず、その気になれば、多彩な野菜作りのできる恵まれた自然環境といえる。そんなこともあり、畑にはいつも10数種類の野菜を併行して作っている。
商品作物を生産しているのではなく、あくまでも自家消費が目的の家庭菜園にすぎない。たくさん作ったところで、親戚や知り合いに配るだけで、一円の収入にもならない。にもかかわらず、年がら年じゅう時間に追われ、のんびりしている暇がない。毎週1泊2日で、実働1日という日程にも無理があるのだが、とりわけ、4月下旬から6月初旬までと、9月から10月中旬までは忙しい。
今年は4月下旬からの1ヶ月間に、ソラマメ・ジャガイモ・タマネギ・ニンニク・ラッキョーを収穫し、そのあとにスイカ・ナス・サツマイモ・トマト・キューリ・ゴーヤ・オクラの苗の植えつけや種まきをしている。この時期に夏秋の作物冬春の作物を交換させる。早いはなしが、畑の衣替えをするわけだが、作物の出来具合や天候の成り行きを見極めるのが難しい。そのため、収穫と植えつけの進行が混乱して、いつもきりきり舞いになる。 田舎の朝は早い。夏の季節なら4時すぎには目が覚める。起きたらすぐに畑にでる。夜間にたっぷり水分を補給した野菜が瑞々しい。ぼんやりと眺めているだけでなんとなく気分が高揚する。1日のうちで私の大好きな時間である。陽が昇るのと前後して、あちこちの農道を軽トラックが行き交う。農家の人たちが特産の花卉を栽培するビニールハウスを見てまわっているのである。ハウス内の温度と換気の調整をするのだが、一番の目的が何かといえば、花卉の育ちぐあいの観察と健康状態の診断にあるのだという。
農家の人たちほとんどは幼なじみである。顔を合わせれば、声をかけあう。あれこれ立ち話をしているうちに、作物の育ち具合や病虫害・鳥獣被害などの最新情報が得られる。彼らは自分の畑だけでなく、よその畑にも目配りを利かせている。私の家のような野菜畑のようすまでよく分かっている。
同じ種類の野菜を同じように作っても、豊作の年もあれば不作の年もある。一番大きい要因は、なんといっても天候ということになるが、もちろんそればかりではない。今年はソラマメ=写真・下=が私の家のあたりでは不作だった。私の場合は4合の種から90キロ余りを収穫しているから、それほど悪い成績でもなかったが、栽培農家のなかには収穫する前に後片づけをすませてしまったところもあったという。

ソラマメは連作障害が厳しい。その対策として土壌消毒剤や土壌改良剤を用いるのだが、それも効果がなかったということかもしれない。私も連作障害に悩まされ、栽培方法を変えてみたり、土壌改良剤を試みたりしたが、うまくいかなかった。いまは土壌改良剤も使っているが、少なくとも2年の空白期間を設けるとともに、ソラマメ以外のマメ類も作らないようにしている。ところが、今年の場合も、収穫前に樹が枯れてしまうとか、しっかり実をつけていない箇所がそこかしこにみられた。原因は連作障害のせいだという意見が多いが、春先の低温のせいだという人もいて、確かなことは分からない。
病虫害と鳥獣被害も野菜の栽培を難しくしている。
ソラマメでいうと、アブラムシがつきやすい。1つの株から何本もの幹が伸び、春先に花が咲くのだが、ちょうど実をつけ終るころになると、決まったように、一番上のやわらかい芽の部分に、アブラムシが発生する。アブラムシを見つけたら、その樹だけでなく、畑全体のソラマメの芽を摘んでしまう。すると、それ以上は広がらない。
ところが、今年にかぎっては、早くからアブラムシがついた。まだ満足に実がついていないから、芽を摘むわけにはいかなかった。消毒することも考えたが、妻がそんなことをしたら人にあげられない、といって反対するので、それもできなかった。仕方がないので、ソラマメの1本々々を見てまわり、アブラムシを払い落していった。
翌週に行ってみると、払い落としたはずのアブラムシがむしろ勢いを増している。こんなことをしても埒が明かないと思ったが、2人で何時間もかけて払い落としていった。3週間目になって、我慢もこれまでと思って芽を摘むことにしたのだが、そのときには、アブラムシは幹の下まで広がっていた。このままだと全滅しそうな気がするし、そうならなくとも、まともなものが収穫できるとはとうてい思えなかった。ところが、次の週になって妻と2人して驚いた、というよりも、目を疑った。アブラムシは1匹も残らず、まるで何ごともなかったように、ソラマメ畑から姿を消していたからである。

(途中略)
宮本常一の名言がある。
自然はさびしい。しかし人の手が加わるとあたたかくなる。
このあとに「そのあたたかなものを求めてあるいてみよう」と続く。1960年代のTV番組『日本の詩情』(日経映画社)のナレーションである。
耕作を放棄した田畑は、たちまちに草茫々の荒地に姿を変える。自然に回帰しようとするのである。自然とは人間の力の及ばない領域の総称といっていいかもしれない。私たちは人の気配の消えた風景に心を癒されることはない。まして、そこで生まれ育った人なら、なおさらのことである。
だが、物事には始めがあれば終わりもある。
これから5年もすれば、否も応もなく、私は80歳になる。常識的に考えれば、畑仕事はなんとかこなせる。とはいっても、車を運転して習志野と館山を往復するのは、体力的に難しくなるばかりでなく、はた迷惑な行為として嫌われるのはいうまでもない気がする。
2021年6月15日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その7
【岸井成格さんの父・寿郎さん】。
岸井寿郎さんの最初の奥さんは病気で死去。2人の男児が成人した後、再婚した夫人も昭和17年に出産のため入院した時、亡くなりました。昭和18年4月に再々婚された慶子夫人との間に、成格(三男)さんと巍次(四男)が生れました。36ページにものぼる慶子夫人の「夫を偲んで」から、抜粋して紹介します。
「夫を偲んで」⑪
昭和20年8月15日、どこかで用意されていた“平和”という言葉で終戦を迎えたのは、それから間もなくのことでした。その後暫くして、古閑少佐と特高の一人は自決をして果てたということを聞きました。
終戦を迎えながら、自ら命を断たなければならなかった人達が余りにも痛ましく、しかも別荘に関わりのあったことがいつまでも痛く心に残りました。もう一人の特高は、夫に就職の依頼にきました。あの誇らしさは一朝にして失われ、見るかげもなくうらぶれ果てた憔悴の姿でした。しかし生きていてくれたことが、あんなにうれしく私の心をゆさぶったことはありませんでした。夫のいう一人一人に与えられた大切な命なのです。
終戦と共に軽井沢へも政界、財界の人々が次々に集まり、私の家への出入りも多くなってきました。しかし避暑地の冬は余りにも早く、10月6日に四男の巍次が誕生しましてからは日増しに寒さが身に浸むようになりました。夫は大森の山王にあった関係会社の寮をあけさせて、ひとまず単身上京し、総ての準備を整えてくれました。普通の邸を寮に使用していたものですし、留守居の母娘がその儘残って手伝ってくれることになりましたので、夫の生活に支障はありませんでした。
私は寒さの中で産後の体の回復を待ち、11月に入ってからはじめて東京の土を踏みました。軽井沢で会合を続けていた方々も次々に上京し、軽井沢構想は漸時具体化して行き、日本自由党の結党式をあげる運びとなりました。自由党の名付親は夫で、世界の自由党でなければならないから日本はいらないという意見でもあったのだということを聞きました。しかし夫は間もなく追放を受けました。選挙区の方々が心配して次々に上京し、慌ただしい毎日が続きました。
その後、名門報知新聞の復刊の企画に加わり、社長に就任し、昭和21年末に復刊第一号を出しましたが、そのとたんにまたまた追放の追い打ちをかけられました。被追放者は新聞、雑誌、ラジオ、映画等広報関係に従事してはいけないということなのです。「政界を急に追放せられた以上、新聞に籠って言論で思う存分やっみるのはむしろ私の本命の仕事」と申していた矢先の出来事でした。
「まあ、仕方あるまい。戦時中責任の地位にあったことに間違いはないのだから。政治を続けてやれば、俺の体そう長くは持つまいと思っていた。長生きをして若い人達を指導してやろう。また子供で俺に似たのがいたら志を継いでやることになるさ。それで良い」
と私に申しておりました。ある雑誌の寄稿文の一部に当時の心境を次のように記しております。
『孔子は「五十にして天命を知る」といった。少しはわかるような気がした。孔子程の聖哲も時到らねば志を得ず、退いて後輩を教えて晩年を送った。もし若くして志を得ていたら、不朽の聖哲に達することはできなかったかも知れない。「人間万事塞翁が馬」。それから私の家には平和な日常が続くようになりました』と。(つづく)
「夫を偲んで」⑫
確かにその通りの生涯に入って行きました。若い政治家や財界人の指導に当たり、表面には出ません。でも夫の意見がその儘政府の見解として大きく各紙面を賑わしたこともしばしばありました。結局は政治に関与していたことになるわけで、当時の日本には夫は大事な人であったと思います。政治関係の方の出入りの他に、戦前やっておりました日本橋の会社と同じ光景も展開されました。就職、金策、食糧その他諸々の用件をたずさえて入れかわり、立ちかわり多くの人々が夫を頼って訪ねて来ました。
夫は誰がどんな用件で訪ねて来ても大変うれしそうでした。それはお互に心の通じ合う人々であったからなのです。話がはずんでいつしか用件が時局談に移り、時のたつのも忘れている様子でした。
「良い人間程困っている」、戦後の混乱時にはなお一層その傾向が強くなりました。戦争を大いにあおった人達こそ、恥も外聞も忘れてGHQに取り入っての追放解除の暗躍に躍起となっていました。善悪、清濁が自ずと表われ出る皮肉な時代でもあったのです。
こうした中で夫は政界から身を引く決心を致しました。そのため、追放解除後はせっかくの選挙区の方々の熱望にも応えられず、厚意を無にしなければなりませんでした。夫もそのことが一番心残りであったようでした。その後は文字通り悠々自適の生活に入りました。毎年軽井沢で7、8、9の3カ月を過ごしました。政界の方々の他に石坂泰三氏、原国造氏など財界人もしばしば訪ねて来られ、碁に興じておられました。
石坂氏は、東京帝大の4、5年先輩でいらっしゃいます。戦時中と違いまして夫の周囲に機密の会合がなくなり、食事をしながらの氏と夫とのさわやかな政談に心引かれて、つい座を立つのを忘れることもありました。客を迎えることは主婦にとっては生きた学問をさせて頂ける絶好のチャンスでもありました。夫の友人はどなたも非常に家庭を大事にされていたように思いました。決して甘やかすという意味ではなくて、しっかりそこに根をおろしているという感じでした。家庭の重要な意味と、妻や子供にも大いに責任のあることを痛感せられました。(つづく)
「夫を偲んで」⑬
石坂氏が病身の夫人を非常に労わっておられたことも雑談の中にしばしば出て参りました。また学生であった令息の友人達が毛布一枚かついでぞろぞろと別荘に押しかけて来たので、逃げて来ましたと愉快そうにその様子を話しておられたことなど、人間石坂氏の一面を見せられることも多くございました。
石坂氏の食事のなさり方、好物など人柄そのままに豪放で大変ほほえましいものがありました。また永野護氏が軽井沢の拙宅に泊られたときのことでした。茶室で一人で庭を眺めておられましたので、お茶をたてて差しあげようと思って参りますと、「世間では僕のことを机竜之助などといっていますが、如何がでしょう。ご主人を大変適確に評価されるそうですが是非聞かせて下さい」とのことに全く赤面致しました。夫のことを勝手に評価して「見損うな」などと叱られている私なのです。
永野氏は戦時中、玉川へもたびたび来られ、国事に奔走していられた様子も存じておりますし、また前日は大勢の兄弟を親がわりに育てられたという昔語りも聞かせて頂き、私の考えていた永野氏の口から語られるのに相応しい話と、尊敬の念を深めていたところでした。「どうも陰険だということらしいのですがね」と、大変真面目なお話のようでした。
夫が参りますと氏はまた同じことをいわれました。
「そういう誤解を受け易いところは多分にあるよ、君」
「そうかな、気を付けないかんな」
「上に立つものは警戒心を持たれると真実が耳に入らんようになるからな」
「そうだな、注意しよう」
最初は単に笑い話で済む問題かと思っていましたが、噂も疎かにせずに、まず受け入れて考える、その会話が二人の間でさらりと進められて行きました。
津島寿一氏は、夫の出身地香川県の先輩で、気に入った別荘が見つかるまでと軽井沢の拙宅でしばらく一緒に暮したことがありました。夫人も静かな方でしたが、氏も永らくイギリスに滞在しておられたせいか典型的な英国風の紳士でしたので、あくまでも礼儀正しく、端麗で、人間津島氏の一面を見せるということはありませんでした。夫と時の経つのも忘れて碁に興じたり、経済談義に花を咲かせたりしておられました。
ある日、二人が碁盤を囲んでいた時、夫人が「その場で勝敗のきまる勝負の世界なんて、厭、厭」と肩をすくめて見せたのが、如何にも優しい夫人らしくて印象的でした。
料理に凝っていらした氏は、コックを抱えておりましたが、夫人があるとき女中の切り残した細い沢庵のしっぽをつまみ上げて、
「私は小さい頃、沢庵のしっぽというニックネームでしたの。一番末っ子のせいもありましたけど、実はしなしなしたしっぽが好きでしたので」。
人間そのものが通の域に達していたのでしょうか、さり気ない話し方をされる方でした。(つづく)
「夫を偲んで」⑭
私は夫の傍に生き、多くの方々に接することが出来て本当に仕合わせであったと思っております。夫はこうした生活の間に、山歩きも致しました。澄んだ空を眺めながら、「またそろそろ地球を料理するか」、ということで技師を伴ない、別荘番に弁当などを持たせて戦後間もなく鉱山や温泉の探索をはじめました。
鉱山は東大の石和田章三先生、温泉技師は三雲康臣氏でした。夫は工学、化学共に豊富な専門知識を持っており、また地質学にも勝れた見識を持っていましたので、石和田氏、三雲氏共に夫の意見を尊重して調査を進めておりました。
いつの頃からか、私は単に出歩きのお伴のつもりでしたのに、すっかり地球の内臓を探る仕事の虜になってしまいました。
政界に入る前に新聞界から初めて事業界に入ったばかりの頃は、夫も最初から大鉱山に取り組んで大変苦労もし、勉強もし、また大きく儲けもしたようですが、その頃は主に非金属の鉱山を見て廻り、長硅石の鉱山を買い取り、他にまだ海のものとも山のものとも解らない鉱石の開発にも興味を持っておりました。
「きっとこの白さが役に立つ」といった具合に簡単に鉱山を買い取り、それから分析や、化学試験などをさせてその結果を楽しみにしておりました。それをアート紙、農薬その他に使用可能なものにして業界に送り出しました。
これより先にも硝子、陶器に同じ苦心の末世に出したものが既に20数年老舗のブランドを誇っています。不思議な才能の持主でした。これだけ投資したらこれだけ儲かるなどということは余り念頭にはおいていなかったようです。もちろん良い悪いは別として金儲けが主でなかったことはたしかで、大事業を引き受けてもらいたいという申し出でには応ぜずに、若く有為な人材を推薦する努力をしておりました。
一生の仕事として選んだものは儲ける儲けないの問題ではなくて、やはり政治、新聞であったようです。鉱山、温泉の仕事は地球に穴をあけて、無から有を生じて世の中を潤したいということでしたので、様々な試験の失敗を繰り返して成功を見た時の嬉しそうな顔には温かい人間味が溢れておりました。「金は勝手にうしろからついて来よった」と申しておりましたが、全くその通りでした。自由に勝手に生活をしておりましたのに、不思議に経済的には大変恵まれておりました。(つづく)
「夫を偲んで」⑮
温泉調査もまた楽しいものでした。夫は地質学者の異端者的な存在であった三雲氏の調査技術に惚れ込んで、夏はいつも氏と私、それに別荘番、ある時は写真技師まで伴って浅間周辺と申しましても何十キロも離れたあたりまでですが、隈なく調査して廻りました。地質学的に種々難しい原理はあるのですが、兎に角それらの上に機械で実際にキャッチした地下の脈の形態が合致して行く面白さは、夫ならずとも魅せられてしまいます。
爆烈口と称する地下深くひそむ小噴火口を探り当てた時は、三雲氏は子供のように嬉しそうでした。勝れた温泉脈の元となるものでした。その近くは崩れ易いので掘るわけには行きません。その上火山の近くを掘ったときと同じように湯がなく、ガスが噴出するということで爆烈口から走り出ている温泉脈を地質、地形などを見ながら適当な場所を何キロ、あるいは10何キロも離れたあたりまで探索します。
5万分の地図の上に、実際にキャッチした点を記し、その2カ所を結んで延長すると、先に記しておいた爆烈口あるいは火山に間違いなく走って入ります。あるいは反対に探索した脈の線が放射状に走って一点で結ばれ、そこを訪ねてみますと、古い噴火口であったり爆烈口が発見されたりもします。
大断層の上に建築物がある場合には三雲氏のいっていた通りに大変腐蝕や崩壊が早く、また神経痛その他の長患いの人が住んでいることも信じ難い程適確に立証されてゆきました。強烈な放射能のせいでした。山津波のあったあたりには大断層がありました。
三雲氏はドイツで地質学、温泉、水源、石油等の調査の修業をされ、ドイツ人の恩師から譲り受けた機械で調査していました。放射能を捉える時、自分自身の体がアースの役をするらしく、食事をすると嘔吐を催しますので梅千を食べながらの作業でした。
機械の正体は決してみせませんでしたが、現代のものから見てあるいは原始的であったのかも知れません。原始的であったからこそ人間の知恵が徒らに加味されずに宇宙の法則とぴったり合致するということにもなるのでしょう。
氏は全国に大きな数多い実績をもっておりました。自分の学説を何ものにも侵されまいとする態度はかたくなにさえ思える程でしたが、夫は20数年来彼にのみ任せ、その技量を高く評価しておりました。何万年、何10万年前の地質の成り立ちや法則との関係などから解き明かして行く温泉脈の原理の面白さは、いつしか引き入れられて納得が出来てゆきました。
山野の下草の枯れているときが一番調査し易いわけですが、夫は体力づくりや山歩きの楽しみを兼ねてのことですので季節を問いません。大体気候の良い時期に出かけますので、三雲氏も大変であったろうと思います。美しい自然の中で、私は夫と同じ目的に深い興味を持ち、瞼しい山道を手をさしのべ合いながら汗し、そして語り合いました。
火山の周辺に身を置くとき、いつも二人で見に行きました大遺跡展、古代美術展のポンペイ、メソポタミアツタンカーメン、ヴェルサイユ展などの興奮を新たに覚え、溶岩、地層断層、焼石の考察がいつしかそれら古代人の生活様式、美術品の持つ神秘さに話が移って行きました。自然と融和して生き続けた人間を、いとおしむ心に相応しい雰囲気の中に二人はいたのです。それは甘く、はかなく、もの悲しいものでした。その中にとらわれたときいつしか二人の間にも美しい神秘の恋が芽生えていたのかも知れません。今、鮮烈な思い出となって蘇って参ります。
夫は温泉調査の足跡を各地に残し貢献致しました。20数年行動を共にした三雲氏も夫より一足先に旅立たれました。(つづく)
「夫を偲んで」⑯
政治、新聞、鉱山、温泉のすべてが夫の人間愛から出たものでした。
「おとう様は人一人が一生、かかっても難しい仕事を180度の転換をしながらいくつもやり遂げ、何人分もの人生を送られたのですね」。
巍次がはじめて社会人になったとき改めて驚嘆していました。夫は政治、経済はもちろんすべての新しい知識も絶えず吸収し、世界の情勢に目を向けて的確な判断を下し、後に続く一人一人を大切に指導し続けておりました。夫に接した方々は夫の精神からきっと何かを受けて下さったものと信じています。
成格は父親のすべてを大変尊敬していたようです。自然を愛した夫は人間そのものをも非常に愛していました。だからその本質や生き方に深く目を注ぎ人間追究の手を最後まで緩めることなく「ジュラント」の世界の歴史6、700頁の本を1日100頁程の早さで読み進み、月1回の配本を待ちかねておりました。核心に触れるところには栞を挟んでおき、私に後でゆっくり読むように、そして時間ができたら一巻から丁寧に読むが良いと申しておりました。
奇しくも全32巻を読み終えて間もなく、私に「あの本はもういいんだよ」と申し最後まで確かな思考力を持ったまま、それらの過去の人々の中に融け込んで行ってしまいました。
「ジュラント」のほかに、伊藤清の明治精神に生きる、富永健一の社会変動の理論、L・エルコーザーの知識人と社会、永井陽之助の柔構造社会と暴力、マーシャル・マクルーハンの人間拡張の原理=メディアの理解などをつぎつぎにひもといて、読書三味の明け暮れでした。
これより先、亡くなる4カ月程前のある日夫は私の手を握りながら突然「お前は俺の手で作りあげた立派な財産だ、これをおいて死ねますか」と申しました。その時は、本人もそうであったでしょうが、私も別れるなどとは夢にも思っていませんでしたから「お前をおいて死ねますか」といった愛の極限のような言義だけが大きく私の心を震わせました。思わず涙ぐみながら、恥かしさも手伝って堅くなって俯いてしまいました。仕合わせ過ぎるような気もしましたが、夫の口からぎりぎりの愛の言義などを聞くと痛々しい気も致しました。
そんなことをとつおいつ考えているうちに、私を財産などといった言義が少々心に掛りはじめました。
「財産って……」
思い切って、私は小さな声で聞いてみました。私は夫の心の疲労を極力防ぎたい気持から年毎に会話は手短かになって行きましたが、かえってお互の心の触れ合いは深さを増していました。
「宝ものでもええ」
おおむ返しにいつものほほえましい素直な返事がはね返ってきました。
「俺のやってきたことはすべて俺の心だ。そのことはお前も十分に知っていたはずだな。小笠原の会社、土地もそうだ。ぜひ金にしたいという人に頼まれて援助のつもりで買って上げたものだ。戦時中は食糧難に苦しんでいた東京の人々を救ってやりたいと思い、肉、野菜、果物、乳製品、砂糖等当時手に入らなかった品々を船で運んで無償で配給してあげた。それはお前も知っての通りだ。戦争が激しくなり船が行けなくなってしまい、一部にしか行き渡らなくて残念であったが、つまり俺が財産といった意味の中には物とか金とかの観念はない。心あるいは命といってもええ。解ったかい?」
私は黙って聞きながらひたすら夫に長生をしてもらいたいと念じていました。80歳といえば既に天寿を全うしたと考えられる年令には違いありませんが、全く持病というものがなく、したがって夫も私ももう20年共に元気で暮したいと願い、お互いにあらゆる努力を払ってまいりました。そしていつしかそれが確かなもののように思いはじめていたのです。(つづく)
「夫を偲んで」⑰
そんなことをあれこれ思いめぐらしていた私に夫はさらに尻上りの優しい声で「解らんかい?」と問いかけてきました。「解りました」と答えた時私の日からは既に涙が流れ出していました。
「小笠原に老人の楽園をつくりましょう」と私が提案すると、夫は「うん……。」と答えて目をとじ、それから「あの人も、この人も連れて行ってあげよう」と早速人選に取りかかり、楽しく話し合いました。
その人はもう逝ってしまったのです。「そのうちに私達も小笠原のお月様を眺めて暮しましょう」と毎日のように語り合っていましたのに。
「病気だ」とは決して申しませんでした。中央広告通信、東京ポスト社長岩田富美氏を夫は20数年来わが子以上に可愛いがっておりました。氏は夫の体を案じて大きな病院に優秀な医師団を構え、いざという時に備えてくれました。また成格も慶応その他の病院の院長、副院長と懇談を重ねて備えを固めておりました。しかし遂に夫の翻意を促がすことはできず、最後に静かに近距離の病院に入院致しました。院長が立派な方で夫の意を尊重して扱って下さいましたことを心から感謝しています。治療は受けたくないという夫の意になるべく添うようにはかって下さいました。
急であったにも拘わらず、設備の整ったドックの部屋を二つ提供して下さり、万全を期して下さいましたが、夫は静かに自分自身の心で命を見詰めながら最後まで死を意識することなく、明日を信じて永遠の眠りにつきました。私には生命に対していざという時死を覚悟しての強さがありました。夫には生きている限り死を認めない強さがありました。私も夫にならって、弱い体で医薬から離れて20数年になります。その強さの相違をはっきりと知らされた瞬間でした。
アメリカ在勤の巍次も入院と同時に帰国し、最後の孝養を尽し得たことは何よりでした。夫は亡くなります5カ月程前から巍次に会って話したいと申しておりましたから。
夫は成格(毎日新聞政治部記者)、巍次(伊藤忠商章ニューヨーク駐在、26才)、それに孫の大太郎(東大教養学部在学、18才)、雄作(慶応義塾高校在学、16才)、美恵子(同中等部在学、12才)たちをはじめ、甥姪の子供達や、岩田氏の長男の健作ちゃん、長女の典子ちゃん、など夫を尊敬し慕っていた多数の良い後継者に恵まれております。夫の心が永遠に引継がれて参りますことを願ってやみません。
夫の人生をより有意義なものにし、常に見守って下さいました多くの皆様に心から感謝申しあげます。(「夫を偲んで」おわり)
(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年6月8日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その6
【岸井成格さんの父・寿郎さん】。
岸井寿郎さんの最初の奥さんは病気で死去。2人の男児が成人した後、再婚した夫人も昭和17年に出産のため入院した時、亡くなりました。昭和18年4月に再々婚された慶子夫人との間に、成格(三男)さんと巍次(四男)が生れました。36ページにものぼる慶子夫人の「夫を偲んで」は、激動の時代に寿郎さんがどのように生き抜いたかを詳細に書いています。抜粋して紹介します。
「夫を偲んで」⑤
昭和16年12月8日、真珠湾奇襲攻撃の戦果に酔いしれたのも束の間、昭和17年4月にはB25の陸爆機により東京および名古屋は初空襲を受け、更にその年の6月5、6日にはミッドウエー島沖の日米の海戦で日本軍は壊滅的な打撃を受けました。その後は坂を転げ落ちるような敗戦の一途を辿っていたのですが、大本営は相変らず目覚しい戦果の発表をし続けておりました。事実とは全く相違していましたが、そのことはいち早く夫の耳には入っていた様子で、
「大本営の発表をメモしておけ、事実との相違を調べるから」
といっておりました。夫の和平工作は同志の方々と共に進められていたようでした。
昭和19年1月には次男が学徒出陣で沖縄に向かい、6月には夫の身を案じ続けていた姑を亡くし、7月には長男を司政官としてビルマに送り、9月には三男の成格が誕生しました。孫の出産を楽しみにしていた姑を失ったことは夫と共に大きな痛手でございました。戦時中で思うように孝養の尽せなかったことも心残りでした。
夫は香川県の古い藍問屋に生まれましたが、父を早く亡しく、母の手一つで育てられました。姑の言葉のうちで特に私の心に残ったものを拾ってみることに致しました。間に合わぬ使用人をよく労わり他の者に、「足らぬ者(能力のないもの)には足してやるより仕方がないではありませんか」といい、またいつも口先ばかりの人には、「心で思うて頂くことも有難いことですが、本当にして頂く方がもっと有難いことです」と一寸苦言も呈しました。
子供の教育については一見識を持っておりました。「不道徳の芽だけをつみ取ってあげれば良いのですよ。良いことは誉めておあげなさい、心の栄養ですからね。善悪のけじめは一番難しいことですね。言い聞かすより前にまず親が自分の心にしっかりと問うて見て、あやふやなうちは決して口にしてはなりません。間違うたことを押しつけることになりますからね。これは一難かしい……」 自分に言い聞かすように話しておりました。(つづく)
「夫を偲んで」⑥
熱海といえば、古い友人の川島正二郎氏とは同じホテルでしたのでしばしば落ち合い、時には成格、巍次も交えて時局談にひとときを過ごすこともありました。昭和19年末から20年にかけて、夫は母を亡くした悲しみに浸る間もなく、国の将来を案じて東奔西走し、夜帰宅してから原書で英米の空軍の実態などを調べ、それを翻訳して私に清書をさせていました。国会演説で軍の拙劣さを追究するための資料の一つでした。
その日も使用人達が寝静まってから、広い邸の離れの一室で、その上尚且つひそひそとあたりを憚って話し合いながら明け方まで続けられました。
「勝てるのでしょうか」
「敗けるさ、最初から勝味などはない」
「敗けるって……。それは大変なことではありませんか」
「大変なことだよ」
「敵が上陸して来るようなことになったら、私達は皆殺しにされてしまうのでしょうね」
「手むかうから殺される。アメリカ人は降伏した相手を皆殺しにする程野蛮じゃない。今より良くなるよ」
「降伏……」
私は夫の顔に目をとめました。
たった今重大なことを目にした人とは思えない静かな表情でした。しじまの音のみの静寂の中で夫のページをくる、かすかな音だけが息ずいていました。
「だからこれ以上無駄に国民の命を失わせてはならんのだ」
夫がぽつりと重く口を切りました。
続けて何かを話していなければやりきれない気持なのに、もう話すことはなくなってしまいました。犬の遠吠えでも良いから何か大きな声で、今のこの静寂を自由に勝手に思いきり破ってほしいと思いました。
日頃の夫の言動から、勝つと思っていたわけではありませんでした。軍の独走の中で、和平に導く時期と方法が問題だと漏らしていたことがありました。停戦協定の時期はもう失してしまったようです。既に昭和19年7月にはサイパソ島玉砕により、マリアナ基地を失ってしまった責を問われて東条内閣は総辞職をし、小磯内閣の時代に移っておりました。
降伏をしても今よりは良くなるといった夫の言葉は、軍の横暴によって自滅の道を辿っていた日本が兎に角新しく生まれ変わるということのようでした。目かしくをはずして国民の一人一人がそれをはっきりと認識しなければならない最後の時期に来ていたのです。
「だから……」と夫は言葉をきり、「これ以上無駄に国民の生命を失わせてはならんのだよ」とまた同じ言葉を繰り返しました。(つづく)
「夫を偲んで」⑦
戦時中の激しい生活の中で夫がほっと一息つくのは、生まれて間もない成格のお守りをする時でした。大きな椅子の上にあぐらをかき、その中に赤ん坊を入れて、丁度巣の中の小鳥を覗き込むような格好で「良い子じゃ、良い子じゃ」と飽かず眺めていました。
成格に対する父の愛情は生涯を通して変わることなく続き、成格もまた大変父を尊敬しておりました。高校生の頃からは、父子というより恩師と愛弟子のような話し合いが多かったように思われました。
玉川用賀は当時大変不便な所で、その上ガソリンは次第に入手が困難になり、運転手も出征や徴用で取られてしまいましたので、夫が毎日出て歩きますのもなかなか容易なことではありませんでした。
しかしそうした所にも拘らず、多くの方々がよく訪ねて下さいました。当時衆議院議員であった永野護氏、楢橋渡氏、日本出版会々長の久富達夫氏、河出書房社長の河出孝雄氏などはしばしばお出でになり、殊に永野氏はいつも庭の木の間を夫と密議をこらしながら歩きまわり、その儘風のように去って行かれる忙しさでした。
昭和20年の5月中旬であったと思います。小磯内閣の時行なった夫の国会演説の原稿は一室に缶詰にされた上、激論の末に当時の陸軍次官の手でその3分の2を抹消されてしまったと聞きました。しかしその重要な部分の一部を敢えて発言し、翌日の朝日新聞の朝刊であったと思いますが、一面の真中に囲みの記事で掲載されました。それから間もなく軍を批判したということで憲兵隊に逮捕の指令が出されたのです。
楢橋氏が事前に知って早速知らせに駆けつけて下さいました。氏は急ぎの用事があるからと、すぐ帰って行かれました。夫は私を伴って自室に入り、暫らく黙って座っておりました。そのさり気なく寛いた姿勢から、むしろこうした場合の夫の強さを感じました。
「あいつらに俺がくくれてたまるか」と一人言のように申し、「俺に一つのチャンスを与えることになるだけだよ」と今度は私に話しかけました。逮捕されるかも知れないということは、既に二人共感じていたことでした。
しかし夫の言葉は何らかの成算があってのことに違いありません。一年程前にスパイの嫌疑で軍法会議にまわされ、死刑の判決を受けた青年の無実を立証して連れて帰ったことがありました。
「軍の首脳部だろうとアメリカ人だろうと、全部が全部敵味方に分かれてしまっているわけじゃない。止むなく立たされてしまった異なった立場で、実は同じことを考え合っている。誰も彼もがそう馬鹿になれるもんじゃないよ。一部の奴らを除けば通じ合うものは今も昔も少しも変ってはいない。話せばわかるもんだよ。だがしかし、このことにも限度はある。あくまでも詔勅による聖戦ということになっているからだ」。
いいたいこと、やりたいことがどこかで止められる。通らないのです。でも通さねばならなかったのです。決して油断はなりませんでした。首相の小磯国昭氏は古くから夫とは懇意な間柄でそんな乱暴をするはずはないと申しておりましたし、軍の首脳部にも記者時代から親交のあった方々も多かったのですが、既に下剋上が横行している軍の内部では、上司の知らぬ間に何をしでかすかわからないということでした。
殊に憲兵隊はなお東条の勢力下にあったのです。逮捕令は決して軽視出来ませんでした。当時陸軍は戦況の不利で焦躁しており、邪魔気のものは暗黙の中に取り除く位のことは平気でした。しかしその後間もなく玉川の家は戦災を受け、その翌日には逮捕状のあった渋谷の憲兵隊は跡形もなく焼け落ちてしまいました。邸の片隅に焼け残った倉庫を住まいにして、私達は戦災で失った女児の野辺の送りを済ませました。(つづく)
「夫を偲んで」⑧
その後軽井沢の別荘に落ちのびました。玉川の家より広大な建物の中には前々からの布団、衣類、食器など2、3家族分位はありましたので不自由なく暮すことが出来ました。
楢橋渡氏一家は横浜で戦災を受け、私達より一足先にこの別荘を仮住いにされて暮らしていました。国際地区軽井沢には敵機も近寄らず、東京で受けた空襲は一夜の悪夢ではなかったろうかと錯覚する程の静かさでした。
しかし夫の身辺は東京以上に慌しさを増して参りました。鳩山一郎氏、石橋正二郎氏、坂本直道氏、本野大使など軽井沢におられた方々と往来して語り合い、また私宅その他でしばしばその会合も持たれるようになりました。外国関係者も在日者は殆んど軽井沢に集まっており、スイス大使は隣りに住んでいました。夫の仲間はいろいろのルートから大戦の真相や世界の情報をいち早く入手していました。日本の破局はその頃既に時間の問題でした。会合のときの論議は、如何にして徹底的敗戦を食いとめるか、また一方、万一の場合の後始末と再興の策如何、などでした。
しかし軽井沢でも特高警察が常に夫達につきまとっていましたので、油断は出来ませんでした。東京でも同じような会合が持たれていました。ある日、鳩山氏が軽井沢の拙宅に来られた時、あいにく私は疲れのため伏せっておりました。
別荘には1000坪程の見事な苔庭がありまして、氏はそれをめでつつ庭から入って来られ、客間を通り抜けながら、「いま葱の土寄せを済ませて来たところです。奥さんはお料理が上手なそうで、今日は楽しみにして来たのですが残念でした」といわれ、夫と共に応接間の方に去って行かれました。夫は、現在疵を負っていない、つまり国民の納得の出来る人は鳩山氏位のものだと申して、氏の今後に期待を寄せておりました。その後私は身重の体に大きな打撃が重なり、床につく日が多くなりました。
昭和20年7月のある日、突然表玄関から大広間にかけて慌ただしい足音と大きな話し声がし、まどろみかけていた私は驚いて飛び起きました。楢橋氏一家は既に浅間温泉に移られ、夫は軽井沢と東京とを行ったり来たりの生活が続いておりました。
あいにくその日は上京中で、家に別荘番一家と、夫が私の体を案じて東京から連れて来てくれた年老いたばあやだけでした。慌てて駆けつけて来たばあやは、「軍人さんが」と言ったきり驚いて口もきけません。やがてどたどたと無遠慮に日本間の方まで入って来た彼等は土足のままです。(つづく)
「夫を偲んで」⑨
「ご主人は?」
逮捕に来たのかも知れない……。
さっと血の気が引き、体の氷る思いで私はじっと苦しさに絶えていました。
「今おりません、旅行中です」
「ああそぅですか」
4、5人の将校達はどやどやと客間の前を通り過ぎ、中庭をまわって浴室の方へ行つてしまいました。
「広い浴槽ですな、これなら一どきに5人や10人は大文夫でしょぅ」
大声で話し合いながら浴室から調理室にまわり、それから二階、階下の各室を検分してまた広間に戻ってきました。逮捕に来たのではないことを知ると私は急に強くなり、彼らについて大広間に入りました。彼らは大きな丸テーブルの上に地図を広げる真似をして、「この部屋を会議室に使えますな」などとあれこれ勝手に相談をし合った後、
「この先の近藤別荘に近々皇太后陛下がご疎開遊ばされるご予定です。ここを参謀本部に使用することになるでしょう。ご主人に伝えておいて下さい。また明日来ます」といい残して、さっさと引き上げてしまいました。
ちなみに昔三井の建てたこの別荘は、帝国ホテルを設計したライト氏が設計に3年を費やしたということで、その後も日本館、洋館共に、くるみ、糠、あるいは牛乳などで磨きあげられたもので、土足で入るようなものではありませんでした。一体私達をどこへ追い立てるつもりなのだろうと暗胆とした気持になり、また急に疲れが出てそのまま大広間の椅子に倒れてしまいました。くやしさと逮捕に来たのではなかったという安堵の気持とが交互にこみあげて参りました。電話で知らせを受けた夫は、その日のうちに帰って参りました。
そして私の報告を黙って聞いただけでした。翌朝早く起きた夫は、「運動せんと難産になるぞ」と私を伴ってゆっくりと庭を散歩し、昨日のことはあまり気にもしていない様子でした。
「今日は何時頃来るといっとったかい」 「うっかり致しました。聞きもらしました」 「そうか、あんな頭で国を台なしにしてしまいよる。無作法は奴らじゃ」 「……」 「あいつらに会ったらまたすぐ東京へ行くよ。せんならんことがたくさんあるからな。体に気を付けないかんよ」 「はい。でもお留守中に入り込んで来るようなことがありましたら……」 「今日きっぱり話をつけておく、そんなことはさせんよ」
逮捕命令の出ている今、余りきついことをいって火に油を注ぐようなことになってはと、心配でもありましたが、また一方ではいつもの夫らしい大局をふまえてのものの考え方と対処の仕方があるのであろうと思う気持もありました。(つづく)
「夫を偲んで」⑩
昼頃軍人たちが門からなだらかな坂道を玄関に向かってやって来るのを、大広間で見ていた夫はやおら立ちあがり、一足先に玄関に出て何の気負いもなく彼らを待ちました。
「昨日伝えておきましたが」
「俺はこの家の主人の岸井だ。名前をいい給え」
「古閑です」
「東条のむこだね」
「は」
「東条が取れというたか」
「いや」
「帰ってそういい給え。軍は勝手に国の資材を使うてたちどころに勝手なものを建てよる。俺は東京の本宅を焼かれた。その上別荘までよこせとは何事だとな。君らの理由は勝手に何とでもつく立場だ。しかし俺はそうはさせんよ。解ったら帰り給え」
夫の今の心情その儘の静かな叱るというよりは諭すようないい方でした。息を呑んで直立不動の姿勢を取っていた彼らに表情の変化さえ与えませんでした。彼らはその儘敬礼をして帰って行きました。
「もう来ることはない」
翌日夫はそういって東京へ発ちました。ところがその翌日から私服の二人の男が無断で庭の中をウロウロと歩きまわりはじめました。「一人は軽井沢の人間で、特高警察の人です」という別荘番の言葉に、いよいよやって来たなと思い、夫に連絡をしようと思いましたが、よくよく考えてみますと、夫は上京中ですし、家を取りに来た様子でもありません。
逮捕命令の出た時でさえ「逃げもかくれもせんよ、そんな必要もないし、第一仕事にならん」と申して軍部との折衝も続けていたようですから、こちらに逮捕に向かってしかも無駄な時間をひねもすウロウロしている必要もないわけでした。何のことやらわけが解りません。仕方がありませんのでこちらも遠くから彼らを観察することにきめました。彼らは周囲より少し高台になっている邸の中から一日中外を眺めています。
別荘番にそれとなく話しかけさせて見ましたが職務上何もいいません。無断で入って来て我がもの顔に居座っています。こちらとしては全く妙なお荷物を抱えて暮しているような気持でした。
一週間程たって夫が帰ってきました。空襲、逮捕の危険の中を歩いている夫です。帰るたびにひそかに夫の無事を心から神に感謝しました。夫は彼らの側に行き、何やら四方山話でもしている様子で、ニコニコと話し合っていました。そして別荘番にいい付けて二脚の椅子を彼らのために用意させました。私の家の近くにはアルゼンチン、スイスなどの大公使の別荘がありました。彼らはそこへ出入りするスパイの容疑者をチェックしていたということでした。もちろん夫の身辺と、出入りの人々を見張っていたことも確かでした。 「もうその必要はなくなる。古閑達もそうだが気の毒な奴らよな―」と夫は嘆息を漏らしておりました。
夫から見て気の毒な人々は敵味方の区別なく、そこら中に充満していました。敗戦も未だ知らず、明日の命もわからずに何かを信じて職責を守っている若い彼らの顔を、夫は見るに忍びなかったようです。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年6月2日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その5
【岸井成格さんの父・寿郎さん】。
元東京日日新聞政治部員だった岡田益吉さんが「岸井さんは語る」と題して、18ページにわたって書いています。当時の東京日日新聞の内情と政治の動きについて以下、紹介します。
<麻生久氏と自由党>
岸井さんは、戦時中郷里香川県から衆議院議員に当選した。政治には興味はあったが、政治的野心はなかったと思う。社会運動の中心人物であった麻生久氏とは、三高時代から刎頚の友であった。しかし前述したように、ソ連の実情を視察して帰国した岸井氏は、盟友麻生に「社会主義は官僚制度の幣害がひどくなるのでダメだ」と批判していた。
その後、近衛第一次内閣の末期、38名の社会大衆党を擁した麻生氏は、亀井貫一郎や橋本欣五郎陸軍大佐(のちに赤誠会長)らと組んで、「近衛公によって日本に国家社会主義を実現する」という計画を抱いた。そして連日のように岸井氏に協力を熱心に頼んだ。
岸井氏は「近衛などはアテにならぬから止せ」とはげしく反対したが、自分の自動車を一台麻生に提供して、「君は自分の好きなようにやれ」といっていた。がついに麻生氏は「もうすでに新内閣の大蔵大臣に岸井寿郎をするよう、近衛と約束してある。どうしても自分を助けて欲しい」と膝詰談判にまで及んだ。
岸井氏もさすがに断りかねたのか「君とは切っても切れぬ友情で今日まできた。自分は反対だが、ヨシッ、それでは君と心中しよう」と快話して、鉱山その他岸井氏の財産を処分して、政治資金までつくった。その翌朝、かんじんの麻生久氏は心臓病で急死してしまい、岸井氏は茫然自失した。 これが氏にとって、城戸事件とともに一生の痛恨事であった。
岸井氏は、こんな大きな二つの挫折感を乗切って80歳の天寿まで生きつづけたのであって、その剛毅と純情さは他人のまねができないことであった。岸井氏の用賀の家の前に、東条英機大将の家があった。東条がある日、自分で、改良式の七輪(しちりん)と金具のない木の鍬を岸井邸に持ってきた。岸井氏は仕方なく無言で受けとったが、奥さんがあとで東条邸に礼に行ったといって、大変怒ったそうだ。
衆議院書記官長大木操氏の「大木日記」に、岸井代議士の名が幾度か出て来るが、その内容は少しも書かれていない。恐らく、当時軍部を憚かるような発言だったので、故意に省略されたのではないかと推測される。終戦前、用賀の自邸を空襲で焼失されたので、岸井氏は軽井沢へ閉じこもった。
ここで坂本直道氏(元満鉄パリー事務所長)の紹介で鳩山一郎氏と懇意になり、終戦とともに、馳せ参じた芦田均、林嚢二などと、新政党樹立の計画に参画したことはあまり知られてない。その後坂本直道氏と上京して、石橋正二郎邸の一隅で、新党計画をつづけたが、いよいよ旗上げの前夜、交詢社で最後の準備会をしたとき「党名を何とするか」が議題に上った際、岸井氏は真っさきに発言して「自由党とすべきだ」といった。「日本自由党」というものもあったが、「日本は不要だ」と岸井氏は強く主張した。「世界の自由党」を意図したのではないかと思う。何れにしても、現在の自由党の命名者は岸井氏だったのである。
晩年「雀百まで踊る」と称して、日曜夕刊「東京ポスト」を創刊して、無料配布という破天荒の新しい新聞を企画したのは、いかにも新聞人、岸井氏らしい貴重な置き土産であろう。(つづく)
◇
岸井寿郎さんの最初の奥さんは病気で死去。2人の男児が成人した後、再婚した夫人も昭和17年に出産のため入院した時、亡くなりました。昭和18年4月に再々婚された慶子夫人との間に、成格(三男)さんと巍次(四男)が生れました。36ページにものぼる慶子夫人の「夫を偲んで」は、激動の時代に寿郎さんがどのように生き抜いたかを詳細に書いています。抜粋して紹介します。
「夫を偲んで」①
夫のことを書こうと思いましても、こみあげるものに遮られて遅々として進みません。でも与えられた命を謙虚に享受し毎日を大切に生き抜いた夫の一面を思い出しますままに綴ってみることに致しました。
結婚当時、夫がこんなことを申したことがありました。
「叩かれて潰れてしまう様ではいかん。叩かれても蹴られてもゴムまりのように跳ね返ってついて来い」。
当時は戦争も末期の大変な時代でしたから、夫の帰宅はいつも遅くて、午前2時3時ということも珍らしくはありませんでした。夜中に二重まわしの衿元を少しはだけて、ゆっ<りと車から降り立つ姿からは、思わず胸の引き締まるような気魄が感じられました。私は夫の任務の重要さも、言葉一つに命の懸っていた当時の立場も、十分に心得ていたつもりでしたので、必死について行こうと懸命でした。
ところが毎日よく叱られるのです。といいますよりは、何もしないうちに先に叱られてしまうといった方が当たっているのかも知れません。その上、力のこもった大きな声ですので、ひどく叱られているような気持になってしまいます。
「もんぺなどはくな、世の中が汚のうなってかなわん。格好など好きにしとればよろしい。それよりも女はどんな時も女でなければいかんよ。夫と子供の大事さ、可愛いさを見失ってしもうては何もかもがわやじや(駄目になってしまう)」。
前日の昼下りに庭で夫と共につい耳にしてしまった塀越しの立話を、その時ふっと思い出しました。息子を叱叱激励して特攻隊を志願させたと二人の母親が話し合っていたことでした。「女は愚かなもんよな― 。姿を構えさせておだてればいつしか心までも鬼になってしまいよる」。その時夫は憮然とした面持で私を見詰めました。しかし戦時下に夫の意の儘にしたがうことは大変難かしいことでもありました。当時の常識と既成観念も無視してかからなければならない場合も出て参ります。
昭和18年の冬近い頃であったと思いますが、玉川用賀の拙宅の近くに住む東条英機氏(当時の首相兼陸相)が訪ねて参りました。その前にも二、三度来られましたが、夫は何時も中に招じ入れようとはせずに、表玄関のドアーの外に立たせたまま話しておりました。その日は秘書に粘上のコンロと木製の鍬とを持たせて、「私の手製ですが大変具合が良いので使ってみて下さい」ということでした。
「それは有難う」
素気ない返事で、相変らず内と外とで暫らく話を交わし、やがて氏は帰って行かれました。両肩を落とし、背を丸くして俯き勝ちに歩いて行く氏の後姿は大変佗びしいものでしたが、何か深く考え込んでいる様子がひどく心に掛りました。
私は東条氏に会ったのはこの時が最後でした。丁度その頃近所の家に親戚の者だという老人がしばしば訪ねて参り、その都度私宅へも立寄りました。時局に関する話をぜひ伺わせて頂きたいということでした。(つづく)
「夫を偲んで」②
「あの老人は東条の親戚だそうじゃ。今日軍の主脳部の人間が注意してくれた」。
東条氏の来られた数日前に夫が申していたばかりでした。兎に角うっかり心の許せない夫の身辺でした。
2、3日後に私は田舎から送られて来た「あんぽ柿」をたずさえて東条家を訪ねました。鍬とコンロのお礼のつもりでした。が、ただそれだけであったといっては、心の隅に少しうしろめたさが残ります。何ともいいようのない不安がつい東条家に足を運ばせてしまったのです。夫には内証で出かけましたのもそのためでした。
軍行動を批判した場合には、統師権の干犯という言葉があって軍の一部の者の独断専行ではありましたが、一国の宰相であろうと、国会がそれを取り上げようとした場合であろうと、軍部は天皇の御名において統師権の干犯は許さぬと強く反発したようですし、またことと次第によっては命にかかわることにもなりかねなかったのです。
東条家から帰ったとたんに激しい夫の怒りに震え上がりました。
「旦那様はご存知かと思いましたので」と女中がオロオロしておりました。迂闊なことをしてしまったという悔恨と、夫の立場を傷つけてしまったのではないだろうかという不安に一層かり立てられる結果になってしまいました。
夫には押しても突いてもどうにもならないと感じさせる強さがありました。黙ってじっと座っている姿から殊に強くそれを感じました。強さというよりは、偉さというものなのかも知れませんが、実はその言葉でさえ満足の出来ない、もっと大きな何かが心に迫まって来るのです。信念などという生やさしいものではなくて、まるで宇宙の法則のような安定感がありました。あるいはそれは夫の本質というものであったのかも知れません。人間本来の姿がそこにあるといった感じなのです。衒いも、翳りもなくて、そのために人間の弱さによって怯むということがないせいでしょうか。微動だにしないような強靭さがあって、それが夫の風格となっていたように思われました。(つづく)
「夫を偲んで」③
話は前後致しますが、昭和の初期に高等女学校に在学していた私は、当時の逼迫していた日、英、米の国交問題とか、除々に戦争に追い込まれて行く八方塞がりの日本の国情とか、あるいは不況を背景にしてのサンガー夫人の産児制限のこととか、兎に角、暗い講演ばかりをよ<聞かされて、多感な少女時代を過ごしましたので、「聖戦」ということも仕方がないのだと是認する気持が強かったのです。
そうしたある日、遇然私は岸井寿郎という人にめぐり逢いました。永らく病床にあった最初の妻をつとに亡くし、その後子供達のためにやもめ暮しを余儀なくされておりましたが、彼等も成人し、再婚をしたばかりという時でした。昭和16年の5月頃であったと思います。
私はその時、幼時にきめられていた縁談を断り、そのために起きた様々な経緯からのがれて家を出、当時牛込に住んでいた叔父の軍令部出仕の海軍中佐の家に身を寄せて、ある学校に在職していまました。私にとっては大変有意義な毎日でしたし、また華々しい戦果にまだまだ国全体が酔いしれていた時でもありました。私は彼の会社の応接間で彼から思いがけないことを聞かされました。
「聖戦などというのは誤魔化しですよ。無謀な一部の軍人達の思い上った出世慾と陸海軍の勢力争いとに、この戦争は端を発しているのです」
『叔父に聞かせたい言葉なのだろうか、いや違う』と、私は自問自答しながら彼の鋭い眼差しを真直ぐに見返しました。口に出すのを憚からねばならない言葉でした。私の動揺を見て、彼は優しく言葉を続けました。
「ものを教えている貴女がこんなことを口にしてはえらいことになる。時期が来るまで心に収めておかれた方がよいでしょう」。
彼は客を待たせてあるからと、さっさと部屋を出て行ってしまいました。会社には連日大勢の人々が様々な用件や相談を持って詰めかけておりました。鉱山会社と土木会社を経営していたのですが、私は最初、彼は何をしている人なのだろうかと不思議に思ったくらいでした。
「こんな世の中になると、良い人間程困っている。面倒見てやらんならん人がたくさんいるのでね」といっておりました。今考えてみますと、各界の上層部にひろがる深く広い交際範囲と、彼自身の力とが相俟って多くの人々を援助する手だてとなっていたように思われます。大変因縁めく話になりますが、会ったばかりの私に戦争の真実の姿を知らせておきたかったことについて、結婚後次のように話しておりました。
「初めて会った時、これは結婚することになる人だと思った。再婚したばかりの俺が何故そう感じたのか未だに解らない」。
だから真実を知らせたかったのだということなのですが、真偽の程は解りません。が、嘘だとも思えないのです。どういう力がそうさせますものか……。はっきり解かることではありませんが、心からきれいに消し去ことも出来ません。(つづく)
「夫を偲んで」④
近衛の新体制構想によって生まれた大政翼賛会は政心一新、時局収拾のためのものでした。しかし、結局は麻生久氏が落胆の余り病を重くしてしまわれた程のものに作り変えられてしまい、好戦的な革新右翼の温床となり、あるいは一部の内務官僚に利用されるだけのものという結果になってしまっていたのです。そのためにかえって彼は渦中に飛び込む決心をしたのだと思います。彼が当選して間もなく、私は招かれて玉川の邸を訪ね、はじめて彼の母に会いました。彼が最も敬愛し、畏れてもいた人でした。私達は翌18年4月に結婚致しました.
その頃麻生久夫人が度々玉川へ訪ねて来られ、無産運動に生涯をかけていた若き日の氏と夫との姿を、巧みな話し方で彷彿とさせて下さいました。
当時令息の良方氏はまだ18、9の弱々しい文学青年でいらしたらしく、母上から伺った話は、夫人との恋愛問題とその結婚へのいきさつ等で、その後話題の美しい夫人を伴って来られたこともありました。今の良方氏を拝見し、偉大なお父上の政治家としての素質を受け継がれたばかりではなく、文、画才と様々な特質に恵まれていられることに驚かされます。
かつて夫は、革命10年祭のロシアを訪ね、その破廉恥犯の数の多さと、日本の国土の狭さ資源の乏しさに、適応し難い共産国家の現状を目のあたりにみて、その後は自由主義者としての道を歩んでおりましたが、主義を異にしてからむしろ麻生氏との人間的な繋がりは深さを増していったようでした。
河野密氏、片山哲氏、河上丈太郎氏、浅沼稲次郎氏、水谷長三郎氏、西尾末広氏、三輪寿荘氏、棚橋小虎氏(夫の姪の主人)、野坂参三氏等、革新政党の多数の方々とも永い間深い交わりを持っておりました。浅沼氏が亡くなります少し前、会の帰りに大井の宅まで夫を送って来て下さったことがありました。夫を最長老としていつも厚く遇し、革新政党への夫の苦言もよろこんで受け入れていられたと聞いておりました。
昭和19年の夏頃であったと思いますが、政治犯として10年余り獄中生活を送っていた佐野学氏が釈放になり、玉川の家に来られました。軍の圧制で総ての実行を封じられた氏は、「差し当たってどうしたら良いものか」と大変憔悴しておられましたが、出るために節を曲げざるを得なかったことに対して夫は、「命を落としては何もならんよ」と申し、
「体調を整えながら、このざまをしっかりと見届けておくことが今は一番必要だ、自由に動ける時がもうすぐ来るよ、君」
と、氏の肩を抱くようにして励ましておりました。しかし、氏は良い時代にもう一度活躍の機を持つことなく、亡くなり、あの時の顔を思い出しますたびにお気の毒でなりません。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年5月28日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その4
【岸井成格さんの父・寿郎さん】。
元東京日日新聞政治部員だった岡田益吉さんが「岸井さんは語る」と題して、18ページにわたって書いています。当時の東京日日新聞の内情と政治の動きについて興味津々の内容です。以下、紹介します。
<城戸事件の真相❷>
また編集の城戸、営業の吉武という鉄壁の陣は、朝日新聞その他の競争紙に、つけこむスキもない完璧のものであった。ところが、城戸氏が本山社長亡きあと(昭和7年12月)会長となった後、ある日吉武氏に呼ばれこういわれた。〝城戸氏に対して君も知っているように、今日まで誠心誠意協力援助してきたのに、いまになって私を首切るというのだ。全く『狡兎死して走狗烹らる』のたとえの通りで、私としては売られたケンカは買わぎるを得ない。いま社内は城戸派と反城戸派と対立して混乱しているが、君はどちらにもつかず、じっとしていくれ〟といわれ、ほんとうにびっくりした。私は実際、こういう血と血で争う醜い状態にがっかりして、もう新聞はやめようと心の底深く決意した。
私が反城戸派と目されているのも心外だが、城戸氏が大阪に行ってから私を相談相手にしなくなったのも事実だ。私は、いずれ首切られるものとマナイタの鯉のごとくじっとしていようと決意していた。ところが向う(城戸派)の方が倒れてしまったので、あっけにとられてしまった。しかし、今にして考えると毎日新間が城戸氏を失ったことは、返す返すも残念でたまらない。
当時私は胃潰瘍で心身衰弱しており、家内も重病で瀕死の床にあった。それでも何とかもう一度、城戸、吉武両氏が提携して毎日新聞を完璧の域に置こうと、最後の勇気をふるい起こして、再三城戸氏に面会を求めたが、城戸氏は東京にきても私には会おうとは絶対にしない。仕方なく大阪までも行ったが、新屋茂樹が代理で会うというので、新屋ではどうにもならない。
私の腹案は、吉武氏は城戸氏より10歳も老年である(岸井氏は城戸氏より10歳若い)。そこで、今すぐではないが、私が吉武氏を口説いて、円満にやめさせるから、ケンカはやめてもらいたいと城戸氏にいうつもりだった。そのころ、城戸会長のほか、欠員になっていた社長に吉武氏という噂があったことも事実だ。私があのころ体力が充実していたら、もっと勇気を出せたであろうし、出すべきであった。
城戸事件こそ私にとって終世の恨事だった。城戸氏を批判するつもりはないが、いま考えると、10年、時代がちがうということはバカにならない。城戸氏でも吉武氏でも何といっても封建時代の空気に育っていて、いいにしても悪いにしても私のような民主主義の教育を受けていないことが根本原因だと思う。時代の思想というものは恐ろしい。重役ともなると、何でも自分の思う通りになると信ずる傾向は封建主義の名残りではないか」。
城戸事件当時、私も岸井政治部長の下にあったし、いろいろ見聞することもあったが、私は派閥の争いなどには興味もなく、岸井氏の述懐についてコメントを加える必要もないが、岸井氏にとって一生の悲劇であったことだけは確かであったと信ずる。(つづく)
<正力松太郎傷害事件>
城戸事件の直後、岸井氏は政治部長から吉武営業局長の下に営業次長となり、東北の大冷害問題について、東北6県の救済運動のため奔走した。これは東日の東北に対する大キャンペーンであった。ところへ突如として昭和10年10月、読売新聞社長正力松太郎氏が暴力団員に傷害を受けるという事件が起こった。
当日、東日販売部長で岸井氏の輩下であった丸中一保が東日に出入りしていた熱田佐に、正力刺傷を示唆し、熱田の乾分・長崎勝助が正力社長を襲った事件である。岸井氏は丸中を再三取調べ、そんなことはなかったことを確めていたので、熱田が岸井氏に面談したときも「丸中も相当教養ある者だから、さようなバカ気た依頼をするはずもないし、必要もない。東日とすれば読売の進出など眼中にない」といい切っている。
しかし事件は営業局長吉武氏にも波及してきたので、岸井氏は吉武氏に、「この事件は私が全部かぶって責任を負う」といったが、実はその前日に岸井氏は検事局の取調べのさい、熱田に答えたと同じく「そんなバカなことはない」といっているので、事件の泥をかぶることもできなかった。結局、丸中は伊豆で自殺し、吉武氏の退社となって、岸井氏は吉武氏の慰留で社に残ってしまった。昭和12年1月、岸井氏は当時の東日編集総務久富達夫氏(岸井氏の後任として政治部長になった)を東京会館に招き、東日退社の決意を明らかにした。
「僕の健康は難症だ。それに僕の信頼していた先輩たちは次々に社を去っている。一方僕は新聞というものに昔日のような情熱を失ってしまった。これ以上在社しても僕にとって人生の浪費だ」と悲痛な告白をしている。僕の信頼していた先輩たちとは、恐らく城戸氏と吉武氏だったのではないか。(つづく)
<大平洋石油会社創立す>
それからの岸井氏は実業界の人となったが、私は岸井氏はあくまで新聞人だったと思うし、実業界の氏のことはよく知らない。ただ一つ、メキシコの油田を開発しようとしたことだけは記録しておきたい。
昭和11年ごろ、斉藤実(海軍大将、首相内大臣)の密令を帯びて池田佐忠という人が、メキシコの石油開発権を獲得して帰朝したが、船中で2.26事件のため斉藤内府が殺されたことを知って絶望した。メキシコ在留日本人会長都留氏とともに、東京で奔走中、たまたま岸井氏の事務所を訪れた。岸井氏は石油資源をもたない日本の窮状をかねて憂慮していたので、王子製紙社長藤原銀次郎氏を口説いて、その斡旋方を依頼した。
「藤原さん、あなたはもう一会社の社長におさまっている場合ではない。国家のため、財界全体のために働くべきだ」と熱心に勧告したので、藤原氏も心を動かし、ついに王子製紙をやめた後、資本金500万円の大平洋石油会社を創立して社長となった。その副産物として、藤原氏が長年社長に居座っていたため人事が停滞していた王子製紙も、高島菊次郎氏が社長となり、足立正氏が専務になるというように、人事が刷新された。このさい、岸井氏は新会社の重役にもならず、一株の功労株も受けとらなかった。これは財界の美談として伝わっている。(つづく)

(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年5月26日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その3
【岸井成格さんの父・寿郎さん】。
元東京日日新聞政治部員だった岡田益吉さんが「岸井さんは語る」と題して、18ページにわたって書いています。当時の東京日日新聞の内情と政治の動きについて興味津々の内容です。以下、紹介します。

<東京日日新聞入社事情>
私は、戦後岸井さんを自宅に度々訪ね、主として時局に関して、氏の犀利な批判をきくこととしていたが、時には、氏の半生の生きた記録をきくこともあった。氏は自慢話など大きらいだったので、大部分こちらから質問したのに渋々答えてくれたのだが、晩年はいくらか好々爺になって、笑いながら、「こんなこともあったさ」という調子で話してくれた。
ある時、「こんなつまらない話でも、君が勝手に書いておいてもいいよ」といったことがある。 馬場剛著「明治、大正、昭和の日本」という本にこんな一節があったので、氏に問いただしたことがあった。
「桂(太郎)内間は2月11日(大正3年)に総辞職したが、大阪、神戸、広島に騒擾事件が起こり、17日から3日間、京都の事件は激烈を極めた)。その前夜三高の弁論大会がYMCAで開かれたが、今は名士である岸田幸雄氏や岸井寿郎氏が熱弁をふるい、しばしば臨席警官の中止をくい、はては演壇で学生と警官が組打ちをやる光景もあった。その翌日の夜、同じ会場で犬養木堂(毅、当時国民党々首、後政友会総裁。昭和7年首相として5.15事件で兇弾に倒る)の演説会があり、その群衆が円山公園へ行き、それから市内交番の焼打ちをやったのである」。
これが大正2年の第一次憲政擁護運動であった。三高学生岸井氏は血の気の多い青年であったことがわかる。
「私はそれから、犬養木堂について各地を回わり、憲政擁護演説会でしゃべっていた。それで木堂の知過を得た。大学を出たとき木堂を訪ねて、〝私はケンカ早く、どこに就職しても永続きにないと思うが、どうしたらいいか〟と相談したところ、木堂は〝それなら司法官になればいい。判事でも、検事でも、身分は一生保障されているから首になる心配はないよ〟と答えたので、私は検事になった。ところがやはリケンカばかりしていて、自分ながら困っていた。これをきいて当時東京日日新聞にいた、三高時代からの盟友、麻生久君(岸井氏とともに東大新人会を創立し、のち社会大衆党書記長となる)から〝では新聞記者になれよ。ここなら、いくらケンカしても大文夫だ〟といわれて、東京日日新聞社に入社したわけだ」。
狙介な犬養木堂と横紙破りの岸井氏は肌があったのだろうと思うが、これから氏の東日時代がはじまったわけである。官僚、軍閥と終生戦いぬいた犬養木堂と、東大新人会の思想的支柱であった吉野作造のリベラリズムは岸井氏の骨の髄まで透徹していたことがはっきりする。
ここで忘れないうちに書き足しておくが、ある日氏はこう語った。「戦後、あるアメリカ人が自分を訪ねて来て、大正デモクラシーから大正マルクシズムに転換して行った時分の人で、今日残っているものは貴君だけだから、その転換期の話をききたいというので、話してやったことがあった」と。そのアメリカ人の名も、その話の内容も聞きもらしたが、氏の社会主義批判は後述しよう。
岸井氏と犬養木堂の奇縁は、いつか氏が財界の大御所故官島清次郎氏(元日清紡績社長)に知遇を受けたという話にも関連していると思う。宮島翁は戦後、吉田茂、池田勇人、両内閣の陰然たる相談役であった。なぜなら、犬養と官島は切っても切れない関係であり、恐らく、岸井氏はかなり昔犬養の紹介で官島氏に会ったものと想像される。(つづく)
<山本(権兵衛)内閣成立のスクープ>
岸井氏は大正13年(私が東日に入社)ごろは整理部におり、当時酒豪ぞろいの東日編集局にあって負けず劣らずの酔虎の一人で、それが氏の痼疾であった胃潰瘍の原因となった。
その後政治部に入り文部省担当、東日紙上に「教育論」を連載したが、大正12年9月1日の関東大震災の瞬間、氏は山本権兵衛海軍大将が三度目に大命を拝して組閣中の築地海軍水交社の中庭にいた。水交社二階で山本伯と平沼騏一郎(当時検事総長)と司法大臣就任の交渉が行われていた。この司法大臣の椅子がきまれば、第二次山本内閣は成立するという瀬戸際に、大地震が襲来したのであった。他社の記者はみんなバラバラに逃げてしまったが、岸井記者はブルブル震動していた一本の立木にしがみついていた。そして、山本、平沼の交渉成立を確認するまでふみとどまった。その上、自動車を返さないで止めておいたので、すぐさまこれに飛び乗って社に戻り、山本内閣組閣完了を告げた。
このスクープは地球を一回りして、また東京に返電され、他社の知るところとなった。こういう際の氏のガン張りぶりは日に見えるようである。
<外紙を排して国産品主義をとる>
正力氏と岸井氏とのつながりは、もう一つあった。昭和9年1月岸井氏は本山社長の密命を帯びて、米国とカナグに新聞用紙の調査に行った。このことを探知した正力氏は、野沢商会の店主を岸井氏と同船させ、ロスアンゼルスで岸井氏に協力を依頼させるという強引さであった。
氏はカナダの各製紙会社を歴訪し調査をまとめてロスアンゼルスに帰ってくると、その野沢商会店主なるものは、その間2ヵ月、ロスアンゼルスのホテルで岸井氏の帰りを忍耐強く待っていたという。どこまでも、くいついて行けという正力氏の執拗さに氏も感心したという。氏の調査では、外紙は連(4頁新聞1000部)3円ぐらいで国産新聞用紙よりも連50銭安かった。
しかし、岸井氏が本山社長に提出した報告書の結論は「外紙はなるほど国産品より安く、外紙を使用した方が有利であるが、一旦緩急あった場合、外紙依存は危険であるばかりでなく、国産新聞用紙も漸く改善されようとしているし、将来新聞用紙の国内自給を確立することが、重大意義を有する」といって外紙購入方針を否定した。もともと熱烈な愛国主義者であった本山老社長も岸井氏の明決なる正論を欣受して、由来、毎日新聞は外紙を一度も使用しなかったし、王子製紙はこの毎日の膨大な新聞用紙需要によって、その後着々発展の途をとり、わが国の製紙界の進歩に寄与するところ人であった。王子製紙その他、ひそかに岸井氏の炯眼と決断を徳とした。
一方、ロスアンゼルスでは野沢商会店主の熱意にほだされて、岸井氏は快よくある有力なカナダ製紙会社社長に紹介状を書いてやったので、彼は、正力氏の念願に応えて安い外紙を手に入れることができた。当時読売新聞は販売部数が急激にふえる上り坂にあって、用紙購入に困惑していたので、一息ついたわけである。新聞社では上り坂の時の方が財政上苦しいのであって、この外紙問題でも正力氏は岸井氏の恩恵を受けたわけである。戦後、正力氏も岸井氏も追放の憂き目をみて、毎日、岸井氏は淡々として日本倶楽部で正力氏と碁を囲んでいたが、「正力の碁は、いつも相手の石を大きくとりかこむ一方だが、一つ破れ目が出ると総崩れになる面白い碁だった」と笑っていた。(つづく)
<国際連盟脱退論>
岸井氏が政治部長に就任したのは、満州事変勃発直後で、いまの若い人は理解し難いが、その頃の軍部はいまいわれているのと大ちがいで、政治的に極めて弱体であった。満州事変などは、軍として精一杯の窮余行動で、せっばつまった自衛策にとゞまっていたし、国内世論はその実態を認識していなかった。帝国主義とか、侵略主義とかいう景気のいいものではなく、国内も極度に経済的不況であり、日本としてどこかに脱出路を見出すほかなく、一方満州における日本の条約上の正当な権利は、張学良排日政権のため侵害され、全く追い詰められた状勢にあった。
ワシントン会議で成立した九カ国条約には、中国が国際条約を守るべきだという条項はなく、片手落ちのものだった。その上国内世論は不統一で、この際日本の新聞の言論は、浅薄な大正デモクラシーと大正マルクス主義に支配され、日本の現実について全く認識不足であった。このとき、岸井氏が大毎、東日に連載した「満州のわが移民村」と、「国際連盟脱退すべし」(何れも昭和8年)の二論文は最も特異なもので、一般言論界が満州事変に対して、暗にこれを非難するだけで、その実態を分析せず、国論を指導する気追と英知を欠いていたのに対し、積極的かつ建設的な主張であった。また、岸井氏独得の思想と勇気のある言説であった。昭和8年10月、関東軍以外の何人も行かなかった、北満の永豊鎮(のちに弥栄村)第一次開拓移民地に、岸井氏ははじめて乗込んで、現地を視察したのである。昭和9年1月に、氏は「満州移民と国策」という一篇を追加して、単行本として出版した。その内容について詳細に書く余裕はないが、この本は、氏のものの考え方を如実にあらわしているだけでなく、今日でもなお含味すべき思想を示している。
一言にしていえば、大正デモクラシーの基となっている自由主義には幾多の複雑な要素があったので、リベラリズムとして正当なる評価をされていなかったことがつくづく感ぜられる。氏のリベラリズムには濃厚な現実主義が基底となっていた。自由とは、外物にとらわれず、事実をありのまゝに見てこれを自由にとらえることだということが、今日の評論家、政治家の多くはわかっていない。ややともすると、リベラリズムを理想主義的にのみ空想して、現実の分析を忘れ、軽挙妄動する傾向が今日でも多い。
これは自由主義の本質ではないと思う。岸井氏の満州移民に対する批判には、軍部のやり方をはじめ、満州という環境に適応しない方策を指摘しながら、満州移民の絶対必要性を主張し、かつ、その可能性をこまごまと論じている。こういう実際的な評論家は、今日でも絶無ではないかと思う。
国際連盟脱退論でも、岸井氏のは連盟が満州国承認に反対するのがけしからんというような書生論ではなく、国際連盟そのものが不合理なやり方をしていることを、具体的に沢山の実例をあげて指摘している。こんな連盟にいつまでもかかずらっていることは、日本の国際的地位をかえって危うくするから、早く脱退した方がいいという実際的な考え方であった。
岸井政治部長は、東日紙上に堂々署名して連盟脱退論を連載していたが、当時の外務大臣幣原喜重郎氏を3回も訪問して会談している。官僚的秘密主義の幣原はついに岸井氏に胸襟を開かなかったらしい。当時、陸軍省担当であった私に「陸軍で話のわかるャツを紹介しろというので、私は荒木陸相の懐刀といわれた小畑敏四郎少将(当時参謀本部第三部長)に岸井氏を紹介した。氏は小畑と会談後「軍人としては、よく話がわかっている」と一言洩らしていた。話は連盟脱退の件であったらしいが、幣原がわからないので、やむを得ず軍部と話をしてみたのだと思う。
戦後、幣原の手記が公表されて、幣原の連盟論が全く岸井氏の説と同じだったのをみて笑っていた。自由主義というものが、あくまで現実主義でなければならぬという岸井哲学は今日こそ、もっと徹底して理解されるべきだと痛感する。(つづく)
<城戸事件の真相❶>
昭和41年10月28日、元毎日新聞会長城戸元亮氏は85蔵の高齢で道山に還った。私はすぐ岸井氏に電話で訃報を伝えた。電話の声で、氏が万感交々至るといったような沈痛な表情であったことが看取された。
前述したこともあるが、東日主幹城戸氏は岸井氏の最も敬慕する新聞人であり、城戸氏からいっても岸井氏は最も信頼する部下であった。当時城戸氏幕下として「東に岸井あり、西(大阪本社)に新屋(茂樹)あり」といわれたくらい城戸、岸井というラインは緊密なものがあった。それが昭和8年城戸氏が衆望を負って大毎会長となるに及んで、世にいう「城戸事件」という新聞界稀にみるお家騒動が起り、心ならずも岸井氏は城戸氏と訣別し、それだけでなく城戸派から岸井氏を目して城戸氏を裏切ったものと今日でも非難している悲劇となってしまった。
右の電話で、岸井氏は「城戸さんの葬儀はいつか、是非行くよ」と悲痛な声でいったのを今でも覚えている。一体城戸事件の真相はどうたったのが、岸井氏は果して城戸氏を裏切ったのか、私もそれまで、一度も氏にたずねたことはなかった。
城戸氏の葬儀の日、岸井氏は毎日新間に入社したばかりの三男成格君を同伴して、告別式に参列した。かつての城戸派の人々とも氏は久闊を叙していた。その翌日、岸井氏から電話がかかって「一寸来てくれ」というので岸井邸に行った。氏は一寸改まった口調で次のような「城戸事件の真相」を語った。私は、そのときの言葉をそのままに記録しておく。
城戸事件についてはいままでどんな懇意な友人にも、まして家族などにも一言も話したことはない。いろいろな人に迷惑をかけてはいけないし、ことに城戸さんにどんな経路で耳に入ることがあるといけないと思って今日まで固く沈黙を守ってきた。いま城戸さんも亡くなられ、君は城戸さんともよかったので、真相を話しておく。私は城戸さんを尊敬し、ずいぶん世話にもなり、新聞人、ことに編集陣の人として、えらい人と今でも信じている。君も知っているように、大正天皇がなくなって年号が大正から昭和に変ったとき、毎日新聞が、新しい年号は「光文」であると誤報した「光文事件」というのがあった。
皇室中心主義の本山彦一社長は激怒して東日主幹であった城戸さんを首切り、外遊させてしまった。私は営業局理事吉武鶴次郎氏を訪ね、〝社長はあまりに横暴ではないか、城戸氏というあれだけの人物を首切るとは何事か。私は体を張っても、この乱暴なやり方に反対して、あばれてみせる〟と厳談した(本山、城戸、吉武三人は何れも熊本出身)。
すると吉武氏は〝いま君にあばれられては困る。城戸氏は必らず私が本山社長を口説いて社に復帰するようにするから、君はじつとしていてくれ〟というので、私は城戸氏復帰運動を一切中止することにした。城戸氏はすでに外遊していた。ところが私にも外遊の社命が下った。そして古武氏が私を招いて〝城戸氏復帰のことは本山社長の内諾を得た。だから君はすぐ出発していまロンドンにいる城戸氏に会って、その旨を報告し、決して軽挙妄動しないように言伝えてくれ〟といった。私もこれで一安心して横浜を立った。
おどろいたことに、本山社長が横浜埠頭に重役でもない私をわざわざ見送ってくれた。これは全く異例のことなので、城戸氏復活のことはウソではないと思った。そしてロンドンで城戸氏に会い、あなたの社復帰は決定したと告げると、城戸氏も喜んで、〝それでは君はすぐ日本に帰って、私の復帰後の準備工作をしてくれ〟といった。私は〝イヤ、私もはじめての洋行だし、2年ぐらいヨーロッパで遊んでいたい〟と断った。城戸氏は私より先に帰国すると、果して大阪毎日主幹として立派に復活していた。
私はソ連を回ってゆっくり帰国した。ソ連では監獄まで視察したが、収容されている囚人の大部分が経済事犯なのを知って、私は統制経済ないし社会主義は汚職と、官僚腐敗を伴うものでダメであると思った。これが盟友麻生久氏と意見の一致しなかったところで、私の自由主義は、右のファッショも、左の共産主義も不自然な統制主義であると否定する。私も、他人事でなく城戸氏には画したつもりだった。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年5月24日
1964年東京五輪を取材した磯貝喜兵衛さん(92)の連載一部〝復刻版〟『日本のスポーツ 発展の歴史』―フェイスブックから転載
アジアで初の東京オリンピックが開かれた昭和39(1964)年。開会直前の毎日新聞夕刊で、12回連載の『日本のスポーツ・・・発展の歴史』を当時、オリンピック報道本部にいた私が一人で書きました。引っ越し荷物の中から見つけたその切り抜きから、④回目の「古代からの人気種目・相撲」(昭和39年5月1日夕刊)を、よろしければご覧ください。
日本のスポーツ 発展の歴史④ 古代からの人気種目・相撲

〇・・・無類の相撲好きだった作家の尾崎士郎は、随筆「相撲を見る目」でこう述べている。
「相撲に親しむ気持は東洋人にとって先天的なものなのであろうか。幼童の遊びを見ていると、すぐ相撲がはじまる。だれが教えたわけでもない。四つに組んで投げ打つというのは、必ずしも勝負の観念に立脚した技法ではなくて、自然の動作のようにも思われる。」
相撲が古代から日本人の間でごく自然に発生し、親しまれたことは古事記や日本書紀の伝説が裏書し、埴輪や須恵器に残された相撲人形をみても明らかである。建御雷命(タケミカズチノミコト)と建御名方神(タケミナカタノカミ)とが出雲で力くらべをし、国ゆずりの決着をつけた話や、野見宿禰(ノミノスクネ)と当麻蹴速(タイマノケハヤ)の相撲伝説は、日本人の相撲好きをよく物語っている。
〇・・・相撲の語源は「すまひ」(素舞・相舞)からきている。折口信夫の「日本芸能史ノート」によると、「相撲は神と精霊との争いを表象した演劇的な要素が強かったが、力くらべがみんなの興味を集めたことからスポーツ的な面に拡大されていった。」という。国と国との領分を決めたり、農村と農村とが互いの豊凶を占うのに相撲が盛んに用いられた。奈良時代聖武天皇の天平六年(734年)から平安時代、高倉天皇の承安四年(1174年)まで毎年宮廷で行われた相撲節会(せちえ)は一種の「年占い」だった。全国から力自慢の相撲人を集め、国を二つに分けて団体戦をやらせ、これを天皇や貴族が鑑賞した。このころは土俵がなく、投げたり、引き倒したりして、手や膝が土につくと負けになった。
〇・・・貴族階級の節会相撲に対して、地方の民間でうけつがれてきた野相撲、宮相撲は鎌倉時代に入ると武士のスポーツとしてクローズアップされてくる。体力をきたえ、戦場で敵と一騎打ちに勝つためにも相撲は大いに役立つとあって、武士の間で流行した。源頼朝は陣中で武将たちによく相撲を取らせて楽しんだ。伊豆で相模と伊豆の武士たちが余興に相撲を取ったとき、俣野五郎が21人を勝ち抜いた。これに挑戦した河津三郎が俣野の連勝を破ったが、物言いがついて喧嘩沙汰まで起きる騒ぎ。これがもとで河津は俣野方の工藤祐経の家来に遠矢で殺され、曽我兄弟の仇討ち物語がはじまる。この事件で当時の武士たちが、相撲にどれほどエキサイトしたかを知ることができる。
〇・・・織田信長も相撲が好きで、天下を取って近江の安土城に落ち着くと、全国から千五百人の相撲人を集めて相撲の会を催した。土俵が出来たのも戦国時代の末期である。相撲を取り組む力士のまわりには、見物人が自然に輪をつくる。「人方屋(ひとがたや)」と呼ばれる円型が土俵を生んだわけで、土俵が設定されることによって、相撲は単なる力くらべから、技巧の競技になり、スポーツとしてのルールも整ってきた。
〇・・・有力な領主や富豪がなかば職業的な力士をかかえるようになると同時に、神社仏閣の建立や修理をする資金作りの名目で「勧進相撲」があちこちで催された。江戸時代になると、職業力士の勧進相撲はますます盛んになり、興行化してくる。元禄年間は京都、大阪が中心で、大関・両国梶之助などが活躍。つづいて江戸相撲が繁栄し、横綱・谷風、小野川を中心にした寛政の黄金時代を迎える。
〇・・・明治維新は相撲の世界にも革命をもたらした。大名に抱えられていた力士たちは封建制度の崩壊でよりどころを失ったが、文明開化が進むにつれて近代化され、明治5年、それまで女性の見物が許されなかったのが、11月場所から2日目以降は女性も見物してよいことになり、明治10年からは初日を含んでまったく自由となった。明治、大正時代は華族、実業家、軍人などの支援を得、昭和に入ると大衆の人気を集めて大相撲が安定した時代を迎える。
〇・・・一方では高校相撲、大学相撲がアマチュア・スポーツの伝統を守り、地方によっては神事相撲の歴史を偲ばせる村相撲や少年相撲も盛んだ。たとえば長野県小諸の八幡神社で八朔(はっさく)相撲の少年力士が町内を練り歩く行事など、相撲が庶民の間で古くから愛されてきたなごりを見せている。
〇・・・日本のスポーツのなかで、相撲だけは古代から現代まで一貫した人気をもち続けてきた。東京教育大の和歌森太郎教授はその理由をこう語る。
『日本人の民族性は淡泊というか、単純というか、非常にさっぱりしている。相撲の勝負も土俵という限られた空間のなかで短時間に終わってしまう。しかし、単純ななかに集中力をもりあげ、ものすごく充実した力と力、技と技がぶつかり合う。見物する方でも、そこに相撲の醍醐味を感じるのだ。同じ格闘技でも、たとえばボクシングのように、何回も殴り合いを続けるのと違って、しごくあっさりしている。日本人の気性にピッタリ合ったスポーツである点が、相撲という日本独特の競技を生み、育てたのだと思う。』
〇・・・雲をつくような大男を、小柄の力士が投げ飛ばすというのも、相撲独特のおもしろさだ。日本人の器用さが高度に発揮されるスポーツ・・柔道、レスリング、体操といった種目がオリンピックで有望なのも、相撲の歴史と考え合わせると興味深い。
磯貝喜兵衛さんのフェイスブック
https://www.facebook.com/kihei.isogai
2021年5月24日
社会部旧友、宗岡秀樹さん(73)の「弟の孤独死」が、滝野隆浩・専門編集委員の連載『掃苔記』に
『掃苔記』(2021年5月23日付け)に登場する「退職した先輩記者のМさん」は、航空部長などを務めた社会部旧友、宗岡秀樹さん(73)です。毎日新聞リタイア組を中心メンバーとする季刊同人誌『人生八聲』春季号(26巻)に掲載された体験記を基に、滝野編集委員が取材しました。宗岡さんの同人誌原稿を転載します。

緊急事態宣言下の最悪事態~たった一人の弟の孤独死 宗岡 秀樹
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出されていたさ中、独り暮らしをしていた9歳下の弟が自宅マンションで寂しく逝った。生涯独身。誰にも看取られず、たった一人の肉親である私にさえ、親しく付き合っていた友人たちにも別れを告げることもなく63年の生涯を終えた。自らが意図しないままの姿で見つかった時には約1カ月が過ぎていた。若い時から年2回は海外でスキーを楽しみ、仲間とお酒を酌み交わすことが大きな喜びだった。3年前にリタイアしてからはその度合いはさらに高くなったようだ。だが、昨春来の不要不急の外出自粛、長い巣ごもりでそれがかなわなくなった。ストレスをため込み、孤立し、命を縮めることになったのではないか。ある意味、コロナ禍の犠牲者だ。「もっと連絡を密にしていれば…」「苦しんだだろうに。なぜもっと早く気づいてあげられなかったのか」。自問自答し、悔やんでも悔やみきれない思いが駆け巡っている。
弟の様子がおかしいと気付かされたのは、2月のある日の夜、よく一緒に酒を飲みに行ったというサラリーマン時代からつながる仲間からの電話だった。 2週間ほど前から電話しても出ず、LINEでメールを送っても「既読」がつかない。その後も何回か連絡を取ろうとしたが同じ結果だった。前日にも若い仲間がマンションまで行って、インタホンを押しても応答はなかったという。「私たちではもうどうしようもありません。心配なのでお兄さんに確認してもらえませんか」というものだった。
直ぐに携帯、固定電話で連絡を取ろうと試みた。しかし、留守番録音に切り替わってしまい話は出来なかった。
弟は会社を定年退職してからは再就職せず、〝隠居生活〟を送っていた。時には慕ってくれた飲み友達たちと、時には一人でお酒を飲む暮らしを続けていたようだ。飲んでいて夜と昼が逆転したことが結構あった、と私に話していたのを思い出した。これまでも電話しても出ないことがままあった。つながらなくても「また酔っぱらって寝ているのだろう」。若干の胸騒ぎはしたものの私自身を慰めその日は寝た
翌朝、やや陰鬱な思いを抱きながら弟のマンションに行った。オートロックのドアの前でインタホンを押した。が、やはり応答はない。鍵を預かっていないので管理人に事情を話して開けてもらえないか頼んだ。管理人も鍵を持っておらず「開けるには『カギの百十番』という鍵開け業者に頼むしかありませんが、お金がかかりますよ」という。もどかしい気持ちを抑え、直ぐに電話するようお願いをした。しかし、警察官の立ち会いがないと開けられない、とのことだった。
そこで今度は私が最寄りの警察署に電話した。

それまでの状況を詳しく説明すると、相手は私を落ち着かせようと、丁寧な口調で「安否確認ですね。こちらもいろいろ準備が必要なので少々時間がかかりますが待っていてください」との返事だ。「早く会いたいのに」。心急くばかりの中、小一時間経ってやっと屈強そうな警察官一人がやってきた。新型コロナだけでなくその他の感染症を含めての対策や部屋の中に賊が潜んでいる可能性も考えてのことか、かなりの重装備だった。
屈強そうな警察官、管理人、管理人が呼んでくれた管理組合の役員、そして私が見守る中、鍵開け業者の作業員が開扉に取りかかった。てっきり鍵穴からピンセットのような小さい器具を使って開けるのかと思ったがそうではなかった。ドアスコープのレンズを外し、その穴からL字型に曲がった鉄棒を差し込んで操作した。ドアノブのサムターンを内側から動かそうと何回か試みた後、カチッという音とともにロックが外れた。ノブを回してドアが開いたかと思ったら、ドアチェーンがかかっていた。この時点で弟は中にいる可能性が高いと悟った。「部屋で寝ていて、何事もなかったかのように出てきてくれ」「弱っていて動けないのか」。「それともまさか?」……。期待と不安が錯綜した。
ドアチェーンに挑んだ作業員は「これは厄介なんだ」と言いながらテグスのような細い糸を引っ掛けて外そうとしたが、難儀しているようだった。繰り返し、繰り返し試行した後、チェーンが外れてドアが開いた。
すぐに入って弟に会いたかったが、警察官に制止された。私たちは何も触らないよう注意を受け、ドアの外で待機させられた。警察官は一人で中に入り、ゆっくりと部屋の点検を始めた。隠れているかもしれない不審者に襲われないよう警戒しているのか、慎重な足取りで奥へと進んでいった。
警察官が再び姿を現した時には相当な時間が経過したように思われた。そして重苦しそうな口調で「奥の寝室のベッドの脇で仰向けに倒れられていました。ちょっと日数が…」と話した。
覚悟をしていたとはいえ、危惧していたことが現実になってしまった。最悪の事態を知らされた時、幼い頃に一緒に遊んだこと、いつもニコニコしていた様子などがにじんだ風景の奥に思い出され、悔しさと悲しさが一挙にこみあげてきた。
弟は昨年1月にイタリア北部ドロミテ・バルガルディナで、3月にはオーストリア・チロルのサンアントンでスキーを堪能していた。少なくとも昨春までは並大抵の体力ではないほど元気だったはずだ。それが長い巣ごもり生活で酒量が増え急激に老け込んで消耗したに違いない。「年を重ねただけでは人は老いない。理想を失うとき初めて老いる気がする。そして希望を見い出せなくなったら生きる気力を失う」――の言葉が痛く感じられた。
警察官は直ぐに救急隊と刑事課に連絡した。先に駆けつけた救急隊員3人が室内に入ったあと刑事一課、鑑識課の計3人の警察官が到着した。刑事一課の警察官はしばらくして出てきた救急隊員に質問していた。そのやり取りが聞こえた。
「中でどんな処置をしたのですか?」
「はい、心肺蘇生を試みました」
「で?」
「蘇生しませんでした」
「AEDは使わなかったのですか」
「信号が出なかったので使いませんでした」。救急隊員は持ってきた担架を広げることなく縦にしたまま引き上げていった。
代わって警察官たちが中に入り部屋の中の検証を始めた。鑑識課員の検証が続く中、私は玄関先で刑事一課の警察官から「遺体には外傷や争った形跡もなく、密室だったので事件性は薄いと思われます」と告げられた。そばに解熱剤が見つからなかったことなどから新型コロナ感染症でもないという。
その警察官は「ご遺族と関係者の方へ」と題した見開き1枚のパンフレットを渡し、私の事情聴取を始めた。
パンフレットの表紙には「法律に基づいて警察が行う手続きや埋葬の手続きを説明し、ご理解をいただくために作成したものです。」などと記されていた。
中面左には「遺体発見から火葬・埋葬までの手続き」として事件性が疑われる場合とない場合の流れ図が示されていた。右面は「なぜ、警察がご遺体を調べるのですか」「なぜ、家の中を調べたり、写真撮影をするのですか」「なぜ、病歴や生命保険の加入状況などを聞くのですか」「なぜ解剖するのですか」という4項目の質問にその答えが書かれていた。
パンフレットの内容に沿って説明を受けたあと、弟の部屋を訪ねることになったいきさつや生活ぶりのほか、「最後に会ったのは? 話をしたのは?」「兄弟の仲は?」「生命保険はどうでしたか」などと細かく聞かれた。
2、3時間が経過しただろうか、やっと中に入れてもらった。初めて踏み入れた弟の部屋はタバコの臭いがきつかった。少し散らかってはいたが、生ごみも残っておらず、〝男やもめ〟の部屋のわりには思っていたほど汚れてはいなかった。
寝室に案内され、ベッドの脇でパジャマをはだけさせて変わり果てた姿で横たわっていた弟を目にした時、頭が真っ白になった。声も出なかった。以前の面影は全くなく、目がくぼんだ顔をまともに見ることができなかった。ただ、真冬だったせいか想像していたほどには傷んでおらず異臭もそれほどではなかった。
私が放心しているように見えたのか、「もう一度しっかり顔を見て身元確認をして下さい」と警察官に促された。ミステリードラマじゃあるまいし、別人が代わって倒れていたとは考えられない。発見された状況から見て弟に間違いないと思ったが、実は顔を見ただけでは確信が持てなかった。返事をためらっていると「身体的特徴は?」と聞かれた。「確か左手の甲に黒子が…」と答えると、警察官は弟の手を取り黒子を見せながら「それで間違いありませんね」と言って確認は終了した。
検証が済むと警察官は部屋に残されていたという鍵の束、マイナンバーカード、キャッシュカード、預金通帳などの〝貴重品〟とともに「テーブルの上に置いてありました」と現金数十万円を手渡してくれた。
ただ、死因と死亡日時はまだわからない。これを解明するため警察官は「医師の判断で解剖になる」と説明しながら、一応私に「解剖承諾」にサインをするよう求めた。弟の遺体は事件性が認められないため翌日、行政解剖に付されることになった。ちなみに事件性の疑いがある司法解剖の場合は解剖の費用は公費負担、遺体の搬送や保管、修復に伴う費用の一部も公費で賄われるが、行政解剖の場合は検案・解剖、遺体の搬送、保管の費用すべてが遺族の負担になるという。
その日は暗く沈んだ重苦しい気持ちで帰宅した。弟と同じ酒好きで独り暮らしをしている息子への電話と妻からのやさしい慰めの言葉以外、老夫婦間の必要以上の会話はなかった。
翌朝、警察署から電話があった。解剖の結果が出たのだという。検証で部屋から近くのコンビニのレシートが見つかり、買ったものが冷蔵庫内に残っていた。死亡日はそのレシートの日付の翌日だと推定された。弟は突然死でもあったのだ。
そして死因を聞いて驚いた。
「アスベスト肺、肺気腫による呼吸不全」
後で渡された死体検案書の解剖主要所見の欄には「両肺癒着及び肺気腫。胸膜側にプラークを形成する。左右心室拡張……」などと記されていた。
自分の健康管理には無頓着で毎日のように酒を飲んでいたというので、てっきり肝臓障害の類かと思っていたがそうではなかった。確かに空調設備の会社に勤務し、設計とともに現場管理に従事していたことはあったものの、これまで咳き込んだことや息苦しそうにする姿などは見たことはなかった。まして標高1000~3000メートル級のスキー場まで行き滑走しても何の問題もなかったのだから肺が石綿で蝕まれていたとは予想だにしなかった。
知人から聞いた話だが、アスベストによる疾患は潜伏期間が長く、ばく露してから数十年経って発症、死亡することがあるという。国の補償もあるという。この点については別の機会に取り上げることになるかも知れない。
死亡日と死因が分かり、死体検案書が作成されたことで弟の死に関しては警察の手から離れ、葬儀への流れに移った。
弟の遺体は警察署から紹介された葬儀屋が引き取り、翌日、手厚い化粧を施し、髪の毛や口・あごひげを整えてくれた。棺に入った弟の顔は元気な時とはほど遠く、顔色も良くないが眠っているように繕ってもらっていた。弟がベッドの脇で横たわっている姿を目にした時には、最初は、こんな哀れな弟を私の家族だけでなく他人にも見せたくはなかった。寂しいけれど極々近しい者だけで供養してあげよう、親しかった仲間には遠くから拝んでもらえればいい、との思いが強かった
しかし、化粧をしてもらった弟の顔を見て考え直した。「寂しく息を引き取ったのだから、最後は大好きだった多くの人たちに囲まれて見送ってもらう方が弟も喜ぶだろう」と。自粛ムードのご時世であってもささやかながら敢えて通夜も葬儀も行う一般葬で弔うことにした。
というのも、弟の様子を心配して電話をかけてきてくれた仲間に最悪の事態を伝えたところ「そばでお別れをしたいという仲間がいっぱいます。彼の人気は高く、慕っていた部下も沢山います」「お酒を御馳走してもらった人も多いと思います。弟さんを囲む会、もあるくらいですから」と聞かされたからだ。本来であれば通夜の席で弟の仲間の人達とお酒を交えて話をしたかった。ただ、夜の飲食自粛要請が出ていることもあり、お斎(とき)は控えさせてもらった。
十分なソーシャルディスタンスを取って行った通夜・葬儀には弟が勤めていた会社関係の仲間を中心に、私が予想していた数の倍近い人たちが足を運んでくれた。涙を流しながら手を合わせてくれた女性もいた。「会社を去って3年にもなるのに、こんな時期にこんなに多くの人が……」と正直、驚くとともに、胸が詰まった。
後日、弟のマンションを訪ねると、玄関ドアの前に白いユリの花束が置かれていた。
悔しさ、無念さは尽きないが、生涯独身で通しても弟は寂しくはなかったんだと、今は勝手に自分自身に言い聞かせ元気づけている。
× × ×
孤独死。年間約3万人が一人寂しく生涯のピリオドを打っているという。高齢化社会の進展とともに人間関係が希薄になっていく中で社会問題化して久しい。国、自治体のほか郵便局や多くの団体が独り暮らしのお年寄りを対象に「みまもり」活動などの対策を取ってきてはいる。だが、昨春来の新型コロナウイルス禍でさらに深刻化しているという。政府は2月19日、内閣官房に孤独・孤立問題の対策室を設けたほどだ。
周りを見回すと独り暮らししている知り合いは何人かいる。しかも大酒家。でも、まさか自分の身内から孤独死者を出すなんて思ってもみなかった。
実をいうと、正直なところ私と弟は成人してからはそれほど連絡を密にとっていたわけではなかった。一緒にお酒を酌み交わしたこともそれほど多くはない。歳が離れていたせいもあるが、お互いの生活を尊重した形で「便りの無いのは良い便り」とばかり不要不急のコンタクトもあまりしてこなかった。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大で巣ごもりの生活が一年近く続く中で、緊急事態は〝異常事態〟であることの認識が私には不足していたのではないか。弟にはこれまでと同じ係わり方で過ごしてきて良かったのか、兄としてもっとしてあげられることがあったのではないか、と自責の念に駆られている。今となってはもう遅いが、この時期、離れていた家族に連絡をこまめにすることの大切さを痛感させられた。三密を避けるのはもちろんだが、不用不急でも〝密コール〟〝密メール〟を心掛けるべきだった、と自省する毎日だ。
孤独死については様々な観点から取り上げた記事や書物も少なくない。私も取材したことがあるが、多くは遺族や周辺からの取材で社会に投げかけている。慚愧の念が大きいからか、周りの人達に思わぬ影響を及ぼす恐れがありそれをおもんばかってか、身内側からの記録はどちらかと言えば少なめだ。
少し長くなったが、忸怩たる思いの中で自らのショッキングな体験を敢えて細かく記させてもらった。
2021年5月21日
福島清さんの「岸井成格さんの父・寿郎さん」その2

岸井寿郎さんの6歳上の友人・山下芳允さん(報知新聞記者)の「畏友、岸井君との半世紀」から、の続きです。
<ハシゴ酒>
書かずのブンヤ、青年記者岸井君は文字通り夜を日についでのハシゴ酒。そんなわけですからいつも給料袋に入っているのは、前借金の紙キレばかりです。それも毎月、毎月。たまにお金を拝めても、10円そこそこ。これで生活のできるはずがありません。岸井君の妻君は偉かったのですねェ。金ならぬ前借金の書付の束をポイと渡されて、どうやって生活を工面していたんでしょうか。
あるとき、いつものように月給袋を渡すと、珍らしく前借伝票の中に12円。そこで妻君「これっぽっちでどうしようもありませんネ」「オオ、それなら芝居見に行こう!」とあり金はたいて本郷座に出かけ、それでチョン。
岸井君は家のことなどおかまいなしに、バー「ライオン」や「マンハッタン」、台湾喫茶店とでもいうのか「ウーロンチー」などで、小さな身体に酒を注込む毎日でした。私はこれまた反対に、酒がまったくイケず、夜、岸井君とつき合うことはまれでした。が、あるときなど岸井君は、結婚して目も浅い私の家を夜中の1時、2時に襲い、玄関の戸をドンドンたたいて起こします。酔っている彼は、大声で叫ぶは、友人が子供の土産に持ってきたヨコブエいたずらしてビーピー吹くはで、近所迷惑もはなはだしく、アルコール類を一滴も置いていない私の家では、家内もずい分面喰ったようです。
また、大臣以下、役所の幹部と記者団とが会合したある有名な料亭では、相当高価な柴檀の茶ぶだいの上に乗り、はねるやらとぶやら、果ては鞍馬式に仲間とともに騒ぐやらで、とうとう茶ぶだいをこわしてしまいました。数日たって、私は、そこの女将と文部大臣室の前でバッタリ会いました。女将が何をしにきたかは、いうまでもありません。以来、岸井君の奇行(?)はちょっと減ったようです。しかし奇行は減ってもハシゴ酒だけは延々と続いていました。後に胃腸をこわす大病をしましたが、下地は充分すぎるほどできていたわけです。
岸井君のハシゴ酒についていける生身の人間は、新聞社に酒豪多しといえども、そういませんでした。このことだけでも、岸井君の飲みっぷりがうかがえます。毎日新聞の記者に、イトキンなどという豪の者が多くいて、岸井君のフトコロ目当てによく飲み歩いていたらしいのですが、あるときはさすがの岸井君も、もうこれ以上つき合いきれない、とみるや、次の飲屋に行こうと誘うイトキンを振りきるために、走り出そうとする市電に駆け寄って一人だけ飛び乗ってしまいました。当時の市電にはドアがなく、柱がついているだけでしたので、柱につかまって逃げ去る岸井君めがけて、イトキンは「スリだァ。スリだァ。今その電車にスリが乗ったぞォ!」と、どなったというのです。電車に乗った岸井君は車内の人にジロジロにらまれ、大弱りした、と翌日記者クラブで話していました。最近会ったときにもその話が出て、私は「それはキミ、嘘じゃない。キミの名は寿郎、すろうだから」と大笑いしたものです。(つづく)
<日本一キレイな紙面と首切>
当時の新聞の刷りは全国的にみてキタなく、東京日日新聞はもとより関東大震災の影響もありましたが、震災にあわない新聞社の新聞も例外ではありませんでした。これは大きな問題で、岸井君はその仕事におおいに生きがいを感じ、男として取組みました。とはいえ、岸井君にしてみれば、華やかな記者生活から、むしろ地味な印刷の仕事であり、法律こそ勉強したが印刷はまったく未知の世界。しかもきわめて難問題をかかえている時期に、彼一流の“強気”で工務部長として乗込みました。
例のごとく、当座はほとんどこれといった仕事もせず、3月、半年と、酒にあけて酒に暮れるという毎日だったようです。ところが実は彼の偉いところなのですが、毎夜印刷、工務部の上級幹部一人一人をつれては銀座で飲み歩き、ドジョウすくいを踊ってはいても、決して酒にのまれることなく、それらの人々から印刷技術の数々、仕事に対する態度、働き振りをつかんで、改善の急所を学び、研究していたのです。
そしてその間、改革についての腹をきめ、これを実行に移し、まず、古い幹部をスパッとやめさせてしまいました。随分思いきったやり方です。しかし、岸井君の考えでは、能率が上がらず、紙面の刷新がなされないままでいるのは、それまでのやり方が悪く、幹部の責任でもある。彼等に代えて若い人をドシドシ登用する。幹部に支払っていた給料との差額がだいぶ出る。これをすべて若い人にまわす。それで仕事もバリバリやらせる。毎日何もしていないようにみえた岸井君は、毎日新聞の工務部、というより、日本の新聞のキレイな紙面づくりのために案を練り、腹を固めていたのです。活字、インク、用紙、輪転機、ありとあらゆる点について納得ゆくまで研究し、それも机上のプランではなく、自分の目で確めて実行したのです。ボタン一つで色々な工程が流れる作業をする機械もアメリカからイチ早く購入し、われわれの目を見張らせました。岸井君の研究は工務だけにとどまらず、販売、その他にまで及んでいます。今でも、毎日新聞の紙面はいちばんキレイだと思います。新聞全体では、また逆もどりの傾向にあるのは、残念です。
ともかく、岸井君は、当時日本一キレイな新聞、という偉業を打ちたてたのであり、本山彦一社長はいたくその功績をたたえ、社員一同の前で金一封(中味は彼の前借伝票で棒引)と記念品の金時計を贈った、とのことです。
戦後は新聞界から去り、鉱山事業を手がけました。もちろん、金など身についてはいません。とくに山形の硫黄の山を引受けたときなども、きわめて平気な態度であっさりといったものです。「オイ、オレの香典と思って5万円出せ」。当時同期の友人はそれぞれ相当の地位についている年輩でもあり、そうした友人をまわり歩いて金を集めました。後にヤマを松尾鉱山に手放すことになったとき、岸井君は借りた金を3倍から5倍にして、キレイに返しました。金に執着しない岸井君らしいやり方です。
その岸井君にも、ひとつの大きな夢がありました。岸井君らしい大きな夢です。家に来ないかと電話があって出かけると、きまって小笠原の地図を広げていました。2年前の夏、元気に小笠原に出かけて行ったほどです。
「海は澄んでいるし、魚はうまいし、気候はよし、空気もキレイだ。オイ、お前も行ってあそこに保養所を建てよう!」などと、島の話をするときは、童子のように顔をほころばせていました。
尊敬する友人を持った私は幸せでした。それだけに、いまの寂しさはひとしお身にこたえます。(つづく)
*岸井印刷部長のことは、元東京日日新聞政治部員・岡田益吉さんも書いています。
岡田益吉さんの回想
<印刷部の根本改正>
昭和6(1931)年9月、満州事変勃発とともに、岸井氏は政治部長となった。恐らく氏の親分であった城戸元亮主幹(昭和3年主幹となる)の抜櫂によるものと思う。氏はこのことと関係はないが、「城戸さんは面白い人事をやる人だ」といったことがある。氏を政治部長とした城戸氏に知己を感ずるとともに、「自分のような八方破れのものをよく政治部長にしたものだ」という含みの意味もあったようにきこえた。
岸井政治部長はあの満州事変の激動期に印刷部長を兼務していた。政治部副部長には柔軟性のある久富達夫を抜櫂し、この剛の岸井部長と柔の久富副部長ぐらい名コンビはなかった。当時の東日政治部は、「猛将の下に弱卒なし」で、手のつけられぬサムライ記者が雲集しており、何れもよく働いた。政治部のことは後回しとして、岸井印刷部長は、多年禍根となっていた印刷部の根本的改革に氏特有の蛮力をふるった。
第一に印刷部の資材のヤミ横流しなどをビシビシやっつけた。ひどいときは名うての乱暴職工を工場のコンクリートの柱に縛りつけるという思い切ったこともやった。こういう強圧も加えたが、 一方能率を上げた職工20数名に懐中時計を身銭を切って与えたりした。ガンコおやじ然とした氏の半面に涙もろい温情主義がかくされていた事実は、親近した若い連中はよく知っている。氏はこういう温情なり憐憫の心を表面にあらわすのを絶対に好まなかった。いつも自分の愛情をそっと示すやり方をし、しかも、その方法は行届いた適切なものであった。
この印刷部の改革は、東京日日新聞(当時は大阪が毎日新聞本社で、東日は東京支社となっていた)に月々5万円(時価で5億円)の黒字をもたらし、従来、大阪本社から補填されていた赤字を解消してしまった。かくして、東日ははじめて大阪本社から経済的に独立したのである。主幹の城戸元亮氏も営業局理事の吉武鶴次郎氏も手を打って心から喜んだ。本山彦一社長は岸井氏に金時計を贈ってその労をねぎらい、大阪印刷部の改革も依頼したが、これだけは岸井氏は最後まで断っていた。
この印刷部改革は、岸井氏の社内における確固たる地位を築き上げ、本山社長をはじめ、城戸、吉武両重鎮の信頼を、一身に担ったと思われる。そればかりでなく、東日の印刷面のいちじるしい刷新は他社の注目するところとなった。社内的に財政上の赤字を克服しただけでなく、紙面の鮮明さは格段で、当時新興の気運に乗っていた読売新聞社長正力松太郎氏も、これに着目して、大胆にもライバルである東日印刷部長岸井氏に強引に会談を申込んだ。
ここに斯界の両鬼才である正力氏と岸井氏との出会いが行なわれたのである。正力氏は顧間の小野瀬不二人氏とたった二人で、丁重に岸井氏を迎えて、印刷面の改革方法について教えを乞うた。岸井氏はただこう答えた。「印刷工場に金を注込んで設備をよくするだけではタメです。要は人にある。正力さん、貴方が直接工場に乗込んでやらなければ、決してよくはならない」と。
それから精力的な正力氏は陣頭指揮で工場に臨んだ。社長が大組みまで立会うほどの熱意であった。読売の紙面はみるみるうちに進歩した。なお岸井氏は停年になった束日の優秀な印刷工員を推薦して読売の工場に送込んで、正力氏を援助している。「要は人である」というのが氏の人生哲学だ。
※岸井成格さんは、この2編を読ませたかったのでしょう。当時、毎日新聞東京本社は活版からCTSに完全移行しました。制作方法が変わっても、「『要は人である』ことを貫け」と言いたかったのだと思います。「印刷部改革」のことは「毎日新聞百年史」(1972年刊)「技術編」には見当たりません。それだけに貴重な証言です。
余談。「活版は昭和とともに去りぬ」でした。「昭和」は1989年1月に終りました。活版制作の毎日新聞は、昭和が終わった年の12月11日付の群馬版、栃木版が最後でした。この日は、私の51歳誕生日でした。当時、CTS移行の活版側責任者でしたので、最後にCTSに移行する面の日程について、この日にすることを主張したところ、あっさり決まりました。本当は私の出身地である長野版にしたかったのですが、それは編集局側の事項ですのでダメでした。毎日新聞の活版制作の最終日が私の誕生日であったことは、誰も知りません。私だけの活版惜別記念日です。
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年5月20日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ「東京ラビリンス」のあとさき その12(後編)
私の駒込名所図会(3)染井吉野と霜降・染井銀座(後編)=註と記事、写真の一部略 文・写真 平嶋彰彦。
全文は http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53460857.html
染井の長池から発した谷戸川は、巣鴨や西ヶ原からの湧水や下水(したみず)を併せつつ、染井通りを遠巻きにする形で、北から東へ向きを変えながら、現在の染井銀座から霜降銀座を流れた。霜降橋交差点は本郷通りが谷戸川を渡るところで、かつては霜降橋が架かっていた。その先が谷田川通りで、東南に流れて、中里から田端にいたる。さらに日暮里付近で向きを南に転じ、谷中(台東区)と千駄木・根津(文京区)との境になっているよみせ通りやへび道などの道筋を流れたあと、上野の不忍池に注ぎこんでいた。川の名前は上流の駒込付近では谷戸川または境川、中流の田端付近では谷田川、下流の谷中・千駄木・根津付近では藍染川と呼ばれていた。
現在、谷戸川は源流の長池から不忍池にいたる流路のすべてが暗渠になっている。
この川は水はけが悪かった。そのため、大雨が降ると、下流の谷中・千駄木・根津付近では、しょっちゅう氾濫し、町中が水浸しになった。
タウン誌『谷中・根津・千駄木』は第3号で、暗渠化する前の藍染川(谷戸川)について、古老からの聞書きと地元で集めた史料により特集を組んでいる。下記の引用は、そのうちの1つである。
明治末まではあさりやしじみが採れ、小魚が釣れた。子供は泳いだり水浴びをした。…大正5年8月、大雨が4、5日降り続いたが、川沿いに二階家が少なく、天井裏に寝起きしたり素人作りの筏まで出た。そこで地元の衆議院議員秋虎太郎氏を動かして官庁に町ぐるみの請願を行ない、大正7年から排水工事を始めて、千駄木地区は9年10月に暗渠化された(野口福治さん(故人)「ふるさと千駄木」より、明41年生、茶舗野口園)。
いい方を変えれば、明治から大正になると、あさりやしじみは採れなくなり、小魚も釣れなくなった。明治末というのは、染井霊園の周りの寺院が東京の市中から移ってきた時期にあたる。おそらく谷戸川に沿ったあちこちで、それまでの田園地帯から市街地への転換が急速に進んでいたものと思われる。千駄木では、1918(大正7)年から谷戸川の排水工事がはじまり、2年後に暗渠化されたのは、筆者が書いているように、町ぐるみの請願が功を奏したのかもしれない。しかし、この地域の水害対策は昨日今日のことではなく、かなり以前からの懸案事項であったようにみられる。
というのも、その洪水より3年前になる1913年、東京市は藍染川(谷戸川)による谷中・千駄木・根津一帯の水害対策として、「藍染川上流より谷中初音町四丁目を経て荒川にいたる排水路」という工事計画を立案しているからである。
この計画書を読むと、以前からこの川はしばしば氾濫をくりかえしていたことが分かるのだが、同書では氾濫の原因をこんなふうに説明している。
藍染川は染井・西ヶ原両高地に発し、流域は甚だ広大であるが、市内谷中・根津の地に入ると、その水路は流量に比べて甚だ狭小であるのみならず、構造が極めて粗悪であることから、一朝大雨に際会すると、雨水を排除することができない。その結果、沿川の谷中・根津一帯に氾濫をもたらし、その被害面積を測定すると約7万1千坪にもおよぶ。
では、水害を防ぐ具体策はなにかというと、氾濫の常襲地域の手前に分水装置を設け、それまで不忍池に注いでいた流路を変更し、荒川区内を経由させ荒川(現在の隅田川)に放流しようというのである。河口の三河島には、この計画書の立案された同じ年に、汚水処分場(現在の水再生センター)が完成する予定だった。そこで、流路を変更した谷戸川の水を、この処分場で浄化してから放流することを考えたのである。
故ニ本計画ニ於テハ下谷区初音町4丁目ニ分水装置ヲ施シ、新ニ府下三河島ニ至リテ荒川ニ合流スル延長1千658間余ノ大排水路ヲ設ケ、一朝豪雨到ラバ上流全部ノ雨水ヲ之ニ導キテ荒川ニ放流し、分岐点以下ノ水路ハ単ニ本郷台及び上野台並ニ沿岸ヨリスル雨水並ニ汚水ヲ収容排セシムルコトトセリ。
下谷区谷中初音町4丁目は、現在の台東区谷中3丁目である。ここは道灌山の南東にある低地で、道灌山を越えた北側にJR西日暮里駅がある。計画書でいう分水装置とは、道灌山から西日暮里駅の地下に通じる「藍染川トンネル」のことである。
この「排水路」計画の考え方に疑問がないわけでもない。というのも、川の流量に比べ川幅が狭いというなら、川幅を広げるとか、川底を浚うなどの改修工事をすればいいからである。しかし、そうはならなかった。土地買収の経費や下水管敷設の工事費が莫大になるのみならず、工事そのものの困難さが予想されたからだというのである。
在来水路を取拡ケントセバ勢沿岸ハ多大ノ土地ヲ買収セザルベカラザルノミナラズ、下流吐口神田川ニ達スル迄長距離ニ亘リテ広大ナル下水管ノ築造ヲ必要トシ其工事費莫大ニシテ工事亦甚ダ困難ナルヲ免レズ。
谷中から三河島にいたる新たな水路は、京成電鉄本線に沿って開削され、上記のように、排水は三河島の汚水処理場で浄化し、荒川に放流された。この計画の実施により、文京区・台東区側の千駄木・谷中から不忍池までの流路は暗渠化され、沿川一帯の人々は水害の危険から解放されることになった。
そのいっぽう、新たな問題も生じた。どうしてかといえば、そのころには京成沿線の荒川区内でもやはり市街地化が進んでいた。西日暮里から三河島の汚水処理場までの水路は、行政的には下水道である。にもかかわらず、沿川住民の生活感情をないがしろにし、蓋をかぶせない状態のまま、長年にわたって放置していたからである。
谷戸川の上流にあたる駒込や染井の一帯では、1931(昭和6)年に埋立工事がはじまり、1940年までには暗渠化された。現在の霜降銀座と染井銀座は、その流路跡につくられた商店街である(ph12~20)。川添登は小学校1年のとき、駒込から西巣鴨へ引っ越した。その1年後に谷戸川の埋立工事がはじまったことになる。(註20)。
駄菓子屋の前の道をさらにすすむと谷戸川にぶつかり、川に沿って下ると霜降橋へでるが、その途中に活動写真館があったり、サーカスが小屋掛けする場所があったりで、いわば場末の繁華街になっていた。谷戸川は、川とはいえ、角材と板材とで土留めされた底を、雨でも降らない限り、わずかな水がちょろちょろ流れるだけのものになっていて、私たちはドブ川とよんでいたが、たまにはオタマジャクシが泳いでいて、それをとったりもしたのである。
駄菓子屋の前の道というのは、本郷台地の上にある染井通りから谷戸川へくだる染井坂通りのことである。川添登の一家がこの坂道の中腹に引っ越してきたのは、連載その10で書いたように、関東大震災の直後であった。それまでは、谷戸川に沿って田んぼが続いていたが、川添が子どものころには、すでに民家で埋まっていた。とくに染井坂の下には、長屋が建ちならんでいて、それをバラック呼んでいたともいうことである。
現在の霜降銀座と染井銀座になっている一帯は、おそらく関東大震災のあと、東京市中からの人口の流出現象にともない、本格的に市街地化したものと思われる。
『コンサイス東京都35区区分地図帖』は、戦災焼失区域を赤く色分けして表示した区分地図である。連載その1で書いたように、『東京ラビリンス』のもとになった『昭和二十一年東京地図』の取材では、いつもこの地図を持ち歩いた。
この『地図帖』をあらためて見てみると、1945(昭和20)年の米軍による空襲で、川添登が記憶する谷戸川沿いにつくられた「場末の繁華街」をはじめ、駒込・巣鴨一帯のあらかたの地域が赤く塗りつぶされている。罹災を免れた箇所は、染井霊園とその南東側に隣接する高級住宅地、伊藤伊兵衛政武の墓のある西福寺と染井稲荷神社の境内など、ごくわずかしか確認することができない。
終戦後の1951年、朝鮮戦争が勃発した翌年になるが、商店街の店主を中心に霜降銀座栄会が設立されている。染井銀座をふくめ、戦災で壊滅した「場末の繁華街」が、現在のような家族連れでにぎわう商店街へ再生する足がかりをつくったのも、そのころではなかったかと思われる。
それ以上の詳しいことはわからないが、都心の繁華街に眼を向けると、この年の12月、銀座界隈の露店が取り払われ、その替りに三十間堀埋立地の露天デパートに移転することが決まっている。都内にはそれまで7000余りの露天商がいたとのことだが、そのうちの約4500がすでに「自発」的に廃業し、新宿・上野ではすでに協同組合のデパートに移転したともいう。それより4ヶ月前の8月、東京都は御茶ノ水駅下の谷間・上野寛永寺の墓地(「葵町」)・浅草の隅田公園(「アリの町」)などにあったバラック建築を年内に撤去することを決めている。朝鮮戦争による特需景気を契機にして、終戦直後のいわゆる闇市時代は終わりをむかえつつあったのである(以下略)。

2021年5月19日
「畏友、岸井成格君との半世紀」を福島清さんがFBに連載


5月15日。89年前のこの日、犬養毅首相が暗殺された。乱入した海軍軍人は「話を聞こう」という犬養に「問答無用」と言って射殺した。49年前のこの日、沖縄は日本に復帰した。だが依然として米軍基地が「問答無用」とばかりに居座っている。2015年、沖縄の苦難の歴史と基地被害を渾身の思いで訴えた翁長雄志・知事に対して、当時の菅官房長官は「戦後生まれなので、沖縄の歴史はなかなかわからない」と言って、辺野古基地建設を強要した。
そして3年前のこの日、毎日新聞OBでTBSニュースキャスターだったジャーナリスト・岸井成格さんが亡くなった。2015年、当時の安倍首相に忖度した連中が岸井批判の全面広告を出して攻撃した。だが岸井さんは断固として対決しひるみませんでした。
岸井さんは、1976~1977年にかけて毎日新聞労組が再建闘争に取り組んだ時、「開かれた新聞」として再建することを目指した「編集綱領制定委員会」の組合側メンバーの一員でした。2015年に発行した「夢を追いかけた男たち―毎日新聞再建闘争から40年」で、岸井さんは「最近の『安保法制』その他の安倍晋三内閣の強引な政治運営、『小選挙区制』導入以降、目に見える形で進行する政治の劣化、そして何よりも政権のメディアへの干渉、介入、これに対する主としてテレビ・メディア側の萎縮ぶりは危機的な状況が続いている」と強く警鐘を鳴らしました。
これより前の2007年、岸井さんは毎日新聞の広告企画特集で、小宮山洋子さん(元厚生労働大臣、衆議院議員)、山野正義・学校法人山野学苑理事長と鼎談しました。美容と福祉の融合を目指すという山野学苑の方針に、岸井さんは「生きがいの原点に」と評価していました。
菅政権の暴走が続く今、岸井さんはどんな思いでいるでしょうか。
【岸井成格さんの父・寿郎さん①】

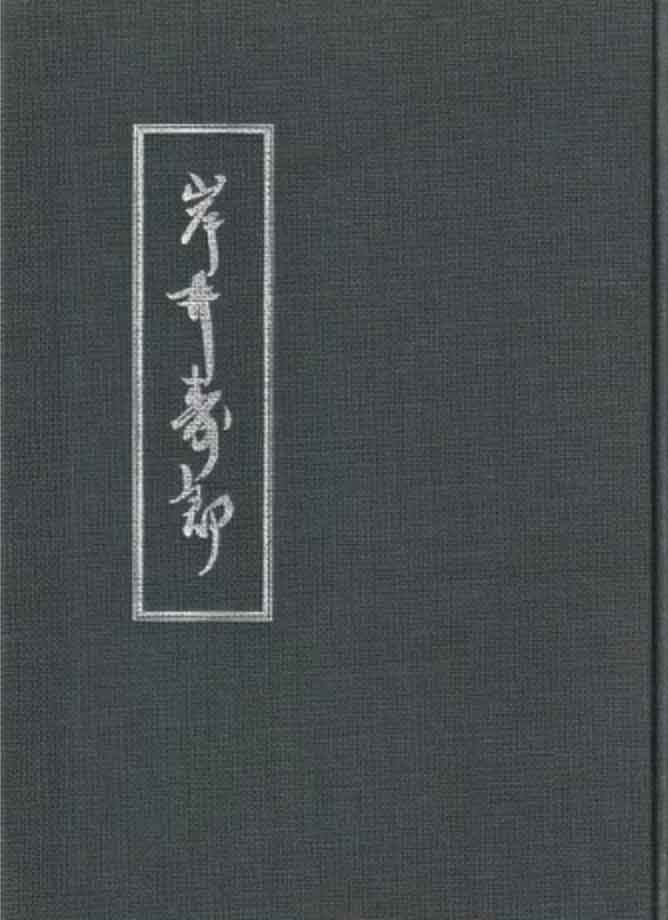
1990年頃、岸井成格さんが私の職場にきて「親父は昔、東京日日新聞の印刷部長だった。参考になるかも知れないから」と言って、追悼集「岸井寿郎」(きしい・としろう)をくださいました。友人たち13人の追悼の言葉に加えて、慶子夫人の36ページもの「夫を偲んで」、そして遺稿4編などが掲載されています。
読み返してみました。大正から昭和の激動の時代に立ち向かった寿郎さんの姿勢は、岸井成格さんに受け継がれていると同時に今の社会に対する警鐘のよう思いますので、いくつか紹介します。略歴は、遺稿集に年譜がありませんので、追悼文に書かれていることなどからまとめてみました。
1891年5月28日香川県豊田郡常盤村(現・観音寺市)生まれ。香川県立三豊中、第三高等学校を経て、1917年東京帝国大学法学部卒、司法官試補を経て、1919年大阪毎日新聞社入社、1930年政治部長兼印刷部長、1937年退社。実業界へ。1942年香川2区から衆議院議員、1945年12月まで1期。以後再び実業界へ。1970年10月1日、79歳で死去。
最初に6歳上の友人・山下芳允さんの「畏友、岸井君との半世紀」からです。
<温情検事> 岸井君は帝大出の法学士ですが学校にはほとんど行かなかったので、独学でモノにした、といった方がふさわしいでしょう。卒業したといっても、免状も取りに行かずのままで、戦災で焼けていなければ、いまでも東大に残っているはずです。当時東大の卒業証書といえば、それだけで後光のさす自慢のタネになるのですが、目に見える証として、ふつうの人間なら後世大事にする証状とか勲章とかには、一向関心がありませんでした。
学校などへは真面目に出ていなくても、岸井君の頭の良さは誰もが認めるところです。郷里の三豊中時代には、むずかしい函数の問題を見事に解き、それを完壁に解説したのは開校以来、岸井君が唯一人、と教師を驚嘆させ、いまだに語り草になっている、ということです。
帝大卒業後はしばらくウロウロしていたようですが、地方裁判所の検事になりました。しかし岸井検事の成績はさっぱりあがりません。というのは、できるだけ前科者にさせたくない、という信念から、初犯者には彼独特のあの厳しい説教をして、ドンドン釈放してしまうからです。若冠20数才ですから、どんな説教をしていたんでしょうか……。
結局検察当局としては、成績があがらないということになり、そうした岸井君のやり方について、“びっこの鬼検事”として有名を馳せた秋山検事ともよくやり合い、喧嘩して遂に検事をやめてしまいました。その頃から岸井君は、強きには強く、弱きには弱く、というやり方を通し、自分の信ずるところを曲げませんでした。(つづく)
【岸井成格さんの父・寿郎さん②】
<ケンカ寿郎> 喧嘩をしてやめてしまった検事の職から、一転して東京日日に入社。まず内務省づめになりました。時の内大臣は、地方官出身で勤厳真面目な男爵・湯浅倉平でしたが、向かうところ恐れるものなく、ポンポン歯に衣着せずモノをいう岸井君は、ここでも大臣と喧嘩してしまいました。そのために文部省にまわされたのですが、その頃私も報知の記者として文部省を担当しており、「一橋会」という記者クラブをやっていたため、岸井君とはよく顔を合わせていました。
岸井君は、何も仕事をしない。夜は2時、3時までも銀座を飲み歩き、ほとんど発表原稿など書きません。それで私が原稿をカーボンで書き、控として一枚は手許に残し、上の一枚を彼が書いたようにして送る、というようなこともやりました。しかし、表面では何もしないかのようにみえて、こまかなことにもよく気づき、ものごとを大づかみに、大局から見ていました。やることすべて大ざっばな岸井君と、正反対に私はコツコツとやる方なので、われわれ二人は気が合ったのでしょう。
大臣であろうが誰であろうが人見知りせず、相手が強ければ強いほど闘志をムキ出しにするので、ケンカが絶えません。ケンカ、といっても、もちろん信念を押しての口論、激論です.それでも文部大臣の中橋徳五郎(大阪財界の大御所で、大阪商船社長)には可愛がられ、仕事はせずに、よく碁を打ちに遊びに行っていました。岸井君の碁は、正式に教わったり、定石を鵜呑みに憶えるのではなく、自分の頭で考え、組立ててゆく、ケンカ碁の典型だったようです。
当時、私がおりました報知は、部数70万を誇り、講談社の野間清治氏から三本武吉氏に移っていました。
岸井君も東京日日の政治部でしたから、書かずのブンヤ岸井君との政治談義には熱が入り、相手が私でない普通の人だったら喧嘩にもなっただろうと思われる場面がいくらもありました。(つづく)
(福島 清)
※福島清さんのフェイスブックは
https://www.facebook.com/kiyoshi.fukushima.102
2021年5月17日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ「東京ラビリンス」のあとさき その12(前編)
私の駒込名所図会(3)染井吉野と霜降・染井銀座(前編)=註と写真の一部略 文・写真 平嶋彰彦。
全文は http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53443544.html
染井通りは、連載その10で書いたように、江戸時代につくられた由緒のある通りで、六義園の北側で本郷通りから分岐し、北西方向に真っすぐ伸びている。
『江戸切絵図』「染井・王子・巣鴨辺絵図」とGoogle地図を重ね合わせると、染井通りの南側には、六義園すなわち大和郡山藩松平(柳沢)家の下屋敷に隣接して、伊勢津藩藤堂家の下屋敷があった。さらに進むと播磨林田藩建部家の下屋敷につきあたる。そこが現在の染井霊園である。それにたいして、染井通りの北側はどうかというと、植木屋の店舗が軒をつらねていた。通りから奥へむかって、なだらかなくだり斜面がひろがり、植木屋たちはそこを開発して花園をつくり、浮世絵にも描かれたような江戸名所の1つに発展させていた。
染井霊園をはじめて訪れたのは2012(平成24)年の暮れだった。園内には冬空を仰ぐように枯れ枝をのばすソメイヨシノ(染井吉野)の古木が立ちならんでいた。
桜の樹の下には屍体が埋まっている!これは信じていいことなんだよ。何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。
なんとなく梶井基次郎の『桜の樹の下には』の冒頭が思い浮かんだ。

そういえば、西行にもサクラの花を死と結びつけた有名な歌がある。
ねがはくは花のしたにて春死なんそのきさらぎの望月の頃
染井霊園に咲くソメイヨシノを眺めてみたくなり、翌年の春にもう一度訪れることにした。出かけてみると、サクラは花の盛りだったが、死者たちに遠慮があるのかどうか、墓参りの人をのぞけば、一般の花見客は数えるほどしかいなかった。
全国各地の公園・街路・川堤・学校などに植えられている花樹の多くはサクラだが、サクラといっても、その筆頭はソメイヨシノである。ソメイヨシノの特徴は、接ぎ木で容易に増やすことができ、幼木のうちから花を咲かせることにある。それも葉の出る前にたくさんのみごとな花をいっせいに咲かせる。オオシマザクラとエドヒガンザクラの交配種だとされるが、自然によるものか人工によるものか、またその現場がどこかもはっきりしない。しかし、これを日本中にひろめたのは染井の植木屋の功績だということである。
染井の植木屋たちがソメイヨシノを売りだし始めたのは幕末のころらしい。徳川幕府がたおれ、明治維新になると、新政府は近代国家に見合う社会的環境を全国に整備していった。そのときに、公共の場所にふさわしい花樹として選ばれたのがサクラだった。そのなかでもとりわけソメイヨシノが好まれ、それも1本とか2本ではなく、たいがいは相当数を集合させる形で植えられた。
ソメイヨシノが出はじめたころの呼び名はヨシノ(吉野)だった。ヨシノは地名と同時にサクラの総称だった。奈良吉野はサクラの名所として知られる。古典文芸に出てくる吉野山のサクラはヤマザクラだそうである。ヨシノのままだと奈良吉野のサクラと紛らわしい。そこで、頭に産地のソメイ(染井)をかぶせ、ソメイヨシノと呼ぶことにしたのだという。
駒込の染井はソメイヨシノの故郷である。電車に乗って駒込へやってくる人に、薦めてみたくなるサクラの名所はどこかとなると、染井霊園のほかに思いつかない。かつて植木屋が軒を連ねた染井通りにソメイヨシノの大木は見あたらない。江戸一番の植木屋とうたわれた伊藤伊兵衛政武の墓のある西福寺門前の染井よしの桜の里公園とか、染井坂通りの門と蔵のある広場の周りには、ソメイヨシノの大木がないことはないが、周りにならび立つビルの現代的な景観に埋没してしまっている。これはなんとなくさびしい気がする。
染井霊園は、東京の市街地の周縁につくられた共同墓地の1つである。1874(明治7)年、青山霊園(現港区)・雑司ヶ谷霊園(豊島区)・谷中霊園(台東区)とともに開設された。園内には二葉亭四迷・山田美妙・岡倉天心・高村光雲と高村光太郎智恵子夫妻などの墓がある(ph4、註7)。染井霊園の周りには慈眼寺・泰宗寺・専修院・蓮華寺・勝林寺・本妙寺などの寺院と境内墓地が建ちならび、一大埋葬地としての景観を呈している。いずれの寺院も染井霊園が開設されてから約30年後の明治時代の終わりごろに、東京の市街地から移転してきている(註8)。そのうちの泰宗寺・専修院の墓地およびその隣の天理教の墓地などがある場所は、植木屋伊藤伊兵衛の屋敷地だったところだともいわれている。
「江戸切絵図」をみると、染井通りを遠巻きにするように、西から北へさらに東へと向かって、川が流れている。川の名前は書いていないが、川を挟んで右側には「此辺染井村植木屋多シ」とあり、左側には「此辺西箇原(西ヶ原)村」とある。
これが谷戸川である。
谷戸川ついて、『新編武蔵風土記稿』は「上駒込村」のなかで、源流は染井の長池から発していると書いている。
谷戸川 北境西ヶ原村の接地に流る、或は境川とも呼ふ。染井の内長池と云池より西ヶ原村へ沃(そそ)く。
駒込は上駒込村と下駒込村に分かれていて、染井は上駒込村の枝村である。だが、染井だけではちょっとつかみどころがない。谷戸川の源流とその川筋については、『御府内備考』の「千駄木坂下町」に、より具体的な説明がなされている。
一 堀 幅九尺程
右は字谷戸川と唱澁江長伯様御預り、巣鴨御薬園ゟ出、田端村新堀村下駒込村と町内東の方谷中感応寺古門前町と当町の間を相流、谷中駒込の堺に御座候。
一 石橋 長さ弐間、幅八尺
右は谷戸川へ掛り候て合染橋と唱候者も有之由
千駄木坂下町は現在の文京区千駄木2、3丁目のことである。千駄木坂は、団子坂の別名で、その坂下に開かれた町ということから千駄木坂下町と称した。そこを幅9尺(約2.7m)ほどの川が流れていて、合染橋という名の石橋が架かっていた。これが世にいう谷戸川で、その水源は巣鴨にある澁江長伯預りの御薬園である、というのである。
そうすると、『風土記稿』のいう染井の長池は、『御府内備考』のいう巣鴨御薬園のなかにあったようにみられる。では、それは現在のどこらへんにあたるのだろうか。
『江戸切絵図』で谷戸川の上流方向をたどってみると、建部家の下屋敷(染井霊園)の西側をさかのぼったその先で、藤堂家の下屋敷と巣鴨御薬園の境にたどりつく。どちらも武家地である。屋敷内のようすを知りたくとも、邸主の名前のほかはなにも書いてない。しかしながら、それより先に川らしきものは見あたらない。だとすれば、このなかに水源があったと考えてよさそうである。
『御府内備考』のいう御薬園があったのは、現在の中央卸売市場豊島市場のあたりとされている。これと隣接するのが藤堂家の下屋敷だが、その西側の端が薬園との境で、現在の岩崎弥太郎墓地のあたりとみられる。したがって『風土記稿』と『御府内備考』の記述を『江戸切絵図』に照らし合わせると、中央卸売市場豊島市場と岩崎家の墓地があるあたり、すなわち、染井霊園の南側かその周辺のどこかにあった、という推定が成り立つ。
ところが、長池があった場所は、染井霊園の南側ではなく、北側であったともいわれている。たとえば、江戸・東京の歴史研究で知られる鈴木理生は「現在の豊島区巣鴨五丁目(駒込5丁目の誤り)の染井霊園の北側にあった長池を水源とし」と『図説 江戸・東京の川と水辺の事典』に書いている。
また文京区教育委員会は藍染川と枇杷橋(合染橋)の現地案内板で、「長池(現在の都営染井霊園の北側低地)」としている。あるいは、豊島区HPの「桜・ツツジの花香る町散策コース(駒込方面)」には、「(染井霊園は)元は建部内匠頭下屋敷跡で、西側には谷戸川源泉の長池があったそうです」とある。
どれも専門家の記述だから、それなりの根拠があるにちがいなく、無視できないのだが、筆者の力不足もあり、該当する史料を見つけだせないままでいる。
それはさておき、川添登は『東京の原風景』のなかで、「オタマジャクシといえば、なんといっても染井通りにいまもある天理教の教会の庭の池であった」という少年時代の思い出に続けて、この長池について、次のように回想している。
染井の墓地にいくと、コジュケイが行列をつくって歩いていた。墓地のはずれには池があり、終戦直後までは釣り堀として残っていた。これがかつての谷戸川の水源地、長池だったのではないだろうか。
染井霊園を見わたすと、東側は台地の上で、西側は台地の下という地形である。それにたいして、染井霊園の西側にも、向かい合うように、やはり台地がある。つまり、霊園の西側の端は、2つの台地から斜面が落ちこむ谷間の底、いわゆる谷戸の地形になっていて、それが南北を線状に貫いているのである。したがって、川添登の引用文にある「墓地のはずれ」とは、そのどちらかの端ということになる。
染井通りからの染井霊園の入口は、方角的には霊園の北東の外れになる。園内を西側にまっすぐ歩いて、斜面を下りきったその向かいが、慈眼寺とその境内墓地である。ここが「墓地のはずれ」の候補地の1つになる。鈴木理生や文京区あるいは豊島区のいう染井霊園の北側とは、このあたりをさすものとみられる。
染井霊園と慈眼寺墓地の境は、駒込5丁目と巣鴨5丁目の境でもあり、それに沿って人と自転車だけが通れる生活道路がつくられている。慈眼寺の墓地は、南北に細長い短冊形になっていて、道路を南に向かって歩いていくと、墓地がつきたところで、中央卸売市場豊島市場の塀が右側にあらわれる。それにたいして、左側は染井霊園の南側の端にあたるところで、谷戸のつきあたりといった感じの窪地になっている。
「墓地のはずれ」に該当するもう1つの候補地は、おそらくこのあたりのことだと思われる。終戦直後までそこに残っていた釣り堀が長池ではなかったか、と川添登は推測しているが、この場所は『江戸切絵図』に描かれた谷戸川の川筋ともおおむね合致する。もしそうだったとすれば、暗渠化するまでの谷戸川は、染井霊園と慈眼寺墓地の境になっている生活道路に沿って流れていた可能性が高いと考えられる。
(以上、前半)
2021年5月12日
「ラグビーは毎日なんだよ」…同志社、早大、東京芸大ラグビー部のこと
日曜日の朝刊(5月9日付)に、同志社大ラグビー部を1面丸ごと特集していた。同志社大ラグビー部は、毎日新聞とも結構深い関係があるので、いくつか補足をしてみたい。
まず同志社ラグビー部の歴史。元毎日新聞のラグビー記者・池口康雄(東大ラグビー部OB)はこう書いている。
「慶応義塾がラグビーを導入したのが明治32(1899)年。この12年後にようやく旧制三高、同志社、京都一中と、東海道をひと飛びして京都にラグビーの芽がふき出した。関東以北では慶応の努力にもかかわらず一向に根づかず、二番目の早稲田まで実に19年という歳月を要した」(『早稲田ラグビー』朝日文庫1987年刊)
同志社は、慶應義塾、三高に次いで日本で3番目に創部した。
慶應義塾vs同志社。対校戦では最も長い歴史を持つ。ファーストマッチは、創部翌年の1912(明治45)年1月9日。京都の三高校庭で、だった。

「スコアは忘れたが、大敗した」と、同志社のフルバックで出場した鈴木三郎が『同志社ラグビー蹴球部創立25周年記念誌』(1935年刊)に書き残している。
鈴木は、卒業して大阪毎日新聞(大毎)の記者となり、外信畑を歩んだ。1941~44年ブエノスアイレス特派員という記録が残っている。
「大毎ラグビー部」は、「関西における実業団チームの第1号」(『関西ラグビーフットボール協会史』)で、1926(大正15)年1月結成。そのファーストマッチ北野中学校戦に、鈴木はHBで出場している。
その試合のメンバーがスゴイ。FWに松岡正男(慶應義塾蹴球部〈ラグビー部〉の草創期の中心選手。当時経済部長。羽仁もと子の実弟)、久富達夫(東大ラグビー部第2代キャプテン)、「大毎野球団」から野球殿堂入りの小野三千麿(慶大)、高須一雄(慶大、のち南海ホークス初代監督)、井川完(同志社大)と、SOで川越朝太郎(旧姓棚橋、京都一商)の4人。TBに中村元一(第1回早慶ラグビー戦の時の早大マネジャー。晴れの特異日11月23日に試合日を決めた。元仙台支局長)。
「ラグビーは毎日(新聞)なんだよ」。これは現在、花園で行われている全国高校ラグビー大会生みの親杉本貞一(慶應義塾1913年度キャプテン)の言葉である。1918(大正7)年1月の第1回大会の優勝は全同志社で、その後も同志社中学が第3回大会から5連覇、1年置いて3連覇している。
杉本は、第1回慶同戦に出場した。
◇
早大ラグビー部の創部は、同じ1918(大正7)年11月7日。創設者で、初代キャプテンの井上成意が書き残したものを日比野弘早大名誉教授が自著『早稲田ラグビー史の研究』(早稲田大学出版部1997年刊)で紹介している。
井上成意は1916(大正5)年3月に同志社中学を卒業して、早大商科予科に入学した。「ラグビーが発達するためには、野球のように早慶戦が必要」と述べたうえで、「いやしくも私大の雄早稲田にラグビーの如き勇壮なる競技の存在せざることを遺憾として、幼年より親しめる楕円球を初めて戸塚球場に持ち来たり、同志と共に、蹴球せるが早大ラグビーの涵養である」。
野球の早慶戦は、1903(明治36)年に始まったが、両校応援団の過熱から06(明治39)年秋の第3戦から中止となったままだった。
ラグビーの早慶戦は、1922(大正11)年11月23日に始まった。その3年後1925(大正15)年に、野球の早慶戦が復活したのである。19年ぶりだった。
井上成意は、卒業してカルピスに就職した。「初恋の味」でカルピスが大ヒットした時の宣伝部長である。1956(昭和31)年没、58歳。
◇
さて、井上成意の父親井上権之助(1869~1938)も同志社OBだ。同志社ラグビー部史に、1889(明治22)年神学部バートレット教授がサッカーボールを持ち込んだことに始まるとある。権之助がバートレット教授と蹴球を楽しんだ様を同僚が書き残している。
「当時御苑内の芝生の一部が、母校の運動場として使用の許可を得ていたので、学生の所望で創められた兵式体操も、ハルツレット先生(バートレット教授)から初めて蹴球を教わったのもそこであったが、君はそれ等の運動には熱心の参加者であった。脚が短くてかなり矮小な君が、あの長身な先生の肩へ飛び着いて、頸ッたまへ獅咬み着いた珍妙な姿は、今もありありと眼の前に見えて、50年も前の事とはどうしても思われない」
産業人名事典によると、権之助は1890(明治23)年に同志社を卒業して第一銀行に入行。安田銀行本郷支店長、九十八銀行支配人、横浜市復興信用組合常務理事などを歴任している。 7男1女に恵まれ、成意は2男。12歳下の6男、彫刻家の信道は、東京美術学校(美校、現東京芸術大学)が1929(昭和4)年にラグビー部が創部したときのメンバーで、第3代キャプテンだった。
兄弟で大学ラグビー部を創部しているのだ。
美校ラグビーの始めは、山岳画家でのちにアンデスで遭難死した山川勇一郎(1934年油画科卒)。神戸一中のラガーマンだった。

1929(昭和4)年の入学早々、「山川がラグビーのボールを持って立っているではないか。私は思わず駆け寄ってラグビー部発足の相談をした」と、信道は『上野の杜のラグビー部1929-1992』(1993年発行)に思い出を寄せている。
仲間に加わったのは、同級生の真木小太郎(油画科、マイク真木の父親)、川端実(油画科)ら。キャプテンは2年上の菅沼五郎(塑造科)。菅沼は、信道がキャプテンを務めた1931(昭和6)年を除いて34(昭和9)年まで5年間もキャプテンを続けた。
「まずジャージーを作らなければならない。旧食堂でメリヤスシャツをバケツに入れ、黒く染めたのも思い出だ」と信道。オールブラックスである。部史に「井上の発案」とあるが、「試合のたびに、汗で体が真っ黒になった」とも語っている。
兄成意に頼まれたのか、1927(昭和2)年の早大豪州遠征に参加した現役選手助川貞次(39年戦死)が指導に来たことがあった。練習後銭湯に行って「助川さんの体躯は、石膏のヘラクレスのよう。私たちの体躯と差があるので驚いた」と記している。
毎日新聞の美術担当記者だった安井収蔵(2017年没、90歳)が「ああ、東京芸大ラグビー部」というエッセーを残している。こんな芸術家もラグビーをやっていたんだ、という参考に、すでに紹介したラガーマンを除いて安井が取り上げたOBを列挙してみる。
柳原義達(36年塑造科卒)、舟越保武(39年塑造科卒)、版画家清宮質文(42年油画科卒)、彫刻家大國丈夫(45年鋳金科、52塑造科、56年彫刻科卒)、深沢幸雄(48年彫金科卒)、桐野江節雄(49年油画科修士)、元東京芸大教授・彼末宏(52年油画科卒)、画家宮田重雄の長男晨哉(52年油画科卒)、保田春彦(52年塑造科卒)、高塚省吾、彫刻家飯田善国(ともに53年油画科卒)、吾妻兼治郎(53年彫刻科卒)、新妻実(55年彫刻科卒)、藤田吉香(55年芸術学科卒)、インダストリアル・デザイナー栄久庵憲司(55年図案科卒)、アバンギャルド作家篠原有司男(56年油画科修士)、福本章一(56年油画科卒)、工藤哲己(58年油画科卒)。
大國は1941~56年、「戦争による4年間のブランクを除き15年間の学生生活」をラグビー部とともにした。2014年に90歳で亡くなったが、法名は「楕円」の2文字である。 もうひとつ、洋画家で女子美大名誉教授入江観(86歳、56年度キャプテン、57年芸術学科卒)が日経新聞文化欄で「上野の杜ラグビー90年」(2019年10月13日付)を書いている。安井が紹介しなかった芸大ラグビー部OBを挙げる。
漆芸家高橋節郎(38年漆工芸科卒)、インダストリアルデザイナー柳宗理(40年油画科卒)、建築家清家清(美校→43年東京工大卒)、ガラス工芸家岩田久利(51年図案科卒)、画家赤堀尚(54年油画科卒)、画家福本章(56年油画科卒)。
アートディレクター河北秀也(71年ビジュアル・デザイン卒)、彫刻家舟越桂(東京造形大→77年大学院彫刻修了)、木彫の三沢厚彦(87年彫刻科卒、89年大学院彫刻修了)。
◇
「世界のオザワ」小澤征爾(86歳)は、第1回東京都新制中学校ラグビー・フットボール大会で優勝した成城学園のウイングだった。SHに後のロック歌手故小坂一也。1951(昭和26)1月の大会だから70年前である。
小澤の右手人差し指は曲がっている。ラグビーで骨折したのだ。ピアニストの夢は破れ、指揮者に転向した。だから「ラグビーがなかったら『世界のオザワ』は生まれなかったかも知れない」といわれるのだ。
◇
彫刻家井上信道は、2008年に亡くなった。99歳だった。横浜駅西口にブロンズ裸像「ファンタジー」、神奈川非核宣言県記念碑の母子像などが横浜市内に飾られている。
妻の画家井上寛子さんは、早大ラグビーが創部した1918年生まれで、ことし103歳の誕生日を迎えるが、4月に都内で個展を開いた。娘の現代アート作家大野静子さんも、5月12日まで横浜三渓園で開かれた「アートの庭―北欧と日本の作家によるコンテンポラリーアート展」で作品を展観した。
芸術一家である。
(堤 哲)
2021年5月11日
「ミルクワンタン」ついに閉店。有楽町編集局……「すし横」時代の喜怒楽々 喧嘩。ノミシロ。ツケ。給料袋。しょんべん。増ページ。

有楽町時代の編集局入口は「飲み屋」の女将がわんさわんさと押し掛けた。毎月5日・25日、毎日新聞社給料日恒例の騒動が一日中見られる。ツケで飲み食いしたノミシロ(飲み代)をいただきに来ているのだ。出入りする編集局員……主に部長・副部長・古参記者連が女将に“逮捕”されては「払いなさいね!」と言われて渋々、給料袋から直接ナン千円かを渡さざるを得ない。ナン万円も溜まった大先輩も大勢いた。「こん次にしてくれんかなっ……」と泣き言で勘弁してもらったり……。
基準外手当の入った毎月5日の給料袋を袋ごとそっくり女将に渡した大先輩と出会い二人で呵々放笑した。隣接の「丸の内名画座」(映画館)へ逃げ込んで難を逃れた部長もいた。輪転機のある地下を通って狭い階段を上がると映画館の裏に行けた(知る人ぞ知るルート)。ついでにタダで映画1本見ちゃう図々しサ。
★
借金とり女将はほとんどが「すし屋横丁」の店である。「すし屋横丁(すし横)」は昭和20年終戦と同時に生まれた露天、バラック、1杯飲み屋(違法な400店近く)が整理統合を繰り返し、昭和23年(1948)誕生した。正しい名称は「有楽町商業協同組合」。抽選で選ばれた飲食店106軒。ずっと以前だが「思い出のすし屋横丁地図」をモロ(筆者)が作成して関係者に配ったこともあったくらい毎日新聞社には懐かしい“遊園地”(今で言えばテーマパーク)である。界隈は小便臭いのだ。ほとんどの客は店を出た所で立ちしょんべんをしていた。それがまた、いかにも毎日新聞社の会議室であり厚生施設のようでもあり……。
「すし屋横丁」と言っても電気屋があったし、ホルモン屋、バー、洋食、すき焼き、喫茶店、雀荘……みんな知っているのが「吉田」「三友」「花柳寿司」「赤星」「照寿司」「げんぱち」「ミルクワンタン(鳥藤)」「フライパン」「地球」「だるま鮨」「有楽苑」「山楽」「ひろしまや」「珍萬」「宝来」「来々」「アキラ」「板門店」「ぽんぽん亭」「エーワン」「お喜代」・・。
日劇側出入口近くにはマムシの生き血を飲ませるヘビ屋もあった。「げんぱち」なんぞは竹橋移転に合わせて九段に越してきた。「珍萬」をやっていたオヤジが涙を見せながら懐かし噺……「でっかい声で議論するブン屋さんの噺は面白かったア。焼き飯や中華そば、毎日新聞社へ連日出前したよ。食わねえまんまゴキブリ漬けになっていたメシ皿もあったなあ。ウチに来た記者なんかも傍若無人でねエ。俺がいちばんエライみたいな……ニュースでは聞けない秘密も聴いたさあ。いまだから言うけんどよ、あれは、よそで喋って、情報通だなんていわれちゃって……はっはっは」(昭和55年取材時)。テレビも普及していない時代の新聞記者は世間の花形だった。(上の写真=昭和30年代の「有楽町すし屋横丁」のメインストリート)
★
有楽町駅前の「すし横」跡地に出来た「東京交通会館」には「すし横」にあった店が14~15軒もあったが、だんだん消えた。美味・加茂鶴を飲ませる「ひろしまや」は女将さん(故人)の娘が引き継いで今もやっていてモロもときどき飲みに行く(「ゆうLUCKペン」の有楽町特集号が置いてあるよ)。
ついこの前閉じた飲み屋「吉田」はスシ横時代、中通りを北に行って右手にあった。毎日新聞の幹部が連日のように訪れた店で、最近も那須良輔画伯の貴重な直筆絵がたくさん飾ってあった。「隊長」と仇名のあった主人はときどき顔を見せていたが、もしかして逝ったかも? あの絵は相当の高値が付いたろうな。
★
記者同士の新聞つくりに関わる議論・論争・喧嘩はいつものコト。どんなに喧嘩しても飲み代は先輩もちなのはアタボーよ、の世界。我々下っ端記者は飲み代を払った試しがない。そも、すし屋横丁へ同僚と行くなんてことはナイ。デスクや部長や1つ2つ3つ上の先輩と飲る。割り勘なんて言おうものなら張り倒されるから言わない。だからモロも昭和30年代、飲みに行って支払いをしたことはゼロ回。さんざん先輩を「アホかっ、考えが甘いっ」と批判しても、お開きになる際は先輩が女将の目を見て店を出ればおしまい。
飲み屋の女将側も承知の沙汰。目配り一つ、このグループだとこの人、この仲間ならこの人、という具合にツケる人間が判っていた。店を出る際に「お金がひらひら」するお勘定シーンなど見たことがナイ。
新聞も朝刊が16ページになり、夕刊が4ページになり……増頁増頁、編集局各部の記者も増員増員。ゆけゆけどんどんが先行、給料も少しづつでも確実に増額増額して、人間的にもマイナス風は吹かなかった。
★
ミルクワンタンで有名な「鳥藤」が2021年4月23日を最後に「閉店」した(新聞報道で知る)。
飲み屋の閉店がニュースになるのだから社会的価値が高い。敗戦直後の屋台から72年もつづいたんだからエライもんである。「鳥藤」はすし屋横丁の北側の端、入口から入って右側3軒目にあった(今で言えば有楽町駅京橋口の前)。
その頃のミルクワンタンは細かく刻んだ鶏モツ煮を牛乳で煮込み、ワンタンを浮かした汁丼。これが酒飲みには美味しかった。栄養満点。二日酔いのモロなんぞは毎日食べて胃がすっきり。面白い紙面を作るぞ!という戦闘気分に燃えて編集局に出社した。現在は汁の出汁も多少違い、鶏モモ肉やらいろいろ上等の具も入っているようだが、昭和24(1949)年当時はそうはいかない。ワンタン以外は何も入っていなかったんじゃないか。あのころは1杯20円……昭和30年ころから30円? 40円だったか。ミルク(もしかして当時は脱脂粉乳?)の分少し高かった。この辺り、取材しないで書いているから間違いかも知れぬ(鳥藤さんごめんなさい)。閉店時は700円?
初代と、それを継いだ息子さんも故人となり、息子さんの奥さんが最後まで取り仕切っていたと聞く。
「鳥藤」は飲み屋というよりは、今で言うラーメン屋。当時はラーメンという言葉もなく「中華そば」(町に来る屋台は「チャルメラ」)。ここではツケというのはなく現金払い。モロも「鳥藤」ではカネを払った。だいたいに於いてこの店のナマエを「鳥藤」だと知っている人は少なく、誰もが「ミルクワンタン」と呼称していた。すし屋横丁は東海道新幹線開通時に取り壊され(最終的には昭和42年)、「鳥藤」をはじめ幾つかの店は東京駅よりのガード下(今の場所=有楽町高架下センター商店会)へ移転、「玉菊」「楽々」「末廣」「山楽」などと一緒にアーチ式看板には「鳥藤」ではなく「ミルクワンタン」と記されている(現在も)。
うーん、ざんねん、最期の「ミルクワンタン」食いたかったなあ。現在のガード下も「すし横」に景色が似ているもんなあ。お店の壁にはモロ製作の「すし横地図」が極最近も貼ってあった。なんたって清酒はヤカン?から注ぎ、焼酎は一升瓶から減った分で支払い計算などなど、やることが粋なんだよな。
★
有楽町編集局の頃、朝刊13版●●、最終版を降版すると午前4時半にもなっていた。それから出来上がり紙面をワシ掴みにして、すし屋横丁へ連れ立って出陣したのである。紙面の議論をしたあげくにミルクワンタンを食って電車に乗り帰宅した。ちょうど出勤ラッシュだったが反対方向なので座れた。いいあんばいに眠ってしまい、終点の浅川駅(今は高尾駅)まで行き、また東京駅に戻ってしまった「終点完全往復輩」もいた。
すし屋横丁の店は縄張りがあり、毎日の店、朝日の店……が存在し「読売は外堀川を越えられぬ?」「産経新聞は中央通りを越えられぬ?」との噂が飛ばされていた。すし屋横丁はほゞ毎日と朝日が占拠している風だった。入社当時、先輩に「あそこの店は朝日だから行かないほうがいいぞ」と釘を刺されたものだ。
ぐでんぐでんに酔っ払ったあげく読売の宿直室に泊まり込んだ先輩もいた。廊下で近藤日出造(政治漫画家)に出会って「オスっ」と挨拶したゾと自慢していた。毎日新聞のヤツは外堀川を越えて向こう側まで行きやがるん……。
★
その頃の飲み屋の感じは店に入るとオヤジも女将も、客にまでジロっと見られて入りにくいんである。まだまだ「一言さんお断り」の習慣は当然あちこちに残っていた。馴染みの店だと扉を開けたとたん、店じゅうに笑顔が舞い、「らっしゃーーい!」大歓迎されるといった具合。ま、素性の判らぬヤツは入れてくれない。“一応”高級寿司屋を名乗っていた「花柳」などは部長以上しか入れなかった(デスク級も部長と連れ立って行ったものだ)。
昭和30年代までだろう、自宅近所の魚屋も八百屋も酒屋も「ツケで買う」のがキマリになっていて月末集金というのが習慣。買い物は「ご用聞き」に注文したのであった。知らない家には売らない。知らない人は知らない……よく知ってる家には売る……飲み屋も同じである。
それが「ミルクワンタン」は朝日も毎日も一緒に食った。カウンターに隣合わせに座って食った。馴染みの客の「紹介状」がなくてもミルクワンタンは通りがかりの人が自由に食えた。みんな黙して食っていたからかも知れぬ。
★
ある夕方、編集局次長・高原四郎に「鳥藤」で偶然にも隣合わせしたことがある。高原さんも「ミルクワンタン」を食っていた。25歳も年上の大先輩だろうが、誰であろうが、気楽に冗談を言い合い、大笑い会話を交わす自由が有楽町編集局にはあった。
高原四郎と隣合わせたモロが切り出して、石川達三の連載新聞小説“成瀬南平の行状”が掲載禁止になったトキの噺を伺った。この小説は昭和20(1945)年7月14日から1面で連載開始されたが、15回で休載となり、終戦(8月15日)の翌々日(8月17日)紙面に「都合により続稿を打切ります」と掲載されたのみ。休載の理由は判らず仕舞い。熱狂的人気を浴びた新連載モノだったから突然の休載に読者は驚いた。
その後、小説の中身が「官僚・官界を批判」しているとして内閣直属の情報局の検閲に引っ掛かった「事件」だと知った。連載開始直後から「警告」「意図変更」の強い要求を毎日新聞は無視して連載を続けたのが内閣情報局の怒りを買った。何度も何度も呼び出しを食い連日情報局に足を運んだのが高原四郎。学芸部記者?高原四郎が石川達三担当で連載開始の当事者だったからである?(詳しいことは忘れた)。「事件」の委細は書くのが面倒なので省略するが、なんせ高原四郎の噺の経緯は面白かった。敗戦がらみもあって高原四郎は当局の拷問は避けられたとか。
「モロオカ君っ、もう一杯食うか」。二人で二杯目のミルクワンタンをすすった。
達三の小説中に「国民には我慢を強いていながら、軍人・役人は旨いもんを食っている」特別配偶が描かれており、高原四郎は新聞記者も多少なりとも様々優遇を受けている事象を挙げて苦悶していた。戦況を軍部の言う通りに報道していたコトと関係あり? 終戦後も編集局では闇ルートで届いたビールがじゃばじゃば飲めていたのはモロも知っている。
庶民の旨いもんミルクワンタンと石川達三と高原四郎は今も頭の中でくっついている。計4杯のミルクワンタン代は高原四郎が払った。
(諸岡 達一、文中・敬称略)
2021年5月11日
堤哲さんが「ミルクワンタン最期の夜」撮影 社会部記者魂+写真部魂! ジャーナルが宿る身体
「モロさん、撮って来たよ。ミルクワンタン最期の夜……」。
飛び込んで来たのは<堤哲さん(79歳)からの欣喜雀躍>メール。

「えーっ。そりゃあ素晴らしい。感謝感謝」とモロ。堤哲さんのメールはさらに「満員で座るところがなかった」など現場報告が続いていた。2021年4月23日、「最期のミルクワンタン」の写真を撮り何枚か送って来た。ここに掲載しましょう。その夜、ちゃんと現場に行き雰囲気を味わってくるという社会部記者魂と元写真部長魂が合体した身軽さに感動してしまう。

「鳥藤」にミルクワンタンを食いに行くと、昔から不思議と朝日新聞の記者と出くわす。夕刊降版後のことが多いのは時間帯が同じだったから“だけ”だろうか……。毎日記者と朝日記者の「ブン友」を察しないわけにはいかない。
最期の夜、ミルクワンタンを食っていた轡田隆史さんは「私はね、サツ回りがマルケイ(丸の内警察署)で、ここは縄張りなのよ……」と笑っていたという。堤哲さんは「さいたま市の自宅からわざわざ閉店を見届けに来るなん、ヤジ馬の極みではある……いや、社会部記者の鏡であるね」と感じたそうだ。堤哲さん自分も、まさに「そうじゃんか。鏡でもあるし社会部記者の原点だね」とモロ。こうして毎友会HPに写真入りで報告できるのもジャーナルな心がトシに関係なく生き続けているからだ(身体=駄洒落)。

★
貴重なおまけは【堤哲さんの独り言】
『轡田さんは名文記者として知られる。朝日新聞夕刊1面<素粒子>を長いこと担当した。毎日新聞の吉野正弘さん(56歳)が暴走族に暴行を受けて亡くなったとき、こう書いた。《毎日新聞夕刊「近事片々」記者の死に絶句す。筆端、光を吐き、筆頭、花を生じていた人よ。》1989年4月18日夕刊「素粒子」。轡田さんは朝日新聞退職後、テレビ朝日『ニュースステーション』のコメンテーターを務めるなど活躍された。
(以上・ミルクワンタン総まとめ 諸岡達一 85歳)
以上
2021年4月23日
白川義員写真展「天地創造」が東京都写真美術館で5月9日まで

これは、米ユタ州とアリゾナ州にあるバーミリオン・クリフ国立公園の北西端にある岩山の風景である。今、恵比寿の東京都写真美術館で開かれている白川義員写真展「天地創造」(5月9日まで)の入口に飾られた巨大な写真をシャメした。
「ザ・ウェーブ」。①~⑤、5点が展観されている。
《巨大な岩がまるで波が押し寄せるような形で固定されている。このような豪快な岩を手でさわりながら実際に見た事はかつてなかった。このウェーブ周辺は見渡す限り赤と白の岩でおおわれている》
《ウェーブに行くことが出来るのは1日20人。20人に手渡されるのが行き帰り6枚の風景写真が印刷された1枚のパンフである。最初の6枚はウェーブに向かって歩く方向の風景写真で、後の6枚はウェーブから帰る方向の写真。この風景に向かって歩きなさいと指示している》

《実際に現場に行くにはユタ州側の北方5kmあたりから徒歩で南下し、州境を越えてアリゾナ州側を約1km南に歩くと、このウェーブに至る》
英文のタイトルは「The Earth」。地球が持つ美や神秘、荘厳さ。前人未踏の領域に挑戦し続けた写真家白川議員さん(86歳)の集大成の写真展である。前期展「永遠の日本」(Eternal Japan)を見て、「絶景」の数々に感動、後期展「天地創造」に足を運んだのだ。
毎友会HPに紹介するのには、それなりの訳がある。入ってすぐに山岳写真家、白川議員さんの真骨頂、エベレストやアルプスなど世界中の山の偉容が並ぶが、その中に世界8位の高峰、標高8,163m「マナスル東壁」。日の出の太陽を受けてオレンジ色に輝いている。
その先の説明にこうある。《この山は日本人が初登頂をしたのである》
初登頂は1956年5月9日午後0時30分。第3次マナスル登山隊(槇有恒隊長)の今西壽雄さん(京都大学山岳部OB)とギャルツェン・ ノルブ氏(ネパール人隊員)の2人。
巨峰マナスル登頂ついに成功
世界登山史に輝く金字塔
5年間の苦労実を結ぶ
これは毎日新聞1956(昭和31)年5月18日朝刊1面トップの見出しだ。マナスル登山隊の第1、第2次登山隊員だった運動部長・竹節作太が書いた。
《敗戦後10年。第1報が日本に届いたのは5月18日。「祝マナスル登頂」のアドバルーンが16個も上がった》
《登山隊が帰国した6月22日、歓迎の人波は羽田空港どころか蒲田の駅まで人で埋まったそうである》
マナスル登山隊は、1954年の第1次から毎日新聞が全面的に応援して行われ、56 年の第3次登山隊の最年少メンバー日下田実(早大山岳部キャプテン、のち毎日新聞記者)も5 月 11 日に加藤喜一郎氏(慶応大学山岳部OB)と共に頂上に立った。
記録映画「マナスルに立つ」は、登山隊に同行した毎日新聞写真部員、依田孝喜が撮影したもので、依田は1957年、第5回菊池寛賞を受賞した。
(堤 哲)
2021年4月23日
元新潟・長岡支局長、池田友好さん(86)が『ぶらっとヒマラヤ』読後コラム
―新潟支局当時の丸山昌宏社長、広田勝己取締役も登場
池田友好さんが長岡支局長当時、支局員だった浜名純さんから、旬間の「十日町タイムス」に掲載されたコラム2本が転送されてきた。タイトルにある単行本『ぶらっとヒマラヤ』の著者、藤原章生さんは北大山岳部出身。浜名さんは山岳部で藤原さんの先輩に当たり、毎日新聞退社後に編集・出版関係の仕事に携わり、開高健ノンフィクション賞受賞の『絵はがきにされた少年』出版に尽力、2月には柏艪舎から新版が発行された。
池田さんが長岡支局長当時、私はロッキード一審判決直後の1983年12月に田中角栄元首相と作家、野坂昭如さんが対決した選挙を約1か月にわたって取材し、日々、池田支局長、浜名記者に世話になった。
丸山社長は、池田さんが新潟支局デスクだった当時、新入社員として新潟支局に赴任。池田さんは「奥さんも長岡市出身で、2人の交際時から結納まで手助けした間柄」。日本新聞協会会長就任決定に、お祝いのメールを送ったという。
池田さんは長岡支局長から新潟支局長を歴任。牧内節男社長当時のスポーツニッポン新聞社が初めて新潟支局を開設し、販売店主らの要請で初代支局長に就任するため繰り上げ定年退職した。スポニチ支局長退職後は日本報道写真連盟新潟県本部の運営に関わり、今年3月末の解散時は顧問だった。
(高尾義彦)


2021年4月20日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その11(後編)
写真が多いので、冒頭のみ掲載します。全文は下記のURLで検索を
http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/cat_50035506.html
私の駒込名所図会(2)八百屋お七と駒込土物店(後編) 文・写真 平嶋彰彦
先に述べたように、1682(天和2)年12月28日の大火は「駒込」より出火したあと、「本郷森川宿東側」から「松平加賀守上屋敷」(現在の東京大学)に燃え広がった、と戸田茂睡は書いている。
ところで本郷森川宿とは、なんなのだろうか。宿といっても、旅行者を泊める宿場ではなさそうである。それもそうだが、現在のどのあたりをいうのだろうか。
手持ちの資料をしらべると、もともとは1598(慶長3)年に没した森川金右衛門氏俊に与えられた与力・同心の大繩屋敷(集団知行地)だった。つまり、ここでいう宿というのは、居住地の意味である。与力は氏俊の親族ばかりで、全員が森川姓を名乗っていたことから、また中山道に面していたこともあって、森川宿の俗称がつけられた。
ところが延宝年間(1673~81)になって、その大半が陸奥福島藩主本多家(のち岡崎藩主)の下屋敷として召し上げられ、それ以外が先手鉄砲組の組屋敷として残された。というのである。


2021年4月15日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その11
この連載は毎月14日に更新されます。写真が多いので、抜粋を掲載します。
全文は下記のURLで検索を(後編は19日)
http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/cat_50035506.html
その11 私の駒込名所図会(2)八百屋お七と駒込土物店(前編) 文・写真 平嶋彰彦
本郷追分は、中山道と日光御成道の分岐点になる。日本橋から1里の距離にあたり、1766(明和3)年に焼失するまでは、そこに一里塚があった。日光御成道は現在の本郷通りで、岩槻街道ともよばれた。本郷追分を越えると駒込で、次の一里塚は西ヶ原にあった。「ときの忘れもの」の所在地は、本郷追分と西ヶ原一里塚のちょうど中間点になる。
2年前の6月になるが、大学写真部の旧友たちと白山と駒込の街歩きをした。このときの探索地に八百屋お七にゆかりがあるとされる円乗寺(白山1-34-6)、大円寺(向丘1-11-3)吉祥寺(本駒込3-19)が入っていた。
八百屋お七の代表作とされる『天和笑委集』、『好色五人女』、『近世江都著聞集』、『八百屋お七恋緋桜』、『古今名婦伝』に目をとおすと、物語の概略は次のようになっている。
八百屋の娘お七は、1682(天和2)年12月28日の大火で焼けだされ、一家とともに檀那寺に避難したとき、その寺の寺小姓と恋仲となった。年が明けて、実家にもどるが、恋慕のあまりその寺小姓との再会を願って放火、召捕られて、火あぶりの刑に処された。

円乗寺は、『近世江都著聞集』や『古今名婦伝』では、お七が避難した檀那寺とされる。境内にお七の墓がある。墓石は三基あり、中央の首がもげた仏像形の石塔は寺の住職が、右側の石塔はお七を演じて好評をとった岩井半四郎が寛政年間(1789~1801)に、左側の石塔は近辺の人たちが270回忌に建立したという。
大円寺は、『天和笑委集』によると、天和2年12月の大火の火元とされる。山門を入ったところにほうろく地蔵がある。これはお七の供養ために、享保4年(1719)に渡辺九兵衛という人物が寄進したという。ほうろく地蔵のかたわらに庚申塔がたつ。こちらは本郷追分の一里塚にあったものを移したものだそうである。
吉祥寺は駒沢大学の前身である栴檀林のあった曹洞宗の名刹である。『好色五人女』や『八百屋お七恋緋桜』では、ここもお七が避難した檀那寺とされていて、境内にはお七・吉三郎の比翼塚が1966(昭和41)年に建立されている(ph9、ph10)。
大円寺から吉祥寺にむかう途中、本郷通りに面した天栄寺(本駒込1-6-16)の門前に、「駒込土物店」の石碑がたっているのが。なんとなく目に入った(ph7)。「土物店」というのは青物市場のことである。

あとで調べると天栄寺のあるところは、もとは麟祥院領駒込村の百姓地で、そこにさいかちの大木があったことから「一本さいかち之辻」と呼ばれた。近隣の農民たちが野菜を担いで江戸に向かう途中、その木の下で毎朝一休みするのが慣習となり、やがて付近の人たちがそこで野菜を買い求めるようになった。それが青物市場の始まりだいう。
1660(万治3)年、その場所に天栄寺が本郷菊坂から移転してきた。本郷通りを隔てた東側が駒込浅嘉町・同高林寺門前であるが、そこにも土物店ができたことから、街道の両側一帯を駒込土物店と総称するようになった。やがて、町屋が許されるようになり、1745(延享2)年になると、それまでの領主支配から人別が江戸町奉行支配に変わった。駒込の青物市場は、かつては神田市場(現在の多町)を脅かすほど盛んだったということだが、1937(昭和12)年に巣鴨に移転した。
前回にも書いたが、1854(嘉永7)年の『江戸切絵図』(尾張屋版)をみると、日本橋から本郷までの街道筋は市街地化されている。駒込まできてようやく農地や自然地の土地区分をしめす緑色があらわれ、随所に「植木屋多シ」の書込みがある。
しかしおなじ駒込といっても、本郷追分から土物店のあった天栄寺の近辺までは、四方をびっしり家屋敷が立込んでいて、田畑や自然を確認することができない。駒込は江戸という都市空間が田園地帯と接触するいわゆる郊外の地であった。そして駒込という郊外を代表的な商売が植木屋であり、もう一つが八百屋だったことになる。
八百屋お七の事件には異説が多い。異説が多いということは、事件の真相が分かりにくいことでもある。異説が多い原因として、江戸幕府の刑事判例集である『御仕置裁許帳』に記載がないことにくわえ、信頼にたる記録史料が見当たらないことがある。そうしたなかで、ただ一つ確からしくと思われるのが、戸田茂睡の『御当代記』である。
この書には、1682(天和2)年の大火とその後の出来事については詳しい記述があり、翌年春のお七の事件についても、30文字たらずの短文であるが、次のような言及がある。
「駒込のお七付火之事、此三月之事ニて廿日時分よりさらされし也」
駒込の住人にお七という女性がいて放火の罪で召捕られた。事件はこの3月のことで、20日ごろ火刑に処され、遺骸はさらしになった。この箇所は追筆であるとされる。後日に噂話を耳にしたのだろうが、思うところがあり、書き留めたものとみられる。
『御当代記』は5代将軍綱吉時代の様々な事件や世相をつづった見聞記で、1680(延宝8)年5月から筆をおこし、1702(元禄15)年4月で終わっている。その当時を知るうえで貴重な史料と思われるが、戸田茂睡の存命中に公開されることはなかった。
当公方様ハ…天下を治めさせ給ふべき御器量なし、此君天下のあるじとならせタマハヾ諸人困窮仕悪逆の御事つもり、天下騒動の事もあるべし。
家綱から綱吉への世継ぎを評した一文だが、思想表現の自由が許されなかった時代のことである。存命中の公刊など、思いもよらなかったにちがいない。茂睡の没後、自筆原稿は子孫の家に秘蔵され、1913(大正2)年になってから、佐佐木信綱がその存在を世に知らしめ、それより2年後、飯島保作による全文翻刻が『戸田茂睡全集』の一部として、国書刊行会から刊行された。
『御当代記』にしたがえば、天和2年には2つの大火があった。1つ目は霜月28日、牛込川田が窪(現市ヶ谷柳町)より出火、四谷・赤坂・青山・麻布などの大名屋敷を次々と焼き払い、火の手は三田までおよんだ。
物語や芝居で語り伝える八百屋お七の放火事件の発端となったとされる大火は、それよりちょうど1ヶ月後に発生した。こちらの火事は、
極月二十八日、駒込より火出、本郷森川宿東がハ、それより本郷へ出、
松平加賀守の本郷の上屋敷(現在の東京大学)を焼き払った、と戸田茂睡は書いている。さらに火の手は湯島をへて池之端、寛永寺黒門前から下谷へ延焼。そのいっぽう、南東方面にむかった火の手は、神田川の筋違橋、和泉殿橋、あたらし橋(美倉橋)、浅草橋を焼き落し、さらに、日本橋川の常盤橋前の町屋を焼いたあと、日本橋と江戸橋を焼き落した。それにとどまらず、飛び火して隅田川の対岸までおよび、両国の無縁寺(回向院)や深川の永代島八幡(富岡八幡)まで焼き払った、ということである。
見逃せないのは、そのあとに掲げられた次の一文である。
今年町同心八十人御ふちをはなたれ、あたけ丸のかこ丗人、この外方々の鳥見同心御ふちをはなれ候て、渇命いたし、火を付るとの沙汰なり。
町同心は江戸町奉行所に所属する同心のことである。あたけ丸(安宅丸)は、この年に解体された全長30尋(57m)櫓100挺という幕府の巨大な軍船で、扶持を失った水夫(かこ)は、武士の身分であったとみられる。鳥見同心は、御鷹場で鶴・鴈・鴨などを飼育するのが役目で、かたわら町同心同様に隠密を兼ねたとされる。

いずれも下級職といっても、江戸市中やその海辺を警護・防衛する幕府の正式な役人である。その百数十人が、身に落度がないにもかかわらず、とつぜん扶持を放たれ、路頭に迷うはめになった。その腹いせに放火におよんだというのである。あくまでも噂であるといっても、どうみても尋常な社会的情勢とはいえない。
そのような不穏な噂を裏づけるかのように、年が明けても火事は続いた。しかもどれもこれもすべて放火であった。
去年霜月廿八日・極月廿八日両日の大火事より正月ニ至二月迄毎日之火事、昼夜ニ五六度八九度之時も有、是皆附火也。
そこで町々に命じて、1つの町に火の見櫓を2基ずつ揚げさせ、その上に町内の大家役の者を登らせ、火の用心の監視を申しつけた。しかし、なおも放火は治まらなかった。
それと併行して、中山勘解由直守を火付改加役に任命し、配下の与力・同心とともに、横行する放火を取り締まらせることになった。火付改加役は、後の火付盗賊改のことであるが、その捜査の仕方を戸田茂睡は次のように書いている。
中山勘解由父子三人組与力同心ともに、火付見出し候やうに被仰付候ニ付、様々姿をかへ江戸中へ入はまり、火付を見あらはさんと仕候
さまざまに姿を変えて江戸中に潜入したというのは、とかく弊害の多いとされる目明しを使ったにちがいない。目明しは、与力・同心の手先で、多くは犯罪者を放免し、その代償として他の犯罪者を探索させたといわれる。
お七が処刑された2ヶ月後の5月、戸田茂睡は火付改加役の中山勘解由の捜査と取調べの方法を改めて問題視している。これもやはり噂だろうが、誤って捕らえられる人が夥しかった。くわえて、容疑者の取調べには、ためらうことなく拷問が用いられた。とうぜんの結果、身に覚えがない自白を強いられた犠牲者が夥しい数におよんだ、というのである。
火事場ニてうろん成ものをとらへさせらるゝに、あやまりでとらるゝもの夥敷事也。問諍つよくいわざるうちハ死ぬるまでせむるゆへ、とても死するものゆへ火付ニなりても苦をのがれんと思ひ、火付ならぬものも火付と云、科人ならぬものも科といふゆへ、科人多く人の損ずる事夥敷事也。
火付盗賊改役が設置された当初、火付盗賊改は、容疑者を召捕ると、一通りの取り調べを行い、町奉行所に引き渡すことになっていた。火付盗賊改はいわば予審裁判所で、町奉行所は本裁判所の感があった、と法制史学者の瀧川政次郎は『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』でのべている。
そうであったとすれば、お七の事件の場合も、裁判を正式に執り行ったのは町奉行所と思われるが、その前段の捜査と取り調べは、火付改加役の手になるものだったにちがいない。それが自白偏重主義に凝り固まっていて、かつ拷問を常套手段にしていたのであれば、お七が犯人とされた放火事件も、火付改加役とその配下の与力・同心・目明しが結託して捏造した冤罪であった、という可能性もないとはいえないのである。(以上、前半)
2021年4月12日
英国フィリップ殿下の小さな思い出=元ジャカルタ特派員、秋山哲さん

4月9日に99歳で死去されたイギリスのエディンバラ公フィリップ殿下には小さな思い出がある。
1975年だからもう半世紀近くになる大昔の話である。当時、私はジャカルタ特派員だったが、エリザベス女王がインドネシアに非公式で寄港された。オーストラリアからの帰途だったと思うが、王室ヨットで女王一行は到着した。
どういうわけか、女王はインドネシア駐在の外国特派員だけを招いて茶会を開いたのである。みんないそいそと出かけた。部屋の入り口で女王が記者たちを迎え、握手を頂戴した。
女王は部屋の中を巡って、一人一人に声をかける。難しことを聞かれたら乏しい英語力で対応できるか、と不安だったのだが、「あなたはいつからインドネシアにいるのですか」と、こちらの対応力を見抜いてか、単純な質問であった。
一安心して、ソビエトのタス通信の特派員とグラス片手に話しているところへ、スラリと長身のフィリップ殿下が、にこやかにやってきた。こちら二人がそれぞれ名乗りをすると、彼は質問したのである。
「インドネシアで、日本の記者とソビエトの記者が何語で話しているのか」
この人、ウイットの利いた話をするといわれているが、正にそうであった。
私が答えたのだが、後で考えても、うまい答えをしたのである。
「残念ながら英語で話しています」
その後、殿下は近々、日本を訪問する、という話をしてくれた。1975年5月に女王夫妻は日本を公式訪問しているが、その話である。
そして、女王の日本訪問は初めてだが、自分にとっては日本は2回目だという説明であった。1回目はいつだったのかと聞いた。その答え。
「海軍に勤務していてミズーリ号に乗っていた。日本の降伏文書署名式を見ていた」
1945年9月2日、東京湾に停泊したアメリカ戦艦ミズーリ号の甲板で、マッカーサー元帥や重光外相らが署名するのを、女王と結婚する前のイギリス海軍士官フィリップは見ていたのである。この場面は映像でよく見るが、甲板の上には、白い軍装の人たちが歩き回ったり、式典を覗き見たりしている。その中にこの人はいたのである。
これは、あまり知られていないことではないだろうか。フィリップ殿下の訃報を見て、書き残しておこうと思ったのである。
(秋山 哲)
2021年4月3日
国会福島原発事故調から見えたメディアも「規制の虜」? 事故調事務局経験から牧野義司さんが指摘

東京電力柏崎原子力発電所(原発)で2020年3月以降、不正侵入検知の設備10か所に故障があったことが判明し、原子力規制委員会はテロ対策の不備だと問題視、1年後の今年3月24日、東電に対し核燃料搬入を禁止するなどの是正措置を出した。ニュースで大きく報じられたので、ご存知の方が多いだろう。それにしても原発の危機管理という点で、東電は何ともお粗末だ。
東電の原発危機管理がルーズ、という点で言えば、私にとって特別な思いがある。実は、私自身が2011年3月に起きた東電福島第1原発事故の真相究明調査を行う国会事故調査委員会の事務局に1年近くメディア向け情報発信の担当者としてかかわった。事故調査を通じて見えた東電という企業の現実は、かつて毎日新聞経済部記者時代に、東電を取材した時とは全く別の顔を持っており、巨大組織病の数々だった。
福島第1原発の事故調査に関しては当時、国会事故調以外に政府事故調、当事者の東電事故調、それに民間事故調がそれぞれ独自の立場で原因究明調査にあたった。この4機関のうち、政府事故調と東電事故調は事実上の「内部調査」で、仮に国に重大責任が及んだ場合、しっかりとした責任追及にまで踏み込めない弱みを抱えていた。これに対し、国会事故調は、超党派の立場で立法府が行政府を監視チェックし事故原因の究明も行う前例のない形の調査機関であること、特定の権益、利害にいっさい与さない、とくに政府から独立した機関として法的権限も与えられ厳しく真相究明にあたったことーーなどの特性を持っていた。このため、日本のみならず世界中が関心を持つ原発事故の調査を客観的に行える唯一の機関と言っていいのでないか、と私はかかわった当時、思った。
現に、国会事故調報告書は、事故原因について、人災がもたらした事故とはっきり断定した。直接的には地震、そして津波によるとはいえ、土木学会評価を上回る津波が到来した場合に海水ポンプが機能不全を起こし原発サイトの全電源喪失、炉心損傷に至るというリスクがあること、その対策を打つ機会があったにもかかわらず、歴代の規制当局、東電経営陣が問題を先送り、楽観的な見通し判断によって安全対策投資をとらなかったことが響いた。人災と言わざるを得ない、というものだ。また、監視規制する側の官僚が人事異動で十分な現場経験、政策ノウハウの蓄積がないまま、専門特化する監視対象の東電側に政策の方向付けをされるなど、結果的に「規制の虜(とりこ)」現象が起きている、といった問題を厳しく指摘したのも国会事故調だった。
なぜ、私がそんなポジションにいたのか不思議に思われるだろう。実は以前から取材で面識のあった国会事故調の黒川清委員長(以下、当時の肩書)から電話があり「キミは毎日新聞とロイター通信の内外2つのメディアでの取材経験があり、今はフリーランスジャーナリストの立場だ。この調査には日本のみならず世界中が関心を持っており、情報発信が重要だ。記者クラブ制度の狭い枠組みを離れて大胆にやりたい。協力してもらえるか」という依頼だった。私が「意気に感ずです。お引き受けします」と答えたのは言うまでもない。
黒川委員長の指摘どおり、私は毎日新聞で経済部を中心に約20年間、過ごし、45歳の時に毎日新聞を退社してロイター通信に転職し約15年、60歳過ぎからはフリーランスの経済ジャーナリストに転じ、77歳の今もその仕事を続けている。一方でフリーランスでの仕事中に、メディアで培った人脈ネットワークや経済部記者経験、それに問題意識が評価されたのか、アジア開発銀行からメディア向け情報発信でアドバイスしてほしい、との要請があった。そこで、最近の言葉でいう「両利きの経営」でいくことにした。その後、アジア開銀以外に日本政策金融公庫などいくつかでメディアコンサルティングにかかわった。
さて、ここからが本題だ。私は、世界中を震撼させた巨大事故なので、メディアが記者クラブ制度の枠組みを離れて各社ごとに原発事故取材特別専門チームをつくり、その一環で国会事故調などを取材ターゲットするのだろうな、と期待した。外国メディアも同じ対応だと考え、情報発信の仕方にも工夫が必要だ、と思った。
原発にからむキーパーソンの参考人聴取をすべてオープンにすれば、記者クラブ制度とは無関係に、メディアの独自の総合判断でニュースにして内外に向けて情報発信していくだろう、と私は判断した。そして国会事故調は、原発政策にかかわった政治家や経済産業省、資源エネルギー庁幹部、原子力委員会OB、東電幹部などの参考人聴取をすべて公開、かつ同時通訳を入れて即時に内外に情報発信できるような環境づくりで臨んだ。
ところが、国会事故調問題の取材に関しては、各社とも旧態依然の横並びで、政治部の国会担当がカバーすることになった。それも原発事故をめぐる専門的な知識、問題意識の希薄な政治部の若い記者ばかり。取材を受けても、「何かありませんか」のご用聞き取材の域を出ず、問題の本質が何かをしっかりとおさえて書けるのかなと不安になるほどだった。
黒川委員長もこのメディアの取材姿勢にいら立ちを隠せず、公開の参考人聴取後の記者会見でメディアへの不満を口にした。「参考人の考えに対する私の意見を聞くよりも、メディアが参考人聴取で明らかになった日本の構造問題を浮き彫りにし、独自取材で、その構造問題をさらに明らかにすればいい。その結果、検察が動くことになるかもしれない。それこそがメディアの役割でないのか」と。
その黒川委員長は私に対しても不満をぶつけた。「規制の虜の問題は、メディアにも当てはまるな。本来ならばメディアは権力に対する監視機構なのに、その気概が感じられない。記者クラブは役所の広報機関、そこに属する記者、ジャーナリストは政府を代弁する御用記者になってしまっているのでないか。今回の原発事故は、そういった目線で対応すべきだ。オレが間違っているか?」と。
私も、同じ思いだった。政府事故調が非公開・秘密主義なのに比べ、参考人聴取をオープンにする国会事故調はメディアにとって格好の取材チャンスなのに活かしきっていない。私の不満が募り現場記者にとどまらずKOL(KEY OPINION LEADER)の編集委員・論説委員クラスにも働きかけたが、なぜか反応は鈍く、正直、がっかりだった。私がさらにメディアの現場に不満だったのは、フォローアップ取材力の弱さだった。国会事故調報告をもとに検証という形で取材・報道が出来たうえに、世界各国から「真相を聞きたい」という声に対応して黒川委員長が講演行脚などを行った際、同行して世界各国の原発事故への受け止め方を報道すればいいのにと思った。しかし、これらの点に関して、どのメディアも希薄だったのはさらに残念だった。
国会の対応もお粗末だった。国会事故調の報告書が衆参両院議長に提出された後、「立法府が行政府を監視する」と豪語?していた国会は、衆参両院に本来ならば超党派の特別委員会を立ち上げて、今後の再発防止策にとどまらず国の原発政策、エネルギー政策をどうするかを徹底議論するべきなのに、いっさいアクションを起さず、形だけの特別委員会を組織したのはずっと後だった。当初の驚きは、行政府に対して丸投げしてしまったことだ。
国会事故調は事故調査報告に付随した提言で、1)規制当局への国会の監視、2)政府の危機管理体制の見直し、3)電気事業者の監視などに加え、国会に新たに独立の調査委員会の設置、端的には原子力事業者や行政から独立した民間中心の専門家からなる第3者機関として原子力臨時調査員会を設置すべきだ、と主張した。
にもかかわらず、国会は、調査報告書を受け取った瞬間に、すべてが終わったような処理対応で、これら提言に対してアクションを起さなかった。それどころか、すでに申し上げたように、行政府への報告書対応の丸投げだったため、政府側は政府事故調の報告書、それに国会事故調の報告書の2つを抱え込み、対応に苦慮する始末だった。メディアがこれらの国会の対応を厳しく批判キャンペーンもしなかったのも驚きだった。
原発事故から10年がたった今、原発問題にはまだまだ課題山積なのに、国会もメディアもまだまだ踏み込めていないのは、私の苛立ちだ。
(牧野 義司)
2021年4月2日
ラグビー日本代表・キャップ第1号、名フルバックだった寺村誠一さん


まず、次の写真を見て下さい。
「サンデー毎日」1930(昭和5)年11月2日号の表紙である。写真説明に、パント・キック【ラグビー遠征軍選手、寺村本社員】とある。
91年前の1930(昭和5)年、ラグビーの日本代表が初の海外遠征を実施した。その代表選手に東大法学部を卒業、28(昭和3)年に入社したFB寺本誠一さんが選ばれたのである。
もうひとり毎日新聞からFW岩下秀三郎さん(慶應義塾大学ラグビー部OB、30年入社)。2人は試合が終わると、原稿を書いて打電した。
その第一報は、1930(昭和5)年9月3日付「東京日日新聞」にある。
第1戦は、後半に逆転勝ちだった。「在留邦人も肩身が広くなったとで、その喜びはこの上もない」。カナダチームについては「背の高いことは勿論、体重が平均25貫以上(約94kg)、その上足が早いが、こちらが確実なタックルさえすれば、そう恐るべきものではないとの確信を得た」と書いている。
終了後のレセプション。見出しに「番香坡で歓迎攻め/賞揚(しょうよう)されたスポーツマンシップ」。クレジットは「ヴァンクーヴァ―発」だ。
初の海外遠征をした日本代表(香山蕃監督)の戦績は、6勝1引分けだった。10月15日、横浜港に帰国し、翌16日には神宮競技場で紅白試合、19日には花園ラグビー場で関西選抜と歓迎試合が組まれていた。花園には6000人の観客が詰めかけた、とある。
凱旋したラグビー日本代表。「サンデー毎日」の表紙を飾ったFB寺村誠一選手は、W杯で活躍したFB五郎丸歩選手並みの人気だったのか。
遠征中の成績は——。
① 9月1日 ○ 22-18 対バンクーバー選抜
② 6日 ○ 22-17 対バンクーバー選抜
③ 10日 ○ 27-0 対メラロマ(バンクーバーのチーム)
④ 17日 ○ 16-14 対ビクトリア選抜
⑤ 20日 ○ 19-6 対ビクトリア選抜
⑥ 24日 △ 3-3 対ブリティッシュコロンビア州代表
⑦ 27日 ○ 25-3 対ブリティッシュコロンビア大
日本代表選手の栄誉をたたえる「キャップ制度」は、1982(昭和57)年から始まったが、カナダ遠征の第6戦に出場した15+1の16人が、キャップ第1号の栄誉を与えられた。
この試合、開始早々、⑪鳥羽善次郎(明大、のち東京鉄道局)がタックルの際、肩を脱臼して退場した。負傷交代は認められていない時代。カナダチームが選手を1人外したのに気づいた香山監督が15人に戻すよう申し入れたがカナダは聞き入れず、結局日本が鈴木秀丸を(法大)を補充。出場選手が15+1の16人になったのだ。
その経緯は、この試合に出場した毎日新聞の2人の記者が速報した。試合は双方1トライずつだったが、日本代表の貴重なトライは、のちに毎日新聞のラグビー記者となる快足ウイング⑭北野孟郎(慶大)があげたという。当時トライは3点、だったのだ。
ついでにトリビアをひとつ。寺村選手のジャージーの背番号は「1」だった。今なら「15」だが、当時、背番号はFBから始まっていたという。背番号「1」のジャージーは、日本ラグビーフットボール協会に保管されている。
◇
この毎友会HP「元気で~す」で佐々木宏人さん(79歳)の連載「ある新聞記者の歩み」第9回にある、寺村荘治さん(63入社)の父親「戦前のベルリン特派員寺村」は、上記の寺村誠一さんである。

寺村誠一さんは東大法学部を卒業して1928(昭和3)年入社。ベルリンには1938(昭和13)年から3年間駐在、41(昭和16)年に帰国した、と書き残している。
戦後、東京本社資料部長を3年ほど。日本新聞協会発行の「新聞研究」に「新聞切抜の実際」を書いた。「切抜きのぎっしり詰まったケースは日毎成長する生きた百科辞典ということができよう」と、切抜記事の重要性を説いている。
その後、東京本社欧米部長、大阪本社外信部長、論説副主幹を歴任した。『暗号名イントレピッド—第二次世界大戦の陰の主役』など早川書房から何冊も翻訳本を出版している。
2003年8月23日逝去。カナダ遠征チームで最長寿の97歳だった。
キャップ第1号の同僚、岩下秀三郎(のち毎日広告社社長)は1987年12月27日逝去、83歳。北野孟郎(元運動部デスク)は1969年6月28日逝去、57歳だった。
(堤 哲)
2021年4月1日
「子ども大学」に託した一教育記者、矢倉久泰さんの夢
1日発行の季刊同人誌『人生八聲』26巻から転載

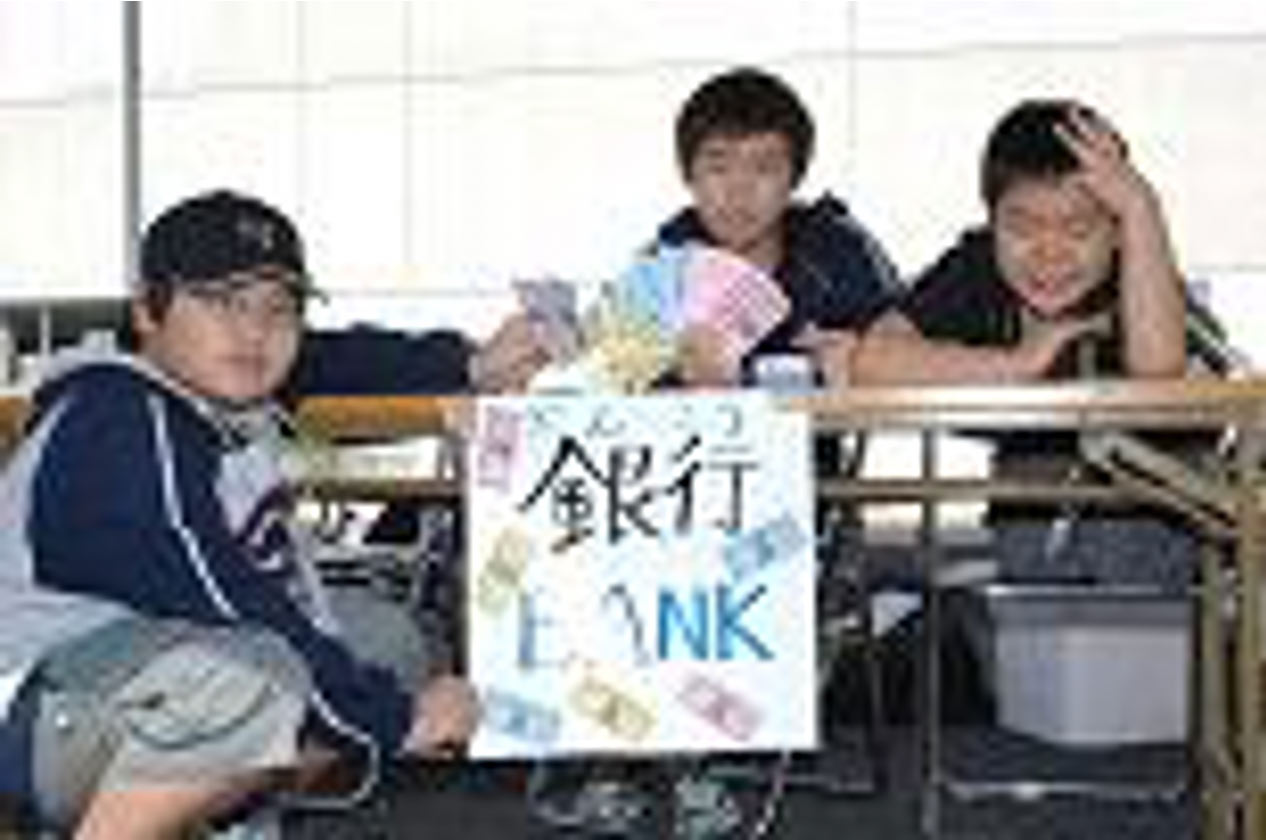

飛行機はなぜ空を飛べるのか、あんな重い物体が地上に落ちてこないのはなぜなのだろう。そんな子どもたちの素朴な疑問に答えながら、学ぶことの本当の楽しさを味わう場としてつくられたのが「こども大学」である。立ち上げ人の一人が、毎日新聞の教育記者だった矢倉久泰さんである。
子どもは人間として成長する過程で、自然や社会についてさまざまな根源的な疑問を抱くが、現在の日本の教育は知識のつめこみ偏重になっているので、「学び」の原点を大切にしたいというのが彼の願いだった。二〇〇八年末に「子ども大学かわごえ」が埼玉県川越市に設立された。
この構想を矢倉さんに持ちかけた元商社マンの酒井一郎さんによると、子ども大学の発祥の地はドイツである。ドイツでも子どもの学力低下への危機感から、教育改革への取り組みがなされるようになった。そのなかから、各地の大学を拠点に、大学の教員たちがそれぞれの専門研究分野に基づき高等教育のレベルの質を維持しつつ、子どもたちの知的好奇心にこたえ、かれらの探究心を養っていく構想がまとまっていく。
二〇〇二年にチュービンゲン大学で子ども大学の第一号が誕生した。最初の講義は「なぜ恐竜は滅びたか?」。大きな反響を呼び、その後、同国の諸都市を中心にスイス、オーストリアを含め一〇〇近い子ども大学が開かれているという。
酒井さんはドイツでのビジネスの第一線をし退いたあと、日本でも従来の教育では満たされなかった教育ニーズに応えるべく、ドイツのような試みに挑戦してみようと思い立った。日本の教育をよく知る矢倉さんと協力して、日本独自のモデルの構築に知恵をしぼり、川越の大学、行政、企業、市民、父兄などの協力を得て、日本初の「市民立大学」を誕生させた。
カリキュラムは「はてな学」、「生き方学」、「ふるさと学」。地元の東京国際大学、東洋大学、尚美学園大学の教員のほかに外部の専門家たちを講師に、「なぜ飛行機は空を飛べるのか?」「なぜいのちを奪ってはいけないのか?」「『はやぶさ』と子どもたち」「原子力発電について考える」など、魅力的な講義が小学生の「学生」を相手に開講した。テレビをはじめ新聞、雑誌で引っ張りだこ凧のジャーナリスト池上彰さんも、客員教授を引き受けてくれた。彼の抜群のニュース解説力は、NHKの人気番組「週刊こどもニュース」でのお父さん役で磨き上げられたもので、池上さんは新大学の趣旨をよく理解してくれ、超多忙のスケジュールの合間をぬって、年1回の講義を続けた。
私も一度、矢倉さんの推薦により講義をした。「『平和』ってなんだろう? ノーベル平和賞受賞者たちのしごと」というタイトルで、一〇〇名ほどの小学4~6年生と父兄を前に話をした。東日本大震災の翌年二〇一二年のことだ。私は当時、千葉市幕張の神田外語大学で教員をしていたが、大学生レベルのことを小学生にわかりやすく話すのは容易ではなく、いささか緊張した。
まず、「『平和』という言葉を聞いて、どんなことを考える?」と質問すると、男の子と女の子が三、四人元気よく手をあげた。「毎日、おいしいものを食べられること」「朝起きてから普通の生活が送れること」「家族や友だちと仲良く暮らせること」という答えが返ってきた。たまたまだろうけど、「戦争のないこと」と答えたのは四人目の男の子だった。
この反応には、やや意外な感じがした。というのは、大学生からは、平和=戦争のない世界という答えがまず返ってきて、それを受けて、現在の世界では平和とはもっと広い意味で理解されているのだという説明として、ノーベル平和賞受賞者の業績が軍縮や安全保障だけでなく、人権、民主化、環境、貧困などの問題解決への貢献を対象としている事実に言及することが多いからだ。
でも子どもたちが真っ先にこのように答えたのは、「3・11」の衝撃の大きさによるのかもしれないと思いつつ、たとえばおいしいものを食べられるには何が必要かを子どもたちと一緒に考えていく。そこで、環境保護活動で〇四年のノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんの新聞記事のコピーを読んでもらう。
地球環境が破壊されてしまったらおいしい食べ物を作ることはできない、そこでマータイさんが世界中の人びとに広めようとしたのが日本語の「もったいない」だと書かれていることを知ると、子どもたちは感動した表情になる。日本語が世界語になることを通じて、自分たちの身の回りの平和と世界の平和がつながっていることが発見できたのだ。
戦争と平和についても、新聞記事を教材にした。〇三年三月にイラクに対する米英の侵攻が迫っていたころ、世界の六〇カ国で、一〇〇〇万人の人びとが同じ日に「戦争反対!」の行動に立ちあがったというニュースだ。その一〇〇〇万人のなかの一人である、米国の一三歳の少女シャルロット・アルデブロンさんが地元の集会で行った反戦スピーチの記事も添付した。スピーチは日本語など9カ国語に訳されてインターネットで紹介され、彼女のもとに三〇〇〇通の反響メールが届いた。
新聞記事は小学生にはやや難しいのではないかと思われたが、小、中学校で教科書に新聞記事が載るようになったので、あえて教材にしてみた。講義後にかわいらしい文字で書かれた「学生」たちの感想文を読ませてもらった。ややわかりにくかった点はあるものの、みんながかなりきちんと私の話を理解してくれたようだということがわかり、ホッとした。
子どもたちがとくに感動したのは、自分たちとほとんど年齢の違わない米国の少女の勇気あるスピーチ、マータイさんの「もったいない」運動。そして、日本の憲法が「戦争の放棄」とともに、世界中の人びとが私たちとおなじ「平和」な暮らしをしていけることをめざした「平和憲法」なのだということも学べたようだ。
「今、『なぜ』と思うものはありますか」という感想文の最後の項目に、何人かがこう書いていた。「なぜ人は戦争をするのかを知りたい」。それとともに、次のような感想もいくつかあった。「平和は簡単にはつくれるものではないけれど、平和な世界をつくるための心を(一人一人が)持つことが、一番大切だと感じました」
もう一〇年まえの貴重な体験がいまとてもなつかしく思い出されるのは、「3・11」から一〇周年を迎えたからだけでなく、それ以前の昨年一一月に矢倉さんが鬼籍に入られてしまったからである。
矢倉さんとの最初の出会いは、文部省担当だったこの先輩記者の応援に、同じ社会部記者だった私が行かされたときである。どんな仕事をしたのかはまったく記憶にないが、ロクに役に立たなかったことだけは間違いない。その後、矢倉さんは教育記者として活躍し、私は外信部に移って国際ニュースを追うことになったが、付き合いは続いた。東京神楽坂の「みちくさ横丁」の行きつけの居酒屋、「小江戸」と称され旧い街並みが魅力的な川越市でふらりと立ち寄った一杯飲み屋で、美味しい酒を飲みながら談論風発した。
アルピニストで毎年の年賀状には前年の山歩きの元気な写真が添えられていたが、昨年から持病が悪化してついに帰らぬ人となった。病院に見舞いに行きたくても、コロナ禍でそれもかなわなかった。
「子ども大学」は川越に続いて鎌倉にも開学し、同市出身の解剖学者、養老孟司」東」・大名誉教授が学長を引き受けてくれたと嬉しそうに報告してくれた、矢倉さんの笑顔を忘れない。でも私が彼との思い出のなかで一番大切にしたいのは、やはり川越での講義であろう。
故人の真新しい墓石には、「矢倉家の墓」ではなく、「平和」の二文字が刻まれている。なぜ一教育記者がそこまで平和にこだわったのか、平和とは何かについてもっと話し合いたかったが、その機会は失われてしまった。合掌。
(永井 浩)
◇
季刊同人誌『人生八聲』春季号(第26巻)は4月1日に発行されました。テーマと著者を紹介します。大半が毎日新聞OBです。お読みになりたい方は、高尾義彦まで、以下のメールアドレスでご連絡ください。送料込みで1部1,000円。yytakao@nifty.com
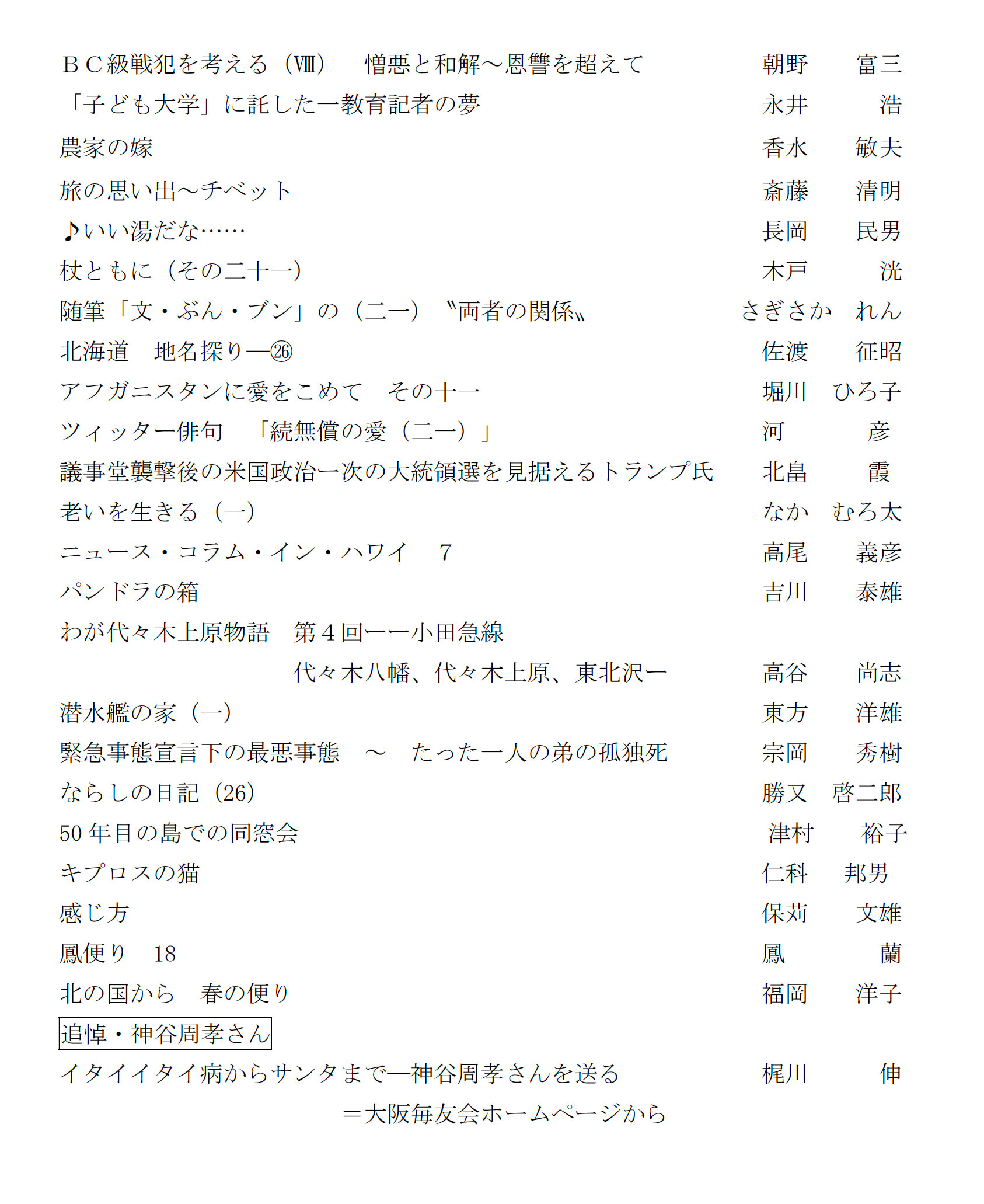
2021年3月22日
警視庁キャップ健ちゃんが訴えた「12の訓戒」
社会部旧友・中島健一郎さん(76歳)がFacebookに、自身のメモを公開した。1985(昭和60)年8月1日に警視庁キャップになった時、クラブ員に話したものだ。
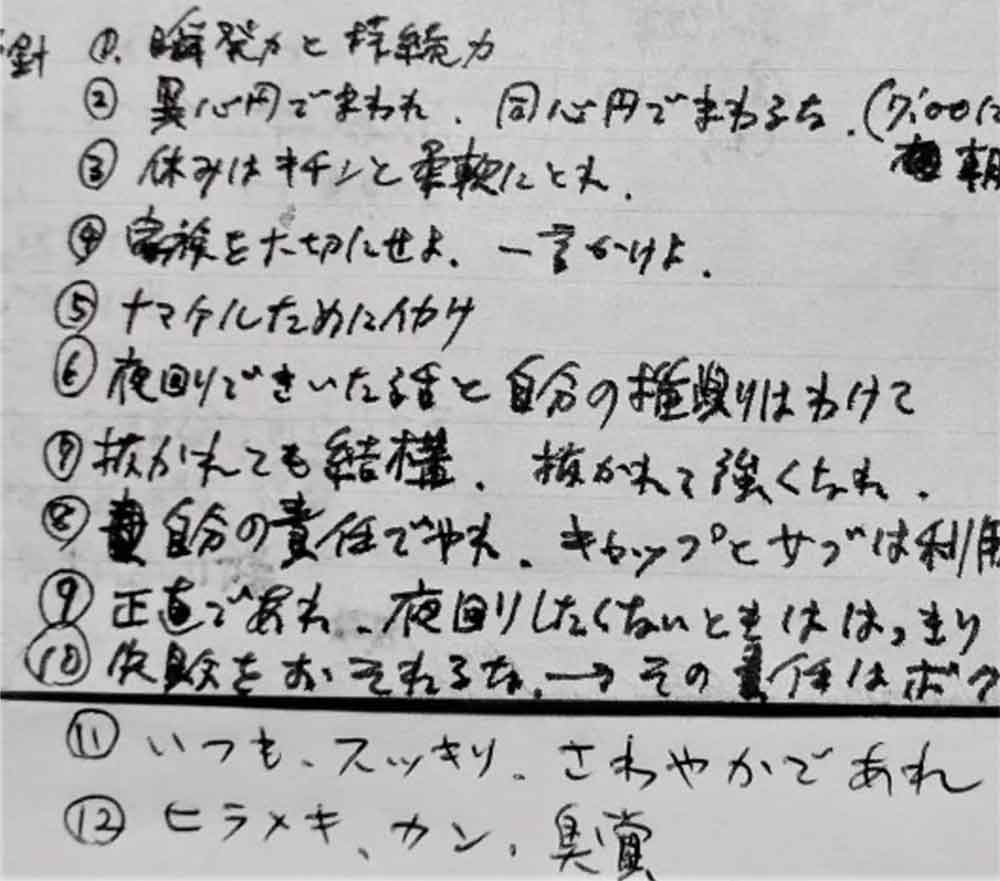
②の「異心円で回れ」は、他の記者と同じように取材して駄目という意味。⑤の「怠けるために働け」は、先手を打って特ダネを書けば、しばらくは怠けていても許されるという秘訣だそうだ。
その時のメンバーは——。サブキャップ取違孝昭(元東日印刷社長)▽捜査一・三課担当恩田重男、広瀬金四郎(故人)、齊藤善也(毎日新聞大阪本社代表)▽捜査二・四課担当武田芳明(東日印刷社長)、丸山昌宏(毎日新聞社長)、原敏郎(パレスサイドビルなどを管理する毎日ビルディング社長)▽警備・公安担当森戸幸生(元スポーツニッポン新聞社長)▽防犯・交通担当中村静雄(船橋市議、元同市議会議長)。
《僕はその年の4月にワシントン特派員から帰国し、宮内庁を担当した後、警視庁キャップになりました。3年間の警視庁時代にサブは取違、警察庁担当から横滑りの常田照雄(元専務)、森戸と3人。1課担当は藤本敏朗、小川一、防犯・交通担当も一瀬博明、平沢忠明と引き継がれました》
《キャップになって直ぐロサンゼルスで起きた銃殺、傷害事件で三浦和義が疑われた「ロス疑惑」の取材に追われました。また8月12日にはグリコ森永事件の犯人からの「くいもんの会社 いびるの もお やめや」という終息宣言でバタバタしていたら夕刻に日航ジャンボ機墜落事件でクラブメンバーを8人現場や日本航空に取材に行かせる修羅場となりました 。とても「怠けるために働け」どころではなかったです》
キャップ中島健一郎(68年入社)、いや健ちゃんは、伝説の特ダネ記者である。長野支局時代の連合赤軍「あさま山荘」事件。犯人逮捕、人質の山荘管理人の妻泰子さんが救出され、軽井沢病院に収容された。精神科医や警察が泰子さんに事情聴取している一部始終を報じたのが健ちゃんだった。
《病院の前は各社の記者・カメラマンでごった返していた。1人裏手に回ったら、病室でのやりとりが聞こえた。機動隊が警備していたが、窓際にへばりついてメモをとった》
「異心円で回れ」の典型である。
警視庁捜査一課担当時代も特ダネを連発した。私(堤)は防犯・交通担当として警視庁クラブに一緒にいたので、よく憶えている。警視庁キャップ内藤国夫(1999年没62歳)、サブ澤畠毅(2021年没81歳)の時代である。
健ちゃんは、その後ロッキード事件の取材班に加わり、警視庁二課担OBの板垣雅夫さん(65入社)と「中板コンビ」で発掘取材、特ダネを連発した。その活躍ぶりは『毎日新聞ロッキード取材全行動』(講談社1977年刊)に詳しい。

写真は、英会話の先生を囲んでの記念撮影である。警視庁クラブで毎週土曜日に英会話教室を開いていたというのだ。前列左から丸山昌宏、中島キャップ、ドーリーン先生、原敏郎。後列左から武田芳明、平沢忠明、森戸幸生、吉田弘之(アジア調査会専務理事・事務局長)、恩田重男、小川一(前毎日新聞取締役)、齊藤善也。
《ナゼ事件記者が英会話かというと、事件の国際化もありますが、英語を学ぶくらいのゆとりがあるべきとの思いからでした。それにワシントン特派員の時に「もっと語学力があったらなー」と臍を噛んだから。七社会では東京新聞がマネして英語教室を始めましたね》
《先生のドーリーン·バーデンさんはアメリカ大使館に紹介してもらいました。会話レッスンでは事件が話題になることが多く、ドーリーンさんは「日本が良く分かる」と喜んでいました》
もう1枚。

前列左から安藤隆春広報課長(のち警察庁長官)、三木賢治(警察庁担当)、小川一、中島健一郎、常田照雄。後列左から2番目から一瀬博明(故人)、吉田弘之、齊藤善也、川口裕之(現監査役)恩田重男、?、原敏郎、山本隆行
《この野球の写真は七社会の対抗戦の時です。共同通信が優勝し、毎日新聞は準優勝でした》
あれから36年——。現在の佐々木洋警視庁キャップ(2000年入社)は、健ちゃんの32年後輩で、警視庁キャップは19代あとである。
(堤 哲)
2021年3月22日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その10(後編)
この連載は毎月14日に更新されます。写真が多いので、抜粋を掲載します。
その10 私の駒込名所図会(1)駒込の植木屋と大名屋敷(後編)
文・写真 平嶋彰彦
『江戸切絵図』で、本郷通りを王子方面に向かうと、本郷追分を過ぎて、駒込の吉祥寺付近にたどりついたところで、ようやく緑色に彩色された田園風景が現われる。近世といっても幕末に近いが、駒込は江戸という都市空間の周縁であり、都市が田園と出会ういわゆる郊外だったことになる。
駒込の田園風景を特徴づけるのは「植木屋多シ」の書き込みで、よく見れば、植木屋が軒を連ねていたのは、吉祥寺から六義園までの本郷通り東側と、それより染井霊園にいたる染井通りの北側であることがわかる。
駒込の植木屋を考察した都市論の名作が川添登の『東京の原風景』である。
川添登によれば、江戸時代の260余年を通じて、鑑賞用の植物としての花卉や植木の栽培技術は急速の進歩をとげた。日本の緑と花の文化が欧米に与えた影響は、浮世絵などよりはるかに大きいものがあった。そうした鑑賞用植物を栽培する最大の供給地が、桜のソメイヨシノで知られている染井を中心に、団子坂、駒込、巣鴨などの周辺地域に大きくひろがっていた、というのである。
川添登は1926(昭和元)年生まれで、小学校1年まで駒込で育った。
ソメイヨシノの発祥の地である染井通りから、東にやや入った個所は、『花壇地錦抄』の著者伊藤伊兵衛の菩提所西福寺と染井稲荷とが並んで建っていることは『江戸切絵図』でもみられるが、この染井稲荷の横を東へ曲がると、すぐに急な坂となる。私の生まれた家は、その中腹の左側にあった。
文中に2カ所、方角を東とする記述があるが、これは誤りで、正しくは北または北北東。急な坂とあるのは、染井通りから染井銀座に抜ける染井坂をさすものとみられる。一家は関東大震災(1923年)の直後、染井坂の中腹にあった借家に引っ越してきたのだが、そこの大家が伊藤つつじ園の持主だった。裏木戸を開けるとつつじ園があり、あらゆる種類のツツジやサツキが植えられ、そこに自由に入って遊んだ、というのである。同書に明確な言及がないが、伊藤つつじ園の持主は、もとは藤堂家下屋敷の植木職人で、のちに江戸一番の植木屋とうたわれた伊藤伊兵衛家の系譜に連なる人物であったとみられる。
江戸時代には、染井の植木屋はどこも花園を持っていて、その一帯は市中からの遊覧客でにぎわう江戸名所の1つとなり、浮世絵にも取り上げられた。しかし、明治時代に入ると経営が苦しくなり、昭和の初めごろには、貸家に切り替えるところが少なくなかった。それでも、大きな屋敷もそこここにあり、そのなかには植木屋の庭園もあったという。
染井坂通りに「門と蔵のある公園」がある。植木屋を営んでいた丹羽家の跡地を整備した公園である。門は染井通りにあった藤堂家の腕木門を移築したもの。蔵は1936(昭和11)年築で鉄筋コンクリート造りの珍しいものである。周りには歴史を感じさせる大きな邸宅があり、染井稲荷からも遠くない距離にあることから、もしかすると、川添登の記憶に残っていたのは、この丹羽家の庭園のことであったかもしれない。

川添登が回想する失われた駒込(染井)の風景を、もう少したどってみよう。
その頃、坂の下は水田が続いていたとのことであるが、すでに民家で埋まっており、とくに坂のすぐ下は、長屋が建ちならび、バラックと呼ばれ、その子供たちとあそんではいけないよ、と母にいわれていた。また染井通りの西側は、藤堂家をはじめとする武家屋敷のあったところで、高級住宅街になっていた。いずれもコンクリートの高い塀をめぐらし、大きな屋敷や本ものの西洋館が建ちならび、昼間でも人通りがなく、人さらいが出るから染井通りから先に行ってはいけない、といわれた。つまり、親から許されていた行動範囲は、染井通から坂(傾斜地)までの間、ということになる。

坂とは、染井坂通りのこと。そのころは、坂の下の低地を西から東へ、谷戸川が流れていた。かつて水田として開かれたその沿岸は宅地化され、長屋が建ちならんでいた。それをバラックと呼んでいたとある。バラックはその場しのぎの仮屋を意味する。この言葉が一般に使われだすのは、関東大震災の直後からである。
もしかして、駒込のバラックの居住者の多くは、関東大震災の罹災者だったのではないだろうか。川添の一家も大震災の直後に引っ越してきた。母親の言葉にある「あそこの子供たちとあそんではいけないよ」というのは、経済的および社会的な格差があったことを示唆する。それにたいして、坂の上の染井通りの南側(引用文中の西側は誤り、正しくは南)の高級住宅街というのは、先に述べた岩崎弥太郎墓地付近のことである。
そこは坂の下とは逆に、羨望の眼差しで見られていたのである。早いはなしが、坂の上も、坂の下も馴染みのうすい別世界だったのである。しかし、子どもたちが、親のいいつけをおとなしく聞いているわけがない。とうぜん越境をする。その冒険の輝かしい体験により、川添登は自分や自分の育った駒込(染井)の素顔を知ることになったのである。
『東京ラビリンス』展を終えて間もない12月10日、六義園(写真・下)を訪れた。40年以上も前になるが、渡り鳥が越冬する都内の名所というテーマで、この名園を撮影したことがある。時期は12月の初旬で、庭園のようすはほとんど忘れてしまったが、オナガガモやマガモが遊ぶ水辺の樹々が、秋色に染まり美しかったことだけは覚えていた。

問い合わせると、コロナ渦だが予約すれば入園できて、いまが紅葉の見どころだという。その日は前日から雨だったが、私が入園した直後に雨はやんだ。そのためか園内は人影がまばらで、鮮やかに色づいたモミジやカエデを贅沢な気分で眺めて廻ることができた。
帰宅してから画像を整理していると、モミジやカエデと一口でいっても、たくさんの種類が植えられていて、素人目にはどこがどう違うのか見分けのつかないことに気づいた。
そういえば、江戸一番の植木屋と評された伊藤伊兵衛政武は楓葉軒とも号している(註11)。伊藤伊兵衛といえばツツジが有名だが、モミジやカエデも得意にしていたのである。六義園で私が見たモミジやカエデの見事な植栽の背景には、駒込(染井)の植木職人が歴史的に培ってきた造園技術が受け継がれているにちがいない。
『新編武蔵風土記稿』に次のような逸話が載っている。
1727(享保12)年3月、将軍吉宗が伊藤伊兵衛政武の花壇植溜を観覧し、御用木として29種の草木を命じることがあった。その翌月、政武は江戸城に呼ばれ、御納戸役の松下専助から舶来の樹を示され、それについて問われると、即座に、自分はいままで見たことがないが、これは俗にいうところの深山楓によく似ているとこたえた。
そのあと、さらにやりとりがあり、政武はその樹を呈せよと命ぜられると、1本の深山楓を盆に移した苗木と、それとは別に深山楓の実のついた折枝をそえて献上した。すると9月になって、松下専助より将軍の内命とのことで、深山楓に舶来の楓樹を接木したものを下賜された。これはたいへん珍しいものだから、生育させその種を世上に広めよ、と仰せつけられたというのである。
上記の将軍吉宗は誤りで、観覧したのはその子の家重だという。『風土記稿』の記述がどこまで事実かはともかく、染井の植木屋が、樹木を採集したり栽培したりするだけでなく、品種改良まで試みていたことは間違いないように思われる。さらにいうなら、伊藤伊兵衛政武は植物の種類や栽培法をまとめた『増補地錦抄』『広益地錦抄』『地錦抄付録』を、先代にあたる三之丞もまた『花壇地錦抄』など、後世に名を残す書物を刊行している。伊藤家にかぎらず、染井の植木屋は、江戸時代の都市近郊における先駆的な農業技術者であるばかりでなく植物学者でもあったと考えられるのである。
明治時代になり江戸が東京に変わると、駒込は近代都市として再編されていくが、川添登が子どもだった昭和の初めごろまでは、まだまだそこかしこに田園風景が残っていた。『東京の原風景』のなかに、川添登が師とも仰ぐ今和次郎の『日本の民家』のなかから、下記の一節が引用されている。文中の「郊外」を駒込(染井)と言い直してみれば川添登のうちなるわが街への想いのたけが、よりいっそう明確に伝わってくる。
人の作ったものは美しい。神の作ったものはまた美しい。一方は都市で、一方は田園であるとするならば、郊外というものはこの二つの接触し合ったもの、とけ合ったものだから、郊外には二重の美しさが現われて、郊外に住家を営む人たちは幸福なわけなのだ。
今和次郎は建築学や民俗学の研究者で、考現学や生活学を提唱した先駆者であるが、関東大震災の直後、上野公園のバラック建築を写真で記録している。『日本の民家』をみればわかるように、スケッチがたいへん上手な人だが、カメラが一般に普及する以前から、フィールドワークの記録手段として、写真を取り入れていたのである。
今和次郎は、戦後間もないころになるが、早稲田の理工学部で教えるかたわら、学生写真部の部長を務めていたということである。情けないはなしだが、私は大学の写真部時代に、今和次郎の著作を読んだこともなければ、名前すら知らなかった。
関東大震災のときのバラック建築の写真をふくめ、今和次郎が残した膨大な記録資料は現在、工学院大学の図書館に所蔵されている。仕事でも何でもないのにもかかわらず、その資料の所在を捜し出し、工学院大学に移管する橋わたし、さらにその整理にいたるまで、尽力を惜しまなかったのが、「ときの忘れもの」を主宰する綿貫不二夫・令子夫妻であったことは、つい最近になって知った。
2021年3月22日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ「東京ラビリンス」のあとさき その10(前編)
この連載は毎月14日に更新されます。写真が多いので、抜粋を掲載します。
その10 私の駒込名所図会(1)駒込の植木屋と大名屋敷(前編)
文・写真 平嶋彰彦
「ときの忘れもの」は、JR駒込駅の南方およそ300メートル、本郷通りと不忍通りの上富士交差点をわたって左折し、1つ目の筋を右折した裏通りにある(写真・下)。上富士交差点の北西側はす向かいには六義園がある。ギャラリーの南側80メートルにみえるのが駒込富士神社の社叢である。
初めて訪れたのは、確か、2018年の秋だった。昨年秋の『平嶋彰彦写真展 — 東京ラビリンス』の打ち合わせのためである。それ以来、ギャラリーにはなんどか足を運ぶことになり、時間があるときはその周辺を歩いてまわることにした。

展覧会を開催中の11月18日、大学写真部時代の仲間との恒例の街歩きで、染井通りをはじめて歩いた。この通りは、六義園の角からまっすぐ北西方向にのびている。しかし、マンションが林立する街並みのようすから、近年に造られた道路と誤って思い込んでいた。このときの街歩きでも昭和の面影をのこすようなものは見あたらず、駒ゴルフガーデンにそびえるレバノン杉の大木と、その近くの「花咲か七軒町植木の里」と刻む石碑をアリバイ的に撮っただけだった。
1週間後の25日、染井通りをもう1度歩くことになった。20年来の友人である詩人の中村鐵太郎さんが『東京ラビリンス』展を観に来てくれた。そのときに、彼の住む1938(昭和13)年に作られた共同住宅を一度ご覧になってみませんか、と薦められたのである。
昭和の文化遺産ともいうべきその共同住宅は、染井通りから南に折れてJR巣鴨駅にぬける通りの途中、岩崎弥太郎墓地と三菱重工社宅の向かい側にあった。
施主は東京帝大機械科卒の技術者で、三井金属に入社し、同社ベルリン支店に10数年勤務した。帰国後に、自宅住居を兼ねた欧米人向けの共同住宅の建設を試みたのが、この鉄筋コンクリート3階建の共同住宅だということである。南側の隣家は、1933年築の1戸建て高級住宅で、こちらも鉄筋コンクリート2階建の見るからに立派な近代建築だった。
1878(明治11)年、岩崎弥太郎は六義園(大和郡山藩下屋敷)を払い下げた。六義園の西側に隣接していたのが藤堂家下屋敷(伊勢津藩)で、あとでわかったことだが、この共同住宅が建っているのはその屋敷地だった。1922(大正11)年、三菱財閥三代の岩崎久彌は、わが国最初の文化村ともいうべき高級住宅地「大和郷」を構想し、六義園周辺の大名屋敷跡を住宅地として整備し、これを分譲した。図書館もその文化村構想の一つで、2年後の1924年、東洋文庫(写真・下)を六義園近くに設立した。
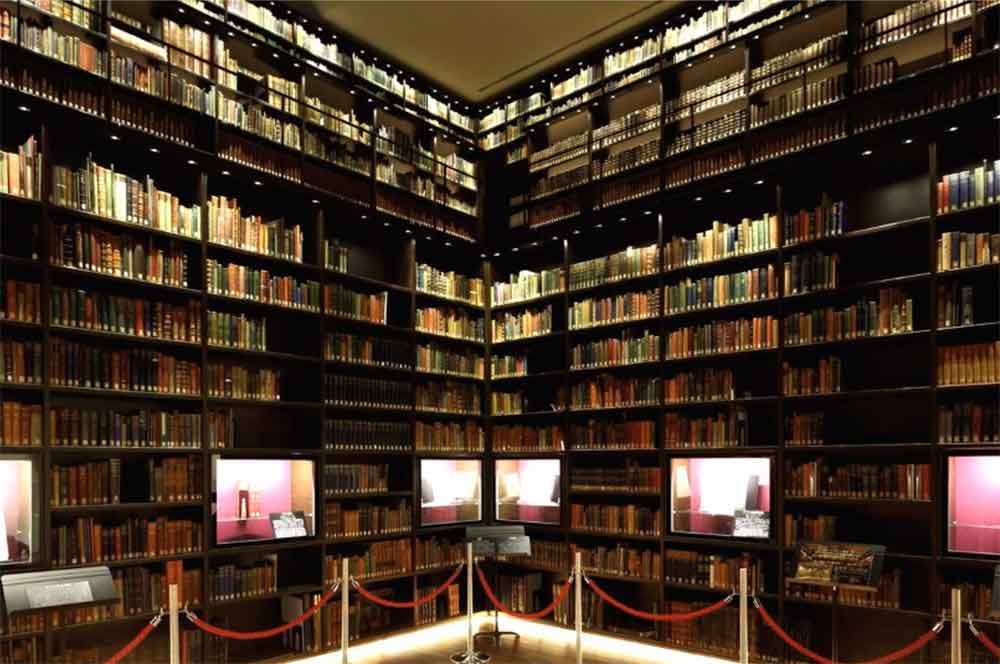
そんなことから、これまでうっかり見落としてきた染井通りがにわかに気になりだし、『江戸切絵図』「染井王子巣鴨辺絵図」(尾張屋版、嘉永7・1854年)にあたってみた。Googleマップで照らし合わせると、染井通りの道筋は江戸時代の後半とほとんど変わっていない。通りの南側ほぼ全域が藤堂和泉守の下屋敷になっていて、西側のつきあたりに建部内匠頭の下屋敷がある。ここは現在の染井霊園である。
それにたいして、通りの北側一帯は百姓地や自然地を示す緑色に彩色されている。こちらは通りの全体に樹木の図を配し、現在の駒込7丁目およびその東側の6丁目と3丁目には、それぞれ「此辺染井村植木屋多し」「同断」「同」と書き込んでいる。
そのなかに1カ所だけ町家(町並地)を示す灰色に土地区分されたところがある。先にのべた「花咲か七軒町植木の里」の石碑のたつ3丁目8番地のあたりで、そこには「駒込七軒町」と記し、「植木屋」と添書きしている。ということは、江戸時代にはこのあたりが染井村の中心地であったと想像される。
「花咲か」の石碑は、通りに面した小さな広場の門前に建っていた。よく見れば、新しいものである。なかに入ると、面積は広くないが、菜園風の趣に造られていて、水路やポンプ井戸があった。門には「私の庭みんなの庭」の表札がかかり、その下の案内板を読むと、この地域の人たちがボランティアで運営しているということである。
ところで、「ときの忘れもの」のある本駒込5丁目のあたりはそのころどんなようすだったのだろうか。『江戸切絵図』をみると、現在の六義園は「松平時之助」の下屋敷になる。時之助は大和郡山藩の藩主で、六義園を造った柳沢吉保の後胤である。本郷通り(本郷筋)の六義園前に「テンチウトイウ」の書き込みがある。通り沿いは灰色の色区分で「上駒込村百姓町家上富士前町」とあるから、町屋が並んでいたとみられるが、その奥は緑色の色区分で、「此辺テンチウ」「百姓地ウヘキヤ多シ」と記している。
「テンチウ」は「伝中」と書くのだという。5代将軍綱吉は、股肱の臣ともいうべき柳沢吉保が造ったこの庭園をたびたび訪れた。このときばかりはお伴の家来が屋敷の周りに数多く待機し、あたかも殿中のようだった。しかし、そのまま書くのは憚られるから、伝中とされた、ということである。
「ときの忘れもの」と駒込富士神社は、この絵図では範囲外になっている。このあたりが載るのは、おなじ『江戸切絵図』の「東都駒込辺図絵」である。
駒込富士神社はどこかというと、「駒込富士前町」の東側に鳥居と社殿の図を描き、「本郷真光寺」と記しているところがある。そこが駒込富士神社になる。真光寺はいまも本郷4丁目にある天台宗寺院で、明治の神仏分離までは、駒込富士神社の別当寺だった(註5)。
ときの忘れものがあるのは、その北側になるわけだが、このあたりは緑色の土地区分になっていて、「此辺富士ウラト云」「百姓地」「植木屋多シ」とされている。
1680(延宝8)年の『江戸方角安見図』「三十三・駒込一(本郷すし・ひがし方)」に富士神社がでてくる(註6)。この絵図では富士塚とその頂上に社殿を描いて「富士」と記し、その横にさらに「ふじ権現」とある。
神社の北側は、嘉永の頃とはちがって、「堀丹波守」の大名屋敷になっている。「ときの忘れもの」がいまある場所も、その広大な屋敷地のなかに含まれるとみられる。『江戸方角安見図』には、本郷通りの西側にはなにも記されていない。柳沢吉保が将軍綱吉から拝領した土地に7年がかりで六義園を完成させたのは、1702(元禄15)年である。それまでは富士権現のほか、このあたりに見るべきものがなかった、ということかもしれない。
2021年3月11日
クマノザクラでお花見を、と元大阪社会部の斎藤清明さん
クマノザクラを、故郷の古座川(和歌山県)流域で愛でてきましたので紹介します。


去年は3月中旬に行って少し遅かったので、今年は早目にと先週4~5日に出かけました。ちょうど満開になったところでした。
クマノザクラは、3年前に森林総合研究所(八王子市)が新種として日本植物分類学会誌に載せたものです。日本のサクラ属の野生種としては、1915年にオオシマザクラが発見・命名されて以来、百年余ぶりのこと。
わたしが少年のころから親しんできたのが、じつは新種だったのです。
ふつうのヤマザクラはいつも4月に咲くのに、古座川べりでは3月に咲くのもあって、「早咲きのヤマザクラ」と呼んでいました。それを近年になって森林総研が地元の県林業試験場の協力で調べると、ヤマザクラとは別種に分類できたのです。
春に帰郷するたびに山にいち早く咲いているのを見惚れてましたが、クマノザクラということになって、いっそう美しく、誇らしく思えてきます。
本州の最南端の清流に映え、濃い緑の山に散りばめられ、なんともいえない風情です。
英国の阿部菜穂子さん(「チェリー・イングラムー日本の桜を救ったイギリス人」=岩波書店=の著者)に知らせると喜んでくれ、フェイスブックで紹介してくれました。彼女が新人で京都支局に来た時以来のつき合いです。
(斎藤清明=元京都支局・大阪社会部)


2021年2月22日
「社会部」が大阪で生まれて120年
「大阪毎日新聞」(大毎、現毎日新聞)に1901(明治34)年2月25日、社会部が誕生した。20世紀最初の年である。ことし創部120年となる。
◇
「はじめて社会部の名称をウッ建てたのは、東西を通じてわが社が真っ先であった」
これは東京社会部の初代部長となった松内則信(冷洋)が「大毎50年」の本紙連載(1932年3月)に書いている。松内は社会部発足の前年、1900(明治33)年入社。東京の「萬朝報」からで、それまで東京・大阪の新聞社に「社会部」はなかったというのだ。
日本の新聞学の開拓者で、東大新聞研究所の初代所長・小野秀雄は、松内社会部長から誘われて「東京日日新聞」社会部員となる。
「東日」がもっぱら名論卓説をぶちあげる「木鐸記者」であったのに、事件があればとにかく現場に駆けつける「大毎」社会部記者。《「頭の記者よりも足の記者が尊い」といわれたのは、この時からである》(小野秀雄著『新聞五十年』)。
欧米の新聞社に「社会部」はない。日本独自のネーミングだが、《「社会部」が素直に定着していったところに、その後の日本の新聞を性格づける基礎があったといえるのではないだろうか。それは同時に反骨とか、野党的とか、反体制とかの精神が新聞活動の真骨頂であると認められることとも通じると思う》と、16代大毎社会部長、のちの編集主幹斎藤栄一が記している(『社会部記者 大毎社会部70年史』)。
「問題意識の視点から取組む」社会部の誕生は、近代ジャーナリズムの幕開けとなったのである。
「大毎」が追いつけ追い越せとライバル視していた「大阪朝日新聞」(大朝)が編集局に「社会係」を置くのが1904(明治37)年12月、と朝日新聞社史にある。東京の朝日新聞に「社会部長渋川柳次郎(玄耳)」が生まれるのが1910(明治43)年4月である。
◇

以下に現在までの大阪と東京の社会部長一覧を掲載する。
初代部長・菊池清30歳。文芸部主任からで、幽芳のペンネームで「己が罪」「乳姉妹」を連載。「家庭小説」の分野を開いた。「小説だけでなく、書も、歌も、菊づくりまで楽しむ趣味人だった」と部長紹介にある。
第2代角田勤一郎・浩々歌客は、慶應義塾創立50年(1907年)に先立ち、1904(明治37)年3月に制定した旧塾歌の作詞者。
第3代福良虎雄・竹亭は、東西の社会部長を務めている。他には第10代平川清風、第20代稲野治兵衛、第22代ヒゲの畑山博の計4人。
第6代奥村信太郎・不染と、東京の初代松内則信・冷洋は、日露戦争で従軍記者として活躍。2人は1905(明治38)年と翌06(明治39)年の2回、鉄道早回り競争の選手として最初は10日間でどれだけ乗れるか、翌年は5,000マイルを何日で踏破できるか競った。
鉄道が国有化される時期で、連日紙面で大々的に扱った。2人ともスター記者だった。
奥村は1920(大正9)年の大毎野球団結成にもかかわり、25(大正14)年のアメリカ遠征では総監督として、ホワイトハウスでカルビン・クーリッジ第30代大統領と面会している。遠征メンバーに野球殿堂入りが3人いた。キャプテン腰本寿、投手の小野三千麿、遊撃手の桐原真二である。
奥村はのちに社長となるが、戦後パージを受け、表舞台から消えた。
第9代阿部真之助。のちにNHKの会長になるが、社史『「毎日」の3世紀』には《反骨のペン貫いた》と、その業績に4ページも割いている。
東京の学芸部長時代、菊池寛、久米正雄、横光利一、吉屋信子、大宅壮一、高田保、木村毅らを社友・顧問として迎え、学芸面の充実を図った。
一覧表の阿部真之助の右側、東京社会部第4代島崎新太郎は、都市対抗野球大会をつくった。1925(大正14)年夏、明治神宮外苑に4万人が入る野球場を新設するので寄付の要請があった。「最高峰を行く野球大会を」と、当時の運動課長弓館小鰐(第1回早慶戦のときの早大マネジャー)と相談。大阪朝日新聞から大正日日新聞に移っていた橋戸頑鉄(第1回早慶戦のときの早大キャプテン)をスカウト、1927(昭和2)年に第1回大会を開いた。
第11代徳光伊助・衣城は、大阪北浜の料亭「花外楼」のボンボン。城戸元亮編集主幹にスカウトされ、聯合通信社(現在の共同通信)からいきなり社会部長となった。読売新聞社会部から「文章のうまい遊軍記者」としてスカウトしたのが、のちの読売新聞1面「編集手帳」の高木健夫だ。
「読者の目を射すような社会面づくりだった」と紹介されている。
高木は、徳光の俳句を紹介している。
外套を肩に新聞記者帰る
格好いいね、決まってる。
32(昭和7)年12月本山彦一社長が逝去、会長となった城戸が翌33(昭和8)年10月に会長職を追われるお家騒動があり、徳光とともに「聯合艦隊」と呼ばれた記者47人が一斉に辞めてしまった。高木も一緒だった。
第13代本田親男は、城戸時代に長崎通信部に飛ばされた。1930年の大風水害の原稿をローマ字で海底電信に載せ、長崎―上海―マニラ―小笠原―東京と渡って、惨状を伝えた。
49歳で社長となったが、「本田天皇」と呼ばれ、社長時代の評判は必ずしもよくない。
第14代の大阪小林信司と東京村田忠一の在任中の1943(昭和18)年1月1日、題字を「毎日新聞」に一本化した。
大阪の第15代浅井良任と東京の第17代森正蔵から戦後だ。
森は45(昭和20)年12月に『旋風二十年』を刊行する。戦時中の昭和裏面史を嶌信正ら7人の記者が書いたもので、発売と同時に売り切れが続出、大ベストセラーとなった。
東京第25代三原信一。51歳での部長就任だった。《まず断行したのは「新旧交代」「信賞必罰」を旗印にした大幅な人事異動だった》《3年間で53人を入れ替え、54人目に三原さんが去ったときの社会部の平均年齢は32・1歳》。
1957年3月第5回菊池寛賞。社会面キャンペーン「白い手・黄色い手」「官僚にっぽん」。
10月第1回日本新聞協会賞。社会面キャンペーン「暴力新地図」「官僚にっぽん」「税金にっぽん」。
「50歳を超えて社会部長になったのは、三原さんに続いて2人目」と東京第34代牧内節男(95歳)。毎日新聞社会部編『毎日新聞ロッキード取材全行動』(講談社1977年刊)がすべてを物語っている。
東京第44代朝比奈豊。2008年社長、11年グループホールディングス社長。2020年にGH会長を退任するまで長期政権だった。
最後に2017年4月に女性として初の社会部長となった磯崎由美。ことしの日本新聞協会賞「にほんでいきる」外国籍の子どもたちの学ぶ権利を問うキャンペーン報道。社会部長の時からキャンペーン報道に噛み、編集局次長として毎日新聞の編集部門受賞、32回目を達成した。=敬称略
(堤 哲)
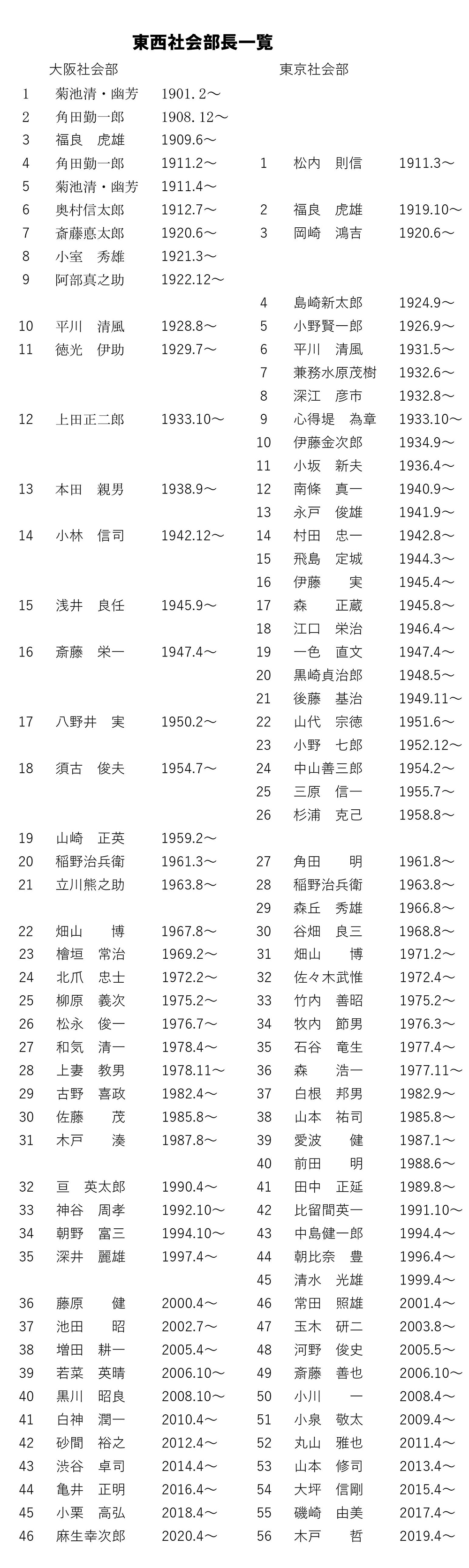
2021年2月19日
お天気キャスターの先駆け・倉嶋厚さんのこと
社会部の遊軍記者になって最初にやらされるのはお天気原稿だ。気象庁の天気相談所に電話して、気象概況を解説してもらい、夕刊早番から出稿する。遅くても午前10時半までにはデスクに渡さなければいけないので、結構シンドイ仕事だった。
ことし関東地方に「春一番」が吹いたのは、2月4日だった。これまで最も早かったのが1988(昭和63)年2月5日。過去の記録を更新したのだ。これも異常気象?
「春一番」は、お天気キャスター倉嶋厚さん(2017年没、93歳)が命名した、と社会部旧友・倉嶋康さん(88歳)がFacebookに書いている。
◇
[春一番] 2021年2月15日
「春一番」は私と年の近い叔父の倉嶋厚が気象庁で予報官をしていた時に命名しました。そのころ私は竹橋の気象庁のすぐ近くにある毎日新聞東京本社の社会部にいて、時々気象庁に遊びに行っては特ダネをつかんだり、叔父がパレスサイドビルに来て地下で一杯やったりしていました。
ある時大阪本社から同期の丹羽郁夫という記者が東京社会部に転勤してきました。私の一番の親友となりましたが、叔父の厚のことを知って私にこうこぼしました。
「大阪で気象台を担当していた時にオレは『大南風』って名付けて盛んに使った。でも『春一番』のソフトなタッチには負けてしまった」と。
自分が作った言葉が後世まで使われるってうれしいことです。え、私? そうだなあ、「ニア・ミス」を「異常接近」と訳したくらいかな。
◇
倉嶋さんは、気象庁主任予報官→札幌管区気象台予報課長→鹿児島地方気象台長を歴任し、1984年定年退職。そのあとNHKの気象キャスターとなる。

お天気をわかりやすい言葉で説明した。「熱帯夜」(最低気温が25度以上の日)は倉嶋さんの造語だ。
「雨一番」も。北海道など北国でその年初めての雪が混じらない雨を呼ぶそうだ。
「台風は大きなバケツ」「ゲリラ豪雨」「光の春」(ロシアでは光のちょっとした変化で春を感じる)。『やまない雨はない』(文藝春秋)はうつ病を克服した自身の体験記の題名だ。「日の差す方角ばかり探している人に、虹は見えない」という言葉もある。
いま人気の気象予報士・森田正光さんが偲んでいる。
《倉嶋さんは、よく「人文気象学」あるいは「風流気象学」といって、普通の人々の生活感覚や、季節感、自然感が大切だと、おっしゃっていました》
《倉嶋さんは、天気解説で大事なことは「おやまあ」「そうそう」「なるほど」の三つだといいます。「おやまあ」は、びっくりするような発見や出来事、そして「そうそう」というのは、今日は風が強くて困りましたね、というような共感、さらに「なるほど」というのは、視聴者の方がその説明を聞いて納得することだそうです》
《倉嶋さんが亡くなられた8月3日は、一年の中で一番暑い時期です。その暑さも楽しみながら、来年から私は8月3日を「熱帯夜忌」と呼ぶつもりです》
◇
丹羽郁夫さんは1970年没、40歳だった。
(堤 哲)
2021年2月17日
ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その9
この連載は毎月14日に更新されます。下記のURLで検索を。
http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/cat_50035506.html
その9 姨捨山のつたかづら
文・写真 平嶋彰彦
芭蕉の『更科紀行』は、1688(元禄元)年に中秋の名月を眺めるため、信濃国更級郡(長野県千曲市)の姨捨山を訪れたときの俳句と散文からなる小品である(註1)。
姨捨山という刺激的な山名が史料に初めて登場するのは、『古今和歌集』の「雑の部」に載る「題しらず読み人しらず」の歌である(註2)。
わが心なぐさめかねつ更級や姨捨山に照る月を見て
『古今集』より約50年後、この姨捨山の歌は『大和物語』でも取りあげられた(註3)。同書は作者不詳の歌物語で、歌の背景には次のような出来事があったと書かれている。
信濃国の更級に、若いときに母を亡くし、姨に育てられた男がいたが、男は妻にそそのかされ、いわれるままに、その姨を山奥に置き去りして帰った。おりしも中秋の名月で、男は月を眺めつつ、思い直して、いったんは捨てた姨を家に連れ戻した、というのである。
ほぼ同じ内容の話は『今昔物語集』にも載っていて、そこでは舞台となった姨捨山は、千曲市南東にそびえる冠着山(「冠山」)のことだとされている(ph1、註4)。

芭蕉が訪れた姨捨山は、『今昔物語集』のいう冠着山ではなく、それよりも4キロあまり北側にある姨捨山放光院長楽寺周辺の山麓であった(ph2、3)。『更科紀行』の本文には、その所在地がどこかについて言及がなにもないが、芭蕉による別稿の「更科姨捨月之弁」には、次のように書かれている(註5)。
山は八幡といふさとより一里ばかり南に、西南によこをりふして、冷(すさま)じう高くもあらず、かどかどしき岩なども見えず、只哀ふかき山のすがたなり。
「八幡」は現在の千曲市八幡のことで、武水別神社(旧八幡宮)を中心とした地域をさす(ph4)。姨捨山すなわち長楽寺はその南西約2キロにある。武水別神社付近からは「かどかどしき岩」は見えない。しかし、長楽寺境内には姨石と称する巨大な岩がある(註6)。


芭蕉は『更科紀行』の翌年、歳旦の句の1つに、こう詠んでいる(註7)
元日ハ田毎の日こそ恋しけれ
「田毎の日」が田毎の月を踏まえているのは、いうまでもない気がする。田毎の月とは、長楽寺門前に広がる四十八枚田と称する棚田の1枚1枚にうつる月をいう。四十八枚田は、阿弥陀の四十八願にちなんで、歌人の西行が名づけたといわれる(註8)。棚田の中央部には、宝永3(1706)年の銘をきざむ田毎観音が祀られている(ph5)。
現在、観光名所になっている姨捨棚田は、この四十八枚田より南側の傾斜地にある(ph6)。芭蕉の来訪から9年後になる1697(元禄10)年、聖高原の大池からの用水堰が建設され、それにともない、姨捨棚田の大規模な開発が進められたのだという(註9)。
それより86年後の1783(天明3)年、菅江真澄がこの地を訪れている。そのときに描いた「姨捨山の月見」をみると、たくさんの人が姨石の上に群がり、千曲川をはさんだ対岸の鏡台山からのぼる中秋の名月を眺めている(註10)。それよりもさらに70年ほど後になるが、歌川広重が『六十余州名所図会』の1枚として「信濃 更科田毎月鏡台山」を描いている。この図絵では、長楽寺の奥に峨々として姨石がそびえたち、門前の四十八枚田の1枚1枚に中秋の名月が描き込まれている(註11)
『更科紀行』の本文には、先に述べたように、姨捨山が更科のどこにあるかの言及がない。そればかりでなく、田毎の月の言い伝えとか、その夜の名月の具体的な描写はなに1つ記されていない。芭蕉がひたすら書き綴っているのは、中山道の途中で出会い、更科まで同行することになった「道心の僧」との意外とも不思議とも思われるやりとりである。
記述にしたがえば、中秋の名月のその夜、この僧は苦吟する芭蕉をみて、「旅懐の物憂さ」に落ち込んでいるのではないかと余計な心配をし、自分が若いときに廻った土地のことや阿弥陀如来の尊い功徳のこと、あるいは自分が不思議に思った体験などを話して聞かせ、気をもんでくれた。しかし、かえってそれが「風情のさはり」となり、芭蕉はただの一句もものにすることが出来なかった。
とかくしてとりまぎれ、気づかずにいたのだが、ふと目をやると、宿のかべの破れから木の間がくれに月影が差し込んでいて、耳をすますと、鳴子の音や、鹿笛の音があちらこちらから聞こえてきた、というのである。それに続けて、「まことにかなしき秋の心、爰に尽くせり」とは書いているのだが、だからといって、芭蕉はすぐに句作を再開したわけではない。
どうしたかというと、芭蕉は「いでや、月のあるじに酒振まはん」と口火をきり、宿の者にさかずきを出してもらい、この僧と酒を酌み交しはじめた、というのである。「あるじ」とは「あるじもうけ」のことだそうである(註12)。芭蕉が主人となり、お客として道心の僧を迎え、ご馳走をしたことになる。
酒を酌み交わしながら、あるいはその後で詠んだのが、次の3句である。
あの中に蒔絵書きたし宿の月
桟やいのちをからむつたかづら
桟や先ずおもいいづ馬むかえ
最初の句の「あの中」の「あの」とは、もちろん中秋の名月のことだが、道心の僧と酒を酌み交わしたさかずきには「木曽の桟(かけはし)」の蒔絵が描かれていた。そのさかずきはふつうのものよりひとまわり大きく、図柄も見るからに稚拙で、風情を欠いていた。都の人なら、手にもふれようとしないとも書いている。しかし、考えてみれば、そんな代物を中秋の名月の中に描きたいと思うはずがない。そうではなく、見かけは田舎じみて卑俗な表現であっても、うちに込められた尋常ではない心模様の気高さを発見したのである。
木曽の桟は、古代より中山道屈指の難所にかかる橋として名高かった。端(はし)とは、ものの発端であり、末端である。橋はこちらの岸とあちらの岸をかけわたす(註13)。それを飛躍させて、この世とあの世をかけわたす橋に重ねてみたのである。
次の句では「いのちをからむつたかづら」と詠んでいる。かけわたされるのは、この世からあの世に生まれ変わる人間の生命ということになる。
『古事記』によれば、ヤマトタケルは東国遠征から帰還の途中、伊勢国の能煩野(三重県亀山市から鈴鹿市にわたる地域)で横死した。その葬儀に詠われた挽歌のなかに野老蔓(ところづら)が出てくる(註14)。
なづきの田の稲幹(いながら)に 稲幹に 葡ひ廻ろふ 野老蔓(ところづら)
野老蔓は山芋の蔓草のことである。蔓草を生命に見立て、これをたぐり寄せる仕草をくりかえし、死者の魂を呼び戻そうとしたらしい。そうした古代の呪術儀礼がこの挽歌に詠み込まれているのではないか、ということである。(註15)。
「木曽の桟のつたかずら」のデザインは、近ごろは見かけなくなった布団を包む風呂敷に描かれた唐草模様や、イギリスの童話「ジャックと豆の木」の豆の木にも通じるように思われる。植物の蔓草が絡み合いながら、どこまでも天空に伸びていく姿に、私たちは生命の不思議さを感じずにいられない、ということではないだろうか。
3句目に「馬むかえ」とある。中古には信濃の望月の駒を朝廷に献上する習わしがあり、旧暦8月15日というから、中秋の名月の日になるが、左馬寮の使者が逢坂の関まで出向いて、その馬を迎えるのが恒例行事になっていたという(註16)。その故事を念頭に置いて詠んだわけだが、望月の駒とは反対に信濃へむかうこの旅で、芭蕉は徒歩ではなく、馬に乗っていた。それを信濃の国境のあたりで出迎えたのが、「道心の僧」ということになる。
世阿弥作の謡曲に『姨捨』がある。中秋の名月を見るため、ある男が京都からはるばる更科まで旅をするのだが、その男を出迎えたのは、ほかならぬ捨てられた姨その人の亡霊という設定になっている(註17)。この物語で生命の象徴として登場する植物は、姨が捨てられた場所に生い茂っていた桂の木であった。桂は中国では月の中にあるという想像上の樹で、転じて月のことだとされるという(註18)。世阿弥は『姨捨』の地謡で、次のように語らせている。
月はかの如来の右の脇侍として、有縁を殊に導き、重き罪を軽んずる、無上の力を得る故に、大勢至とは号すとか。
かの如来とは、いわずとしれた阿弥陀如来のことで、勢至菩薩と観音菩薩を脇侍にしたがえ、一光三尊の善光寺如来として長野の善光寺に祀られている。先にも書いたように、姨捨の四十八枚田は、阿弥陀如来の四十八願にちなんだもので、歌人の西行による命名だとする伝承がある。西行はもちろん作り話に違いない。広重の「信濃 更科田毎月鏡台山」も、現実にはありえない視覚である。四十八枚田の一枚一枚に中秋の名月がうつるのは虚構であるが、阿弥陀如来の尊い功徳を求める切ない願望であったとみられる。

かつての馬むかえに見立てられたこの僧は、年のころ60歳ばかりで、腰のたわむまで荷物を背負い、息をせわしくさせ、足どりも覚束ないようすであらわれた、と芭蕉は書いている。それを見た越人と権七という芭蕉の従者が気の毒に思い、この僧の荷物を自分たちのものと1つにからませ、つまり一蓮托生の形に結わえ、芭蕉の乗る馬に括りつけ、一緒に旅をすることにしたのである。
芭蕉はただの僧ではなく、わざわざ「道心の僧」と書いている。道心とは、仏道を修める心のこと、または13歳あるいは15歳から仏門に入った僧のことだというが、道心坊となると、物乞いをして歩く乞食僧のことだそうである。(註19)。だとすれば、腰がたわむまで背負った荷物はなにかを詮索するなら、町々や村々を廻って、手に入れたお布施の品々とみて、まず間違いない気がする。
この僧が芭蕉の句作を妨げたことは、すでに述べた。若いときから、旅をしながら各地を廻り、阿弥陀如来の尊さを説くとか、念仏を唱えるとかして、人々の極楽往生を祈願したのであり、芭蕉にたいしても同じように話をして聞かせたのである。
芭蕉は僧侶ではなかったが、身づくろいは僧の形にしていた。芭蕉が、自分は何者であるかを、自ら語る記述が『野ざらし紀行』のなかにある(註20)。
腰間に寸鐵をおびず。襟に一嚢をかけて、手に十八の珠を携ふ。僧に似て塵有。俗にゝて髪なし。我僧にあらずといへども、浮屠の属にたぐへて、神前に入事をゆるさず。
近世の60歳といえば、とっくに隠居していい年齢である。この「道心の僧」が、そのような高齢になってもなお、拝みに廻った家々から一紙半銭の施物を貰いうける勧進活動を続けたのは、それが唯一の生活手段になっていて、一所不住の旅をやめることは野ざらしになることを意味した、ということかもしれない。
俤や姨ひとりなく月のとも
いさよいもまださらしなの郡かな

ところで、こう詠んだ後、芭蕉一行はさらに足を延ばし、長野の善光寺を参詣している。『更科紀行』の目的は姨捨山の中秋の名月を眺めることだった。文脈からすれば、この「道心の僧」も善光寺まで同行したものと考えられる。そうだとすると、芭蕉の一行は、助けたつもりの乞食坊主に引かれて、図らずも、中秋の名月に身をもって阿弥陀如来の尊さを感得し、さらに引かれて善光寺参りをした、ということにならないだろうか。
「牛に引かれて善光寺参り」の諺がある。これは信心のない老婆が、干していた布を角に引っかけて走り去る牛を追いかけ、図らずも善光寺参りをしたとされる説話だが、本来の形は「牛に引かれて」ではなく「御師に引かれて」ということだそうである(註21)。
「道心」といえば、説経節の代表作の1つ『かるかや』が連想される(註22)。善光寺の門前に祀られる親子地蔵の由来をかたる唱導説話である。主人公の刈萱道心は筑前国苅萱の武士で、俗生活に無常を感じ、出家して高野聖となった。その子が石童丸で、父を慕って高野山に上るが、刈萱道心は親子の情愛が信仰の妨げとなると考え、高野山を後にして、信濃国へ向かい、善光寺のかたわらに身をよせ、高野聖から変じて善光寺聖となった。
史実の高野聖は、近世になると、非事吏などと書かれ賎しめられたり、「高野聖に宿かすな、娘とられて恥かくな」と悪口を言われたりしたというが、刈萱道心は高野聖の理想像であると同時に、善光寺聖の理想像でもあった。彼らは、善光寺の縁起と阿弥陀如来の霊験を語りながら、結縁の名号札を持って諸国を放浪したとも、村々に如来堂や太子堂を持って念仏講を主宰したとも、あるいは善光寺参りの御師や先達をつとめたともいわれる(註23)。
連載その7では書き漏らしたが、私の郷里の念仏講の経本には、つぎのような御詠歌が載っている。
⇒ 以下、長文になりますので、(註)も含め、URLでご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/cat_50035506.html
2021年2月15日
忘れられない若人たち<私の迎えた新人社員が続々定年>と新実慎八さん

コロナ騒ぎで外出自粛。そこで、ふだん“積読” (つんどく)状態の自宅の書斎を片付けようと、本を並べ替えていたところ、本に挟んであった一枚の写真が出てきました。ラフな格好をした100 人近い若い男女の集合写真でした。よく見ると前列中央に禿げ頭の私らしいのが、笑みを浮かべて写っていました。しばらく考えて、38 年前の1983 年4 月、毎日新聞社の新入社員研修で富士山の5 合目まで登った際、ふもとの合宿所前で記念に撮った写真であることを思い出しました。
研修が終わって、皆さんはそれぞれ全国の支局に赴任しました。この若人がその後一堂に会したことはないと思います。しかも今年までにみんな定年になったはず。再雇用で社に残って仕事を続けている人もいますが、当時の新入生がこのように揃ったのは二度とありません。まさに記念の写真でした。私は東京本社の編集局次長で新入社員研修の責任者でした。「校長先生」と呼ばれていました。各部のデスク(副部長)さんたちが先生として参加し、数人ずつのグループを受け持ってくれました。
この研修のあと、地方勤務の支局を決めて、一人ひとり通告しました。皆さんの受け取り方は様々でした。九州出身のK君は 「青森支局」と告げられて、「なんで南の国から本州の北のはずれ、東北の奥へ行くのですか」とむくれていました。慶応ボーイのO君は、北海道支社といわれて 「飛ばされた」としょげていました。私は地方勤務の意味を説明し「飛ばしたり」「追いやったり」するつもりはないことを理解してもらったと思っています。
K君は論説委員長として活躍し、定年後は専門編集委員として会社に残り、毎週コラムで健筆をふるっています。先日も国会冒頭の菅義偉首相について「物語性を欠く施政方針演説を聞き『もう無理かも』の6文字が頭から離れない」と辛辣でした。O君は中枢の要職、毎日新聞グループホールディングスの内部監査室長兼毎日新聞社社長室(局長職)の勤務を最後に定年退職しました。
研修のとき大阪出身の女性OさんはK君、O君と同じグループだったと思いますが、私たち先生連中は 「あっちゃん」「あっちゃん」と呼んで人気がありました。神戸支局からスタートして大阪本社管内で幅広く活躍し、経済部長、京都支局長、総合事業局長、大阪本社副代表と、いずれも女性として初めてのポストを連続して見事に勤務し、昨年選択定年で退職しました。あっちゃんが経済部長のとき、東西の経済部長会で時折上京してきました。私もパレスサイドビル (現毎日ビル)の経営に当たっていたので、会議後、両部長と食事しようといいながら、時間の調整ができず実現しなかったのは残念に思っています。
新人研修主任を終えて私は総務局長に就任し、新入社員採用の責任者として、84、85年度の採用試験に携わりました。このあと広告局長、中部本社代表となって6年間新人採用からは離れていましたが、名古屋から東京に帰ると、今度は労務・総務担当、続いて翌年には経理・総務を合わせて管理部門統括を命じられて、2年続けて採用業務に携わりました。
ですから前後合計5年度にわたる新人との「縁」があったことになります。この新人とのご縁の前半3年間の皆さんは、すでに定年を迎えたか、続々定年を迎えつつあり、あるいは「いよいよ迫ってきた」と感じている皆さんだと思います。
何事もないように、こんな言い方をしていますが、実は自分では、私が採用に当たった新人の定年を見届けるなんて、全く想像もしなかったことです。まして毎友会の仲間として歓迎し、また一緒に一杯飲めるなんて、びっくりです。うれしいことですが「爺さん、まだいたの」と言われるのが「落ち」でしょう。
私は採用する新人を決めるとき、すぐ戦カとして使える人よりも、毎日新聞社の20年後、30年後を託せる人物であり、広くジャーナリズムの発展に寄与してくれる人材を選んだつもりです。明治の初めのころから、志を同じくする人たちがともに全力を投入して新聞を発行し、輝かしいジャーナリズムを発展させてきた毎日新聞社を、さらに成長させてくれる人たちであると信じて、試験委員の皆さんと〝合格"の判断をしたのでした。
毎日新聞社が1977年に実質倒産し、新人を採用せず、新社を設立して再建を図っていることは、受験した皆さんは百も承知していました。他社に比べて賃金が安く、人員も少ない。「よくわかっています」とも言ってくれました。「でも、自由な雰囲気が好きです」「のびのびと働けると思いました」「本音では、もう少し給料がいいと…」。率直に話をしてくれました。そしてよく働いてくれました。採用に当たったものとして深く感謝しています。
面接試験に臨んだ皆さんの真剣な表情。研修を受けていたときの熱心さ。夜一日のスケジュールが終わって、一杯飲みながら懇親会をやった時のおおらかさ・楽しさ、40年近い昔なのに、覚えているものですね。
忘れられない一人の女性がいます。面接のとき、西武百貨店に勤務していて「歌舞伎」を書きたいから記者になりたい、というのです。いまでもはっきり記憶に残っています。「新聞社では自分の好きなことだけを書いているわけにはいきませんよ」「なんでもこなせる記者になる覚悟がなければ」。面接場は試験というよりたしなめるような雰囲気になりました。面接委員の判定は、「頑張り屋で熱意がありそうだ」「女性の歌舞伎記者が育つかも」と、採用が決定しました。彼女はいま、定年後専門編集委員として残り、歌舞伎を書き続けています。つい先日、中村勘三郎追善狂言の記事、読ませていただきました。
わが子を心配する母親の愛情を強く感じたこんなこともありました。入社が決まって研修中のことでした。女性記者Yさんのお母さんから、娘に内緒で私に会いたいとの電話がありました。Yさんにはばれないように、社内でお目にかかると、「うちの娘は記者になれるのでしょうか。心配で、心配で」。「しっかりしたお嬢さんですよ。いい記者に育てますからご安心ください」とお帰りいただきました。Yさんは経済記者として立派に育ち、雑誌「エコノミスト」の編集長も務め、定年後、先輩記者がやっていた某業界の機関誌編集長を引き継いで活躍しています。過日、旧友会の時、Yさんのいる席でこの母親の話を紹介したら、「いやだわ、そんなことあったんだなんて。全然知らなかった」と、顔を赤くして恥ずかしそうでした。秘密を守っていた方がよかったのですね。反省しています。
大学生のころアルバイトで編集局の専務補助員を4年もやっていたS君には、お茶を入れてもらったり、鉛筆を削ってもらいました。ワープロもパソコンもない時代でした。原稿はザラ紙1枚に30字ずつ、つまり新聞の2行分の原稿を書くことになっていました。記者は鉛筆で大きい字を書いて、印刷工場でわかりやすいようにと配慮していました。鉛の活字を一本一本拾って文章を組む手間のかかる印刷でした。そのS君が優秀な成績で筆記試験を突破して面接に。手心加えることもなく集中する質問を見事にさばいて合格。3か月後、局長になって職場で会ったら、S君は立派な営業マンの顔でした。
研究機関に勤務していたK君、新聞社の営業がやりたいと受験。面接で趣味を尋ねたら「フランス料理を作って食べること」。面接委員から次々に質問が出て、30分間もフランス料理談義が続いたでしょうか。あとはなにも聞かず 「時間ですから」と判定を聞くと、全員「合格」。広告で頑張ったK君はこんな調子で営業成績を上げたのでしょうか。
1年目の受験で僅差で落ち、2年目再挑戦で見事合格のT君。創価大学卒で、どうしても毎日新聞社に入りたかった、と面接で強調していました。なかなかの人物と期待していましたが、創価学会が放っておきませんでした。今や衆院議員として公明党で活躍しています。
毎日新聞社に入社され、ご縁ができた皆さん。定年を迎えられたいま、ぜひ毎友会に入られて、またご一緒に語り合い、論じ合い、呑もうではありませんか。とはいうものの、今年数えで卒寿の私、定年を迎えたばかりの若い皆さんの体力にどこまでついて行けるかわかりませんし、コロナ跋扈の中で老人はおとなしくしていなければならないのは、残念に思います。
(新実 慎八)
※新実慎八さんは、1932年生まれ。56年毎日新聞社入社。取締役中部本社代表、常務取締役管理部門統括、広告担当、パレスサイド・ビルディング(現毎日ビルディング)代表取締役など歴任。一般社団法人海外日系新聞放送協会理事長。

※日本記者クラブ会報2020年12月号「マイBOOKマイPR」から
「年表 移住150年史 邦人・日系人・メディアの足跡」
新実 慎八(毎日新聞出身)
▼日本人移民史研究に必須の一冊
幕末から令和まで150年にわたる、北米、南米を中心とした日本人移住の歴史を、年月日順に網羅した年表。移住先各国の実情、日系社会の出来事、邦字新聞の歩みが同時代史として一覧できる。重要語句には詳細な解説、索引をつけ、年表とは別に14カ国・地域の移住略史を加えた。筆者が理事長を務める海外日系新聞放送協会渾身の労作。日系人関係の仕事に半世紀にわたって取り組んできた同協会の岡野護専務理事(当クラブ特別賛助会員)がまとめた。
風響社 / 5500円 / ISBN 4894892804
2021年2月12日
ロッキード事件から45年 — 岩見隆夫・才木三郎記者の追憶

ロッキード社の秘密代理人児玉誉士夫に21億円——。米上院チャーチ委員会(外交委員会多国籍企業小委員会)から持ち込まれたロッキード事件。1976(昭和51)年2月5日だった。それからことしで45年である。
「児玉を捜せ」。毎日新聞社会部で、最初に等々力の児玉邸へ向かったのは、澁澤重和(当時36歳)と堀一郎(2019年没78歳)だった。澁澤は、この事件の社会部取材班の事務局長として、紙面企画、予定稿の作成、取材費の予算要求まですべてを仕切ることになる。
「児玉さんはご在宅ですか」
「いません。地方に行っております」(『毎日新聞ロッキード取材全行動』講談社77年刊)