2025年3月18日
瀬川至朗早大教授の最終講義は「SNS時代のジャーナリズム」
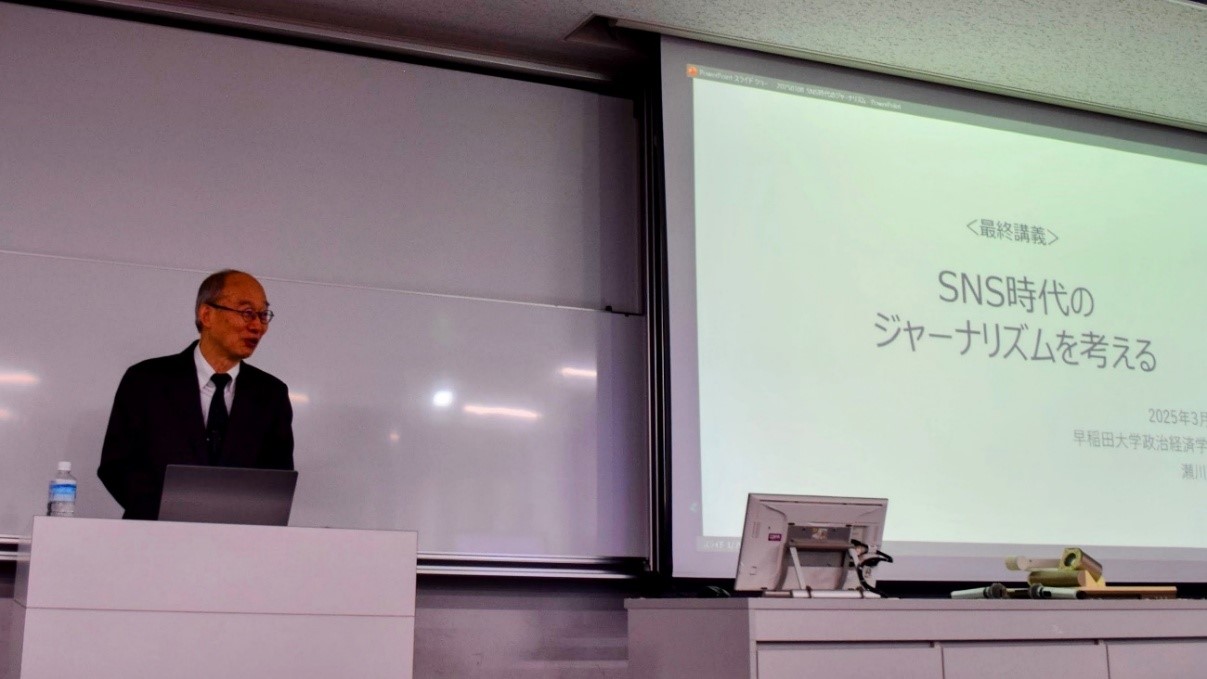
東京本社科学部長、編集局次長などを務めて早稲田大学に転じ、17年間教鞭をとった瀬川至朗さん(政治経済学術院教授)の退職記念最終講義=写真=が3月8日行われました。
「SNS時代のジャーナリズム」と題した講義は教室とオンラインを併せて300人以上が聴講する人気ぶりでした。私はオンラインで受講しました。
瀬川さんは1978年入社、高松支局から大阪社会部を経て東京に転じ、主に科学報道で活躍しました。私とは大阪社会部で短期間一緒でした。
大学ではサイエンスを教えるかと思っていたら、科学的視点を基に広くジャーナリズム一般に研究の視野を広げ、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞選考委員などの役職も務めて多くのすぐれたジャーナリストを世に送り出しました。また、ファクトチェック活動を支援するNPO法人ファクトチェック・イニシアティブを立ち上げ、理事長をしています。私が関わっていた勉強会にファクトチェック関連の講師を紹介してもらったこともありました。
最終講義では、ジャーナリズムの規範・原則やジャーナリストの条件、客観報道とは、などの総論を前段に、兵庫県知事選挙(2024年10月31日告示、11月17日投開票)をめぐるSNSやマスメディア報道の分析が詳細(パワーポイントスライド74頁)に提示され、極めて興味深い内容でした。おこがましい言い方になりますが、こうしたSNSの分析やファクトチェックは本来もっと新聞がやるべき、やれたのではないかという印象を抱きました。
以下はX(旧ツイッター)もやらない私の粗略で不十分な部分的講義報告です。
◇
偏向報道批判の人が「客観中立報道」とよく言うが、ニュースの素材、視点、表現それぞれの選択の時点で主観は入る。重要なのは「第三者的な立ち位置」ではなく「取材・報道プロセスの客観性」である。ネットの時代には堅固で透明性の高いプロセスはより重要になる。客観性を検証可能性という言葉に置き換えて考えてもよい。科学研究の原則と同じだ。
中立性に関して言えば、互いに異なる意見を扱う場合、機械的な公平さではなく、その意見の根拠の強さに応じて扱いの程度を変える必要がある。重要なのは、そうした様々なアクターからジャーナリストが独立していることと、多面的な取材調査を実施して全体像を把握し、ミスリードしないようにすること。意見の多様性は尊重し、その意見に根拠があるかどうかを取材調査することだ。
【兵庫県知事選挙におけるSNS分析】
候補者アカウントによるX投稿の表示回数(インプレッション数=コンテンツが表示された回数)を見ると、斎藤元彦氏は失職表明の9月26日が2800万回と突出し、選挙期間中は低調だったが、終盤に上向き、投開票日前後は3500万回に達した。
有力対抗馬の稲村和美氏はずっと低調で終盤1日だけ500万回に到達した日があっただけだった。
立花孝志氏も当初は低調だったが、告示日には2500万回に達し、投開票日前にも2000万回になった。
X投稿のエンゲージメント数(ユーザーの反応総数)では、斎藤氏の場合は選挙期間中の後半に伸び出し、投開票日翌日に2500万になった。
稲村氏はずっと低調で終盤に300万に届くかどうかだった。
立花氏は選挙期間に入って爆発的な伸びを示し、開票日後は斎藤氏を上回る3000万から3500万回に達することがあった。
まとめると、斎藤氏の場合、失職宣言後9月下旬からのインプレッション数が多いのは、県議会での不信任決議に違和感を抱く層の存在を示唆する。10月下旬から11月初めにかけてのエンゲージメント数の急増は、立花氏の日常のエンゲージメント数に比べると異常ともいえる多さで、県民局長のプライバシー暴露に対する関心の高さを示している。
斎藤氏と立花氏、「斎藤応援」と立花氏の共通フォロワーは、それぞれ29%、44%で、SNS上は「2馬力」選挙の可能性がある。
【新聞とテレビの報道】
新聞は選挙期間中も報道量自体は変わらず。ただし「選挙前」と「選挙期間」の1か月半はほぼ選挙が記事のテーマ。候補者は公平・中立に扱うという選挙報道の「慣例」を強く感じる。テレビは「選挙前」と「選挙期間」は報道量が激減、ニュースのテーマは選挙。選挙報道の慣例の実施というより、選挙時の報道の回避に近い。
新聞もテレビも告発文書の真偽に関する報道は8月まで。その側面での「報道の空白」は2か月以上続いたと言えるかもしれない。それは、候補者を公平・中立に扱うというメディアの固定観念が影響しているのではないか。SNSを「現場」と捉え、その情報を調査する姿勢が乏しかった。また、有権者が疑問に感じる可能性のある各点について「なぜ報じないのか」と説明をする習慣がなかった。
ちなみに公選法には選挙報道の公平・中立を求める条文はない。
【誤情報についての訂正情報を知らせる取り組み】
※ファクトチェック
選挙期間中は日本ファクトチェックセンターによる2件のみ。「稲村氏が当選すると、外国人の地方参政権が成立する」(誤り)など。
※Xのコミュニティノート
誤解を招く恐れがある投稿に対し、事前登録された匿名のユーザーが訂正情報を記録 したノートを付けることができる。同様に匿名の評価者の多様な視点をもつポジティブな評価が得られたノートが公開されるというシステム。
知事失職から投票終了まで168件のノートのうち、「公開」は2件のみ。「一時公開」が7件。少なくとも158件のノートが非公開のままで、稲村氏不利の誤情報も7件含まれる。意見が二極化する分野では、コミュニティノートが機能しなくなる可能性がある。
【SNS時代におけるジャーナリズムの再構築】
① 「検証可能性」を重視する。
なぜ取材に取り組むのか、なぜ報道しないのかをできるだけ明示する。SNS上などの影響力のある情報の真偽を検証して報道するファクトチェックに取り組む。
② 「独立性」を確保する。
発表報道への依存を減らし、自社の責任で取材・報道する姿勢を確立する。「組織のジャーナリズム」だけでなく、メディアとして「個として強いジャーナリスト」の育成に力を入れる。
③ 包括性を維持する。
分断が起きやすいテーマでは、なぜ意見が異なるのかの根拠や理由を取材し、その点も説明しながら報道する。機械的な「両論併記」ではなく丁寧な取材をもとに、根拠の程度や情報の確からしさ、「比例度」を意識した報道をする。
④ SNS時代のジャーナリズムの主役は市民。メディアを信頼してくれという「Trust Me」ではなく、「Show Me」が基本であることを認識し、市民参加の「Engaged Journalism」に取り組む。SNSがジャーナリズムの主要な「現場」と考える。課題提示だけでなく、課題解決型、建設的ジャーナリズムに取り組む。
【最後にW.リップマンの言葉】
「嘘を見抜く情報を持たない共同体に自由はない」
「大きな不安の時代には、不安定な気持ちに作用する特定の意見が、大きな混乱を引き起こすことがある。そのような意見は必然的に根拠が乏しく、現実を見るよりむしろ偏見に後押しされていることが判る」(『Liberty and the News』1920 より)
藤田 修二(元大阪本社社会部)