2025年5月12日
岸俊光著『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』
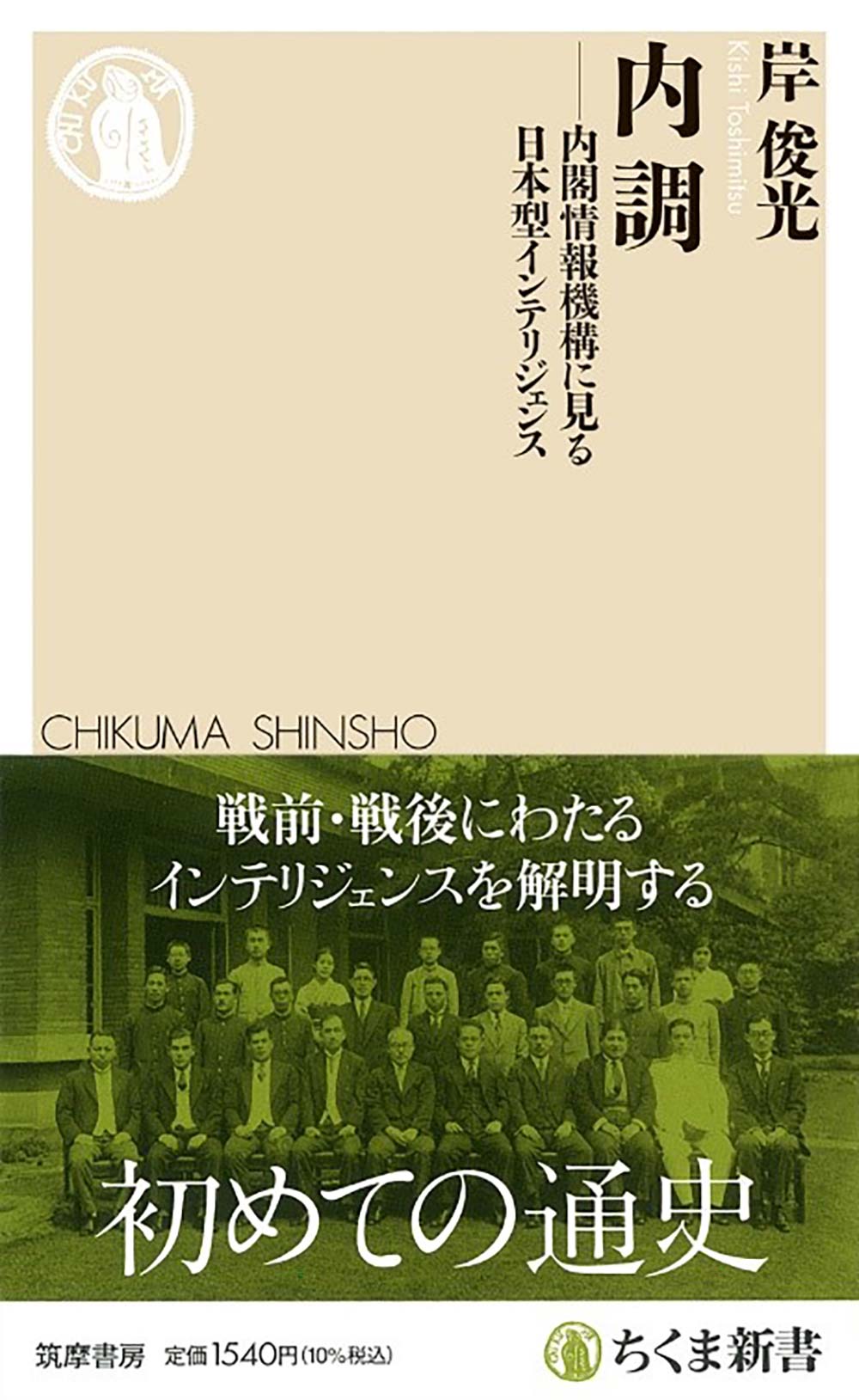
1952(昭和27)年4月に新設され、70年余を経た今も秘密のベールに包まれている「内調」のリアルな実態を、関係者の資料と公文書を基に初めて解明。情報委員会、内閣情報部、情報局と変遷した戦前の情報機関と、内閣総理大臣官房調査室、内閣調査室、内閣情報調査室と変遷した戦後の情報機関を一括して内閣情報機構と位置づけ、情報委員会(同11)年が創設される前夜から、米中接近など動揺する国際秩序への対応を迫られた冷戦期の1972(同47)年頃までの「通史」を描いたものである。
内閣総理大臣官房調査室の創設メンバー、志垣民郎が保管していた内部資料、克明な日記と、内調を批判的に観察し続けたジャーナリスト、作家の吉原公一郎が入手した内部資料を発掘。国立公文書館が保管する戦前の内閣情報機構の「生みの親 育ての親」、初代内閣情報部長の横溝光暉の個人資料を有機的に結びつけることで、国民への啓蒙宣伝という一貫した業務とそれを担った人脈の連続性を立証した。
本書の読みどころは、公文書がほとんど開示されていない戦後の内閣情報機構の活動を体系的に解釈し、戦前の内閣情報機構との繫がりを突き止めた点にある。占領期を経て日本が独立する直前に設立された内閣総理大臣官房調査室は、当時、戦前の言論統制復活を恐れる新聞各紙の批判を浴びた。1960年代の初めに松本清張や吉原公一郎が流出した資料を入手するが、それでも「親米反共」国家を目指した一面を小説の形で描くしかなかった。
筆者は2019年に、佐藤政権の非核政策に影響を与えた政治学者らへの核政策研究を分析した単著『核武装と知識人』(勁草書房)と、志垣の回想録『内閣調査室秘録』(文春新書)を編著として出版。本作はそれらを発展させ、大正期の「大衆の登場」まで遡り、内閣情報機構の半世紀を通して政治・社会の裏面史を浮き彫りにした。すなわち戦前の内閣情報機構は、第一次大戦後のパリ講和会議で日本全権団が中国のプロパガンダに直面したのを一つのきっかけに構想され、総力戦を支える思想戦を展開。戦後の内閣情報機構もそうした手法を受け継ぎ、政府寄りの世論形成に努めてきたのである。
近年、日本でもインテリジェンスに対する関心が高まり、情報機関の拡充を主張する声がある。戦前戦後の内閣情報機関を描いたこの小書が、地に足の着いた議論の一助になれば、と念じている。
(一般社団法人アジア調査会常務理事・事務局長 岸 俊光)
◇
岸さんは、1961年愛媛県生まれ。85年入社。学芸部で論壇記者。論説委員。2009~10年米国ジョンズ・ホプキンス大学客員研究員。日本の非核政策研究により早稲田大学で博士号(学術)を取得。NPO法人インテリジェンス研究所特別研究員。